副業するときに多くの方が疑問に思うのが、「開業届って出さないといけないの?」ということだと思います。
「出さないといけない」と言っている人と「出さなくてもいい」と言っている人が両方いて「実際どっちなの?」と感じることもあるのではないでしょうか。
そこで、今回はそんなモヤモヤを解消すべく、国税庁が出している最新の法令解釈をもとに「副業に開業届が必要なのか」を解説していきます。
さらに、今回は開業届を出すか決めたり、開業届の準備をしたりするために
- 副業で開業届を出すメリット
- 副業で開業届を出すデメリット
- 開業届を出す手順
といったこともお伝えしていきます。
この記事を読めば、開業届を出すか正しく判断できるようになるので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
【お知らせ】
2000名以上の人生を変えるキッカケになった「好きなことで生きていく!WEBデザイナーという働き方セミナー」では、
などをお伝えしています。今だけ無料で開催しているので「WEBデザインの学び方がわからない」「WEBデザイン業界について知りたい」という方はぜひご参加ください。
>>詳しくはこちら
副業で開業届が必要かは概ね自分次第
ではまず、多くの方が疑問に思っているであろう「副業をするのに開業届は必要なの?」という疑問にお答えしていきます。
結論、副業をするのに開業届が必要かどうかは、概ね自分次第です。
「自分次第ってどういうこと?」と疑問に思う方もいると思います。
そこで、ここからは「自分次第とはどういうことなのか」を詳しく解説していきます。
開業届は事業所得を得ている場合に出す必要がある
開業届を出す必要があるかは「副業で得ているのが何所得か」で決まります。
もし、副業で得ているのが事業所得であるなら、その副業は「事業」となり開業届が必要になります。
逆に副業で得ているのが「雑所得」や「給与所得」である場合、その収入にかかわらず開業届を出す必要はありません。
そのため、開業届を出すか迷ったときには、まず得ているのが「事業所得なのか」を知る必要があります。
※厳密には「不動産所得」「山林所得」で収入を得ている場合も開業届が必要になりますが、「不動産所得」「山林所得」を得る副業をしている人はほとんどいないので、ここでは事業所得に絞っています。
参考:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
事業所得かどうかは自分が帳簿をつけるかで決まる
開業届は「事業所得」を得ている場合に、出さなければいけないとお伝えしました。
そうなると次に気になるのは、「事業所得」とはどんなものかということですよね。
これまで事業所得かを判断する材料は
- 利益目的で活動しているか
- 継続的かつ反復的に収入があるか
- 責任を持って計画的に活動しているか
というとても曖昧なものでした。
しかし、2022年10月7日に国税庁から出た「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」という通達によって、副業における収入が事業所得になるか、雑所得になるかは「記帳・帳簿があるか」で判断されることになりました。
つまり、開業届を出したいと思えば、帳簿をつけて副業で得ているものを「事業所得」にすればいいですし、開業届を出したくないと思えば、帳簿をつけず副業で得ているものを「雑所得」にすればいいのです。
結論で「副業で開業届が必要かは概ね自分次第」とお伝えしたのはそのためです。
※事業所得かどうかは帳簿の有無で決まるとお伝えしましたが、なかには例外もあります。
例えば副業で得ている所得が、本業の10%未満である場合や3年赤字状態を放置している場合は、帳簿書類があったとしても、雑所得になります。
また、副業の収入が300万円以上になったときには、その業務に係る現金預金取引等関係書類を提出する必要があります。
開業届を提出するメリット
開業届は提出が面倒くさいことから出していない人もいるのですが、実は開業届を提出するメリットはたくさんあります。
屋号を使えるようになる
開業届を提出するメリットとして、まず挙げられるのが「屋号を使えるようになること」です。
屋号は個人事業主が使える商業上の名前で、
- クライアントから信用されやすくなる
- クライアントの印象に残りやすくなる
- 自分のできることをアピールしやすくなる
- 口座を管理しやすくなる
といった効果があります。
クライアントから信用を得られて、仕事を取りやすくなる屋号は持っておいて損のないものですよ。
ただし、屋号にはルールがいくつかあります。
そのため、屋号をつける前にはルールを確認しておきましょう。
屋号の注意点については、こちらの記事をぜひ読んでみてくださいね。
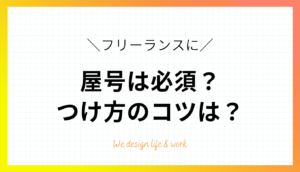
青色申告ができるようになる
青色申告ができるようになるのも、開業届を提出するメリット。
申告方法の1つである青色申告は、白色申告(誰でもできる申告方法)にはない5つの特典があります。
- 税金の特別控除を受けられる
- 赤字を翌年の黒字で相殺できる
- 貸倒引当金を計上できる
- 青色事業専従者の給与を経費にできる
- 30万円未満の減価償却資産を1年で計上できる
なかでも青色申告による税金の特別控除はとても魅力的で、最大65万円の控除(数万円〜数十万円の節税)を受けられます。
青色申告ができるかどうかで、支払うべき税金の額はガラッと変わってくるので副業でも開業届を提出しておきたいですね。
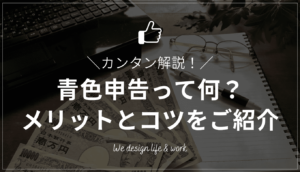
損益通算ができるようになる
開業届を提出すると「損益通算」ができるようになります。
「損益通算」と聞くと難しく感じてしまうかもしれませんが、実はそうでもありません。
赤字の部分と黒字の部分を合わせて相殺させることです。
副業で赤字が出た場合は、本業の黒字部分で相殺できるということですね。
損益通算のメリットは「相殺した分のお金」が控除額になり、節税できること。
万が一、副業で赤字が出たときに少しでも出費を減らせるよう、開業届を出して損益通算ができるようにしておきましょう。
事業用の銀行口座が作れる
事業用の銀行口座が作れるのも、開業届を提出する大きなメリットです。
事業用銀行口座の開設には
- プライベートと事業のお金を管理しやすくなる
- クライアントから信用を得られる
といった効果があります。
プライベート用と事業用の口座が同じだと何にいくら使ったかわからなくなるので、お金の計算をするのがかなり面倒です。
しかし、事業用の口座が作ると、「プライベートで使うお金」と「事業で使うお金」を分けて管理できるので帳簿もつけやすくなります。
また脱税対策の観点から、できるだけ事業用の口座に振り込みたいと思っている企業も多いです。
そのため、事業用の口座を持っているとクライアントからの印象も良いですよ。
事業用のクレジットカードを作れるようになる
開業届を提出するメリットとして、事業用のクレジットカードが作れることもあります。
事業のクレジットカードがない場合、仕事での支払いとプライベートでの支払いは1つのクレジットカードですることになります。
そのため、経費を計算するときには、クレジットカードの履歴を1つずつ遡って、何にどれだけ払ったかを見なければいけません。
しかし、事業用のクレジットカードがあれば、事業用の支払いとプライベート用の支払いを分けられるので、経費を計算するときの手間がかなり少なくできます。
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
開業届を提出するデメリット
ここまで開業届を提出するメリットを解説してきましたが、もちろん開業届の提出にはデメリットもあります。
提出するのが面倒
やはり提出するのが面倒なのは、開業届を提出するデメリットですね。
実際のところ、手続きはそれほど難しくはありません。
しかし、いくつか書類や証明書を準備する必要があるので、事業を始めたばかりで忙しい方にとっては負担になります。
失業保険がもらえなくなる
失業保険をもらえなくなるのも開業届を出すデメリット。
会社員は失業保険に入っているので、会社を辞めたときに国から給付金をもらえるのが一般的です。
しかし、開業届を提出していると、ハローワークから「再就職の意志はない」と見なされ失業保険を受けられません。
※失業給付金をもらってから開業届を出すなら給付金がもらえます。そのため、会社を辞めるまであえて開業届を出さない人もいます。
開業届の手続き3ステップ
ここまでお伝えしたように、開業届には多くのメリットがあるので、副業をしている人は積極的に開業届を出すのがおすすめです。
ここからは開業届の手続き方法について3つのステップで解説していきますね。
ステップ1:開業届を用意する
まずは、開業届の準備からです。
開業届を入手するには
- 税務署に行って直接書類をもらう
- 国税庁のホームページからダウンロードする
といった2つの方法があります。
手書きでの記入はもちろんのこと、パソコンでの直接入力も認められているので、「書き損じて何回も書き直すのは面倒」という方はホームページでダウンロードしましょう。
ステップ2:開業届の必須項目を記入する
開業届が手に入ったら、必要事項を書き込んでいきましょう。
開業届には1〜15の項目があり、1人で事業をしている場合は1〜12、従業員がいる場合は1〜15記入することになっています。
副業の場合は12まで書けば問題ありません。
実際の項目は次の通りです。
- 納税地の税務署名、提出日
- 納税地/上記以外の住所地・事業所等
- 氏名/印/生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払いの状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 給与支払を開始する年月日
注意すべきなのは職業を書くところです。
記入するのは副業の職種です、間違って本業の職種を書かないようにしてくださいね。
ステップ3:必要なものを揃えて提出する
開業届を提出するには次の4つが必要になります。
- 開業届 2枚(控え1枚)
- 印鑑
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(免許証、保険証、パスポート)
忘れやすいのは開業届の控えと、マイナンバーカードです。
マイナンバーカードを持っていないという方は、「マイナンバー通知カードの写し」か「マイナンバーの記載がある住民票の写し」を提出しましょう。
提出場所は自分が住んでいる自治体の税務署か、e-Taxと呼ばれる国税庁のホームページです。
基本的にはe-Taxで提出して問題ありませんが、何か不明な点があるときには税務署に行くのをおすすめします。
副業を始める人からよくある開業届に関する質問とその回答
では、最後に副業を始める人からよくされる開業届に関する質問と、それに対する回答をしていきます。
Q.開業届はいつまでに出さないといけない?
開業届は事業を始めてから1ヶ月以内に提出するのが原則です。
しかし、1ヶ月以内に提出しなかったからといって、特に罰則はありません。
Q.扶養されている人でも開業届は出せる?
結論、扶養されている人でも開業届を提出することは可能です。
配偶者の扶養内でありながらも、開業届を提出して仕事をしている人はたくさんいます。
ただ、扶養者が契約している団体によっては、開業届を出すことで扶養から外される場合があります。
そのため、扶養されている状態で開業届を出すときには、契約団体がどんなルールになっているかを確認するようにしましょう。
Q.開業届を出すと会社に副業がバレる?
開業届を出して、会社に副業がバレることはありません。開業したことは、誰にも通知されないからです。
しかし、開業届提出後の確定申告で副業がバレることはあります。
確定申告のときに住民税を「特別徴収」という形式で納めると、例年より住民税が多いことが会社に知られ、副業をしていることがバレてしまいます。
そのため、副業を詮索されたくない方は「普通徴収」で住民税を納める必要があります。
この方法を使えば副業禁止の会社でも副業がバレる可能性は低くなりますが、100%バレないわけではありません。そのため、就業規則で副業が禁止されている場合は、それに従うようにしましょう。
まとめ
今回は多くの方が疑問に思っている「副業をするのに開業届は必要なの?」という疑問にお答えしました。
お伝えしたことをまとめると、次のようになります。
- 副業で得ているのが「事業所得」の場合は開業届が必要になる
- 得ているのが「事業所得」かどうかは帳簿をつけているかで決まる
それぞれ例外はあるものの、基本この2つを覚えておけば、開業届に関しては間違えることはありませんよ。
また、今回は開業届のメリット・デメリットもお伝えしました。
開業届には「提出するのが面倒」「失業保険がもらえなくなる」といったデメリットはあるものの、それ以上にメリットがたくさんあります。
継続的に副収入を得ていきたいと考えている人は、少し面倒でも帳簿をつけて開業届を提出するのがおすすめです。

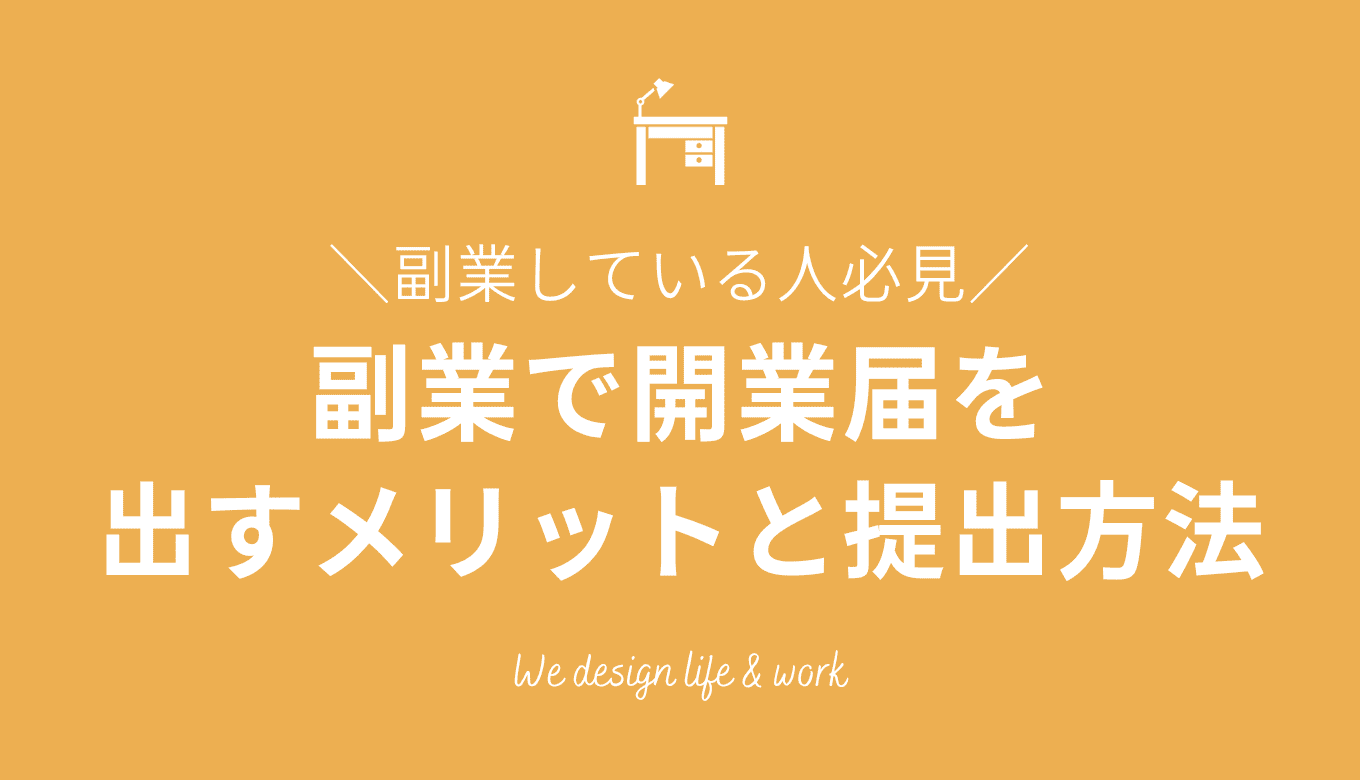
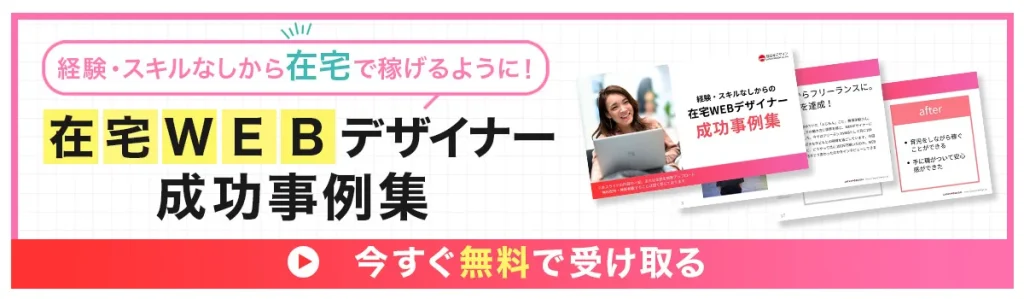
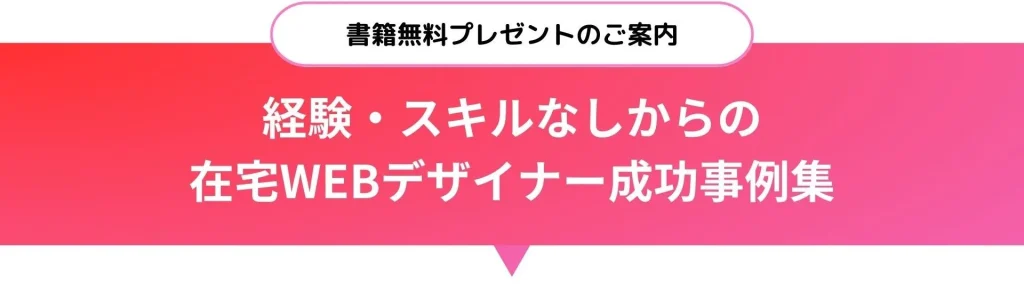
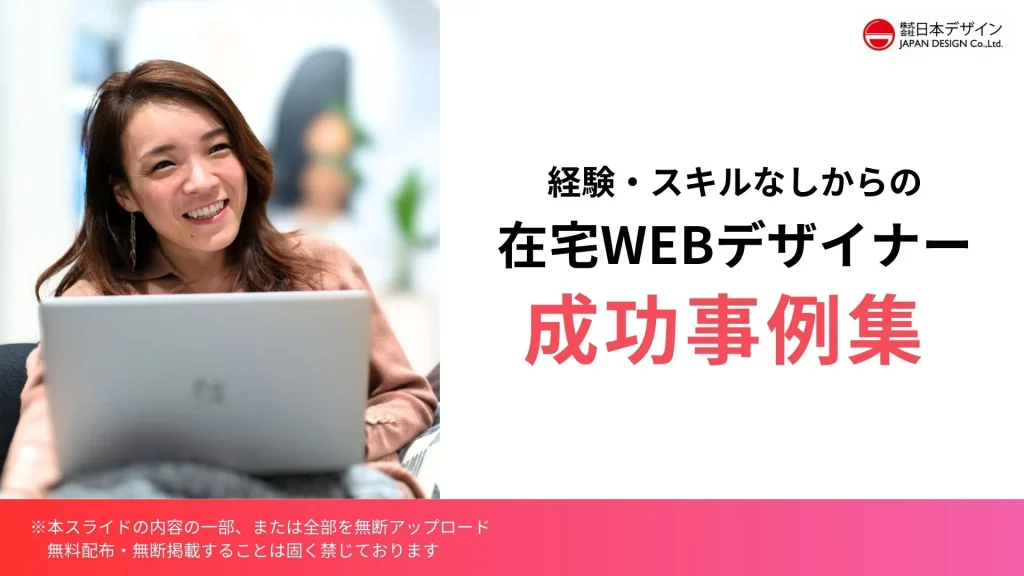
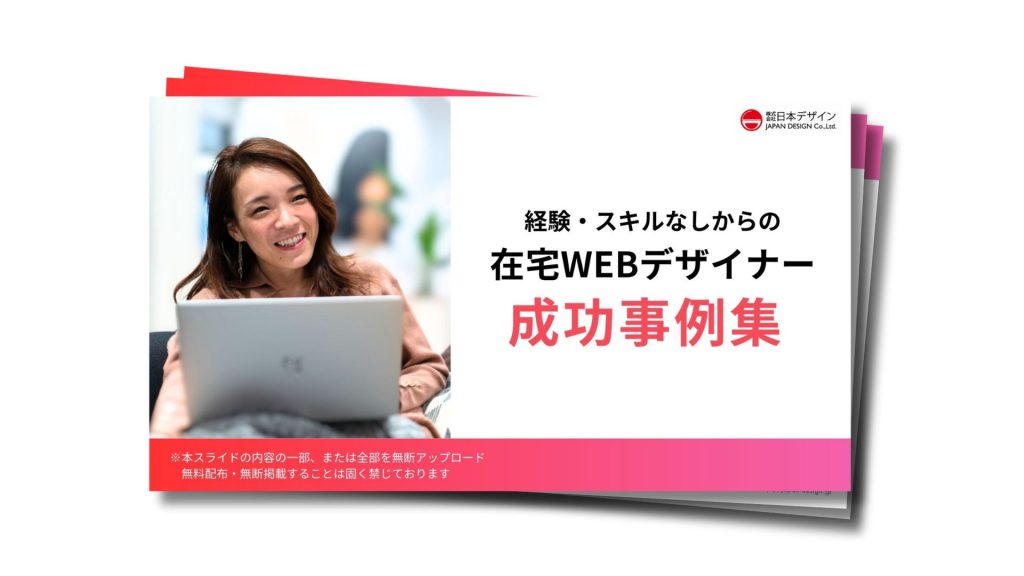
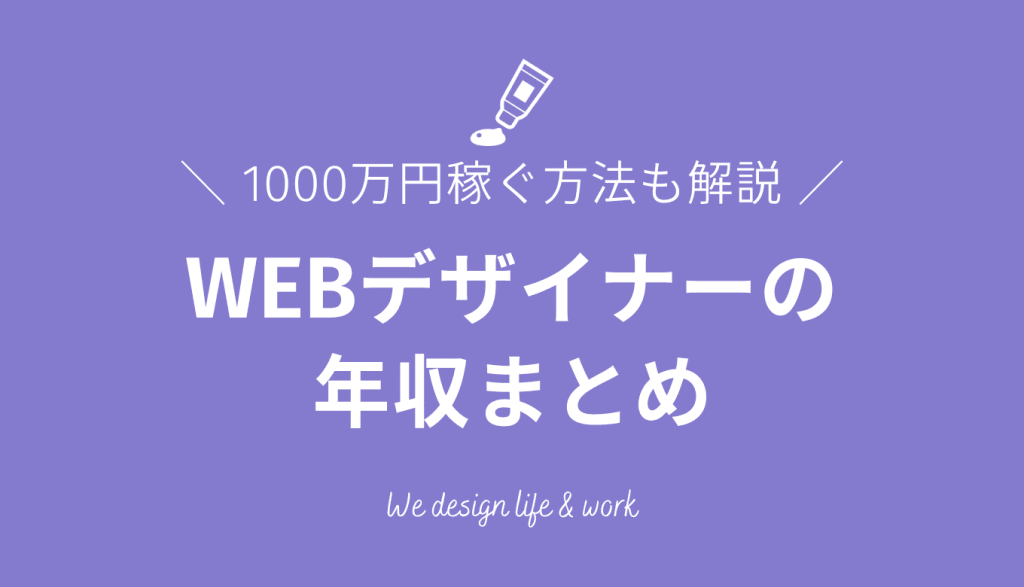
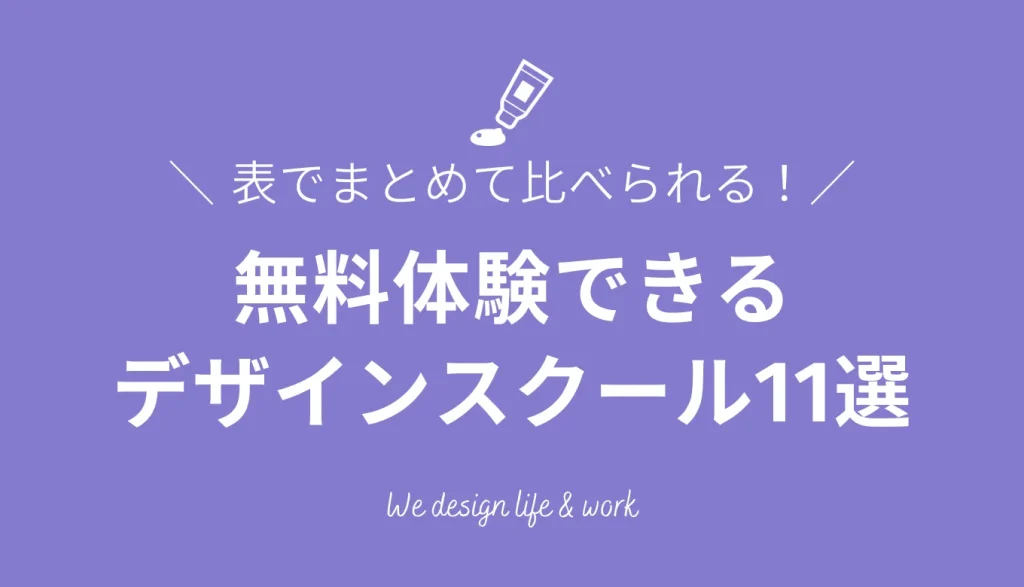
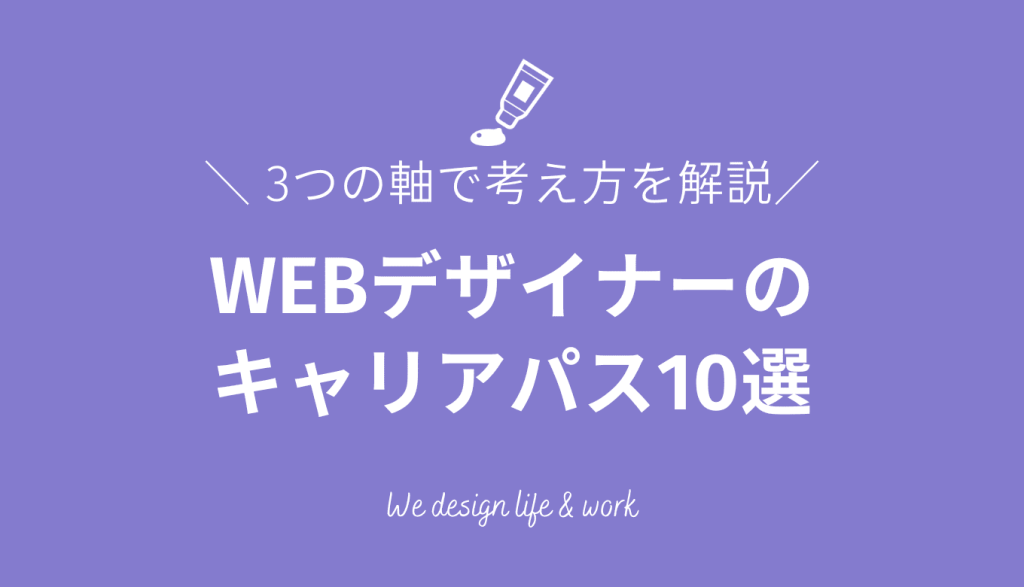
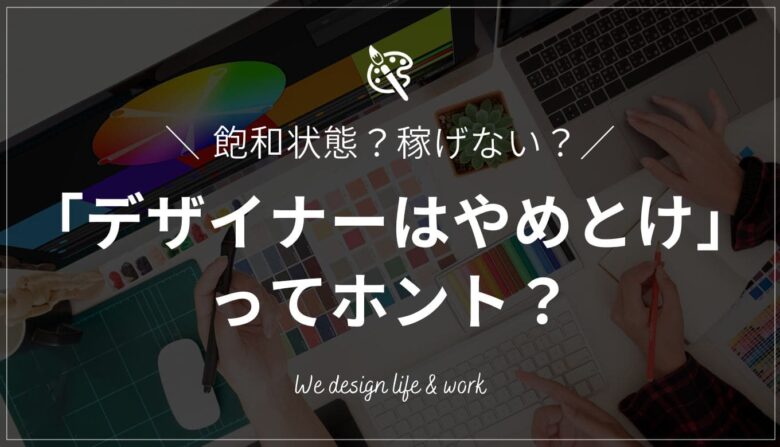
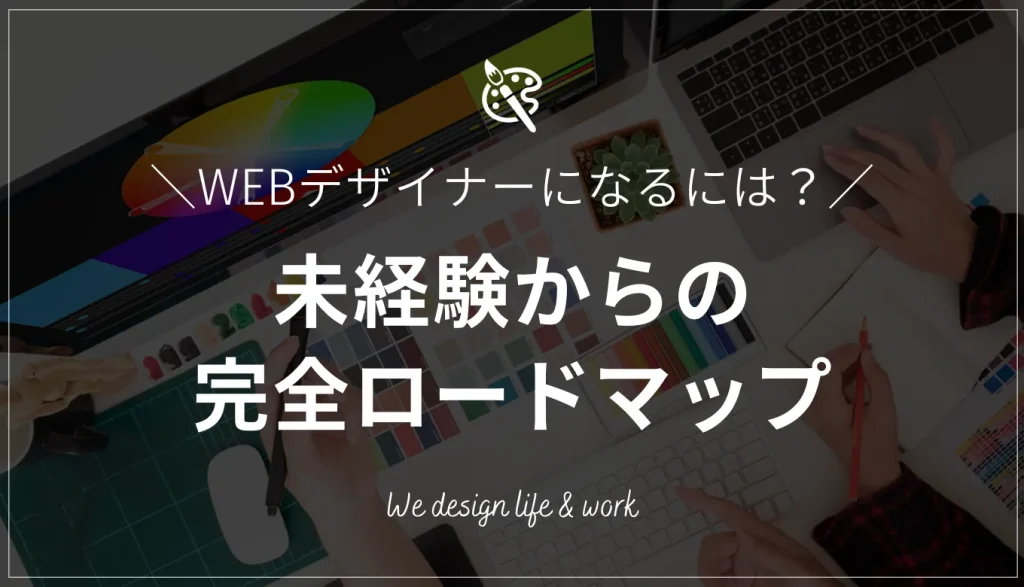
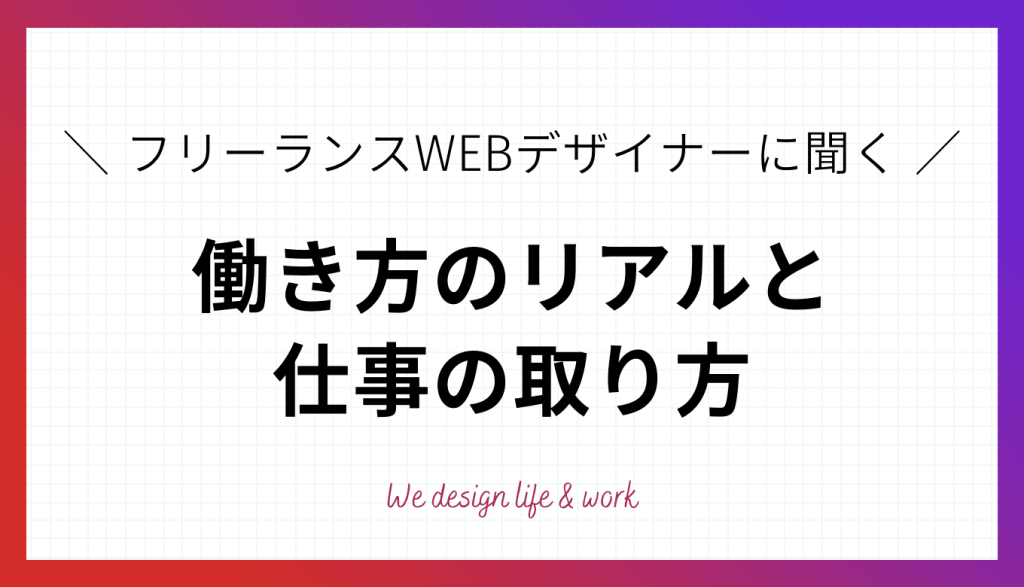
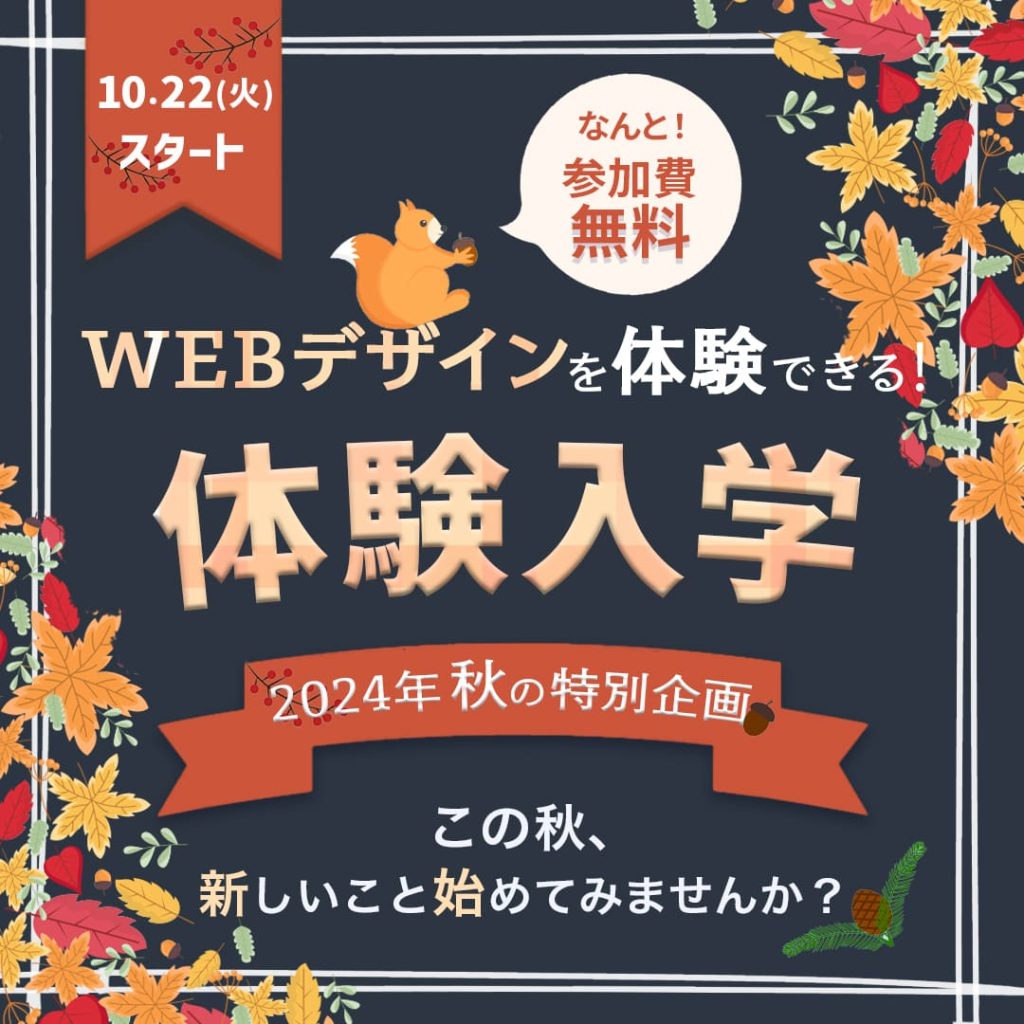

質問や感想があればご記入ください