屋号とは、個人事業主やフリーランスの事業体の名称で、いわゆる法人の会社名にあたります。
事業を行う上での顔のようなものですから、屋号をつける際には、長年使い続けられる、印象的で親しみやすく、魅力的な名前をつけたいですよね。
そこで、この記事では、屋号の決め方をご紹介していきます。
NG例も説明しますので、「こんなはずじゃなかった!」なんて失敗も避けられます。
この記事を参考に、あなたの事業にぴったりな屋号を考えてもらえると嬉しいです。
【お知らせ】
2000名以上の人生を変えるキッカケになった「好きなことで生きていく!WEBデザイナーという働き方セミナー」では、
などをお伝えしています。今だけ無料で開催しているので「WEBデザインの学び方がわからない」「WEBデザイン業界について知りたい」という方はぜひご参加ください。
>>詳しくはこちら
フリーランスが知っておくべき屋号の基礎知識

屋号について
「屋号ってどんなところで使うの?」
「絶対につけなければいけない?」
「一度決めたら二度と変えられないのかな?」
と疑問を持っている方もいるはず。
そこで、まずは屋号について知っておきたい基礎知識を解説していきます。
業務上で屋号を使う場面は多くある
業務上で屋号を使う媒体には、次のようなものがあります。
- 看板
- 名刺
- 銀行口座名義
- レターヘッド
- ハンコ
- 領収書
- 請求書類(見積書、納品書、請求書)
- 包装紙
簡単に挙げただけでも、これだけ屋号が露出する場面があるのです。
このことを念頭に置いて、自分の職種や事業内容に合ったイメージの言葉、文字数、響き、見た目の屋号を考えていきましょう。
フリーランスは屋号をつけなくてもいい
フリーランスに屋号は必須ではありません。
無理につけなくても、開業届の屋号欄を空欄で申請することができますし、確定申告もできます。
実名で仕事を受注することも可能です。
ですから、「気に入った屋号が見つかるまでは、あえて屋号をつけない」という人もいます。
屋号は途中で変えても問題ない
屋号は変更可能です。
変更の手続きも必要ありません。
途中で変更する場合は、変更後に初めて出す確定申告書に、変更後の屋号を記入します。
屋号変更の履歴を残したい人は、開業届を再提出しましょう。
「その他参考事項」の欄に「屋号の変更」と記入します。
もしくは、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する方法もあります。
通常は、住所などが変わった時に提出する届出書ですが、屋号の欄に変更後の屋号を記載します。
この場合も、その他参考事項の欄に「屋号の変更」と説明書きを加えて提出すると良いでしょう。
事業ごとに複薄の屋号をつけてもいい
複数の事業がある場合は、一つ一つの事業に対して、別々の屋号をつけることが可能です。
わかりやすい例でいえば、不動産業とカフェを経営している人が、「〇〇不動産」という屋号でカフェを開いたら、違和感がありますよね。
新しく屋号を追加したい場合には、また改めて開業届を提出します。
屋号欄に屋号とフリガナを記入し、「その他参考事項」の欄に「屋号の追加登録」などと書いて提出すれば、登録手続きが完了します。
フリーランスが間違えやすい屋号と商号・商標との違い
屋号と間違われやすいものとして、商号と商標があります。
商号と商標を知らないと、法律違反をおかしてしまう可能性があるので、ここからはその違いを解説していきますね。
ざっくりその違いを表にまとめると次のようになります。
| 何につける名前か | つける必要があるか | 法に守られているか | |
| 屋号 | 会社 | 自由 | 守られていない |
| 商号 | 会社 | 個人事業主は自由(法人は必須) | 守られている |
| 商標 | 商品やサービス | 自由 | 守られている |
まず、3つは「何につける名前か」で分かれます。
「屋号」「商号」が会社につけるものなのに対して、「商標」は商品やサービスにつけるものです。
商標は法律で守られており、同じ屋号をつけてしまうと法律違反になってしまうので気をつけましょう。
屋号と商号はどちらも会社につけるものですが、法律に守られているかどうかで変わってきます。
もし、自分のつける屋号が他の人の屋号と被っても問題ありませんが、商号と被ってしまうと法律違反になってしまうので気をつける必要があります。
ちなみに、フリーランス(個人事業主)は商号をつけるか自由に決められますが、法人になると必ずつけなければいけません。
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
フリーランスは屋号をつけるのがおすすめ!屋号をつける4つのメリット

フリーランスが屋号をつけるかどうかは自由ですが、特別な理由がない限りは屋号をつけるのがおすすめです。
なぜなら、屋号をつけるのにはメリットがいくつもあるから。
ここからはそのメリットをご紹介していきますね。
クライアントからの信頼を得られる
フリーランスが屋号をつける大きなメリットとしてクライアントからの信頼を得られることがあります。
個人名で活動をしていると何をしている人なのかすぐにはわかりません。
そのため、第一印象として「この人はフリーランス一本でやっている人なのかな?」と思ってしまうのです。
また、個人名の口座には報酬を振り込みにくいというのも企業の本音。
個人名の口座に報酬を支払うと脱税を疑われたときに厄介だからです。
もちろん、全ての企業がそう思うわけではありません。
しかし、少しでも仕事を取れる可能性を高めたいと思う場合は、屋号をつけておくことをおすすめします。
クライアントの印象に残りやすい
クライアントの印象に残りやすいというのも屋号のメリットです。
ものすごく特徴的な名前は例外として、基本、個人名を思い出すのは難しいですよね。
1回会って名刺を交換しただけの人なら、なおさらです。
しかし、特徴的な屋号をつければ「なんでこの屋号をつけたんだろう?」とクライアントの印象に残りやすくなります。
自分のできることをアピールできる
自分ができることを一瞬でクライアントに伝えられるのも、屋号をつけるメリット。
「吉田デザイン」「ムービースタジオ佐々木」といった屋号をつければ、屋号を見た瞬間に何の仕事をしているか理解できます。
逆に「吉田洋子」「佐々木裕二」だけ書いてあると何をしている人かわかりません。
「調べるの面倒だな」と思われて相手にされないリスクもありますし、迷惑メールがきたとも疑われかねないのです。
クライアントが直感的に「この人にデザインをお願いしようかな」「動画のことならあの人に任せよう」と思ってもらえる屋号をつけましょう。
口座を管理しやすくなる
屋号をつければ口座の管理もしやすくなります。
フリーランスはプライベート用の口座と事業用の口座を分けて管理することがよくあります。
このときに両方とも個人名で運用していると、どちらが何用の口座なのか一瞬で判断できません。
たしかに、少し調べればわかることではありますが、小さなストレスをことあるごとに感じることになってしまいます。
屋号をつけること自体は簡単にできるので、ぜひ開業と同時にやっておいてくださいね。
フリーランスの屋号のつけ方Q&A

屋号に関して、まだまだ気になることはたくさんあると思います。
ここからは、屋号の付け方でよくある質問にお答えしていきます。
店名、事務所名を使うべき?
屋号は事業に対してつけてもいい物なので、屋号と店名や事務所名が違っていても、問題はありません。
ただ、お客様に覚えてもらうには、店名と屋号が一致しているほうが良いともいえます。
あるいは、展開する商品やサービス名を屋号にするという方法もあります。何をアピールしたいかによるでしょう。
ペンネームを使ってもいい?
作家や芸術家など、個人の才能やパーソナリティーにネームバリューがある場合は、ペンネームを屋号にしてもよいでしょう。
ニックネームを使う人や、ニックネームと職業名を組み合わせたりする人もいます。
旧姓を使うことはできますか?
もちろん、旧姓も使えます。
旧姓でフリーランスとしてキャリアを積んできた場合は、そのままの名前で仕事を続けたいでしょうし、顧客とのつながりの面でも便利なことが多いです。
英数字を入れてもOK?
英数字を入れた屋号も使えます。
ただ、なじみのない文字や外国語だと覚えてもらえなかったり、すぐに忘れられたりするリスクもあります。
それに、つづりを間違えて、ネット検索しても出てこない、なんてこともあるでしょう。
一方で新しい兆しも見えてきています。
若い世代の個人事業主には、外国語や英数字を好んで使う人が増えています。
お客の層として若い年代をターゲットにしているなら、屋号も今風に自由につけてもいいかもしれません。
ちなみに、記号を入れることも可能ですが、一文字目に記号を入れることは一般的ではないので、やめておきましょう。
屋号に適切な長さは?
屋号が長いと、覚えにくくなってしまいます。
覚えやすさからいえば、短くシンプルなものがよいです。
語感や語呂と合わせて、検討してみてください。
一般的には、3~4文字が覚えやすく、社名や屋号に使われることが多いようです。
業務内容がわかる名称がいい?
業務内容がイメージできる屋号にしておくほうが、メリットは多いです。
地図上であなたのお店や事務所を見つけた人が、仕事を依頼しに訪ねてくる、なんてことも起こり得ます。
他と似ている屋号でも大丈夫?
屋号に独占権はないので、他と似ている屋号となってしまう場合もありますが、同一住所でなければ、同じ屋号を使うことも問題にはなりません。
ただ、間違えられやすかったり、真似していると思われたり、というマイナス面もあるでしょう。
また、インターネットのドメインを取得しようとしたときに、同じような名前の多い屋号だと、ドメインが取れないなんてこともあります。
ただし、商号登記や商標登録されている屋号を使うと不正競争防止法や商標法に抵触したとして、損害賠償を求められることもありますので注意しましょう。
フリーランス必見!「こんな屋号はNG」
屋号を決めるなら、読みやすさ、呼びやすさ、覚えやすさ、がポイントです。
そして、明るい印象や好感を持たれる名称が良いという、わりとふつうな結果に落ち着くことが多いです。
中にはインパクトを狙って功を奏した、というケースもありますが、奇をてらいすぎてはいけません。
以下に、問題となる例を紹介します。
法人格を示す名称(フリーランスの場合)
屋号はあくまでも個人事業主につける名称です。
フリーランスでありながら、「株式会社」や「社団法人」などの法人格を示す名称をつけてはいけません。
また、Inc.、Co. Ltd.、なども同様です。
このほか「銀行」や「証券」などの特定業種を示す名称も使えません。
すでに商号登記してある名称
商号登記や商標登録されている屋号と名前がかぶってしまった場合、お客様を混乱させるような紛らわしい名称をつけたと見なされます。
不正競争防止や商標法の違反で訴えられ、損害賠償を求められることもありますので気をつけましょう。
屋号をつける前に、インターネットや法務局で、同じような商標や商号が登録されていないか、また、同一地域に同じ名前や似た名前のお店などがないか、調べておきましょう。
参考1:法務省「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」
参考2:国税庁「法人番号公表サイト」
社会的にマイナスなイメージのある名称
たとえインパクトがあっても、社会的にマイナスなイメージのある名称は避けましょう。
やはり、社会的にも信用が得られる名前がベターです。
極端に長い名称
覚えやすい文字数は3~4文字と言われています。
ですから、よほど有名な言葉だとか、興味を引くエピソードに関連した名称だとか、語呂や語感が面白いものでない限りは、長い名前では覚えてもらえません。
税務署から目を付けられてしまう名称
これは、名づけ方ではなく、同一住所で複数の屋号を持つ場合の注意事項です。
自宅を事務所にしていて同居する家族も別の屋号で事業をしている場合、複数の屋号でそれぞれに事務所賃料や光熱費を控除していると税務署から二重帳簿の疑いをかけられます。
しっかり別々の事業者であることがわかるようにしましょう。
縁起が良いとされる屋号の特徴
姓名判断と同じように、屋号や社名も縁起をかつぎたくなるもの。
屋号にまつわるジンクスやイメージを紹介します。
画数、文字数
5、7、8、9、15、17は縁起の良い画数であるといわれており、これらの画数に相当する屋号や社名には、ソニー、イオン、ローソン、ユニクロ、セブンイレブン、楽天などがあります。
また、文字数3~4は語呂が良くて、覚えやすいといわれています。
ヒットするといわれている音
コーヒー業界の濁音(スターバックス、タリーズ、boss)や、芸人コンビ名の「ン」(ダウンタウン、ナインティナイン)がつく屋号は、ヒットするといわれています。
その他にも、濁点(゛)や半濁点(゜)がつくと、インパクトがあり、耳に残りやすいとする説もあります。
濁音では力強さ、半濁音では面白さや楽しさを、人は感じるようです。
同様に、カ行は発音するときに「ック」と、一度のどで音を詰まらせてから発するのでスピード感が出ます。
その他にも50音には以下のような特徴があります。
- サ行…さわやかな印象
- タ行…力強い印象
- ナ行…親しみやすい印象
- ハ行…ふわふわほんわかした印象
- マ行…甘えたくなるような安心感がある印象
- ヤ行…やわらかくゆったりした印象
- ワ…エネルギーが勢いよく広がるような印象
あなたの事業のイメージには、どんな音が似合いますか?
屋号の響きがサービスのイメージとリンクするように、音選びにこだわってみてはいかがでしょうか。
まとめ
屋号について、実務面から名づけ方のポイント、避けたほうが良いポイント、ジンクスを紹介しました。
ご自分の事業につける屋号のイメージは湧いてきたでしょうか?
まず、屋号は看板や名刺、書類やハンコ、銀行口座名義など、ビジネスシーンのあらゆる場面で人目に触れることをお伝えしました。
屋号は、ブランドイメージを伝えるのにとても有効かつ重要とわかりましたね。
また、屋号の登録方法や、変更方法をお教えしました。
併せて、屋号はいくつ作ってもいいし、逆につけなくてもいいことも覚えていただけたと思います。
屋号のつけ方としては、次のようなつけ方があることも紹介しました。
- 店名、事務所名
- ペンネーム
- 旧姓
- 英数字の入った名称
- 覚えやすいのは3~4文字
- 業務内容が分かる名称のほうがいい
- 他の屋号と似ていても、問題はない
逆に、以下のような屋号はNGです。
- 「会社」、「Co.」など法人格を示す名称や、「銀行」など特定業種の名称
- 商号登記または商標登録済みの屋号
- 社会的に悪いイメージがある
- 長すぎる
いかがでしょうか。
イメージが固まってきましたか?
屋号は長く使うものですから、まず自分が愛着を持って、わくわくしたり、元気が出たり、安心したり、幸せを感じられる名称を見つけてください。
それがきっと、あなたにとってベストの、個性が光った屋号になるはずです。

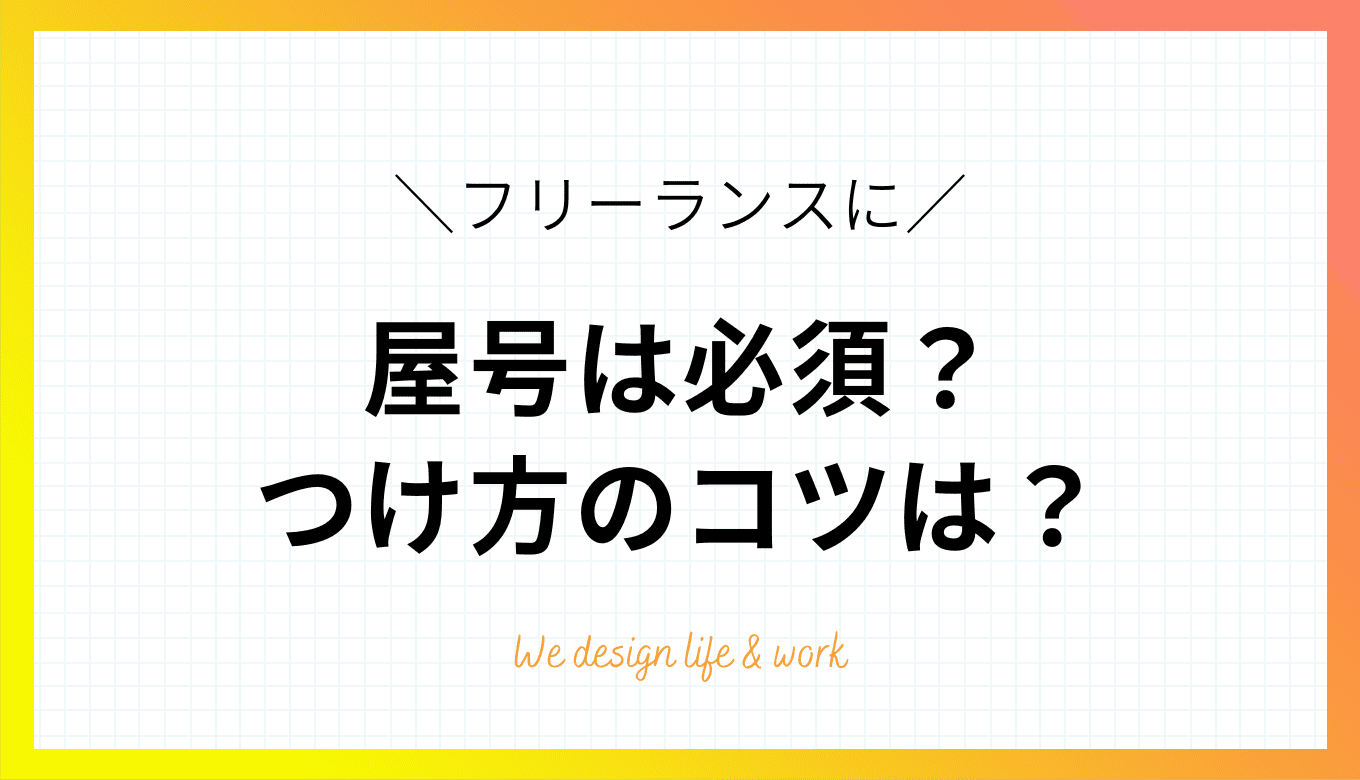
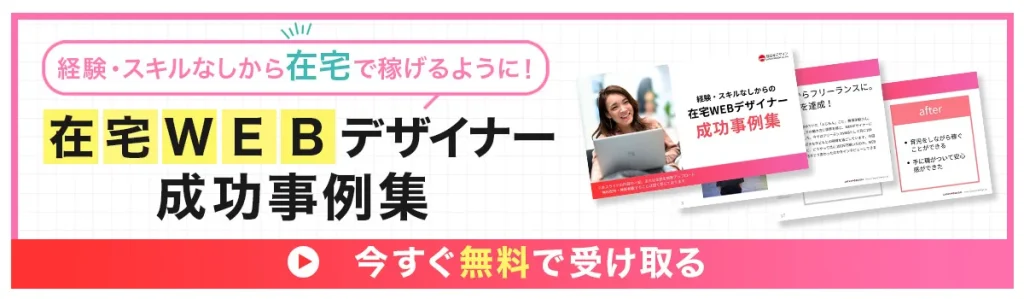
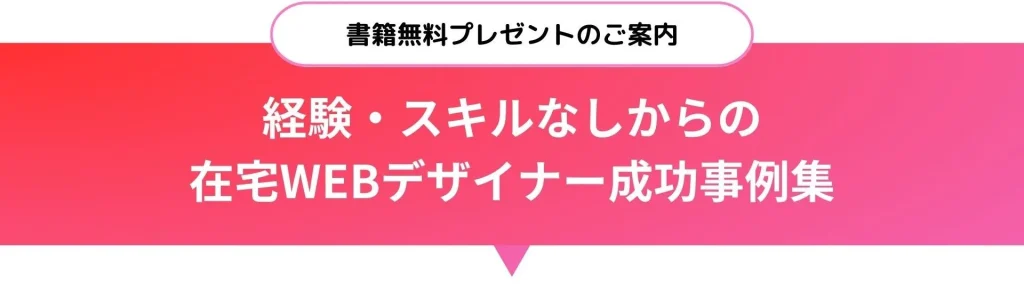
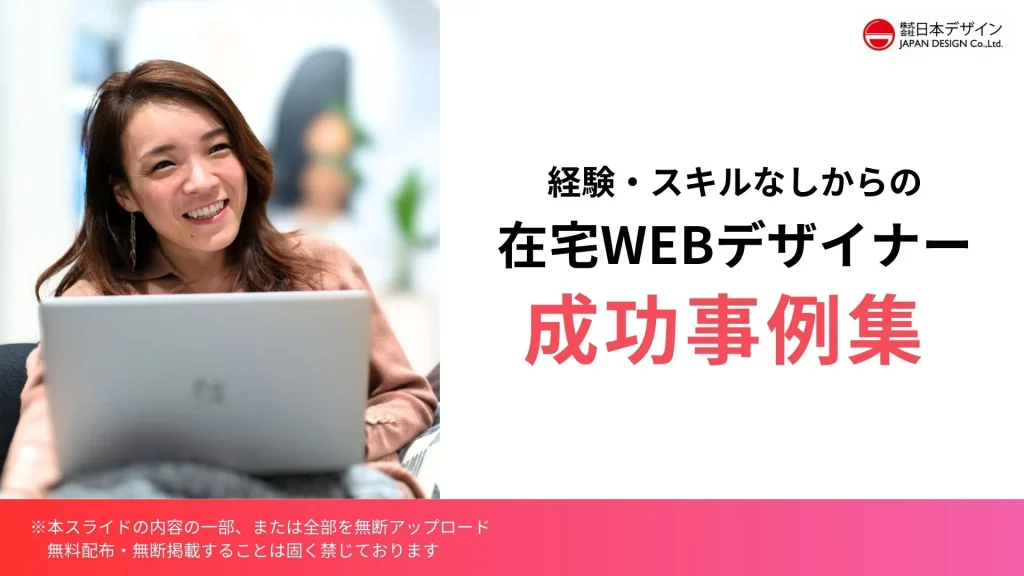
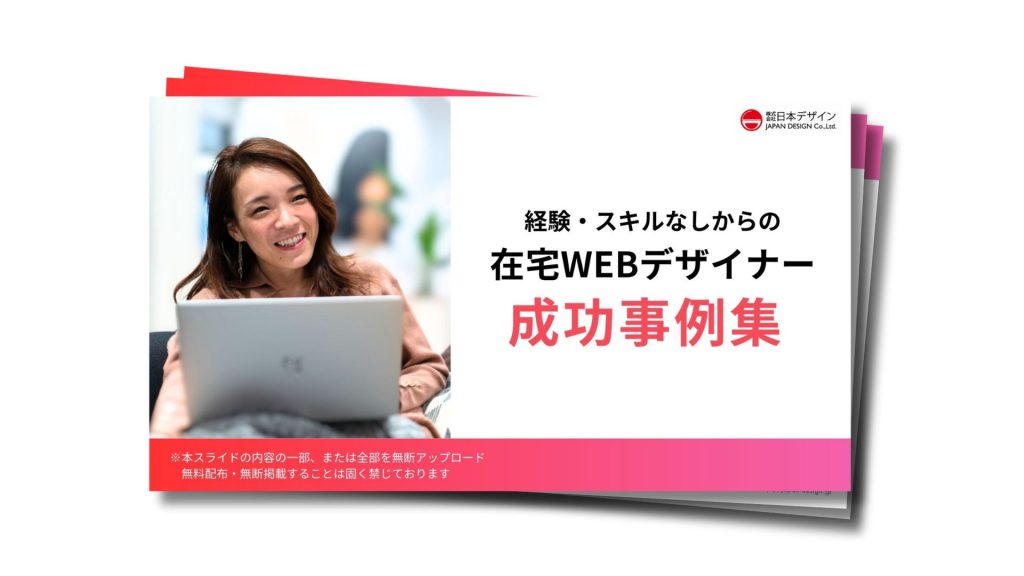
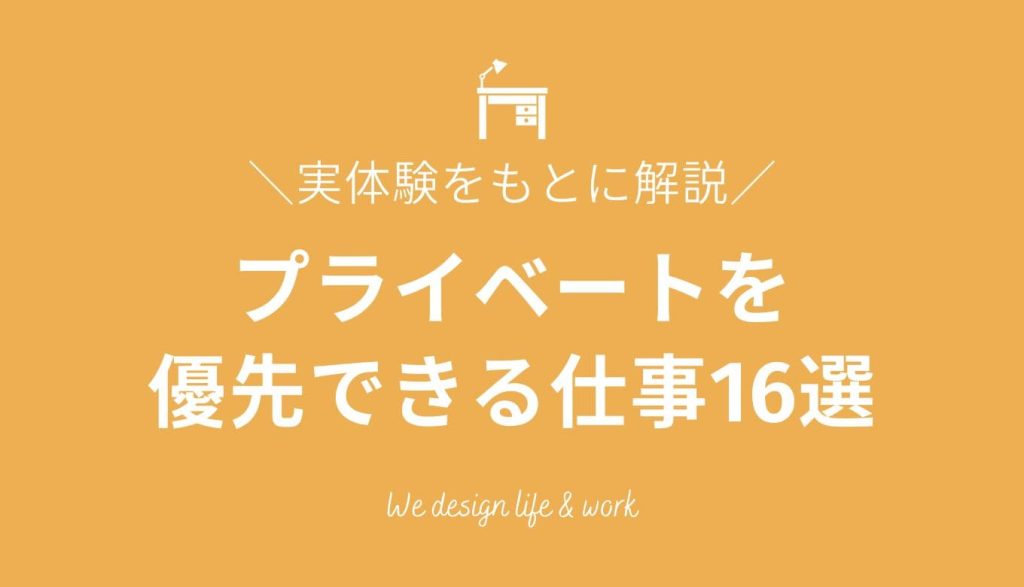
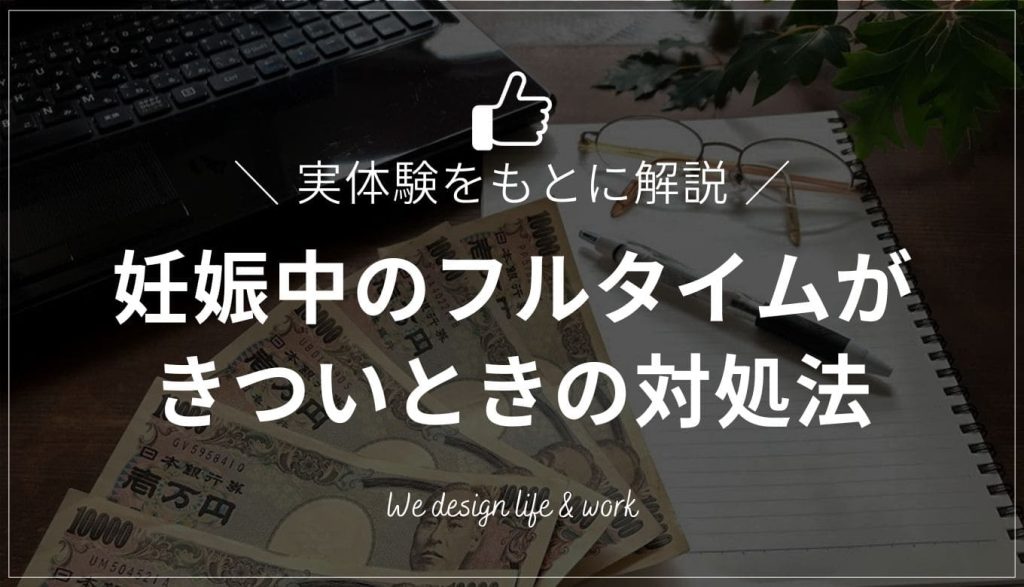
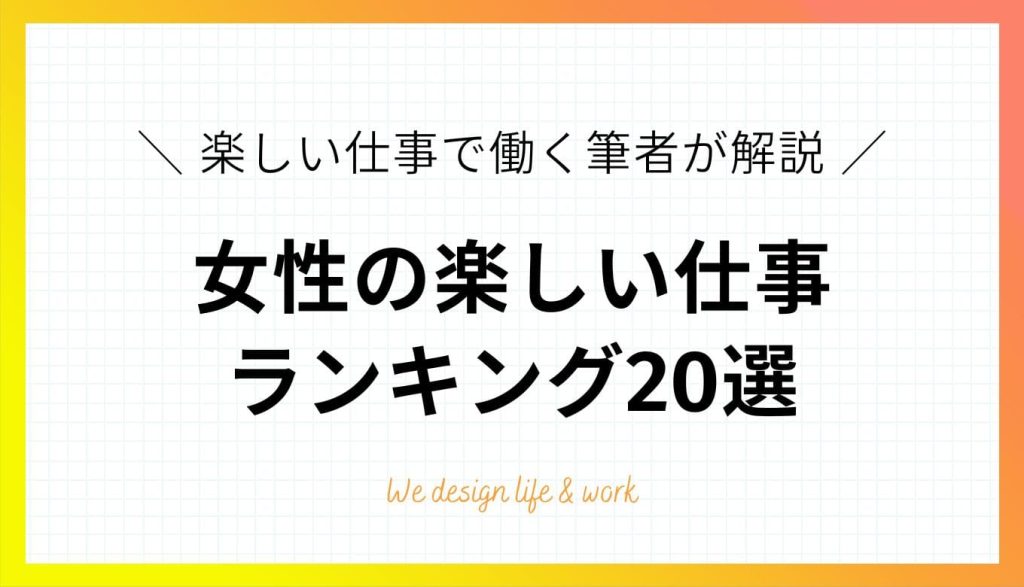
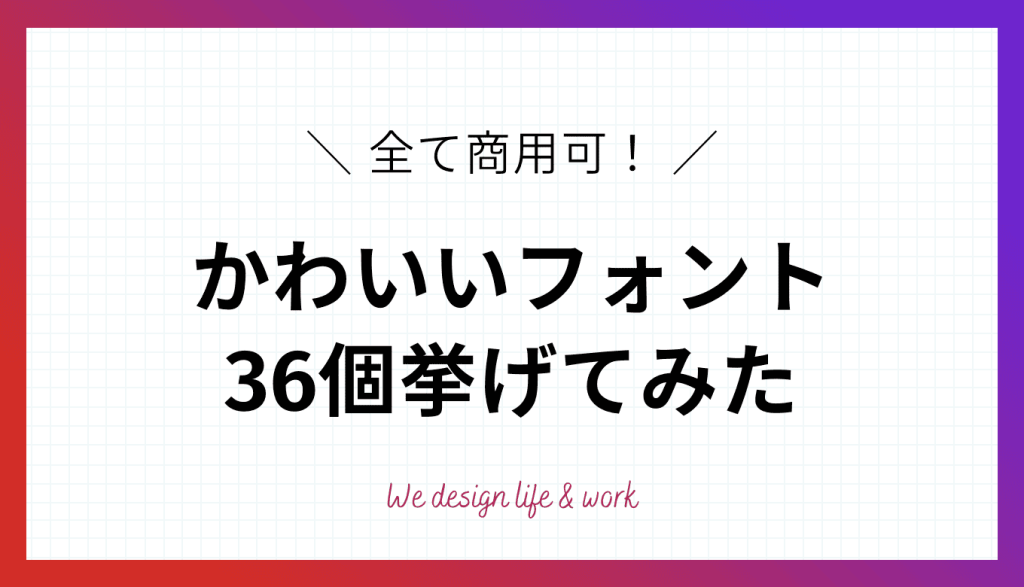

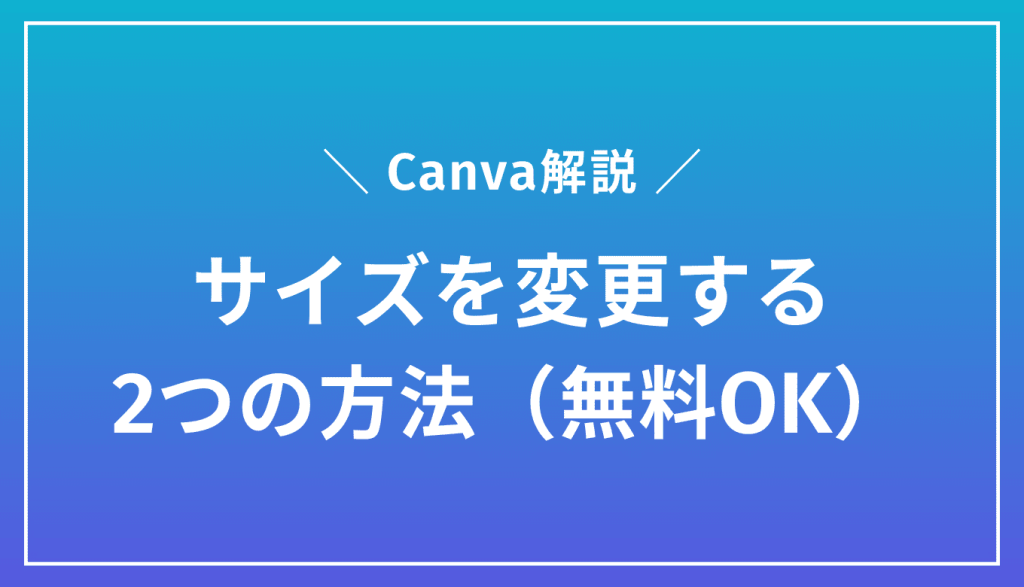
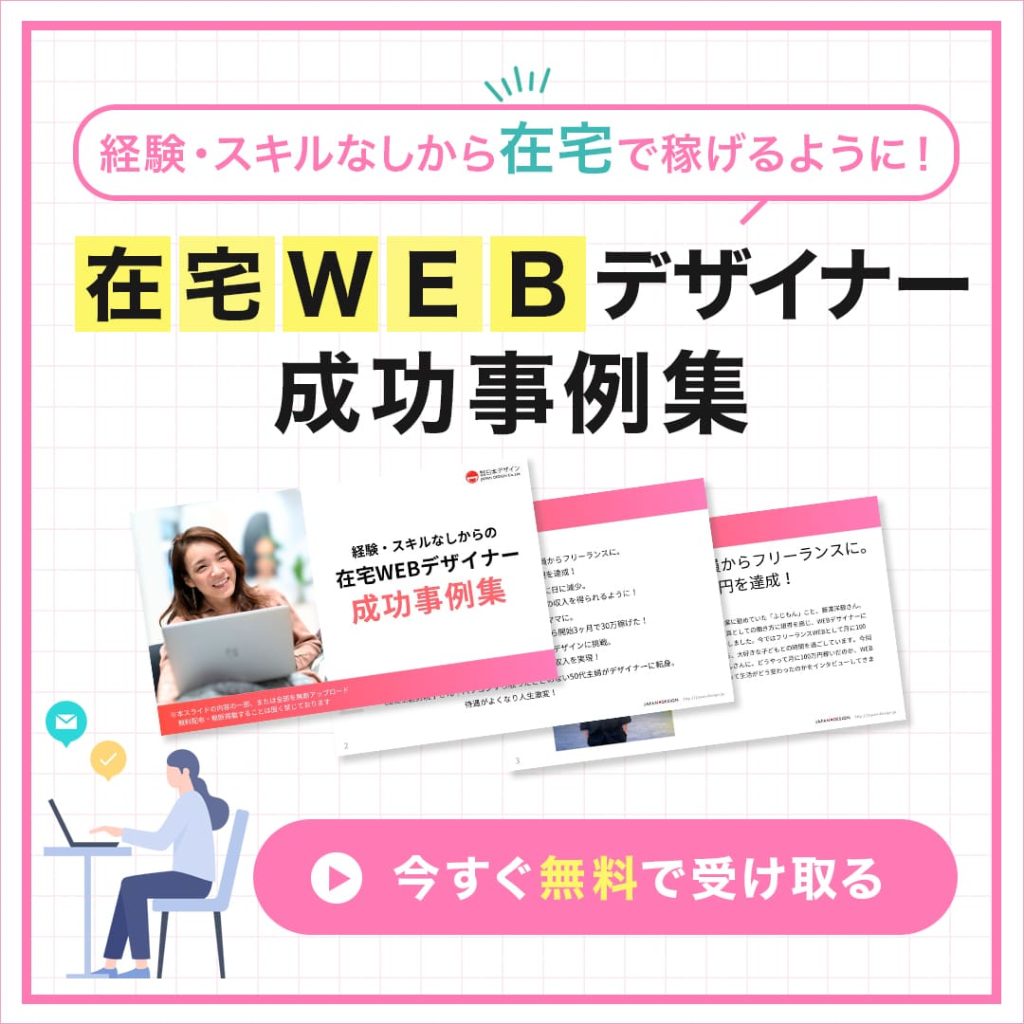

質問や感想があればご記入ください