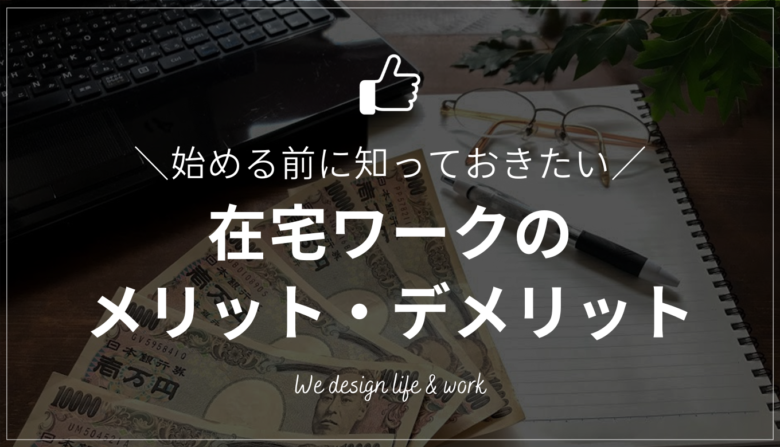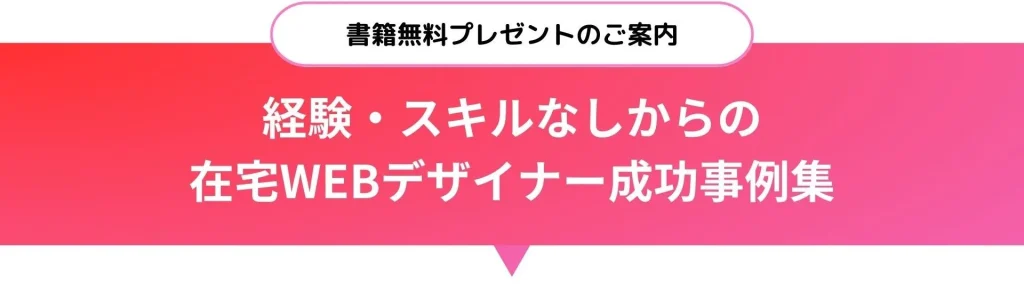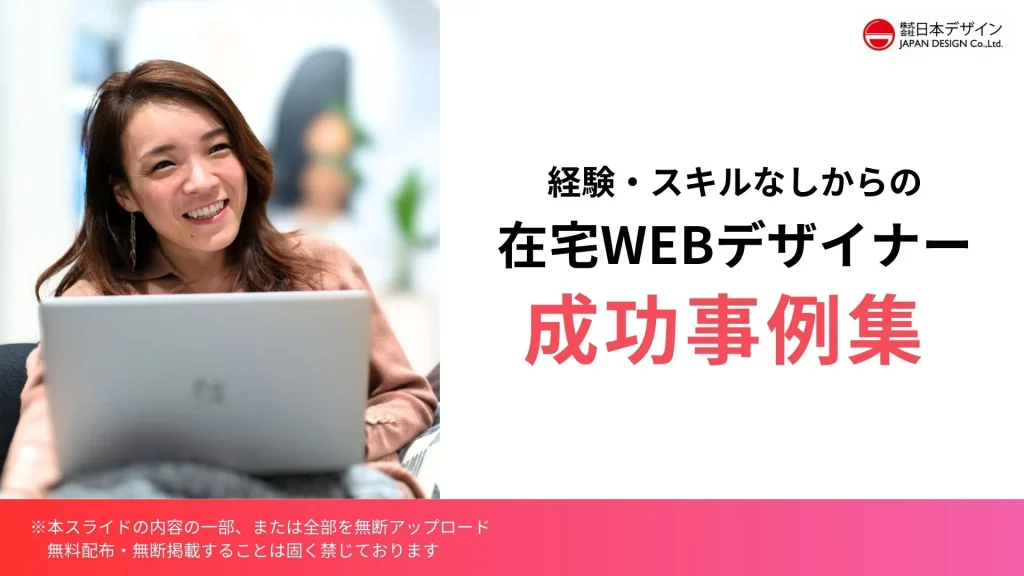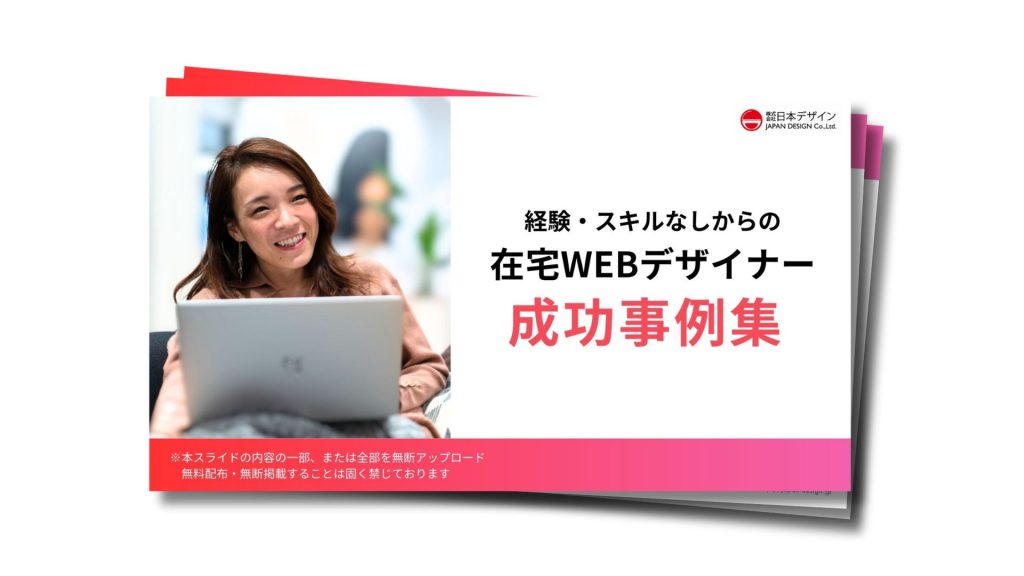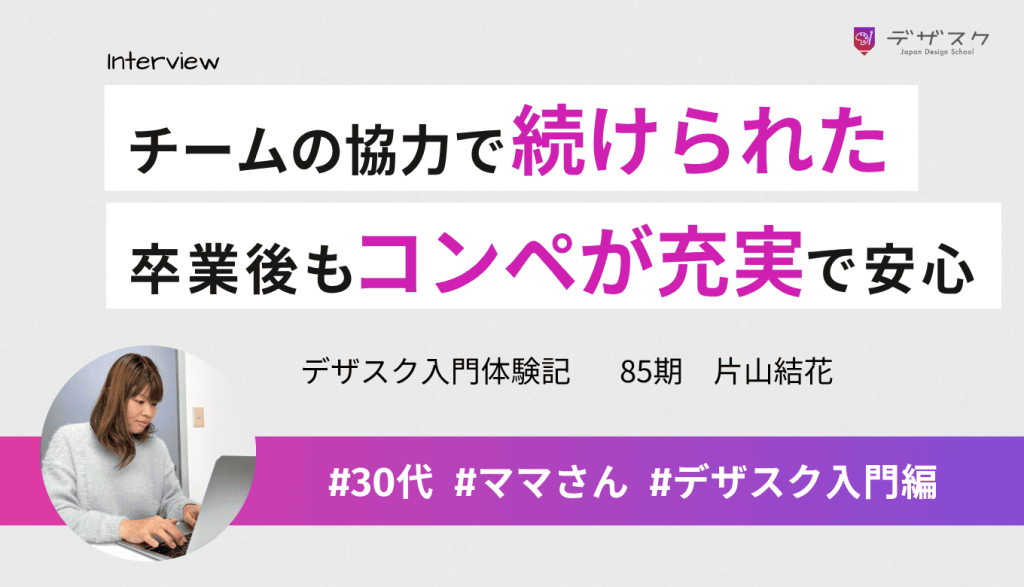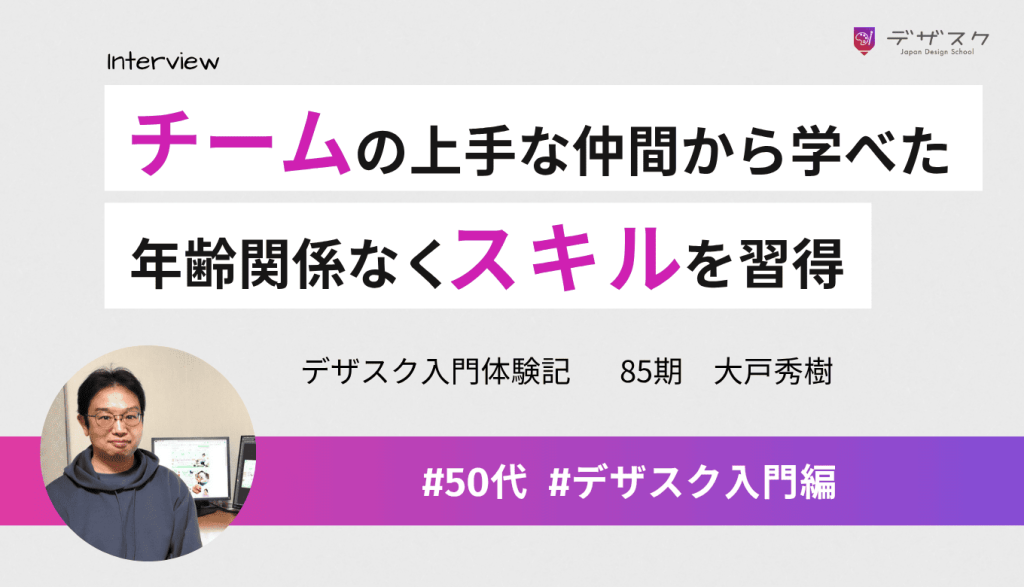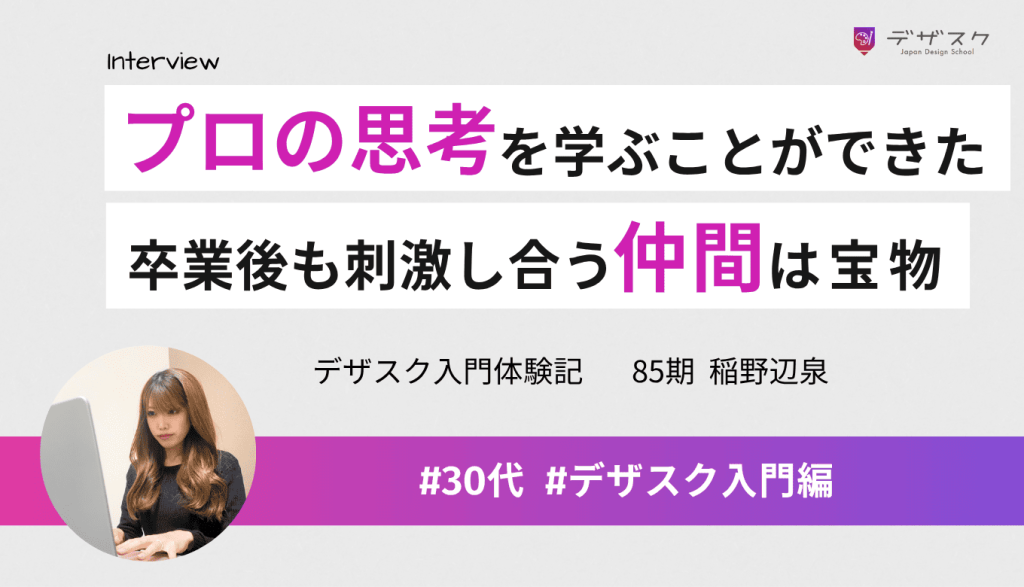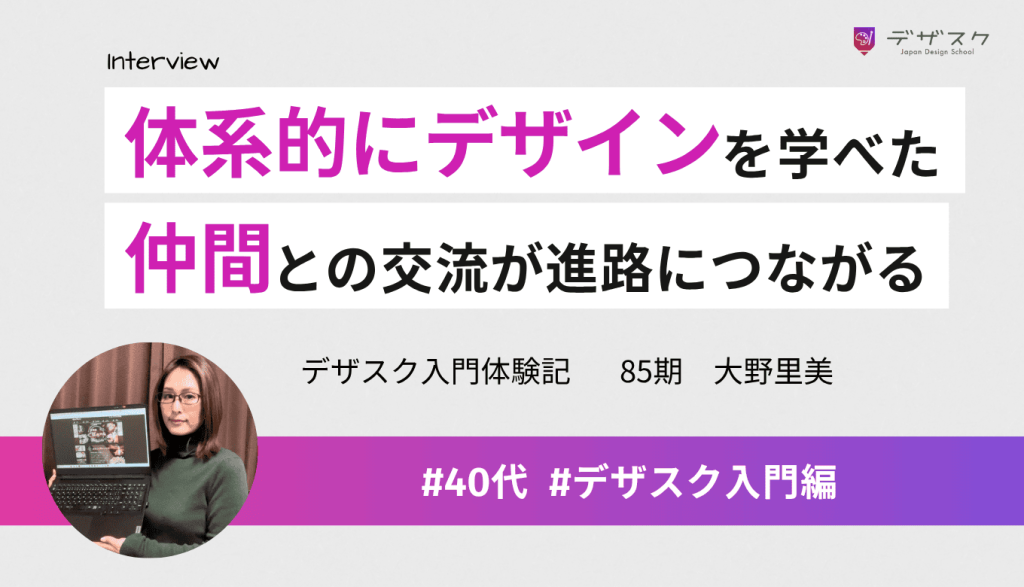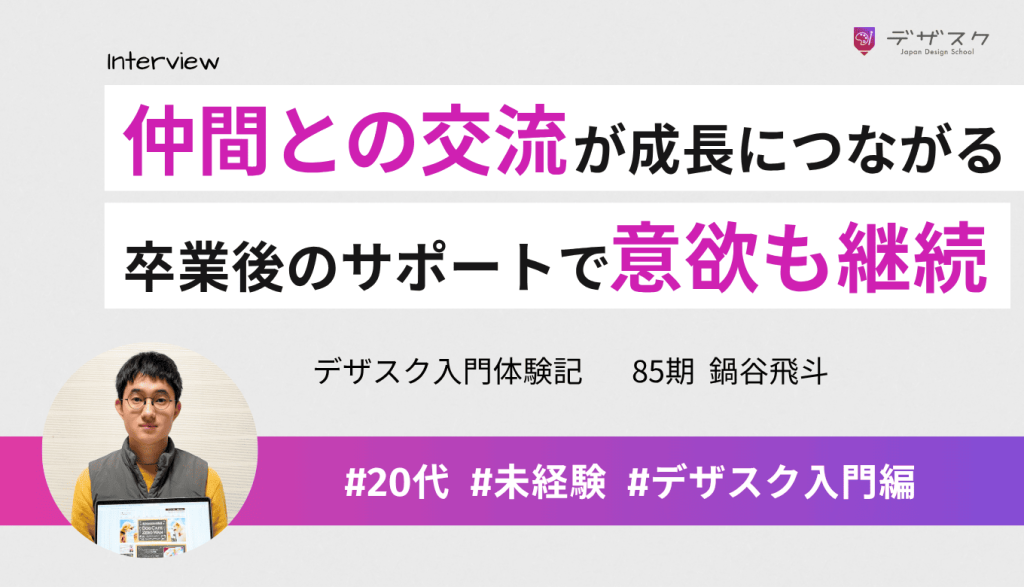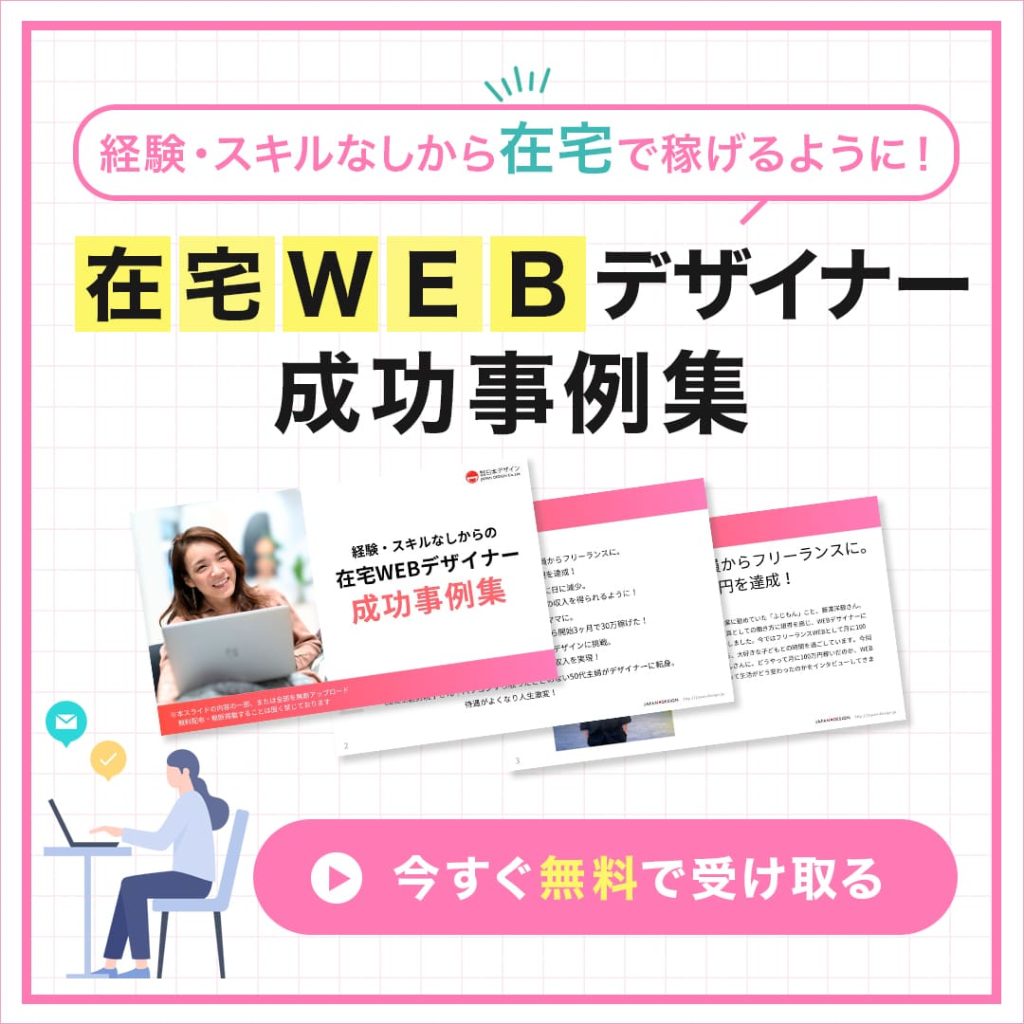コロナ禍や働き方改革に伴い、近年多くの企業で在宅ワークの導入が広がっています。
自宅で働くというスタイルは仕事とプライベートを両立でき、自由度が高いというイメージを持つ方も多いのではないでしょうか?
しかし在宅ワークには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも挙げられます。
そこで本記事では在宅ワークのメリットとデメリットについて詳しく解説し、デメリットの克服方法についても紹介します。
在宅ワークに興味のある方は、ぜひ参考にしてください。
【お知らせ】
3,500名以上の人生を変えるキッカケになった「好きなことで生きていく!WEBデザイナーという働き方セミナー」では、
などをお伝えしています。今だけ無料で開催しているので「WEBデザインの学び方がわからない」「WEBデザイン業界について知りたい」という方はぜひご参加ください。
>>詳しくはこちら
「在宅ワーク」のメリット5選
まずは「在宅ワークのメリット」を紹介します。
メリット1. 通勤時間が無くなる
日本人の平均通勤時間は片道約40分、労働時間の約1割を占めると言われています。
在宅ワークの場合はその1割の通勤時間が不要になるため、その分だけ仕事やプライベートに使える時間が多くなります。
通勤のストレスや疲労が軽減され、ワークライフバランスの向上にもつながるでしょう。
メリット2. 勤務地を自由に選べる
在宅ワークでは、自宅だけでなくカフェやコワーキングスペースなど、好きな場所で仕事をすることができます。
会社の異動に合わせて住まいを変える必要もなく、インターネット環境さえ整っていればどこでも働けることが在宅ワークのメリットです。
極端な例を挙げると旅行先での仕事も可能なので、プライベートを大事にしながら働きたい方にはうってつけかもしれません。
メリット3. 「ワークライフバランス」を保ちやすい
在宅ワークでは家事や育児を挟みながら仕事ができるため、仕事とプライベートの両立がしやすくなると言われています。
たとえばリモートで朝礼に出た後に顧客からのメールを確認し、急ぎのものがなければ家事を消化してから仕事を開始することができます。
他にも午後になって子供を迎えにいく場合、30分休憩をとって子供を迎えに行き、そのまま業務を後ろに30分伸ばして調整することもできるでしょう。
このように時間の調整がしやすいことが在宅ワークのメリットなので、出勤していた頃よりははるかに「ワークライフバランス」が取れた働き方が可能になります。
メリット4. 作業に集中しやすい
多くの人が集まるオフィス内で仕事をしていると、誰かに話しかけられたり、電話対応をしたりと集中力が途切れてしまうシーンも多かったのではないでしょうか。
しかし在宅ワークでは、代表電話への入電は出社しているメンバーが取ってくれ、話しかけられる内容もチャットに代わることでいつでも対応できるようになります。
集中力を途切れさせる要因が少なくなることで、集中力が上がって業務の生産性を上げられることも在宅ワークのメリットと言えるでしょう。
メリット5. 対人関係のストレスを軽減できる
在宅ワークでは、前述の通りメインのコミュニケーションがチャットになるため、人の目線であったり、誰かにずっと気を遣うなどのストレスから解放されます。
職場ストレスの原因の大半は人間関係だと言われている現代において、人と距離をとって働ける環境は理想的ではないでしょうか。
もちろんコミュニケーションが0になるわけではないので、新たに「チャットやメールで連絡する場合の気遣い・マナー」「WEBミーティングのマナー」は必要になってきますが、それでも対面の頃に比べれば気にする点は少ないと言えます。
対面のコミュニケーションが苦手な人にとって、在宅ワークは理想的な環境となるでしょう。
「在宅ワーク」のデメリット5つと対策
続いては、在宅ワークのデメリットを5つ紹介します。
あわせて「各デメリットへの対処法」も紹介するので、もし現在も在宅ワークをしていてデメリットに悩んでいる方、デメリットに恐怖を感じて在宅ワークに踏み出せない方は対策の方も参考にしてみてください。
デメリット1. 仕事環境は自分で整える必要がある
在宅ワークでは自分の家がそのまま職場環境になるため、Wi-Fi環境やデスク、椅子などは全て実費で整えなければいけません。
環境によっては部屋で仕事ができず、リビングにパソコンを持ってきて働かなければならない方もいるのではないでしょうか。
「働く環境なんて、パソコン1つあれば十分」と考えている人もいるかもしれませんが、毎日仕事をしていると徐々に不便さを感じたり、体の不調が出てくることもあるので甘く見ない方が良いでしょう。
このデメリットを解決する手段としては、以下の対策が挙げられます。
- 厚生労働省「自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備」を参考にする
- 家族に協力してもらい、リビングでも働きやすい環境を整える
体に負担が少ない環境を整える場合は、厚生労働省が出している「自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備」を参考にし、集中力を切らしにくい環境を整えましょう。
また、子育て中であったりパートナーも在宅勤務などをしている場合は、家族(子供の預け先として自分やパートナーの両親も含む)の理解と協力を得られるように根回しをしておきましょう。
デメリット2. 仕事とプライベートの境界線が曖昧になる
在宅ワークの場合は「職場=自宅」になるため、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりやすい傾向にあります。
「終業」の認識も曖昧になるため、ついだらだらと仕事を続けたり、プライベートの時間をメールやチャットのチェックに充てることも少なくありません。
仕事とプライベートの境界線が曖昧になると、仕事に集中できなくなってしまうでしょう。
このデメリットを解決する手段としては、以下の対策が挙げられます。
- プライベートの時間は業務に手を出さない環境を作る
- 1日のスケジュールを可視化し、業務時間内に仕事を終えるよう努力する
- 家族に協力してもらい、プライベートの時間へ引き戻してもらう
業務は業務時間に全て終わらせるようにする、就業したら社用スマホやパソコンは電源を落として触らない仕組みを作る、それでも仕事に手を出そうとしたら家族に無理やりプライベートに引き戻してもらうなどの対策をとることが有効な手段です。
デメリット3. 気持ちの面でオン・オフの切り替えが難しい
先述したように「仕事とプライベートの線引きが難しい」ことは在宅ワークをする上でとても切実な問題です。
それは業務面だけでなく、気持ちの面でも同様のことが言えます。
プライベートモードの時に仕事の連絡が来て急に仕事モードがオンになったり、お昼ご飯を食べて少し横になったせいでプライベートモードがオンになってしまったりと、スイッチの切り替えが難しくなることがあります。
このデメリットを解決する手段としては、以下の対策が挙げられます。
- 仕事時は通勤時と変わらない服装にし、業務終了後は着替える
- 業務終了後は仕事に関するものを遠ざけて目に入れない
意識の改善で問題を解決することはむずかしいため、上記のように恰好や仕組みで何とかスイッチのオンオフを切り替えることが有効です。
デメリット4. コミュニケーションが希薄になる
先述したように、在宅ワークは「対人関係のストレスを軽減できる」というメリットがある一方で「対面でのコミュニケーションが不足しがち」というデメリットも挙げられます。
オフィスでの対話であれば一瞬で確認できていたことも、在宅ワークの場合はメールやチャットで確認になるためレスポンスが遅くなります。
また、チャットやメールだと必要なやり取りしかしなくなるので、雑談がなくなり孤独感を感じてしまう人もいるでしょう。
このデメリットを解決する手段としては、以下の対策が挙げられます。
- チャット以外のツールでスケジュールや進捗確認をおこなう
- ZOOMでの交流会などを積極的におこなう
- 些細なことでも「ありがとう」などの反応をしっかり送る
チャット以外のツールを使うことで「離席中」などの状況を共有してやり取りをおこないやすくし、チャット以外でも交流する機会を作り、ちゃんとやりとりの終わりには「ありがとう」などの言葉を絶やさないようにすることがデメリット解消への糸口です。
デメリット5. 家に引きこもりがちで運動不足になる
これは切実な問題ですが、在宅ワークでは運動する機会がほとんどありません。
出勤時は通勤で最低限は動いていた運動すらもなくなってしまうので、普段から運動する習慣がない人は「生活習慣病」に罹患しやすくなります。
特に運動しなくなると「集中力」が低下するので、なんとか運動する機会を作ることが重要になってきます。
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
在宅ワークと相性の良い職種とは?
ここまでは、既に企業から言い渡されて在宅ワークをしている方・これから在宅ワークに切り替わる方に向けてメリット・デメリットを紹介してきました。
しかし本記事を読んでいる方の中には、以下のような方もいるのではないでしょうか。
- 今の会社で在宅ワークはありえない。在宅ワークができる職種に転職したい
- いっそ独立して、フリーランスとして在宅ワークを始めたい
ここからはそんな方に向けて、在宅ワークと相性が良い職種を紹介していきます。
※特にパソコン1台あれば仕事ができるIT・WEB業界が在宅ワークとは相性が良いため、IT・WEBに関する職種を中心に解説します。
在宅ワークと相性が良い職種1:エンジニア・プログラマー
エンジニアやプログラマーは在宅ワークとの相性が抜群です。
エンジニアやプログラミングの職域は広く、システム開発やIoT・AIの分野、WEB制作・アプリ制作Iのプログラミングなど多岐に渡ります。
スキルとパソコンがあれば自宅で作業ができるので、まさに在宅ワーク向きと言えるでしょう。専門職なので在宅ワーカーの中でも高い年収を狙える分野です。

在宅ワークと相性が良い職種2:WEBデザイナー
WEBデザイナーも在宅ワークに向いている職種だと言えます。
WEBサイトやバナーなど、インターネット上のあらゆるデザインを担当するのがWEBデザイナーです。
制作物はオンラインで共有でき、受注から納品まで一括してインターネット上で完結させることが可能となるため、在宅ワークがイメージしやすい職種なのではないでしょうか。
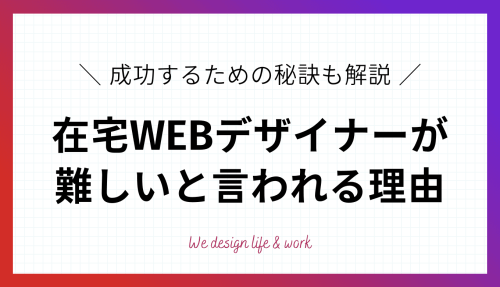
在宅ワークと相性が良い職種3:WEBライター
WEBに関連する業務といえば、WEBライターも在宅ワークと相性が良い職種です。
WEBライターはインターネット上にあるあらゆる文字媒体(オウンドメディア記事・ブログ記事など)を作成する仕事です。
また、それらの執筆に必要な情報をネットや書物から収集することも仕事になるため、オンラインとの相性が抜群だと言えます。
取材など客先に出向く必要がなければ、パソコンで執筆してオンラインで納品することが可能なので、圧倒的に在宅ワークには向いているでしょう。
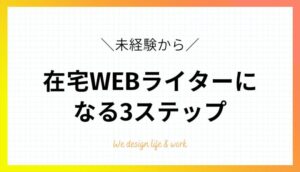
在宅ワークと相性が良い職種4:動画編集
動画編集の仕事も、在宅ワークとの相性が良いと言えます。YouTubeを始めとするSNSでの動画需要が高まり、PRのために動画コンテンツに乗り出す企業も増えました。
企業のプロモーションやサービスや商品の広告、ウェディング動画から個人のYouTube動画などの需要が高く、今では「編集」がアウトソーシングされることも少なくありません。
動画編集ソフトを活用して動画を分割したり、テロップやBGMを入れるなど、YouTube動画なら趣味の延長程度のスキルで始められるので、初心者にもおすすめできる職種です。
在宅ワークと相性が良い職種5:オンライン事務
名刺などの顧客管理、アンケートや企業情報などのデータ入力、音声の文字起こしや商品の発送代行などを在宅で請け負うオンライン事務も最近では人気が出てきています。
在宅ワークの中では報酬が低めですが、Word、Excel、PowerPointなどoffice系ソフトの基本的操作ができ、タイピングのスピードに自信があるなら、量をこなした分だけ収入が得られます。
特に「人間関係に疲れて事務を退職したけど、オンラインなら直接人と関わらずに事務作業ができるから良さそう!」と感じる方にはおすすめかもしれません。
在宅ワークと相性が良い職種6:バックオフィス業務
バックオフィス業務とは、顧客と直接関わることのない社内業務です。
人事・経理・財務・法務・総務・庶務・営業事務に代表されるこれらの部署の仕事は、ペーパーレス化が進んだことで在宅ワークでもおこないやすくなりました。
それにより企業勤めの方が在宅ワークに切り替わるだけでなく、バックオフィス業務を業務委託先に任せる企業も増えてきています。
バックオフィス業務は事務作業が中心なので、チームというよりは1人で作業を進めることが多く、社内で完結する業務でもあるので、セキュリティ面がクリアできれば在宅ワークに適していると言えるでしょう。
在宅ワーカーになるための6つのステップ
ここからは、本格的に在宅ワークを始めるための具体的なステップを解説します。
Step1. ハード面(PC・通信環境)の環境を整える
先述の通り、まずは在宅ワークのための環境を整えていきましょう。
重要な点をチェックリストにしたので、準備をおこなう際に活用してください。
- Inter Core i 7以上のCPUが搭載されたノートPCを用意する
- ブルーライト対策を施す
- セキュリティソフトの契約をする(ウイルスバスター等)
- ネット環境を整える(移動が多いならポケットWi-Fiも可)
- ヘッドセット、WEBカメラ、デュアルモニターを購入する
Step2. 便利なオンラインツールを用意する
PCやネット環境が整ったら、次はオンラインツールを準備していきましょう。
これらも業種によって必要なものは変わるので、ここでは基本的に入っていた方が在宅ワークを円滑に進めやすいツールに絞って紹介します。
- メールソフト(Gmail・Outlookなどの仕事用アカウント)
- チャットツール(Chatwork・Slack・Teamsなど)
- オンライン会議ツール(ZOOM・Google Meet)
- Office製品(Word・Excel・PowerPoint)
- Googleドライブ、Googleドキュメント、スプレッドシートなど
どのツールを使用するかはクライアントや勤務先から指定されることがほとんどですが、ひと通りどのツールも使いこなせるようになっておきましょう。
Step3. 希望する就労形態を決める(雇用型/自由型)
職種を変更する方は、事前に「転職して在宅ワーカーになる」か「フリーランスになる」かを決めておきましょう。
※たとえ在宅ワークと相性が良いからと言って、企業に属する場合は研修として最初の半年~1年間は出社することがほとんどです。
なので転職する場合は先走ってStep1や2の準備をおこなわず、会社からの指示を待ちましょう。
フリーランスを選択する場合も、特にStep2の内容に関してはクライアントから指定があったり、そもそも特定のツールが使えることが応募条件になっているものもあるので、やはり一通りは使えるようにしておきましょう。
Step4. 専門性の高いスキルを身につけて稼げる職種を選ぶ
せっかく転職したりフリーランスになるのであれば、専門性の高いスキルを身につけて高収入を目指しましょう。
先述した【在宅ワークと相性の良い職種とは?】で取り上げた職種がそれにあたるので、気になる方はもう一度見返して、自分がなりたい職業を選んでみましょう。
IT・WEB系で必要なスキルは職業訓練校やオンラインスクールでも気軽に学べるようになったので、仕事を退職したうえで失業手当をもらいながら学習をしたい場合は職業訓練校を、スキマ時間で学習したい方はオンラインスクールを受講することをおすすめします。
Step5. 副業から始めてみるのもオススメ
転職にしろフリーランス化にしろ、いきなりフルタイムの在宅ワーカーに転身するのはなかなかハードルが高いものです。
「実際に始めてみないと在宅ワークが自分に合っているか分からない」
「在宅ワークに切り替えて思うように稼げなかったらたらどうしよう」
上記のような不安がよぎり、踏ん切りがつかずに迷っている人も多いでしょう。
それならまず、副業から始めてみるのがオススメです。副業であれば、パート・アルバイト感覚で始められ、副業フリーランスとして単発の案件を少しずつ経験しながら実績を積むことができます。
興味のある職種が見つかったら、副業から始めてみましょう。
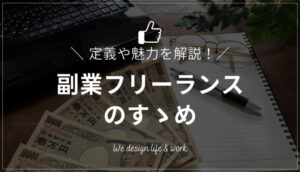
あわせて読みたい
在宅ワークに向いている人の特徴
ここまでの内容を読んでもまだ踏ん切りがつかない人のために、本項目では「在宅ワークに向いている人の特徴」を紹介します。
ここを読んで「向いていないかも……」と感じてしまう方には、おそらく在宅ワークは向いていません。
しかし、もし「これなら得意!」という部分が1つでも見つかれば在宅ワークをおすすめすることができます。
最後の判断基準として、以降の項目を読んでみてください。
特徴1.自己管理能力に優れている
在宅ワークをおこなう場合は「自己管理能力が優れているかどうか」が非常に重要視されます。
自己管理能力が低いと「今日はサボってしまおう」「納期も送らせて良い」などと自分に甘い判断を下してしまい、最終的には稼げない在宅ワーカーになってしまいます。
在宅ワーク中は自分を叱責してくれる上司もいないため、自分でスケジュールを組んで目標を設定し、自発的に動ける人こそが在宅ワークに向いていると言えます。
特徴2.クライアントに「報・連・相」がしっかりできる
在宅ワークでは、メールやチャットなどのツールを介してコミュニケーションを取ることになります。
そのため、こまめな「報・連・相」は必要不可欠です。細かい報告を怠ると、仕事の進捗状況が把握しにくくなり、トラブルが発生するリスクが高まるだけでなくトラブル時の対応にも遅れが出てしまうかもしれません。
クラウドソーシングサイトで仕事をとっている場合は、企業からの評価で低い点数が付けられてしまい、今後の案件獲得に影響してしまう場合もあります。
なので、些細なことでも報告・連絡・相談を怠らず、円滑なコミュニケーションを図ることができる人が在宅ワークに向いていると言えます。
特徴3.コミュニケーションの希薄さが気にならない
在宅ワークはオフィスで働く場合と比べて、対面でコミュニケーションを取る機会が極端に減るため、人間関係の希薄さが気になる人もいるのではないでしょうか。
そこが気になる人にとっては在宅ワークは向いていませんが、反対に人間関係の希薄さがあまり気にならない人は、仕事に集中できる理想的な環境を手に入れられるでしょう。
また「対面ではコミュニケーションが苦手だけど、チャットやメールならマメに連絡が取れる」という方にとっても在宅ワークは向いているかもしれません。
※在宅ワークになればコミュニケーションをとらなくても良いわけではありません。あくまで「コミュニケーションの取り方が変わるだけ」という認識を持っておきましょう。
まとめ|在宅ワークのメリット・デメリットは向き不向き
本記事では在宅ワークのメリット・デメリットを中心に解説してきましたが、正直に言えばこれらは「自分に向いているかどうか」だけの話です。
どちらが良い悪いの話ではないため、あくまで自分の理想とする働き方のために「在宅ワーク」か「出社する働き方」かを選択してみましょう。
あなたの選択が、これからのあなたの人生にとって良いものになることを祈っています。