副業するときに気になるのが社会保険の取り扱い方。
「払わないといけないの?」と疑問を持っている方も多いと思います。
結論、「雇用契約を結ぶ」かつ「一定の条件を超える」と、副業でも社会保険を支払う必要があります。
そこで、この記事では副業する人(会社員と個人事業主のどちらも)が、どんなときにどの社会保険を支払わないといけないかを詳しく解説していきます。
また、「社会保険に加入しなかったときの罰則は?」「社会保険に入って副業がバレることはある?」といった疑問も解消していきます。
この記事を読めば、少しややこしい社会保険のことも、スッと理解できるようになります。
ぜひ、最後まで読んでみてくださいね。
【お知らせ】
2000名以上の人生を変えるキッカケになった「好きなことで生きていく!WEBデザイナーという働き方セミナー」では、
などをお伝えしています。今だけ無料で開催しているので「WEBデザインの学び方がわからない」「WEBデザイン業界について知りたい」という方はぜひご参加ください。
>>詳しくはこちら
会社員と個人事業主が加入する社会保険

副業するときにまず把握しておくべきなのが、会社員と個人事業主がそれぞれどんな社会保険を支払う必要があるのかということです。
ここでは、それぞれが支払うべき社会保険を紹介していきます。
会社員が加入する社会保険
ではまず、会社員が加入する社会保険を紹介していきます。
※会社員の場合、基本は会社が社会保険の手続きをしてくれるので、自分で何かする必要はありません。
雇用保険
会社員の場合は雇用保険に加入することになります。
雇用保険は雇用されている人を守るための保険で、失業手当や再就職手当、傷病手当などを受けられます。
他にも、育児休暇の間や職業訓練を受けるときに必要な給付金が提供されたりと、従業員を安定的に雇用できるように作られたのが雇用保険です。
健康保険
保険料を毎月納めることで、病気やケガなどの医療費の自己負担が30%になったり、手術の費用を一部負担してくれたりする保険制度です。
納める保険料は給料の金額で決まり、保険料の半分を会社が負担してくれます。
厚生年金保険(国民年金保険)
老後に年金を受給できたり、障害を負ったときや加入者が死亡したときに遺族が年金を受け取れたりするのが年金保険です。
会社員は国民年金と厚生年金の2つの保険に加入することになり(厳密には厚生年金のなかに国民年金が含まれています)、厚生年金の保険料は会社と折半です。
国民保険の保険料は定額で、厚生年金は健康保険と同じく給料に応じて金額が決まります。
介護保険
介護が必要になったときに給付金を受け取れる保険です。
給料の金額によって保険料が変わり、会社が保険料の半分を負担します。
介護保険は40歳以上から加入する義務があり、40〜64歳は健康保険料と併せて納付し、65歳以上は年金から引かれて市区町村に納めることになります。
労働者災害補償保険(労災保険)
労働者を守るものである、労働者災害補償保険も会社員が加入できる保険です(次から労災保険と記載)。
勤務中や通勤途中に事故・ケガをした場合、病院での治療や入院の費用に対して給付がもらえます。
会社が全額負担してくれるのが特徴です。
個人事業主する社会保険
続いて個人事業主が加入すべき社会保険について解説していきますね。
国民健康保険
個人事業主は、国民健康保険に加入します。
会社員が加入する「健康保険」とは別物で
- 自分で手続きをする必要がある
- 配偶者や子どもに持たせることができない
といったことが特徴です。
保険料は配偶者を含めた世帯の収入によって決まり、保険料は全額負担になりますが、確定申告のときに所得から控除されます。
国民年金保険
個人事業主の場合は、厚生年金保険に入ることはできず、国民年金保険に加入することになります。
内容は厚生年金保険と同じように、定年後の年金受給がされるものですが、厚生年金保険に比べて受給額が10万円ほど低いです。
年金を増やすには国民年金保険の他に、付加年金や国民年金基金を支払う必要が出てきます。
下の記事で国民年金保険について詳しく解説しているので気になる方は、読んでみてくださいね。
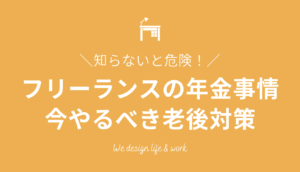
介護保険
介護が必要になったときに、給付金を受け取れる介護保険ですが、基本的に個人事業主は加入できません。
ただ、法人の代表となった場合は話は別。
会社員と同じ扱いで40歳以上から加入義務があり、年金保険と同時に支払わなければいけません。
会社員と違い、保険料は全額自己負担なのでその点は注意しましょう。
労働者災害補償保険(労災保険)
個人事業主の場合、少し特殊な扱いを受けるのが、勤務中の怪我に手当ができる労働災害補償保険(労災保険)です。
個人事業主は労働者ではないので、原則労災保険は適用されません。
しかし、1人親方やIT系フリーランスなど、一部の特別な人のみ、労災保険に加入することが認められています。
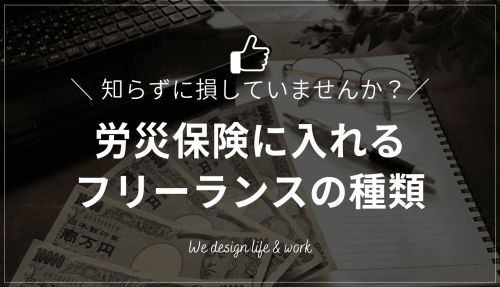
副業で社会保険はどうなる?二重になって増えるの?

結論、副業をする場合、副業で雇用関係を結ぶと(アルバイトやパートをすると)二重で社会保険を支払う必要があります。
会社員と個人事業主で加入すべき、社会保険が違うので、それを分けて解説しますね。
会社員が副業する場合
会社員が副業をする場合、次の4つを支払わなければいけない可能性があります。
- 介護保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 労働者災害補償保険(労災保険)
このうち労災保険は必須で、残りの3つは下のいずれかの条件に当てはまる場合に、支払いの義務が生じます。
- 勤務先が社会保険の適用対象となる事業所
- 1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
- 下記の5つの条件を全て満たしている
・1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
・1か月の賃金が88,000円(年収106万)以上
・1年以上継続して雇用の見込みがある
・被保険者の従業員が500人を超える事業所
・学生でないこと
※適用対象になる事業所は日本年金機構のホームページで検索ができます
ちなみに健康保険と厚生年金保険を二重で加入する場合は、自分で手続きをする必要があります。忘れないように注意しましょう。
個人事業主(フリーランス)が副業をする場合
個人事業主(フリーランス)が副業で雇用関係を結ぶ場合は、次の条件を満たすと、お伝えした4つに加えて、雇用保険に入る必要もあるので注意しましょう。
- 1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
- 31日以上継続して雇用の見込みがある
参考1:厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」
参考2:厚生労働省「社会保険(厚生年金保険・健康保険)への 加入手続はお済みですか?」
参考3:厚生労働省「従業員数500人以下の事業主のみなさま」
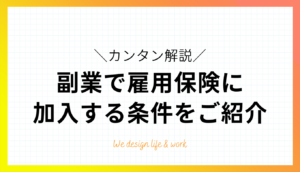
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
副業で社会保険に加入しなかったときの罰則

条件を満たしている場合、健康保険と厚生年金保険の加入は必須です。
マイナンバー制度により、該当者が社会保険に加入しているか、国は簡単に把握できるようになりました。
正当な理由もなく加入をしない場合「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と健康保険法第208条で定められています。
また、あとになって保険に未加入であることがわかると、最大で2年間分の保険料をさかのぼって支払う可能性があるので注意が必要です。
もし上記の保険に加入したくないときは、加入条件に該当しないように勤務時間や日数を調整しましょう。
ただし、保険料は納めた分、将来受給できる年金が増えるメリットがあります。
副業で社会保険に入ると副業はバレる?

社会保険に加入すると、副業がバレます。
アルバイト先などで、社会保険に加入すると年金事務所に「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を送る必要があります。
これが年金事務所で受理されると、社会保険に加入が完了するのですが、それと同時にその通知が「本業をしている職場」と「副業をしている職場」の両方に届いてしまうのです。
通知書のなかには、副業で稼いだお金が書かれているので、一瞬で副業がバレてしまいます。
住民税のようなバレないためのやり方はありません。「会社に副業を詮索されたくない」という方は社会保険料を支払わないようにしましょう。
社会保険に関してよくある質問

では最後に、副業をしたいと考えている人から、よくある社会保険についての質問とその回答をお伝えしていきます。
副業で得ているのが雑所得・事業所得の場合の社会保険料はどうなる?
副業で得ているのが雑所得や事業所得の場合は、社会保険料を支払う必要はありません。
ただし、副業でも事業が大きくなって法人化する場合は、社会保険料を支払う義務が生まれるので注意が必要です。
扶養が外れて社会保険料を支払らわないといけないのはいくらから?
扶養を受けている人は、一定の収入を得ると社会保険料を自分で支払う必要が出てきます。
基本的には130万円を超えたときに、自分で社会保険料を支払わなければいけなくなります。
しかし、副業で雇用関係を結んでおり、次の条件を満たしている人は年収が106万円以上でも社会保険料の支払いが必要です。
- 所定労働時間が週20時間以上である
- 勤務期間が2ヵ月を超える見込みがある
- 勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
- 学生ではない(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)
まとめ
今回は、副業をしたときの社会保険の扱いついて解説してきました。
お伝えしたことをもう一度お伝えすると次のようになります。
次の条件を満たした場合、「介護保険」「健康保険」「厚生年金保険」を支払う必要がある。(「労働者災害補償保険(労災保険)」は無条件で支払わなければいけない)
- 勤務先が社会保険の適用対象となる事業所
- 1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
- 下記の5つの条件を全て満たしている
・1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
・1か月の賃金が88,000円(年収106万)以上
・1年以上継続して雇用の見込みがある
・被保険者の従業員が500人を超える事業所
・学生でないこと
「介護保険」「健康保険」「厚生年金保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」に関しては会社員の場合と同じ。
次の条件を満たした場合、雇用保険を支払う必要もある。
- 1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
- 31日以上継続して雇用の見込みがある
ぜひ、お伝えしたことを参考に自分が社会保険に加入すべきか確認してもらえればと思います。
特に「健康保険」「厚生年金保険」には罰則があるので、確認が必須です。
また、社会保険に加入することで副業がバレてしまう可能性もあります。
社会保険を支払いたくない場合は、労働時間を抑えるか、雇用契約を結ばない業務委託で副業をしましょう。
業務委託についての記事も載せておくので、気になる方はぜひ参考にしてくださいね。
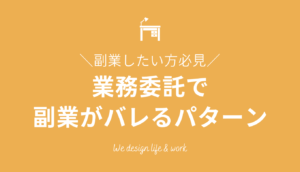

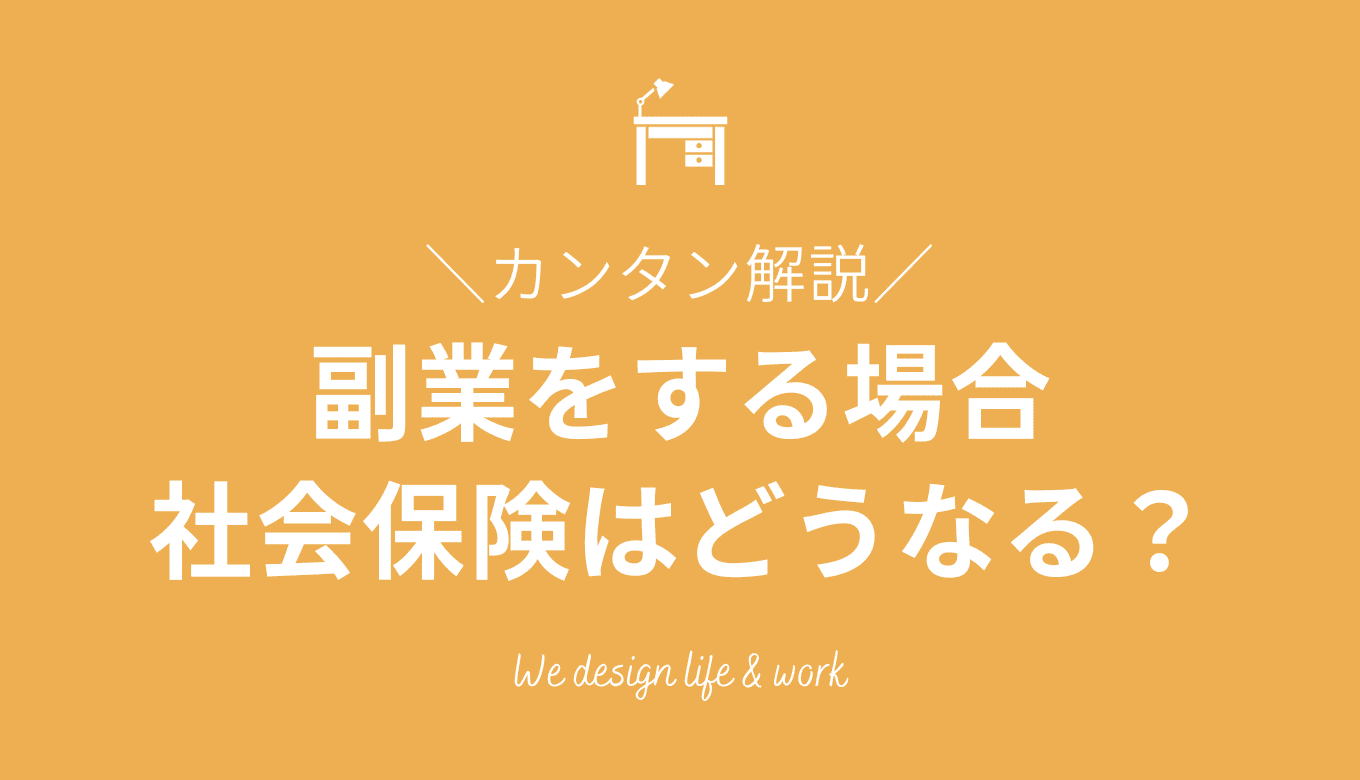
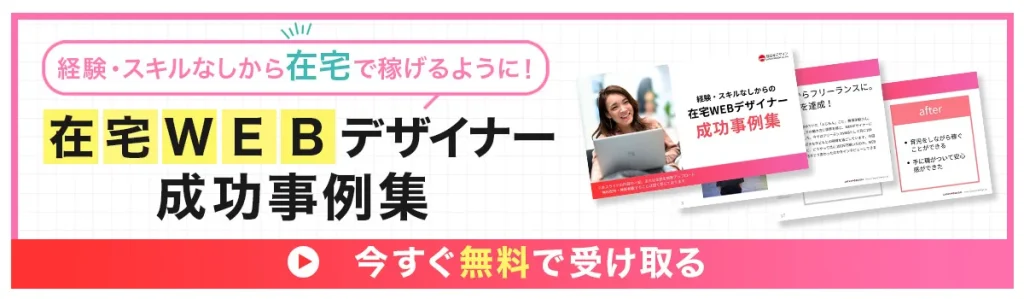
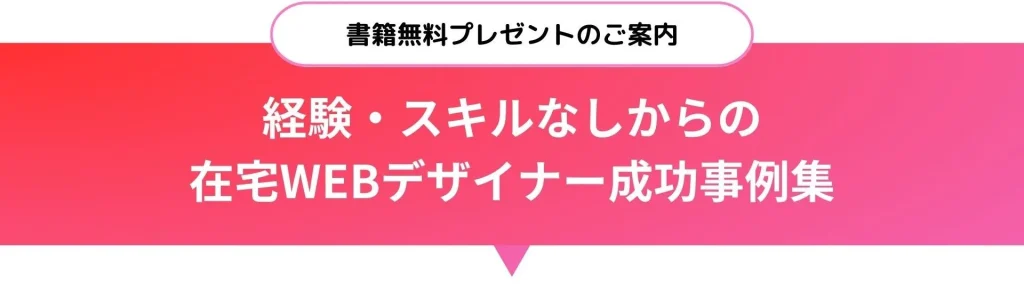
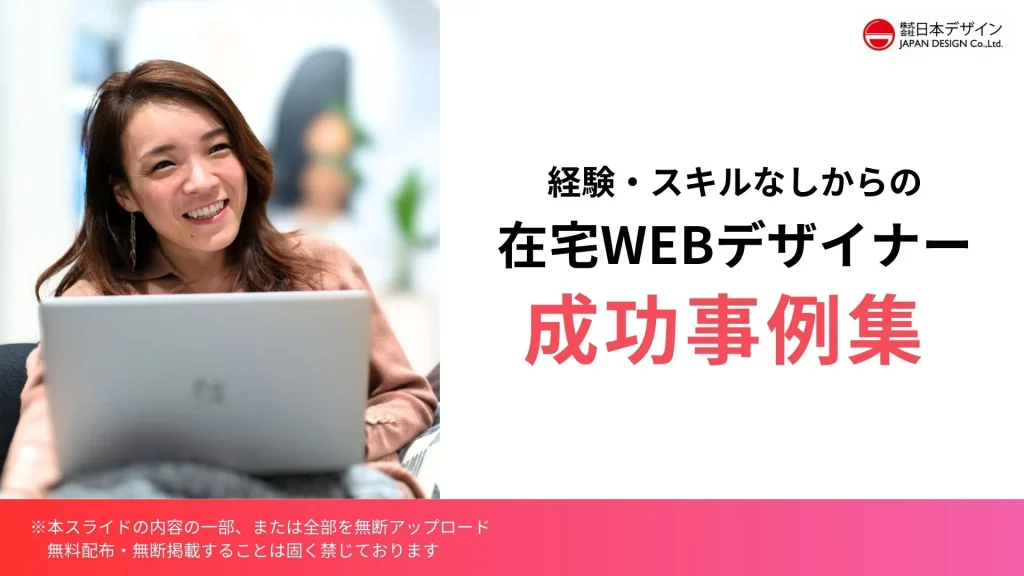
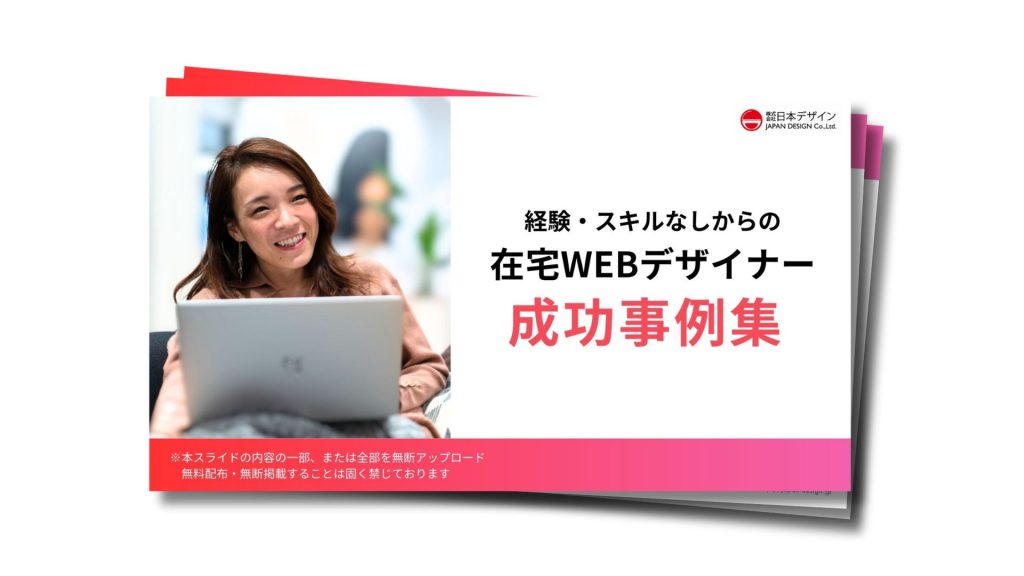
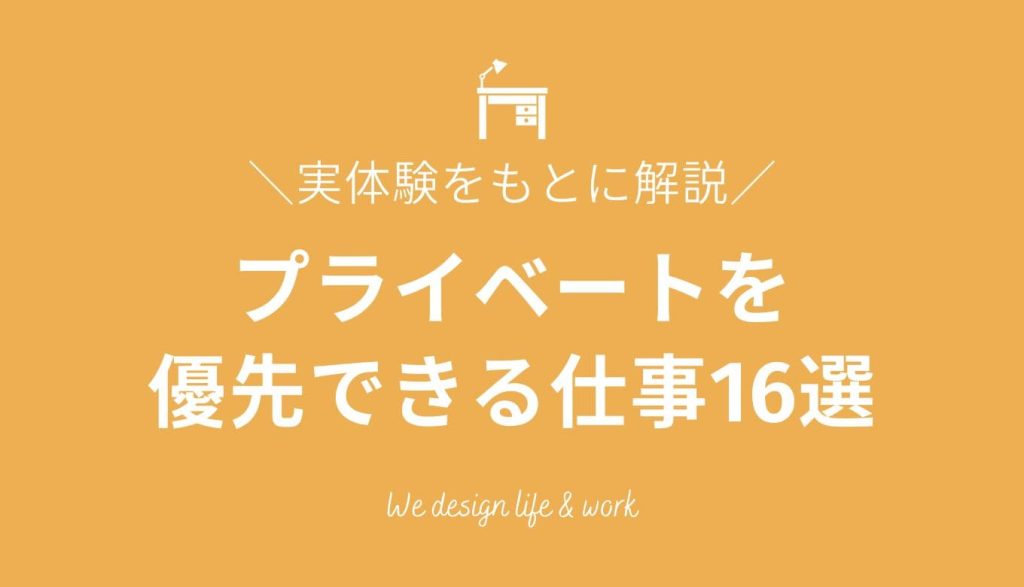
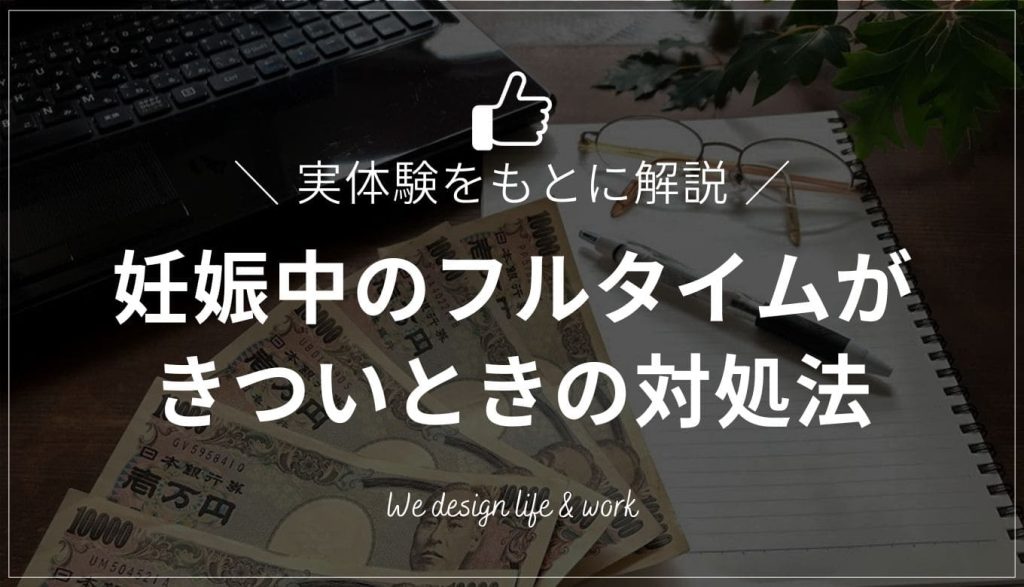
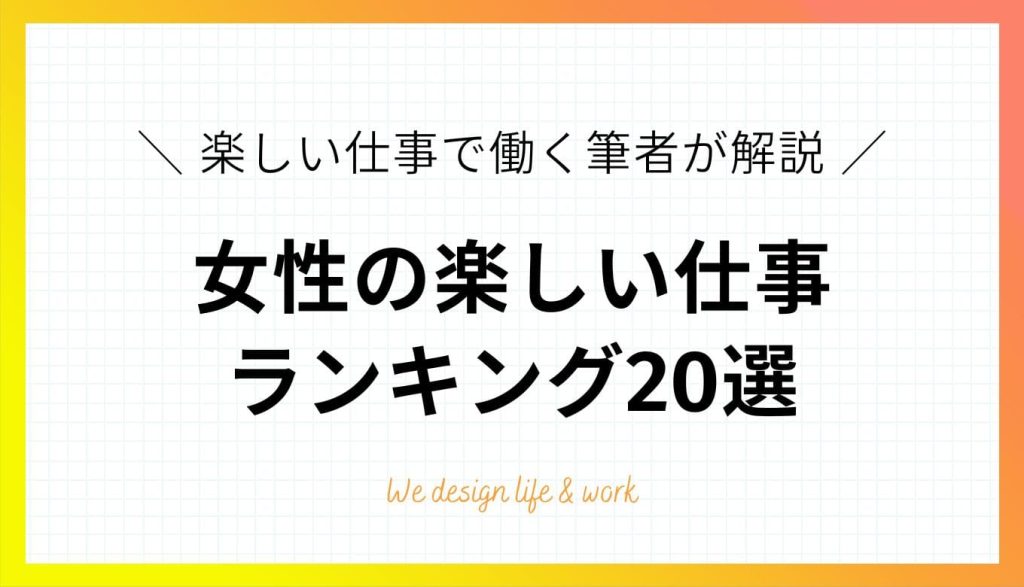
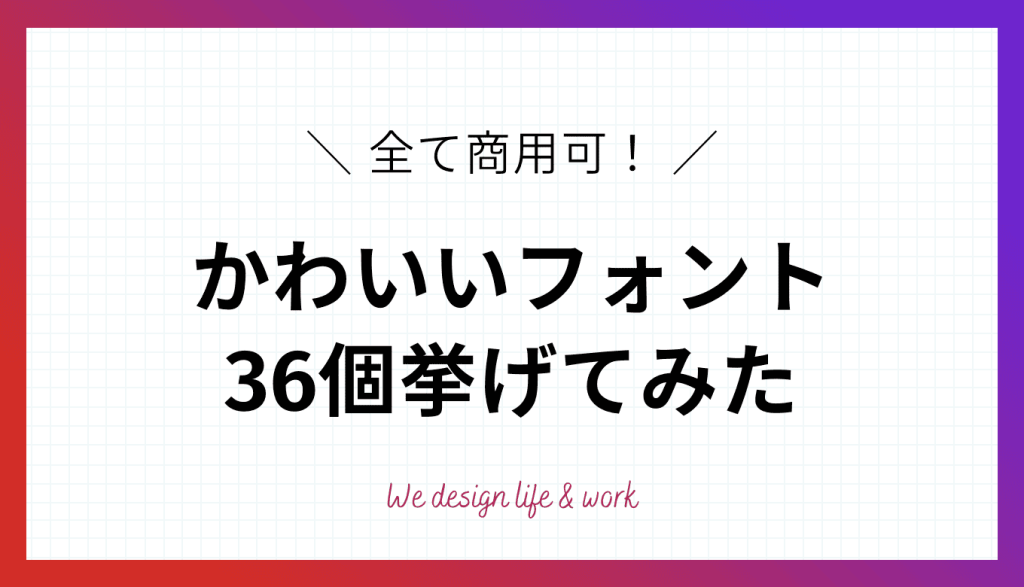

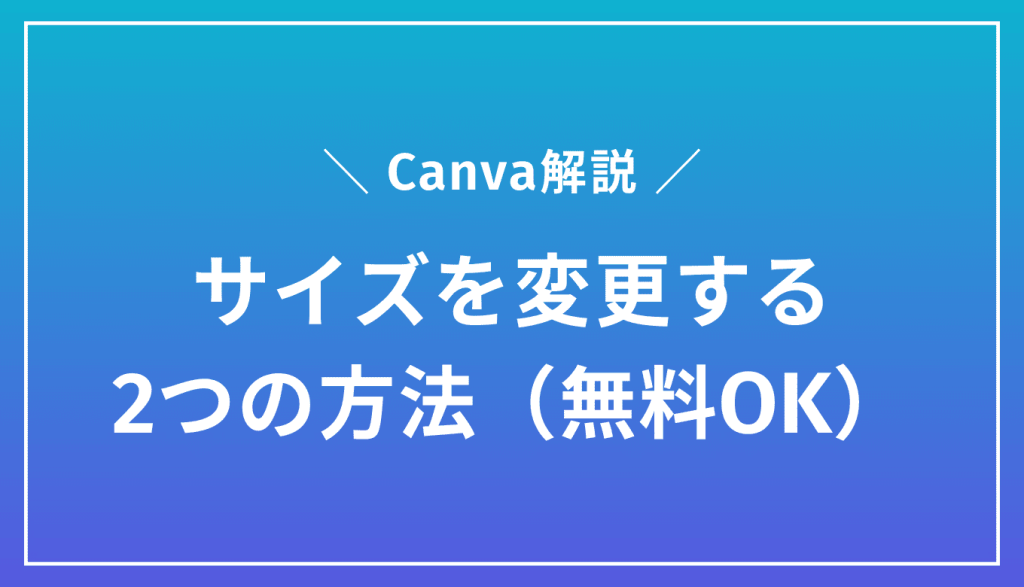
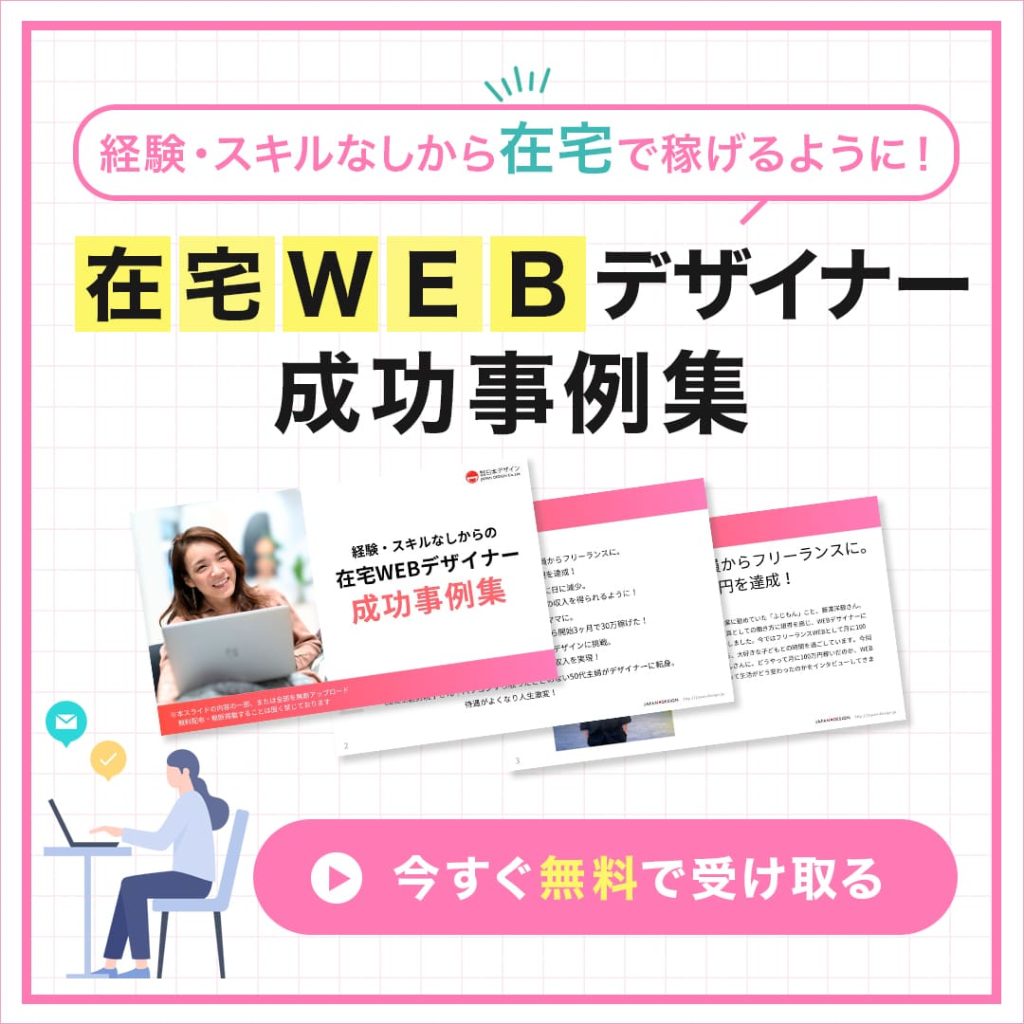

質問や感想があればご記入ください