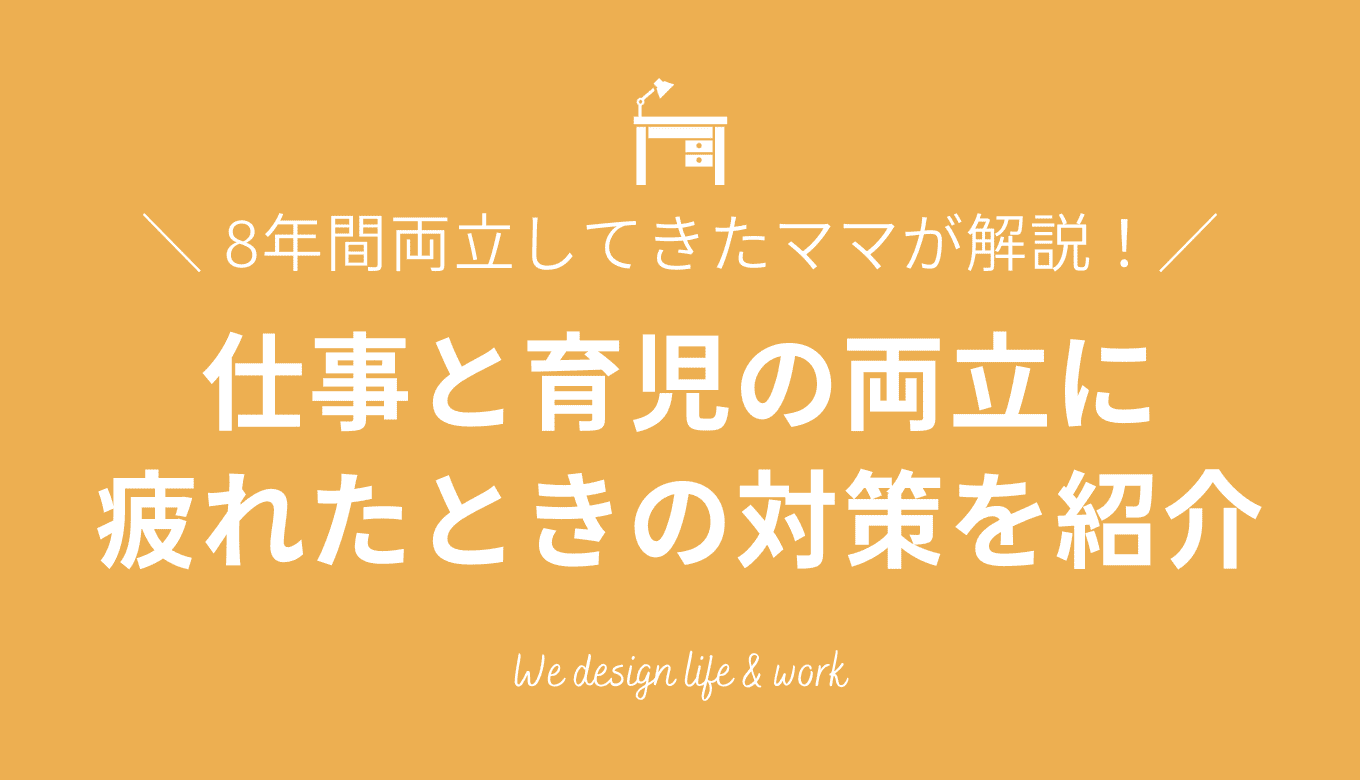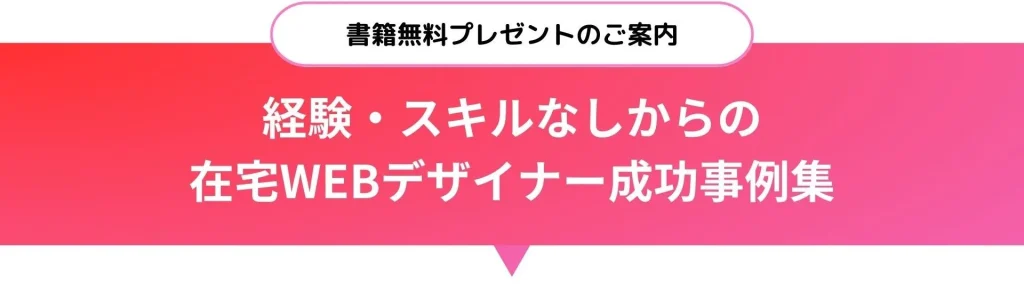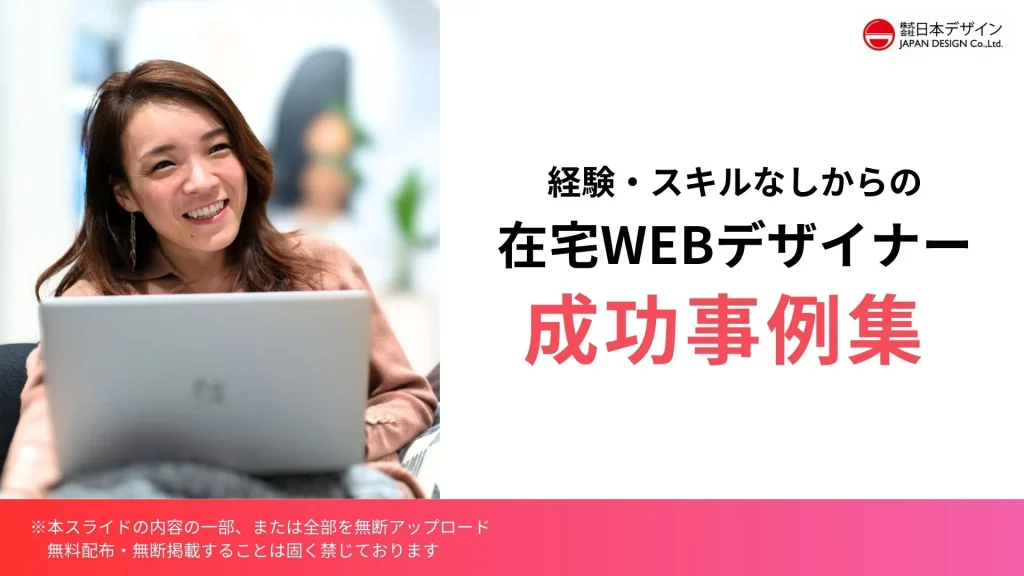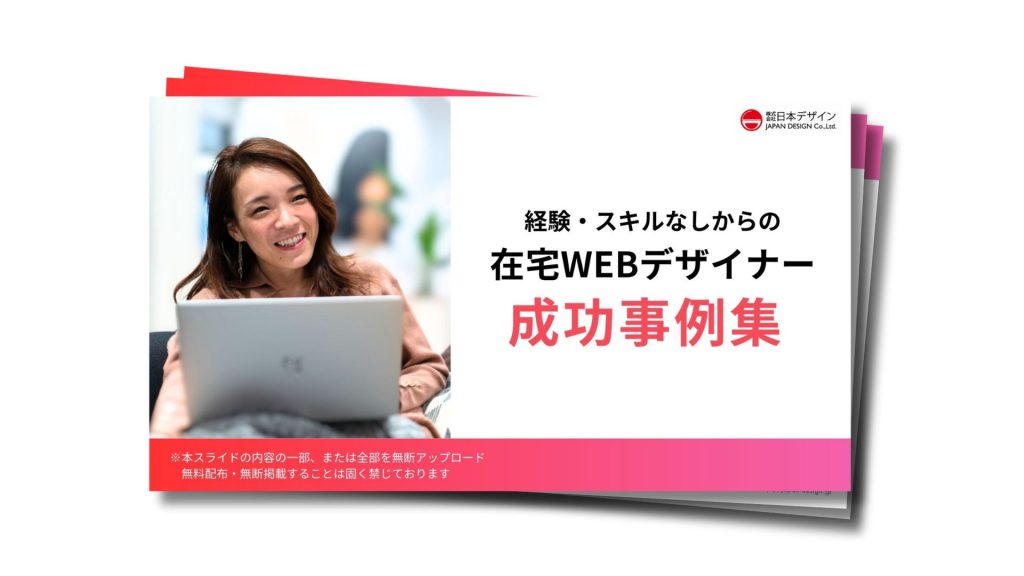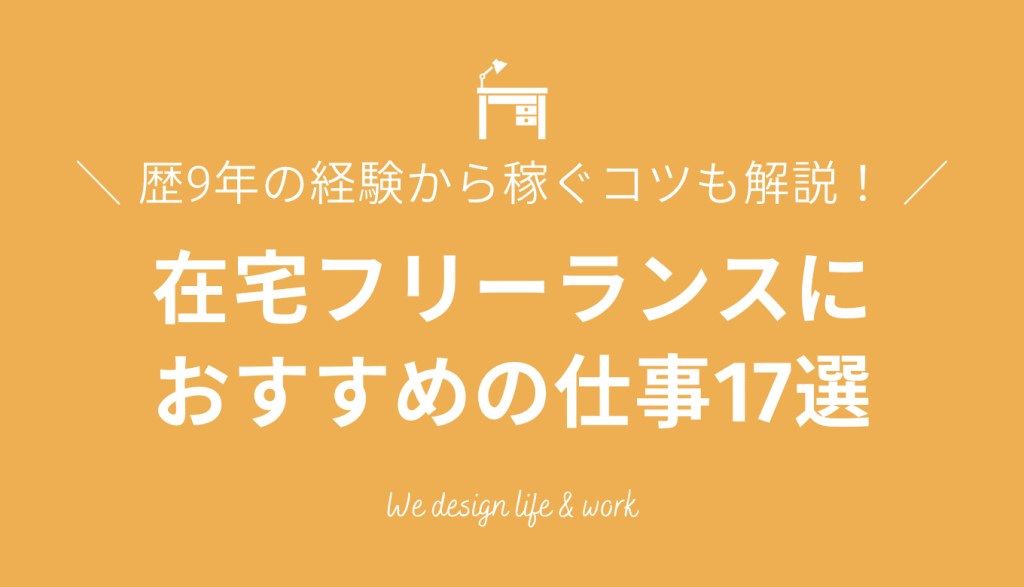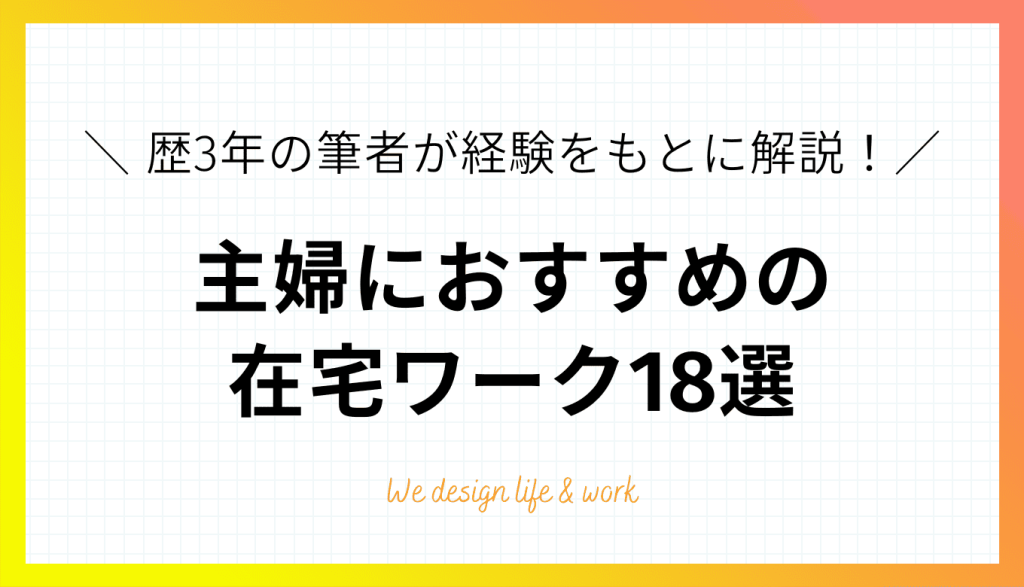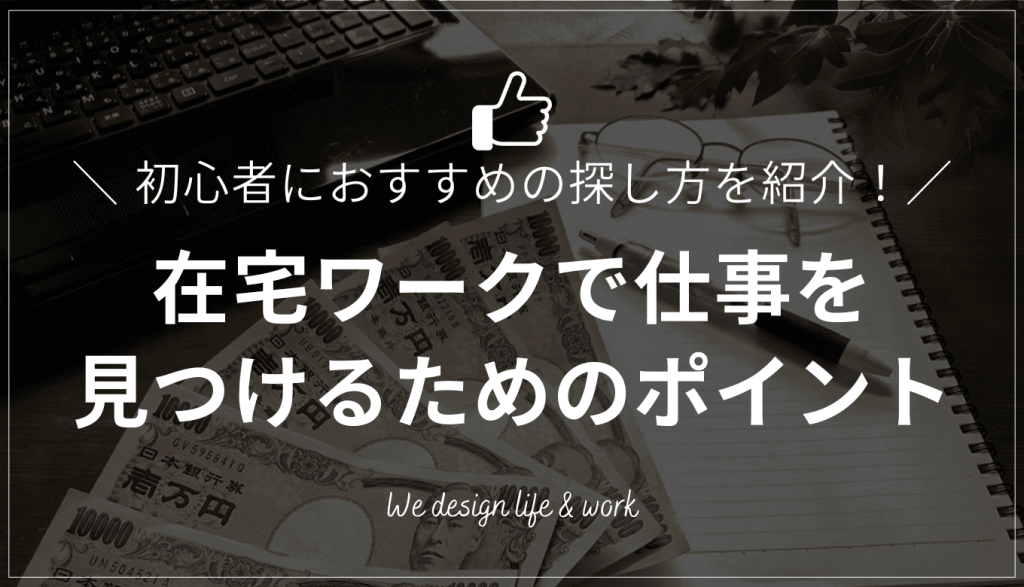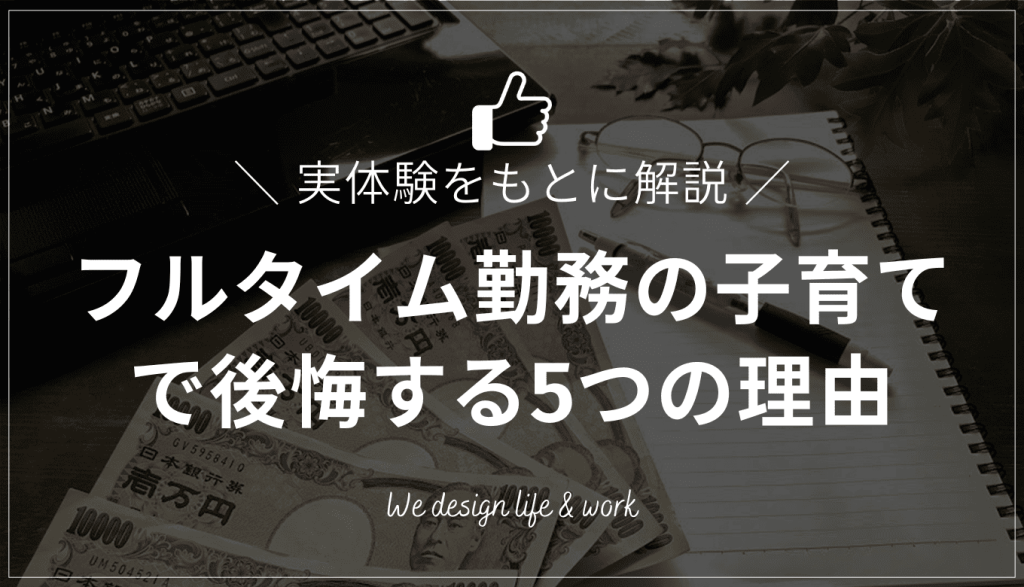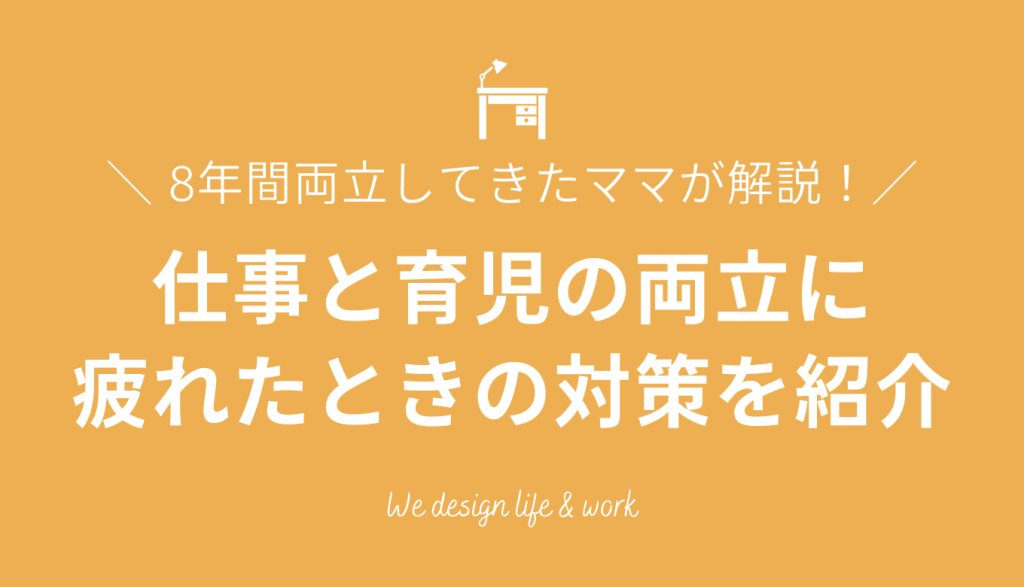「仕事と育児の両立って疲れる…」
「こんなに大変なら仕事を辞めようかな」
仕事をしながら育児を両立するのは、時間的にも体力的にも大変です。子育てとの両立に疲れて、仕事を辞めたいと考える日もあるでしょう。
ママだけで頑張ろうとしてつぶれてしまっては、結果的に子どもや家族に影響します。ママの負担を減らす工夫と、頼れるサービスや制度を活用するのがおすすめです。
実際に、仕事と育児を8年間両立してきた筆者が、疲れたときの対処法に興味がある方へ向けて、対処法と活用すべき制度、両立しやすい仕事をわかりやすくお伝えします。
- 仕事と育児の両立に疲れたときの対策
- 両立を支える便利なサービスや会社の制度
- 疲れた日におすすめのリフレッシュ方法
- 仕事を辞めないで両立を頑張るメリット
- 仕事と育児を両立しやすい仕事3選
実際に両立を続けた今だからこそわかりますが、仕事を辞めず続けてよかったと感じます。子どもが小学生になると、仕事と育児の両立もしやすい傾向です。周りのママも、子どもが年中(4〜5歳)ぐらいから仕事を始める人が増えていました。
実際に体験したことを盛り込みながら、仕事と育児の両立に必要なことを具体的にお伝えしていきます。疲れてしまった方はぜひ参考にしてください。
- 仕事と育児の両立に疲れたらやるべきこと
- 家族に頼る、時短家電を活用する、完璧をやめる、在宅へ転職など、まず負担を減らす工夫から始めます。
- 外部サービスや会社の制度を活用
- ベビーシッター、ファミリーサポート、病児保育、食材宅配
育休、時短、リモート、フレックス、働き方の切り替え
- ベビーシッター、ファミリーサポート、病児保育、食材宅配
- 自分なりのリフレッシュ方法をもつ
- 好きなものを食べる、趣味の時間をもつなどで気分を切り替える
仕事と育児の両立に疲れたときに考えたい解決策

仕事と育児の両立に疲れたと感じたら、まずは以下に紹介する4つの対策を試してみましょう。疲れを放っておくと、仕事も育児も共倒れになるリスクがあります。
- 家族・親戚/義実家を頼る
- 時短家電を活用する
- 両立の完璧をやめる
- 在宅で働ける仕事に転職する
紹介する4つの解決策は、すべて私も経験済みです。それぞれの解決策を活用してよかった点や、具体的な方法もお伝えします。取り入れやすいものから試してください。
解決策1:家族・親戚/義実家を頼る
仕事と子育ての両立に疲れたら、まずは家族や親戚、義実家を頼ってみましょう。身近な人の手を借りると、体力と気持ちの回復につながりやすいです。
育児は毎日続くため、休める時間の確保が必要になります。家事や送迎の負担の分散により、疲れにくくなります。
- すぐに口頭で相談できる
- 子どもを安心して預けられる
- 急な変更にも対応しやすい
- 子どもの性格を理解している
- 金銭的な負担が少ない
例えば、保育園や幼稚園の送迎をお願いすれば、家事だけに集中する時間を確保できます。または、週末に数時間預かってもらい、寝不足を解消するのもおすすめです。
家族や親戚、義実家を頼るときは注意点もあります。
- 子育てのルールを事前に共有する
- 感謝の気持ちや言葉を欠かさない
- 無理をさせない頻度の調整
- 連絡手段を決めておく
- 急な発熱などの対応を共有する
家族や親戚、義実家を頼るのは甘えではありません。私も子どもの父親と協力してお迎えを分担したり、親に預けて外出する時間を確保したり工夫して乗り越えました。
子育ての負担が1人に集中して潰れてしまっては本末転倒です。仕事と育児を両立するためには、1人で頑張ろうとせず周りの協力を積極的に活用してください。
解決策2:時短家電の活用をする
家事負担を減らして育児と仕事の両立を頑張りたいなら、時短家電の活用がおすすめです。時短家電を活用すると、家事に充てる時間が減ります。減った分の時間で休息したり、自分の好きなことをしたりすると、疲労感をおさえられます。
- 家事負担が減る
- できた時間で休める
- 同時進行で用事が進む
- 毎日の作業が減る
- 子どもに向き合う時間が増える
仕事と育児が重なる時期は、常に時間に追われがちです。子どもの世話も片手間になり、罪悪感がありました。
時短家電を使えば、家事が自動で進み時間が生まれます。生まれた時間を活用して一息つく、子どもと話す、早めに寝るなど、疲労回復につながる行動も取りやすいです。
- 食洗機
- 電気圧力鍋(予約機能があるもの)
- 乾燥機付き洗濯機
- ロボット掃除機
食洗機は特におすすめです。時間に換算すると毎日30〜40分は食器洗いに時間を使っていました。食器洗いの時間が減れば、体力消耗を防げて疲れを感じにくいです。
予約機能付きの電気圧力鍋なら、帰宅してすぐに食事ができる仕組みが整います。実際に調理する時間は、食材を切るだけになり料理の時間を半分以下に減らせました。
しかし、時短家電をそろえるには費用の負担があります。すぐに買えない場合もありますが、心身の負担を減らすためのツールと考え、早めに導入するのがおすすめです。
解決策3:両立の完璧をやめる
仕事と育児の両立に疲れたと感じたときは、完璧を目指そうとしていないか一度俯瞰しましょう。家事には終わりがないため、頑張り続けるより力を抜く考え方をもつのがおすすめです。
実際に私も、完璧のハードルをかなり高くもっていて、仕事と育児を両立するために毎日イライラしていました。「ここまでやればOK」などハードルを下げることで、心が安定し結果的に仕事と育児を両立しやすい環境になりました。
- 気持ちが安定する
- 疲れが溜まりにくい
- 自分を責めなくなる
- 余力が残る
完璧な両立とは、個人で考え方に違いがあり上を目指すとキリがありません。だからこそ、できなかったことに目を向けるよりも、できた部分を認める意識を持つことが、気持ちの安定につながります。
完璧をやめるとは、投げ出すことではありません。明日に回しても大丈夫、ここはできていないけれど生きていけるなど、気持ちの余白を保つことです。
洗濯物をたたまずに寝る日があっても問題ありません。無理を重ねない意識が、疲れをためない生活につながります。
解決策4:在宅で働ける仕事に転職する
在宅で働ける仕事へ転職することは、仕事と育児を両立する選択肢のひとつです。通勤や時間の制約が重なるほど、体力と気力は削られ疲れやすいです。在宅で働く仕事なら、育児との両立がしやすい環境に近づきます。
弊社の調査データによると、仕事と育児を両立するには、働き方の自由度を重視する割合が81.8%との結果です。在宅で働ける仕事は、自由度が高い働き方として昨今注目されています。
参考:主婦・ママのフリーランス転身に関する意識調査|株式会社日本デザイン
- 通勤時間がなくなる
- 急な呼び出しに対応できる
- 体力の消耗が減る
- 生活リズムを守れる
在宅勤務は、通勤が必要ないため使える時間が増えます。通勤時間に朝夕の準備や送り迎えに充てるなど、家庭の予定にあわせて仕事と育児の調整が可能です。
子どもの体調不良が起きても、早退や欠勤の連絡で気持ちをすり減らす場面が減ります。
実際に私も、通勤の必要がある事務職から在宅のフリーランスWEBライターへ転身してよかったです。今までの通勤往復に充てていた時間が、休息や子どもと過ごす時間へ変わり、体力的にも精神的にも疲れを感じにくくなりました。
在宅で働ける仕事への転職は、生活全体を見直す第一歩になります。働く場所の自由が、余力を生み、両立に疲れた状態を改善できるためぜひ検討しましょう。
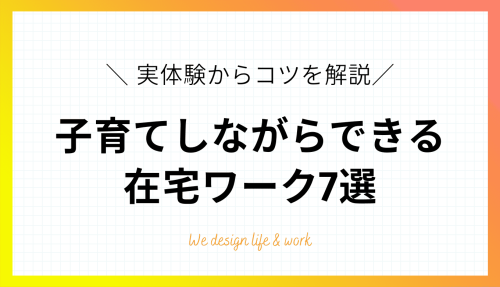
仕事と育児の両立を支えるサービス

仕事と育児の両立を支えるサービスを4つ紹介します。
- ベビー/キッズシッター
- ファミリーサポート
- 病児保育
- 食材宅配
具体的な利用方法や、料金や助成制度は、私が活用した体験に基づいて解説していきます。ぜひ活用を検討してください。
サービス1:ベビー/キッズシッター
仕事と育児の両立に疲れたと感じたときは、ベビー/キッズシッターの活用がおすすめです。人手が足りない場合や、家族で調整ができないときに抱え込まず、外部の手を借りるのも心身の負担を減らします。
- 自宅で子どもを見てもらえる
- 急な残業や予定変更に対応
- 送迎が任せられる
- 自治体の助成制度が使える
- 保育のプロに任せられる
ベビー/キッズシッターは、保育園と違い時間や場所の自由度が高い点が強みです。仕事前後の短時間利用や、在宅ワーク中の見守りも依頼できます。子どもが体調不良で登園できない日は、病児対応できるシッターにお願いすることも可能です。
実際に私が利用しているベビーシッターは、東京都の助成制度が手厚いため気軽に利用しています。助成内容や対象は自治体によって異なるため、最新情報は各自治体の公式サイトで確認してください。
以下は、東京都で実施されているベビーシッター利用支援事業の概要です。
東京都のベビーシッター利用支援事業
| 利用上限 | 児童1人につき年度内144時間まで※ふたご等の多胎児、障害児、ひとり親家庭の場合は児童1人当たり年度内288時間まで |
| 利用条件 | ・最初の50時間は利用料の全額が助成対象 ・50時間を超えた部分はシッターの時給に上限あり(区によって異なる) ・東京都認定したベビーシッター事業者のみ |
| 対象児童 | 未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで) |
| 利用上限 | 児童1人につき年度内144時間まで※ふたご等の多胎児、障害児、ひとり親家庭の場合は児童1人当たり年度内288時間まで |
| 利用条件 | ・最初の50時間は利用料の全額が助成対象 ・50時間を超えた部分はシッターの時給に上限あり(区によって異なる) ・東京都認定したベビーシッター事業者のみ |
| 対象児童 | 未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで) |
上表のとおり、条件を満たせば年間最大144時間分まで利用料の自己負担分が還付されます。私の場合はひとり親世帯なので、還付される利用は288時間分までです。金銭的な負担がほとんどなく利用できるため、とても助かっています。
※上限・対象事業者・自己負担額は自治体・年度で異なります
サービス2:ファミリーサポート
手軽に活用できるファミリーサポートの利用が、仕事と育児の両立に疲れた場合に役立ちます。地域で子育てを助けあう仕組みなため、安心感も得られます。
- 地域の人が支えてくれる安心感がある
- 料金が比較的おさえめ
- 送迎など短時間利用に活用できる
- 顔見知りになりやすい
- 急な予定変更にも対応できる
ファミリーサポートは、市区町村が運営する子育て支援制度です。主な内容は、保育園や習いごとの送迎、保護者の用事中の預かりです。料金は地域差がありますが、1時間700円から1,000円前後になります。民間サービスより費用をおさえられる点が特徴です。
利用の手続きは、以下の流れで進みます。
- 自治体の窓口やWEBで会員登録をする
- 説明会や面談で利用条件を確認する
- 希望のサポート内容にあう提供会員と顔あわせ
- 合意後に依頼を開始し、利用ごとに精算
民間のキッズ/ベビーシッターより初回登録の手間がかかるため、余裕のある時期に始めると安心です。1〜2時間程度の短時間での利用が可能なため、手軽に依頼できる点がメリットです。
キッズ/ベビーシッターとファミリーサポートの違い
| キッズ/ベビーシッターの特徴 | ファミリーサポートの特徴 |
|---|---|
| ・初回登録が簡単 ・長時間利用におすすめ ・事業者への手数料が必要(助成対象外) ・シッターへの交通費が必要(助成対象外) ・シッターの時給は2,500〜3,000円程度 ・助成制度がある | ・初回登録に手間がかかる ・短時間利用に向いている ・料金設定がおさえめ ・助成制度がない ・サポーターの多くは、地域の子育て経験者(保育のプロとは限らない) |
| キッズ/ベビーシッターの特徴 | ファミリーサポートの特徴 |
|---|---|
| ・初回登録が簡単 ・長時間利用におすすめ ・事業者への手数料が必要(助成対象外) ・シッターへの交通費が必要(助成対象外) ・シッターの時給は2,500〜3,000円程度 ・助成制度がある | ・初回登録に手間がかかる ・短時間利用に向いている ・料金設定がおさえめ ・助成制度がない ・サポーターの多くは、地域の子育て経験者(保育のプロとは限らない) |
ファミリーサポートは、生活圏で頼れる関係を育てられます。仕事と育児の両立に疲れたとき、地域の力を取り入れてみましょう。
サービスの内容や料金、事前登録の方法は自治体により異なるため、事前に役所に問い合わせるのが確実です。
サービス3:病児保育
子どもの体調不良時は、仕事と育児の両立が大変で疲れたと感じやすいです。子どもが体調をくずした場面でも病児保育の活用により、仕事の調整を考えるストレスがなくなります。
病児保育とは、子どもが病気や体調不良のときに利用できる預かりサービスです。発熱やせき、かぜなどで保育園や学校に行けない場合でも、保護者が仕事を休めないときに頼れます。
- 体調不良時も預けられる
- 医療機関との連携で安心感がある
- 急な発熱にも対応できる
- 仕事を休まず続けられる
- 保護者の負担を減らせる
病児保育では、医師や看護師、研修を受けた保育スタッフが常駐し、子どもの体調を見守りながら過ごします。
多くは事前登録制で、利用当日は医療機関の受診が必要です。事前登録制が多いため、元気な時期に準備しておくと安心です。
- 自治体や施設のWEBで事前登録をする
- 利用当日は医療機関を受診する
- 利用連絡票を書いてもらう
- 利用連絡票をもって施設へ連絡する
- 空きがあれば病児保育の利用を開始
病児保育の料金は各自治体で異なり、1日数千円かかる地域もあれば、無料で利用できる自治体もあります。実際に上の子が病児保育を利用したときは、9時から17時まで預かりを依頼し、料金は4,000円(助成なし)でした。一方、昨年下の子を預けた際は制度が変わっていて、利用料は無料になりました。
実際に利用しているのは、0〜3歳ぐらいまでの乳幼児が中心です。お弁当やおやつの準備、乳児はミルクや搾乳した母乳、離乳食の準備が必要なので、当日急に利用をしたい場合は準備に追われます。
しかし、医療機関と連携している安心感があるため、病児保育の積極的な活用はおすすめです。
サービス4:食材宅配
仕事と育児の両立に疲れたとき、食材宅配の活用をおすすめします。買い物や献立づくりの負担が減り、毎日の生活に余白が生まれます。時間に追われやすい家庭ほど、効果を実感しやすいサービスです。
食材宅配を活用すると、あらかじめ選んだ食材やミールキットを自宅まで届けてくれます。利用には会員登録が必要で、インターネット上での申し込みが必要です。
料金は週ごとの定期制が多く、1回あたり数千円が目安です。配達日時の指定や、子育て世帯向けの割引が用意されている場合もあります。
- 買い物の外出が不要
- 献立を考える負担が減らせる
- 調理時間を短縮できる
- 重い荷物を持たなくて済む
- 子ども対応に集中できる
一方で、配達や品質管理のコストが含まれているため、食材宅配はスーパーより割高に感じる場合があります。
毎週の定期配送があわない家庭は、スーパーマーケットが提供する宅配サービスを活用するのがおすすめです。使い分けると、費用と手間のバランスが取りやすいです。
実際に私も、定期配送の食材宅配サービスと、都度必要なものはAmazonと提携するスーパーの食材宅配サービスを活用しています。そのため、ほとんど買い物に出ることがないので、欠かせないものになりました。
食事の準備は毎日続く家事です。負担を減らす手段を選ぶだけで、心と体が楽になります。
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
仕事と育児の両立を支える会社の制度

仕事と育児の両立を支える会社の制度も見てみましょう。家族や自治体、民間企業だけでなく、会社の制度を頼れれば同僚や上司の理解も得やすいです。
- 育児休業(母親と父親)
- 時短勤務
- リモートワーク
- フレックスタイム
- 働き方の切り替え
育児へ理解を示す動きが発展している昨今、会社が提供する制度も拡充傾向にあります。ぜひ継続的に制度を調べて活用していきましょう。
制度1:育児休業(母親と父親)
仕事と育児の両立に欠かせないのは、会社の育児休業制度の取得です。育児休業は、出産8週間後以降から原則子どもが1歳になるまで取得でき、条件により最長2歳まで延長できます。
産後休暇と育児休業
| 産後休暇 | 育児休業 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 母親 | 子どもの母親と父親 |
| 期間 | 出産した日から8週間 | ・母親:産休終了後から子どもが1歳になるまで(原則) ・父親:1.出産後8週間以内に最大で4週間(産後パパ育休制度)2.子どもが1歳になるまで |
| 産後休暇 | 育児休業 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 母親 | 子どもの母親と父親 |
| 期間 | 出産した日から8週間 | ・母親:産休終了後から子どもが1歳になるまで(原則) ・父親:1.出産後8週間以内に最大で4週間(産後パパ育休制度)2.子どもが1歳になるまで |
父親には産後休暇がない代わりに、産後パパ育休制度があります。産後パパ育休制度と通常の育休を併用して、子どもが1歳になるまで育休を取得することが可能です。
申請には出産前後に会社へ申し出て、所定の書類提出が必要です。雇用保険に加入し、一定期間働いていれば、母親も父親も取得できます。
- 育児の負担をわけあえる
- 母親の休養時間が確保
- 父親の育児参加が進む
- 復職後の生活が整う
- 家庭内の理解が深まる
育児休業を両方が使うと、どちらか一方に負担が集中しにくいです。父親が早い時期から関わると、授乳以外の家事や育児を自然に分担できます。
また、「産後パパ育休制度」が2022年からスタートしています。産後パパ育休制度は、出産直後から4週間仕事を休める制度です。育児休業と併用が可能で、育児の負担をより分散しやすくなりました。
育児休業と産後パパ育休制度
| 育児休業の特徴 | 産後パパ育休制度 |
|---|---|
| ・出産後8週間経ってから取得可能 ・子どもが1歳になるまで取得可能 ・条件により最長2歳まで延長可能 ・休業中の就業は原則不可 | ・出産後8週間以内に最大で4週間取得可能 ・分割取得できる ・休業中に就業できる |
| 育児休業の特徴 | 産後パパ育休制度 |
|---|---|
| ・出産後8週間経ってから取得可能 ・子どもが1歳になるまで取得可能 ・条件により最長2歳まで延長可能 ・休業中の就業は原則不可 | ・出産後8週間以内に最大で4週間取得可能 ・分割取得できる ・休業中に就業できる |
母親は心身を休めやすく、復職への不安も減ります。家庭の形にあわせ、母親と父親が一緒に育児休業の取り方を考えると、仕事と育児の両立が進みやすいです。
制度2:時短勤務
仕事と育児の両立に疲れたとき、会社の時短勤務制度の活用を検討しましょう。時短勤務は、子どもが一定の年齢になるまで、1日の労働時間を短くして働ける制度です。
法律上の義務としては、3歳未満の子どもを育てる場合が対象になりますが、会社によっては小学校入学前まで使える場合もあります。
実際に私が以前働いていた会社では、子どもが小学校3年生になるまで時短勤務の活用が可能です。就業規則や人事担当者へ確認してみましょう。
- お迎え時間に余裕ができる
- 朝夕の負担が減る
- 体力の消耗を防げる
- 家族時間を確保しやすい
- 仕事を続けやすい
時短勤務の取得形態はさまざまで、始業を遅らせる場合と、終業を早める方法、週休3日にして平日4日はフルタイム出勤をする方法などです。
フルタイム勤務のまま育児を続けると、時間に余裕がなくなり精神的にも疲れてしまいます。時短勤務の取得により、保育園や学童の時間にあわせやすく、急な体調不良にも対応しやすいです。
しかし、時短勤務の取得により収入が減る場合はあります。実際に私も、フルタイムから1時間半勤務時間を短縮していたときは、給料の2割がカットされました。給料カットはあっても、時間に余裕があるほうが疲れにくく、精神的なストレスが減り安心です。
仕事を辞めず、育児と向き合う選択肢として、時短勤務を活用するとよいでしょう。
制度3:リモートワーク
会社の制度としてリモートワークを選べるなら、仕事と育児の両立がしやすいでしょう。リモートワークは、出社せず自宅などで仕事をおこなう働き方です。
パソコンとインターネット環境があれば、社内システムやオンライン会議を使って業務を進められます。
- 通勤時間がゼロ
- 子どもの送迎が楽になる
- 休憩中の合間に家事を済ませられる
- 体力の消耗を軽減できる
- 急な予定変更にも対応できる
リモートワークのメリットは、通勤時間がなくなることです。私たちの調査では子育て世代の66.7%が通勤に負担を感じ転職を考えたことがあることがわかっています。
参考:子育て世代のオフィス回帰に関する実態調査|株式会社日本デザイン
その点、リモートワークであれば、子どもの支度や見送りを落ち着いて進められます。実際に私も会社員だった際、リモートワークの日は子どもを保育園に連れて行くのを1時間遅らせても間に合いました。
また、休憩時間に洗濯や食事の準備を進められ、子どもを連れて帰ってきてからの負担も減ります。
一方で、接客業や現場作業など、リモートワークがむずかしい職種もあります。すべての仕事で使える制度ではありませんが、適した職種を選べば仕事と育児の両立をより身近にすることが可能です。リモートワークができるおすすめの職種は、のちほど紹介します。
制度4:フレックスタイム
仕事と育児の両立に疲れたと感じたら、フレックスタイムを活用するのもひとつの方法です。フレックスタイムは、決まった始業と終業時刻にしばられず、一定の労働時間を満たせば出退勤の時刻を調整できる制度になります。
フレックスタイムを導入する会社は、就業が必須なコアタイムを設けているケースがほとんどです。コアタイム以外の時間を自由に組み立てて、一定の労働時間を満たすことで成立します。朝の支度や送迎に追われる負担が減り、生活の流れが整えやすいです。
- 送迎時間にあわせやすい
- 朝夕の混雑を回避できる
- 体調にあわせ調整できる
- 家事の時間を確保できる
- 仕事に集中する時間帯を決められる
決まった時刻に出社する働き方では、子どもの支度をしながら出勤や退勤の調整そのものがストレスにつながります。フレックスタイムなら、子どもの体調や行事にあわせて開始時刻を動かすことが可能です。
朝を遅く、夕方を早めるなど、家庭の都合にあわせやすくなります。ただし、すべての会社が対応しているわけではありません。窓口業務や現場作業など、時間の固定が必要な職種では利用がむずかしい場合もあります。
制度の有無と運用の実態を確認したうえで、仕事を選ぶ目線も大切です。フレックスタイムを活用し、仕事と育児の両立がしやすい環境を整えたいですね。
制度5:働き方の切り替え
働き方そのものを見直して、仕事と育児の両立をしやすく整えるのもおすすめです。働き方の切り替えは、雇用形態や勤務条件を変え、生活にあった形へ調整します。
責任や時間の重さをゆるめられ、心と体の余裕を取り戻しやすいです。収入や役割は変わる場合もありますが、長く働き続けるための現実的な選択肢のひとつになります。
- 契約社員
- パート社員
- 派遣社員
- 業務委託
- 在宅専任職
働き方を変えると、通勤や残業の負担が減り、子どもの予定にあわせやすくなります。仕事量が明確になり、家庭の時間を確保しやすい点もメリットです。
働き方を切り替えるときは、まずは今の会社に相談し、勤務形態や役割の調整ができないか相談するのがおすすめです。
社内で対応がむずかしい場合は無理を重ねず、これまでの経験やスキルを活かせる職場を求めて転職活動へ進む流れが、仕事と育児の両立をしやすい選択になります。
生活を守れる働き方を選ぶ姿勢が、疲れを減らす一歩です。
仕事と育児の両立に疲れたときのリフレッシュ方法

仕事と育児の両立に疲れたときこそ、リフレッシュするのがおすすめです。誰でも簡単に実践できるリフレッシュ方法を3つお伝えします。
- 自分のためにお金を使う
- 自分が好きな食べ物を食べる
- 自分の趣味に時間を使う
実際に私が試したときの体験エピソードと具体的な方法も解説します。仕事と育児の両立が大変で疲れが限界になる前に、ぜひ実践してください。
方法1:自分のためにお金を使う
仕事と育児の両立に疲れたときは、自分のためにお金を使うとリフレッシュできます。毎日が子ども中心になると、自分がしたい買い物や予定も後回しにしがちで、精神的にも疲れを感じやすくなります。
子どもに関係ない支出は、保護者の役割から一度離れる方法として有効です。短い時間でも、自分を優先する行動が気分を切り替えます。結果として、仕事や育児への向き合い方も落ち着きます。
- 気になっていた服を買う
- 美容を思いっきり楽しむ
- 読みたかった漫画を一気に買う
- 趣味の道具を買う
気になっている服や本、美容にかける時間など、自分だけの支出は心を満たしてくれます。実際に私も、雑誌を読んで気になった服を買ってみたり、美顔器を購入したり自分のためにお金を使いました。
リフレッシュする目的での支出は、忙しい生活のなかで必要なセルフケアです。たとえ少額でも、自分のためにお金を使う体験が、精神的な息抜きになり仕事と育児の両立を継続させます。
方法2:自分が好きな食べ物を食べる
自分が好きなものを食べる時間を作ると、仕事と育児の疲れを癒してくれます。
子ども中心の食生活では、自分の好きな食べ物が好きなタイミングで食べられないことが多いです。自分の好きな食べ物を我慢しない日を作ると、気持ちが満たされます。
好きな食べ物は、子どもがいると食べにくいものがおすすめです。以下のような辛さや苦み、甘さが強いものは、普段の食事や間食では避けますよね。
- 辛いカレー
- ビターなチョコ
- にんにくが効いた料理
- スパイス多めの麺
- 濃い味のつまみ
- 苦味があるゴーヤーなど
- 味の濃いラーメン
実際に私も辛いものが大好きですが、子どもを優先してカレーや麻婆豆腐は甘口です。そのため、無性に辛いものが食べたくなることがあり、我慢せず自分だけ子どもたちと違うものを作ることもあります。
仕事と育児を両立する毎日は、我慢の連続です。自分が食べたいものを選ぶと、リフレッシュになります。
方法3:自分の趣味に時間を使う
仕事と育児ばかりで自分の趣味ができないストレスがあるなら、思い切って趣味の時間をもつのがおすすめです。好きな趣味に集中していると、仕事や育児から解放された気分になります。
趣味に時間を使うメリットは、自分を後回しにしてきた気持ちを取り戻せる点です。仕事と育児に追われる毎日では、自分の好きなものや楽しい気持ちを考える余裕がなくなります。
趣味の時間は、親という役割から離れられる瞬間です。以下のとおり、手軽にできる趣味を実践して自分のために時間を使ってください。
- 音楽を聴く
- 漫画を読む
- 動画を見る
- 散歩する
- 日記を書く
- 写真を撮る
- 塗り絵をする
- ストレッチ
数分でも好きな趣味に向き合うとリフレッシュになり、家事と育児の両立の原動力になるはずです。5分だけでも、自分のための時間があると回復につながります。
誰かのためではなく、自分の気持ちを大事にする時間を確保しましょう。
仕事と育児の両立を頑張ったメリット

仕事と育児の両立を頑張ったメリットを4つ紹介します。
- 金銭的な余裕ができる
- 仕事そのものが気分転換になる
- 頑張る親を見て子どもが助けてくれる
- ブランクがあるより転職にも有利
両立に疲れてしまい仕事を辞めたくなる気持ちもわかります。勢いで退職をした結果、辞めなければよかったと後悔しないためにも、両立を頑張って得られたメリットを知っておきましょう。
メリット1:金銭的な余裕ができる
仕事と育児の両立を頑張るメリットは、金銭的な余裕が生まれる点です。毎日あわただしくても収入があると、将来への不安が少しずつ減ります。余裕資金で生活以外の楽しみや、快適な暮らしを整えることも可能です。
例えば、余裕資金で以下のことができます。
- 貯金に回せる
- 生活費以外の娯楽に使える
- 子どもの習い事にお金を使える
- 住宅購入の資金になる
- 外食に行く
子どもが未就学児の間は育児の手間がかかるため、仕事との両立がより大変に感じます。しかし一方で、教育費はほとんどかかりません。今のうちに仕事を頑張り、お金に余裕をもっておくことがおすすめです。
子どもの成長は思ったより早く、やりたいことや必要な支出は小学校3年生ぐらいから年々増えます。その前に備えられるのは、大きなメリットです。
また、家計の話で衝突しにくくなり、自分で使えるお金がある安心感も得られます。いざというときに、選べる道が増える点も心強いです。
仕事と育児の両立は楽ではありません。日々の両立を積み重ねることで、金銭面の安定を生み、心のゆとりにもつながります。
メリット2:仕事そのものが気分転換になる
仕事をしながら育児を両立していると、仕事そのものが気分転換になることがあります。子ども中心の毎日が続くと自由が制限されストレスが溜まりがちです。一方で仕事中は、ランチ休憩や同僚と気軽に会話するなど、自分のペースで動けます。
育児から解放されている仕事中は、息抜きに感じるのです。
- 同僚や上司など大人と会話できる
- 子育てから一時的に解放される
- 子育て中の同僚に育児相談をして気を紛らわせる
- 子育てでは感じにくい達成感を味わえる
実際に私も、仕事中に好きな時間にランチに行けたり、お手洗いに行けることそのものにありがたみを感じました。
仕事と育児を切り分ける時間は、育児ストレスを和らげてくれます。両立を頑張れば、上手にオンオフの切り替えもできるようになり、仕事の効率もアップします。
疲れて大変とネガティブにとらえすぎず、気分転換のひとつとして気楽に考えましょう。
メリット3:頑張る親を見て子どもが助けてくれる
仕事と育児の両立を頑張る親の姿を見て、子どもが助けてくれるようになります。毎日を必死に家庭を回している姿を見て、自然に子どもは学んでいるのです。
実際に私の子どもも小学校低学年ぐらいから、積極的に手伝ってくれたり、仕事の話ができるようになったり、よき相談相手になっています。
忙しさのなかでも仕事へ向かう姿は、子どもにとって身近な学びになります。バタバタと忙しい毎日を送る様子を見て、努力や責任を感じ取るでしょう。相手を思いやる気持ちや、身の回りのことを自主的にやるなど、子どもの成長につながります。
- 家事の手伝いをする
- 体調を気にかけて声をかける
- 仕事の話が身近になる
- 親の背中を見て、自主的に動く
仕事と育児を続ける毎日は大変です。それでも、その姿は子どもの記憶に残ります。両立を続けたからこそ得られるものです。
メリット4:ブランクがあるより転職にも有利
仕事と育児の両立を頑張ったメリットは、ブランクがある状態より転職に有利になる点です。継続的に働いた経験は、転職を検討する際に有利になります。
- マルチタスクを効率よく進めた実績が評価されやすい
- 限られた時間内での調整力が身についている
- 空白期間がないため、社会人感覚のズレを心配されにくい
例えば、働きながら身についた調整力や段取り力は、職種や業界を問わず役立ちます。子どもの予定と仕事を両立させた経験は、継続力の証明にもなります。
転職市場では、ブランクが長ければ長いほど採用は不利になりがちです。両立が大変ななか、仕事を継続した期間は無駄にはなりません。
将来キャリアアップや転職の可能性があるなら、仕事と育児の両立を頑張っておくと未来の自分を支えてくれるでしょう。
仕事と育児を両立しやすい仕事

仕事と育児を両立しやすい仕事を3つ紹介します。在宅ワークができる仕事なので、通勤に疲れてしまう人や、通勤時間を節約したい人におすすめです。
3つの職種はすべて未経験や初心者でも挑戦しやすく、独立もできます。今の仕事からキャリアチェンジしたい場合や、仕事そのものを変えたいと思っているなら、ぜひ検討してください。
仕事1:WEBデザイナー
WEBデザイナーの仕事は、仕事と育児を両立しやすい仕事です。時間と場所にしばられず作業ができる仕事なため、育児と両立がしやすいです。また、働き方の選択肢も広く柔軟性があります。
- 在宅で完結しやすい
- 自分のペースで進めやすい
- 初心者や未経験からでも挑戦できる
WEBデザイナーは、WEBサイトやバナー画像を作る仕事です。色や文字の配置を考え、見やすい画面に整えます。パソコンがあれば作業でき、通勤の必要がありません。子どもの送迎や急な体調変化にも対応しやすく、生活にあわせて働けます。
仕事と育児を両立する人にとって、移動時間が減る点は大きなメリットです。家事の合間や子どもが寝た後に作業を進められ、まとまった時間を確保できない日でも隙間時間を活用した作業が可能です。
一方で、納期がある点には注意が必要です。予定を立てずに後回しにすると負担が増えてしまうので、作業量を調整して無理なく続けることを意識しましょう。
仕事と育児の両立で疲れやすい人でも、働き方を工夫すれば継続できます。働きやすい環境で、仕事と子育てを両立したいならおすすめの選択肢です。
WEBデザインの特徴まとめ
| 必須スキルと知識 |
| ・基本的なデザイン知識 ・デザインツールの操作スキル(Photoshop、Illustrator) ・基本的なコーディング知識(HTML/CSS) |
| 収入目安/単価 |
| ・月収25〜40万円程度(会社員の場合) ・月収5〜数十万(フリーランス/副業の場合) ・バナー制作:1,000〜10,000円/件 ・WEBサイト制作:10〜100万(規模による) ・ランディングページ:10〜50万 |
| WEBデザインの仕事に就く方法 |
| ・クラウドソーシングサイトを活用する(ランサーズ、クラウドワークスなど) ・求人サイトで探す(インディードや求人ボックスなど) ・スキルシェアサービスに出品する(ストアカやココナラなど) ・ブログやポートフォリオページを作り、情報発信をする ・SNSで検索する(X、Instagram) ・知人から紹介してもらう ・経営者が集まる交流会やオンラインサロンで紹介してもらう |
| 注意点 |
| ・ライバルが多い ・始めは低単価なことが多い ・日々のスキルアップが必要 ・ポートフォリオ制作が必要 |
| おすすめな人 |
| ・デザインが好きな人 ・流行に敏感な人 ・パソコン作業に抵抗がない人 ・自主的に学び続けられる人 |
| 必須スキルと知識 |
| ・基本的なデザイン知識 ・デザインツールの操作スキル(Photoshop、Illustrator) ・基本的なコーディング知識(HTML/CSS) |
| 収入目安/単価 |
| ・月収25〜40万円程度(会社員の場合) ・月収5〜数十万(フリーランス/副業の場合) ・バナー制作:1,000〜10,000円/件 ・WEBサイト制作:10〜100万(規模による) ・ランディングページ:10〜50万 |
| WEBデザインの仕事に就く方法 |
| ・クラウドソーシングサイトを活用する(ランサーズ、クラウドワークスなど) ・求人サイトで探す(インディードや求人ボックスなど) ・スキルシェアサービスに出品する(ストアカやココナラなど) ・ブログやポートフォリオページを作り、情報発信をする ・SNSで検索する(X、Instagram) ・知人から紹介してもらう ・経営者が集まる交流会やオンラインサロンで紹介してもらう |
| 注意点 |
| ・ライバルが多い ・始めは低単価なことが多い ・日々のスキルアップが必要 ・ポートフォリオ制作が必要 |
| おすすめな人 |
| ・デザインが好きな人 ・流行に敏感な人 ・パソコン作業に抵抗がない人 ・自主的に学び続けられる人 |
▼WEBデザインの副業を始める4ステップは、以下の記事で紹介しています。
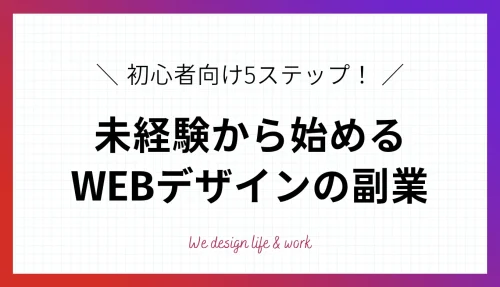
WEBデザインを副業でスタートして、スクール卒業後すぐに10万円稼げた「かすみん」の事例を紹介します。
子どもが小学生になったタイミングで、習い事の送迎などとやりくりしやすい在宅ワークを検討したかすみん。事務職に就いたため、まずは副業でWEBデザインを始めました。
WEBデザインスクールを卒業してすぐ、月収10万円を稼ぐことに成功。案件の応募で気をつけたことや、単価を上げる戦略など詳細は以下のリンクからご覧ください。
▼以下は、子どもと過ごす時間を増やすために在宅ワークを実現したいと考え、WEBデザイナーに挑戦した方の事例です。

「在宅で働けるのは魅力的だけど、本当に自分にもできる?」と不安に感じる方もいるかもしれません。大切なのは、限られた時間の中で何から始めればいいかを知ること。
【逆算式ロードマップセミナー】では、未経験から在宅WEBデザインで月20万円を目指すまでの流れを、無料動画でわかりやすく解説しています。まずは全体像をつかむところから始めてみてください。
仕事2:WEBライター
仕事と育児を両立しやすい仕事で、WEBライターもおすすめです。自分の生活を優先しながら続けやすい働き方になります。場所や時間の自由度が高く、育児中の負担を減らしやすい点が特徴です。
- 在宅で完結しやすい
- 初心者・未経験から始めやすい
- 初期費用がほぼかからない
WEBライターは、インターネット上の記事や文章を書く仕事です。パソコンと通信環境があれば始められ、特別な設備は必要ありません。子どもが寝た後や登園後など、細切れの時間でも作業できます。
仕事と育児を両立する人にとって、通勤がない点は大きなメリットです。家事の合間に作業を進められ、急な体調不良にも対応しやすくなります。自分の経験や考えを言葉にする仕事なので、育児の体験がそのまま強みになる点も魅力です。
一方で、フリーランスや副業をやる場合、最初は単価が低く、収入が安定しにくい面があります。ただ、書く本数を増やし、得意分野を見つけると改善が可能です。仕事の継続により評価が積みあがり、条件のよい仕事につながります。
仕事と育児のどちらもあきらめたくない人にとって、WEBライターはおすすめです。無理のないペースで働きたい人に向いています。
WEBライターの特徴まとめ
| 必須スキルと知識 |
| ・タイピングスキル ・わかりやすい文章を書くスキル ・基本的なSEO知識(書籍やインターネットで学べる) ・執筆ツールの操作(Googleドキュメント、Wordなど) |
| 収入目安/単価 |
| ・月収20〜30万円程度(会社員の場合) ・月収5〜数十万(フリーランス/副業の場合) ・文字単価:0.5〜10円 ・記事単価:2,000〜10,000円 ・記事構成:3,000〜10,000円 |
| WEBライターの仕事に就く方法 |
| ・クラウドソーシングサイトを活用する(ランサーズ、クラウドワークスなど) ・求人サイトで探す(インディードや求人ボックスなど) ・スキルシェアサービスに出品する(ストアカやココナラなど) ・ブログやポートフォリオページを作り、情報発信をする ・SNSで検索する(X、Instagram) ・知人から紹介してもらう ・経営者が集まる交流会やオンラインサロンで紹介してもらう |
| 注意点 |
| ・ライバルが多い ・低単価なものも含まれる ・最初は稼げない ・納期が厳しい案件がある |
| おすすめな人 |
| ・パソコンで文章を打つことに抵抗がない人 ・未経験から収入につなげたい人 ・インターネットでの情報収集が得意な人 ・情報をまとめることが得意な人 ・もくもくとやる作業が好きな人 |
| 必須スキルと知識 |
| ・タイピングスキル ・わかりやすい文章を書くスキル ・基本的なSEO知識(書籍やインターネットで学べる) ・執筆ツールの操作(Googleドキュメント、Wordなど) |
| 収入目安/単価 |
| ・月収20〜30万円程度(会社員の場合) ・月収5〜数十万(フリーランス/副業の場合) ・文字単価:0.5〜10円 ・記事単価:2,000〜10,000円 ・記事構成:3,000〜10,000円 |
| WEBライターの仕事に就く方法 |
| ・クラウドソーシングサイトを活用する(ランサーズ、クラウドワークスなど) ・求人サイトで探す(インディードや求人ボックスなど) ・スキルシェアサービスに出品する(ストアカやココナラなど) ・ブログやポートフォリオページを作り、情報発信をする ・SNSで検索する(X、Instagram) ・知人から紹介してもらう ・経営者が集まる交流会やオンラインサロンで紹介してもらう |
| 注意点 |
| ・ライバルが多い ・低単価なものも含まれる ・最初は稼げない ・納期が厳しい案件がある |
| おすすめな人 |
| ・パソコンで文章を打つことに抵抗がない人 ・未経験から収入につなげたい人 ・インターネットでの情報収集が得意な人 ・情報をまとめることが得意な人 ・もくもくとやる作業が好きな人 |
▼以下の記事では、WEBライターになるための知識や、実体験をもとにしたなり方を解説しています。
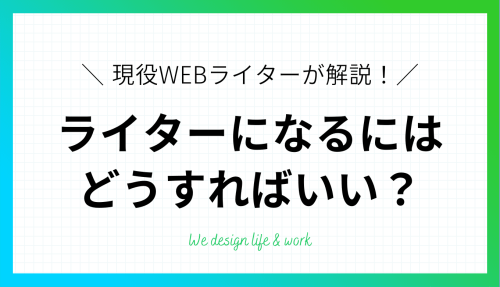
仕事3:オンライン事務/秘書
育児経験を活かせるオンライン事務/秘書の仕事も、両立しやすくおすすめです。生活リズムをくずさず続けやすい働き方になります。裏方として人を支える仕事のため、安定した需要がある点も特徴です。
- 在宅で完結する業務が多い
- 決まった作業を淡々と進めやすい
- 育児経験が仕事に活きやすい
オンライン事務/秘書は、スケジュール管理やメール対応、資料作成などをオンラインでサポートする仕事です。会社に出社せず、自宅からやり取りをおこないます。パソコン操作が中心なので、子どもが登園している間や就寝後の時間も使えます。
仕事と育児を両立する人にとって、急な予定変更に対応しやすい点は大きなメリットです。細かな連絡や気配りが求められるため、育児で身についた段取り力が役立ちます。長時間集中がむずかしい人でも、タスク単位で進めやすい点も魅力です。
一方で、相手都合の連絡が入る場合があります。対応時間をあらかじめ決めると負担を減らせます。条件をすりあわせれば、無理なく続けられるでしょう。
仕事と育児の両方を大切にしたい人や、人を支えるのが好きな人には、オンライン事務/秘書はおすすめです。
オンライン事務/秘書の特徴まとめ
| 必須スキルと知識 |
| ・基本的なパソコン操作スキル ・コミュニケーション能力 ・スケジュール調整力 ・ビジネスメールの文書を作成するスキル ・社会人としてのビジネスマナー |
| 収入目安/単価 |
| ・月収15〜20万円程度 ・時給1,500〜2,000円程度 |
| オンライン事務/秘書の仕事に就く方法 |
| ・クラウドソーシングサイトで探す(ランサーズ、クラウドワークスなど) ・求人サイトで探す(インディードや求人ボックスなど) ・スキルシェアサービスで出品する(ストアカやココナラなど) ・SNSで発信する(XやInstagram) ・知人から紹介してもらう ・経営者が集まる交流会などで紹介してもらう |
| 注意点 |
| ・ライバルが多い ・業務範囲が広い ・パソコンの操作が苦手な人はむずかしい |
| 向いている人 |
| ・パソコンの操作に抵抗がない人 ・経理や秘書業務の経験がある人 ・マルチタスクが得意な人 ・臨機応変な対応ができる人 ・淡々と作業ができる人 ・細部まで注意がはらえる人 ・ビジネスマナーを守れる人 |
| 必須スキルと知識 |
| ・基本的なパソコン操作スキル ・コミュニケーション能力 ・スケジュール調整力 ・ビジネスメールの文書を作成するスキル ・社会人としてのビジネスマナー |
| 収入目安/単価 |
| ・月収15〜20万円程度 ・時給1,500〜2,000円程度 |
| オンライン事務/秘書の仕事に就く方法 |
| ・クラウドソーシングサイトで探す(ランサーズ、クラウドワークスなど) ・求人サイトで探す(インディードや求人ボックスなど) ・スキルシェアサービスで出品する(ストアカやココナラなど) ・SNSで発信する(XやInstagram) ・知人から紹介してもらう ・経営者が集まる交流会などで紹介してもらう |
| 注意点 |
| ・ライバルが多い ・業務範囲が広い ・パソコンの操作が苦手な人はむずかしい |
| 向いている人 |
| ・パソコンの操作に抵抗がない人 ・経理や秘書業務の経験がある人 ・マルチタスクが得意な人 ・臨機応変な対応ができる人 ・淡々と作業ができる人 ・細部まで注意がはらえる人 ・ビジネスマナーを守れる人 |
まとめ
仕事と育児の両立に疲れているなら、まずは周囲の手を積極的に借りて負担を分散する仕組みを作りましょう。子育て世帯向けのサービスや会社の制度も、拡充傾向にあるため、情報収集を欠かさずおこない取り入れるのがおすすめです。
- ベビー/キッズシッター
- ファミリーサポート
- 病児保育
- 食材宅配
- 育児休業(父親と母親)
- 時短勤務
- リモートワーク
- フレックスタイム
- 働き方の切り替え
また、仕事と育児が両立しやすい仕事に就くのもおすすめです。WEBデザイナーやWEBライター、オンライン事務/秘書ならパソコンがあればどこでも作業ができます。通勤が必要なくなる分、毎日の生活に余裕が生まれて精神的にも安心です。
両立に疲れて勢いで仕事を辞めるのは、上記のような職業を検討してからでも遅くはありません。仕事を継続していると、金銭的な余裕が生まれ家計のやりくりもスムーズです。親の役割からいったん離れることで、気分転換の効果もあります。
子育てと仕事の両立に追われる毎日かもしれませんが、一度立ち止まって活用できるサービスや転職の可能性も考えてください。
この記事を通して、あなたの「働き方」や「今後のキャリア」について考えるきっかけになれば幸いです。
もし「負担を軽減するために在宅で働けるスキルを身につけたい」と思うなら、【WEBデザイナーという働き方セミナー】がおすすめです。
実例を交えながら、WEBデザイナーという職業のリアルをイメージしやすく学べる内容です。