これからWEBライターになる人も、WEBライターとして活動している人も「文章力を上げたい」という想いはあると思います。
しかし、そう思ったときに気をつけてほしいのが、文章力の定義。
WEBライターに求められる文章力は、小説家やエッセイストに求められる文章力と違います。
それを知らずに文章術を学んでも、良い記事を書くことはできませんし、WEBライターとして稼ぐのも難しいです。
そこで、この記事ではWEBライターに必要は文章力とはなにかをお伝えしたうえで
- 文章力を上げるために意識すべきこと
- 文章力を上げる練習法
- 文章力を上げるのにおすすめの本
を紹介していきます。
今回お伝えすることを実践すれば、文章力が上がるのは間違いないので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
【お知らせ】
2000名以上の人生を変えるキッカケになった「好きなことで生きていく!WEBデザイナーという働き方セミナー」では、
などをお伝えしています。今だけ無料で開催しているので「WEBデザインの学び方がわからない」「WEBデザイン業界について知りたい」という方はぜひご参加ください。
>>詳しくはこちら
WEBライティングにおける文章力とは?
WEBライティングにおいて、文章力とは「どんな人にも通じるくらい簡単で、わかりやすい文章を書く力」です。
なぜならWEB記事は多種多様な人が読むからです。
例えば「WEBライター 副業」と調べる人のなかにもさまざまな人がいます。
年齢も性別も、経歴もまったく違います。
そのため、一部の人しかわからない専門用語や難しい言葉ではなく、どんな人でも理解できる言葉を書く必要があります。
また、WEB記事の文章にはわかりやすさも大切です。
WEB記事を読みにくる人が求めているのは、あくまで自分の悩みを解決してくれる情報。
文学的な文章や、凝った回りくどい文章はかえって読みにくいと思われてしまうので「わかりやすいかどうか」を重視しましょう。
※誰にでもわかるくらい簡単な文章を書くのは大切ですが、誰にでもわかるくらい簡単な内容を書くわけではないので注意してくださいね。書く内容は読者のレベルによって変えるようにしましょう。
文章力を上げるには型が重要!WEBライターが活用すべき基本の型
初心者の方が文章力を上げるときに重要なのが、文章の型です。
文章にはいくつかの型があります。
型を活用すれば、文章を書くのに慣れていない人でもわかりやすい文章が書けます。
ここでは初心者の方におすすめの型を2つご紹介するので、ぜひ使ってみてくださいね。
PREP法
文章の型として、多くの人に使われているのがPREP法です。
PREP法は「結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→結論(Point)」の順番で伝える方法で、文章が簡潔かつ説得力のあるものになります。
何か主張したいことがあるときによく使われますね。
▼PREP法を使って書いた文章
| 結論:WEBライティングは副業におすすめの職業です。 理由:なぜなら、スキルを磨くことと収入を増やすことが同時にできるからです。 具体例:現にビズヒッツの調査によると、WEBライターになってよかったこととして、「スキルアップができること」が1位、「収入を増やせること」が2位でした。 結論:もしあなたがどんな副業をしようか迷っているなら、WEBライティングをしてみましょう。 |
SDS法
何かを説明するときに使うと良いのがSDS法です。
SDS法は「概要(Summary)→詳細(Details)→要点(Summary)」といった流れで書いていく文章の型で、用語の説明や商品紹介に使うことが多いです。
実際にSDS法を使うと次のような文章が書けます。
▼SDS法を使った文章
| 概要:WEBライターはWEB上に掲載する文章を書く仕事です。 詳細:具体的には「ノウハウ記事の作成」「シナリオの作成」「インタビュー記事の作成」「メルマガの作成」などが仕事内容になります。 要点:特にノウハウ記事の作成をしているWEBライターが多くいます。 |
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
WEBライターが文章力を上げるための6つのコツ
文章力を上げる(良い文章を書けるようになる)のに特別なテクニックは必要はありません。
いくつかコツを覚えるだけで、文章力はグッと上がります。
ここでは文章力を上げるコツを6つご紹介するので、ぜひ実践してみてくださいね。
ターゲットを明確にする
文章力を上げるコツとして、ターゲットを明確にすることがあります。
ターゲットを明確にすればするほど、より読者に寄り添った(読者に刺さる)文章を書けるようになるからです。
例えば「WEBライター 文章力」といったキーワードでも「これからWEBライターになる人に向けた記事」と「現役のWEBライターに向けた記事」では書く内容が大きく違ってきます。
「これからWEBライターになる人」をターゲットにするなら、基本的な文章のルールからお伝えするのがベストです。
しかし現役WEBライターなら少しレベルの高いテクニックをお伝えしたほうが満足してもらえます。
このようにターゲットによってどんな内容を書くかは大きく変わってきます。
だからこそ、誰をターゲットにするかが大切なのです。
もちろんターゲットを絞ることで、当てはまらない人が増えるのも事実です。
しかし、誰にも刺さらない文章ができては元も子もないので、文章を書くときにはターゲットを絞るようにしましょう。
一文はできるだけ短くする
文章力を上げるには、一文の長さを短くするのも効果的。
一文を短くすると文章にリズムが生まれ、テンポよく読めるようになるからです。
文章を短くしたいときは、「〜ので」や「〜が」などの助詞に注目してみましょう。
例えば「私はWEBライターとして稼ぎたいので、文章力を磨いている」という文章なら、「ので」で文章を切れないか考えてみるのです。
文を二文に分けるだけでリズミカルな文章になりますよ。
一般的に一文は40文字〜60文字が適切だと言われています。1つの参考にしてくださいね。
文章に具体性を持たせる
具体的な文章を心がけることも、文章力を上げるうえで大切です。
例えば「文章を書くときは漢字を少なめにして、ひらがなを多くしましょう。」という文章があったとします。
たしかに意味はわかりますし、文法的にも間違っていないのですが、正直どれくらい漢字を少なくすればいいか、ひらがなを多くすればいいかわからないですよね。
一方、同じ内容でも「文章を書くときは漢字とひらがなを3:7にしましょう。」と書いてあれば、どれくらいのバランスで文章を書けばいいかわかりやすく、行動に移しやすいですよね。
このように文章に具体性を持たせることで、一気にわかりやすい文章になります。
文章に具体性を持たせるコツは次の2つ。
- 数値化できるものは数字で表す
- 5W1Hを明確にする
文章を書くときや、見直すときにこの2つが満たされているかを必ず意識してくださいね。
それだけで文章のクオリティが大きく変わります。
5W1H…「When(いつ)」「Where(どこで)」「What(何を)」「Who(誰と)」「Why(なぜ)」「How(どうやって)」の頭文字をとった言葉。状況を表すときに使われます。
同じ語尾が続きすぎないようにする
同じ語尾が続きすぎないようにするのも、良い文章を書けるようになるコツ。
同じ語尾が続いてしまうと、文章のリズムが悪くなるからです。
毎回語尾を変える必要はありません。
2回連続くらいであれば大丈夫です。
同じ語尾が3回以上続く場合にのみ「語尾を他のものに変えられないか」と考えてみてくださいね。
※ただし、「〜ください」「〜しょう」といった相手の行動を促す語尾は2回連続でも鬱陶しく思われることがあります。使うときは前に同じ語尾がないか確認しましょう。
▼語尾が続きすぎている文章
| できるだけ勉強にお金をかけたくない方におすすめのコンテンツがYouTubeです。 YouTubeの魅力はやはり無料でWEBライティングが学べることです。 「無料だと質が低いのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、決してそんなことはないです。 |
▼語尾が続いていない文章
| できるだけ勉強にお金をかけたくない方におすすめなのがYouTubeです。 YouTubeなら無料でWEBライティングが学べます。 「無料だと質が低いのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、決してそんなことはありませんよ。 |
指示語を多用しない
多くのWEBライターがよくやってしまうのが「指示語の多用」です。
指示語とは「それ」「これ」「あれ」「どれ」といった言葉で、前に出てきた言葉の代わりに使うものです。
指示語は同じ言葉が並びすぎないようにする効果があるのですが、その一方で多用すると指示語が何を指しているのかわからなくなります。
特にWEB記事は流し読みされやすい媒体です。
指示語を使いすぎると読者が迷子になる可能性が高いので、できる限り指示語を避けるようにしましょう。
▼指示語が多すぎる文章
| WEBライターとして稼いでいくならSEOの知識も身につけておきたいです。 それを日本語訳すると「検索エンジン最適化」。 ザックリいうと「意図的に記事の検索順位を上げること」です。 WEB記事は基本、それが高ければ高いほど見られます。 それはつまり多くのユーザーがメディアに流入するということでもあります。 メディア担当者としては1人でも多くのユーザーが自社サイトに流入して、自社の商品・サービスを知って欲しい、それを買って欲しいと思っているので自然とそれのあるWEBライターに仕事を依頼したくなるのです。 |
▼指示を最小限にした文章
| WEBライターとして稼いでいくならSEOの知識も身につけておきたいです。 SEOの日本語訳は「検索エンジン最適化」。 ザックリいうと「意図的に記事の検索順位を上げること」です。 SEO記事は基本、検索順位が高ければ高いほど見られます。 それはつまり多くのユーザーがメディアに流入するということでもあります。 メディア担当者としては1人でも多くのユーザーが自社サイトに流入して、自社の商品・サービスを知って欲しい、買って欲しいと思っているので自然とSEOの知識のあるWEBライターに仕事を依頼したくなるのです。 |
漢字とひらがなの割合を3:7にする
文章力を上げるには、ビジュアルを意識することも重要です。
漢字が多すぎると全体的に文章がつまっているように見えて読みにくいですし、逆にひらがなが多すぎると意味の切れ目がどこにあるかわかりにくくなります。
一般的に漢字とひらがなの割合は3:7がベストだといわれています。
実際のところそれほど細かく割合を気にする必要はありませんが、3:7を意識して書くのは大切です。
次に漢字とひらがなの割合が3:7になっている文章を載せるので、ぜひ参考にしてくださいね。
| クラウドソーシングに登録したら案件に応募していきましょう。 「本当に取れるのかな…」という不安もあると思いますが、安心してください。 ここまでお伝えしたことを実践していれば未経験でも仕事を取ることは十分可能です。 逆に自信がないからといって文字単価が低すぎる案件に応募しないようにしましょう。 |
WEBライターが文章力を上げるための練習法
文章力を上げるコツをお伝えしましたが、いきなりそれを実践するのは難しいですよね。
そこで、ここからはWEBライターが文章力を上げるための練習法をお伝えしていきます。
良い文章を模写する
文章力を上げるには良い文章を模写するのがおすすめです。
文章の模写には
- 良い文章にどんな特徴があるか分析できる
- 良い文章が体に染みつく
といったメリットがあるからです。
実際に、WEBライターのなかにも文章力を上げるために、模写をしている人は多くいますよ。
ただし、文章を模写するときには、悪い参考を選ばないように注意が必要です。
参考の質が低いと自分の文章もそうなってしまうからです。
模写をするなら名著と呼ばれているもの、もしくは実績のあるライターが書いた文章を参考にしましょう。
本や映画を要約する
本や映画の内容を要約するのも文章力を上げるのに効果的です。
要約をすることで、情報の大事なところを抜粋してまとめる力がつくからです。
WEB記事を作成するときにはリサーチをしてその情報をまとめる必要があるので、要約力がつくとより良い文章を書けるようになりますよ。
大事なのは「多くの情報から重要な情報を抜き出すこと」なので、要約するのはどんなものでも大丈夫です。
自分の好きな本や映画を見て、それを要約すれば楽しみながらスキルアップができますよ。
ブログを開設して記事を書く
文章力を上げるために個人ブログを開設するのもおすすめ。
ブログを開設すれば、より実務に近い形で文章の練習ができます。
また、ブログには文章力を磨けること以外にも
- ポートフォリオになる作品を作れる
- 記事投稿ができるようになる(WordPressでブログを作った場合のみ)
といったメリットもあります。
WordPressで記事を投稿できるようになれば、クライアントからその仕事をもらえることもありますよ。
Twitterで発信し続ける
文章力を上げるにはTwitterも使えます。
Twitterは140字以内の文章を書く必要があります。(実際には140文字以上も書けるのですが、綺麗に表示できるのは140文字です。)
そのため、自分の伝えたい内容を端的に伝える力が身につくのです。
また、Twitterには多くの案件があります。
日頃から自分のことを発信していると、案件に応募したときも自分のことを理解してもらいやすくなりますよ。
発信をみたクライアントから「仕事を依頼したいです」と声をかけられることもあります。
WEBライターが文章力を上げるのにおすすめの本3選
文章力を上げるために、本で知識をインプットするのも効果的です。
本では、プロのWEBライターが実践していることが具体例とともに紹介されているので、とても役立ちます。
ここでは、文章力を上げるのにおすすめの本を紹介していくので、ぜひ本を買うときの参考にしてくださいね。
『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』
多くのWEBライターが「この本が一番良かった!」といっているのが、『新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング』です。
ニュースサイト「ナタリー」で新人社員を教育している方が、これまでの経験をもとに文章術を教えてくれます。
文章を書くときの77のルールが初心者向けに書かれており、この本に書かれていることを実践すれば文章力がグッと上がりますよ。
▼本書の情報
| 著者 | 唐木 元 |
| 定価 | 1,430円(税込) |
| ページ数 | 208ページ |
| 発売日 | 2015/08/01 |
| 商品URL | 新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング |
『文章力の基本』
文章の基礎をしっかり固められるのが『文章力の基本』です。
タイトルの通り文章における基本が書かれた本で、「てにをは」の使い方から読者に刺さる文章の書き方まで学べます。
良くも悪くも基本的なことについて書かれているので、なかには物足りない方もいるかもしれません。
しかし、この本に書かれている77のルールが全てできている人はほとんどいません。
「知っているけど、できていなかったこと」に気づくために読んでみるのも良いですよ。
▼本書の情報
| 著者 | 阿部 紘久 |
| 定価 | 1,430円(税込) |
| ページ数 | 206ページ |
| 発売日 | 2009/7/24 |
| 商品URL | 文章力の基本 |
『一瞬で心をつかむ 77の文章テクニック』
文章力を鍛えるのには『一瞬で心をつかむ 77の文章テクニック』を読むのもおすすめです。
この本の特徴は文章の型を学べること。
どんな流れで文章を書けば良いのかが具体的に知れるので、インプットした情報をすぐ実践に活かすことができます。
たくさんテクニックが書かれているのですが、特に参考になるのは「文章の書き出し」についてのテクニックです。
記事を書くにあたって「書き始めに時間がかかってしまう」「いつも同じような書き出しになってしまう」と悩んでいる方にはぜひ読んでほしいです。
▼本書の情報
| 著者 | 高橋 フミアキ |
| 定価 | 1,430円(税込) |
| ページ数 | 208ページ |
| 発売日 | 2013/10/29 |
| 商品URL | 一瞬で心をつかむ 77の文章テクニック |
まとめ
今回はWEBライターが文章力を上げるためのコツと練習法をご紹介してきました。
文章力を上げるために意識すべきことをまとめると次のようになります。
- ターゲットを明確にする
- 一文はできるだけ短くする
- 文章に具体性を持たせる
- 同じ語尾が続きすぎないようにする
- 指示語を多用しない
- 漢字とひらがなの割合を3:7にする
文章力を上げるのは難しいことだと思われがちです。
しかし、実際には今回お伝えしたような細かなルールを徹底できれば、文章力は自然と上がっていきます。
また、文章を上げるうえで結局大切になってくるのは、「たくさん文章を書くこと」です。
最初は思うように書けないことも多いですが、とにかく継続して文章を書いてみましょう。
続けているうちに良い文章を書くコツがつかめてきますよ。

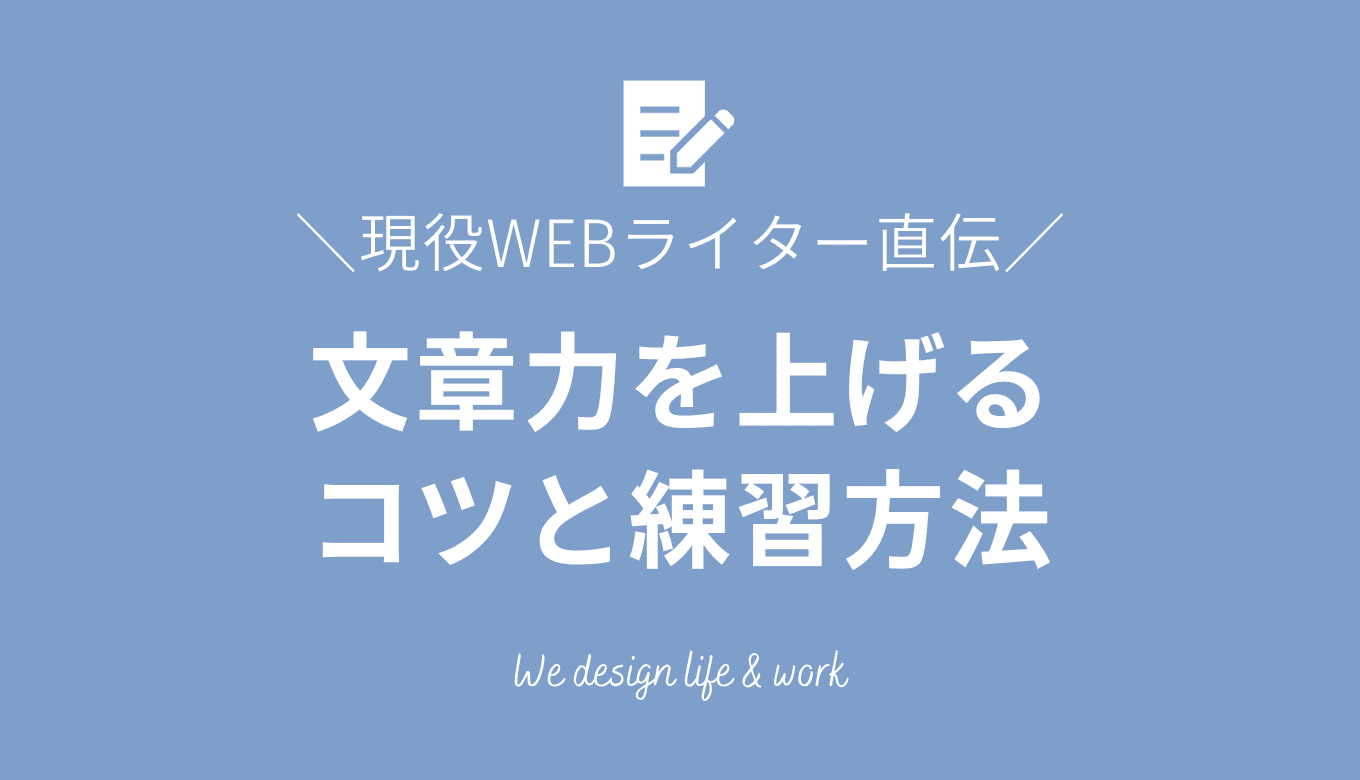
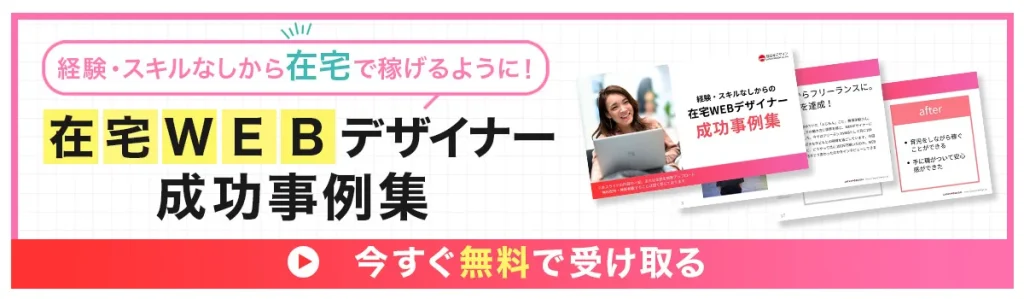
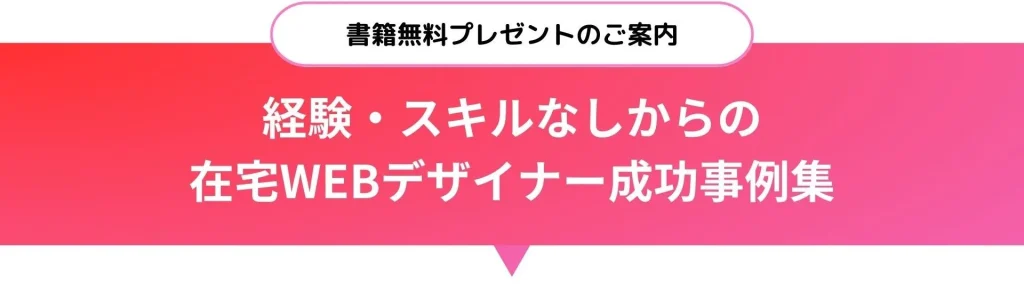
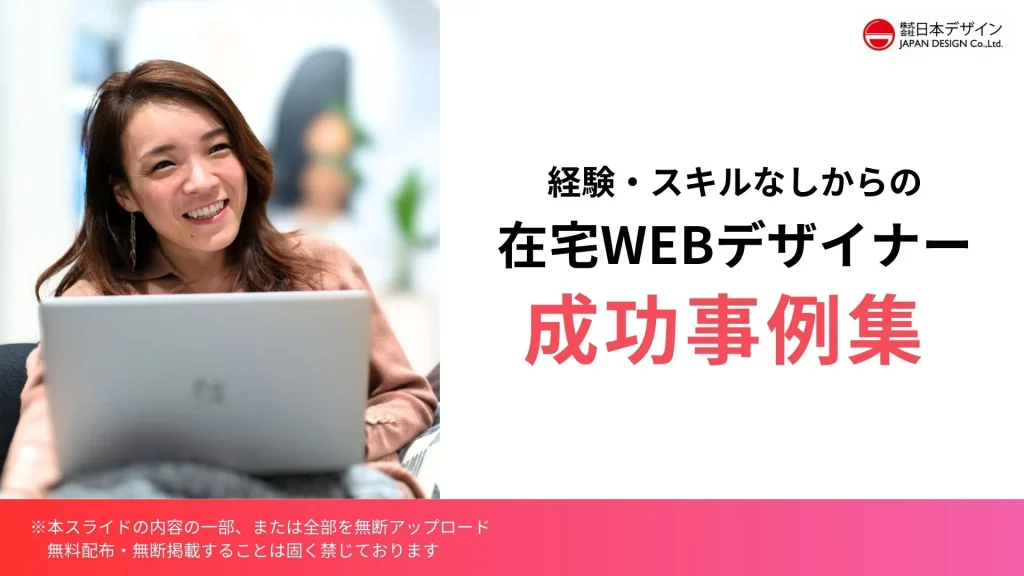
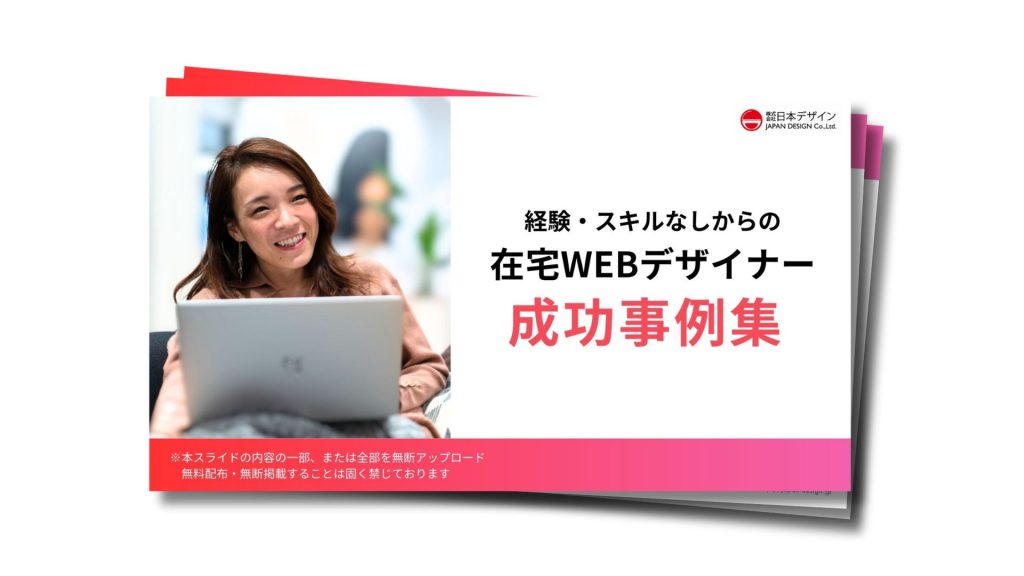
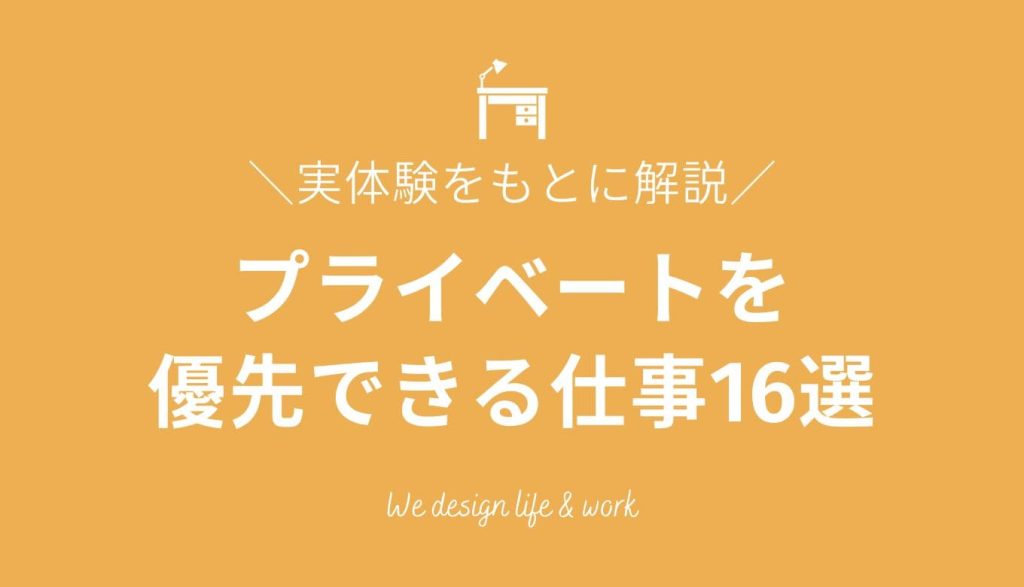
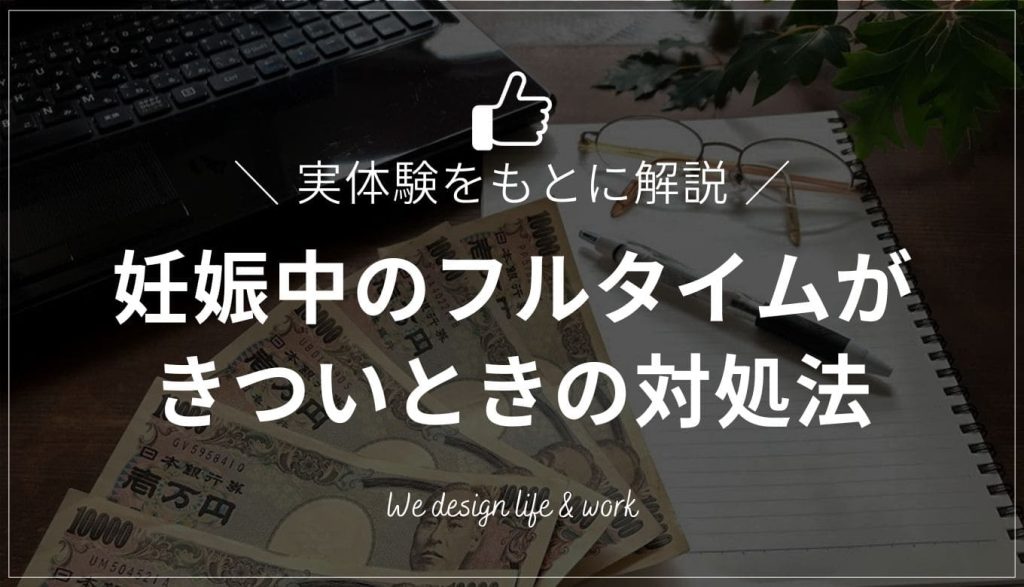
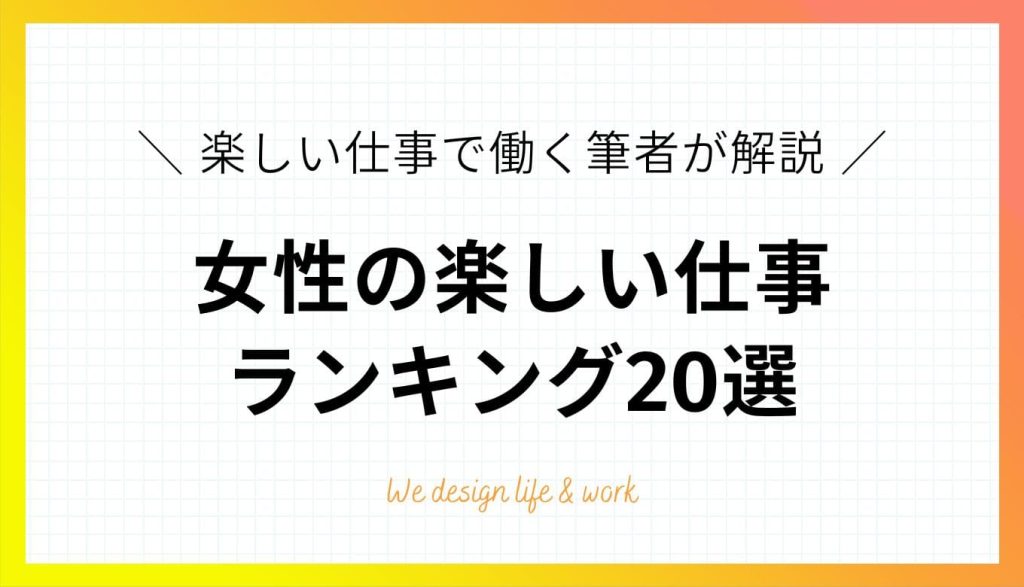
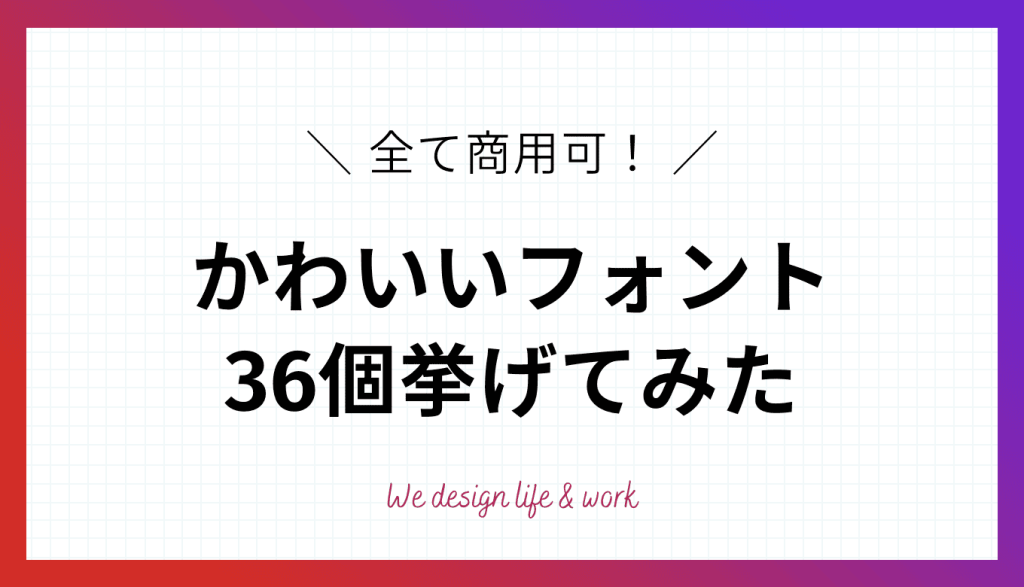

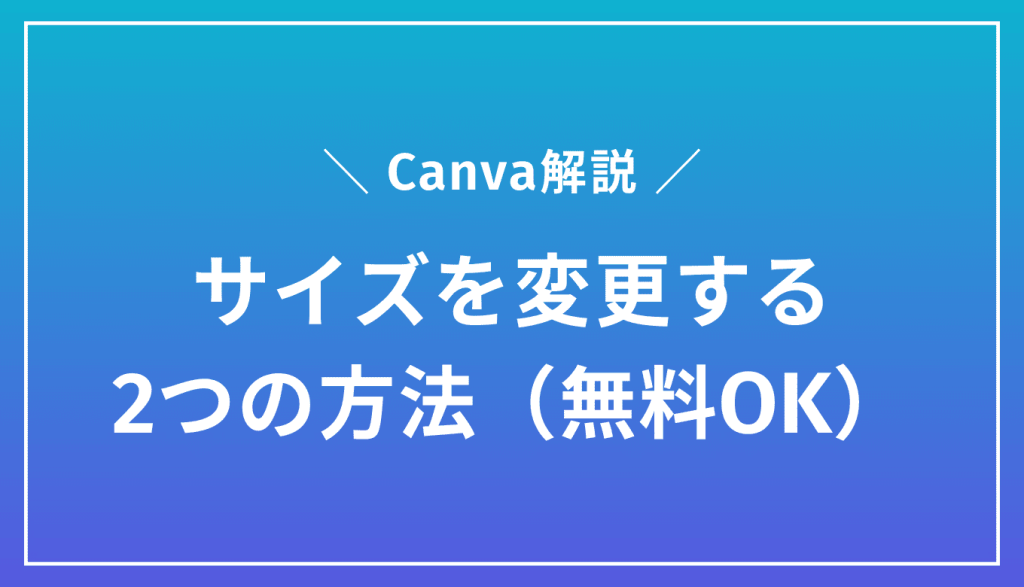
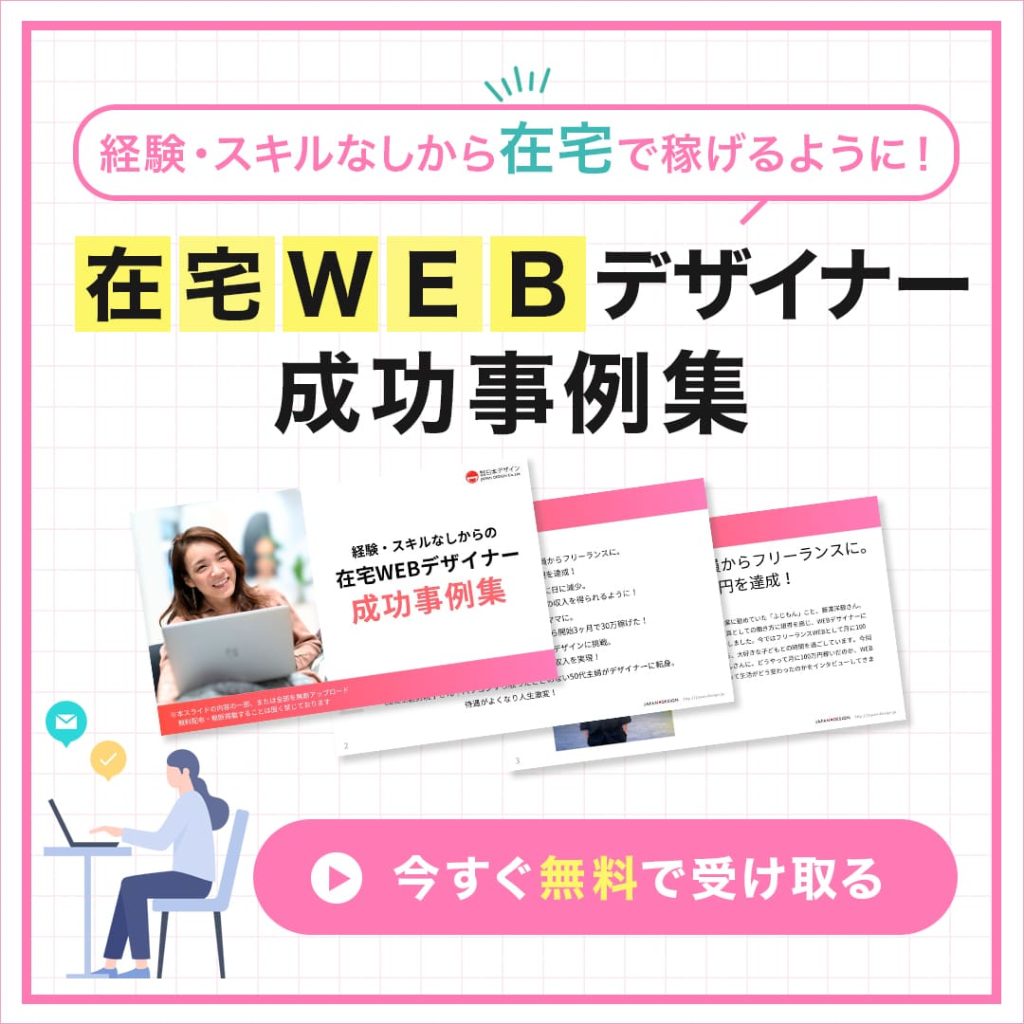

質問や感想があればご記入ください