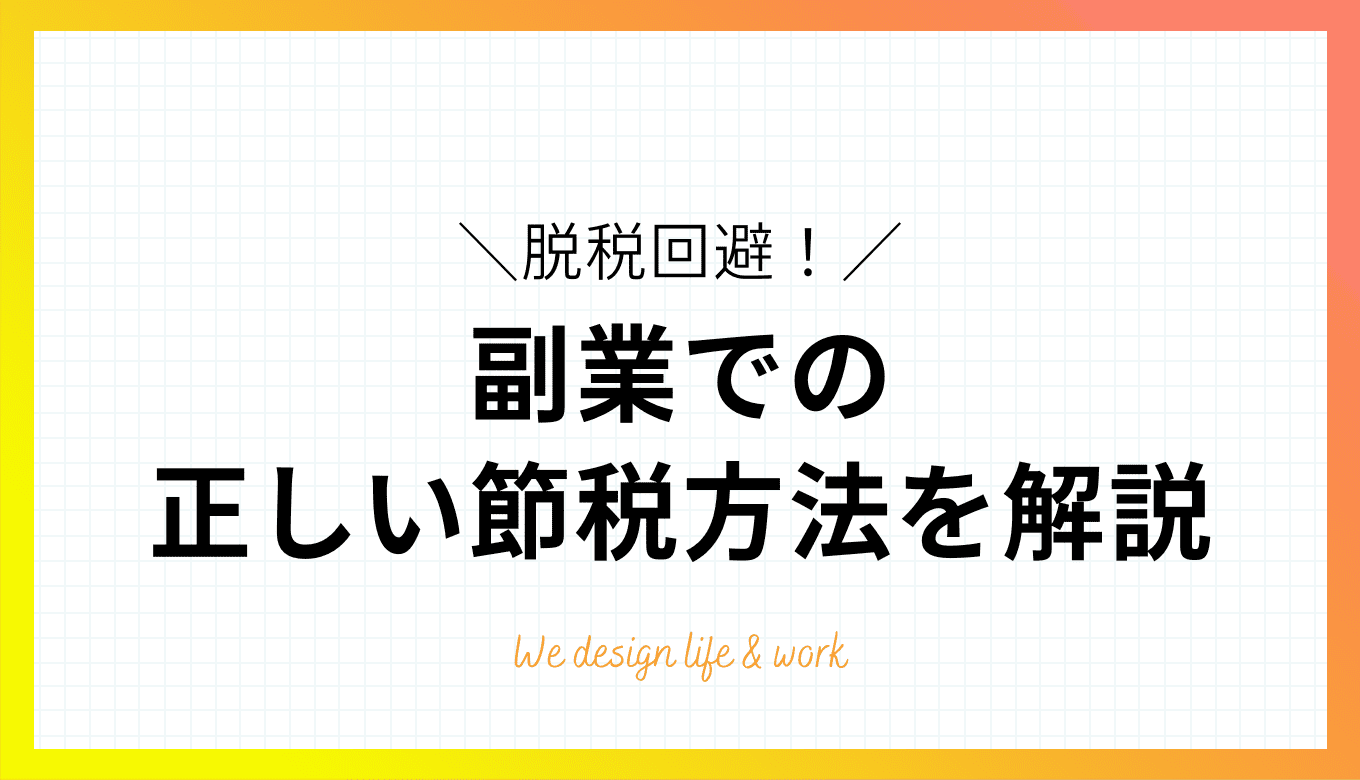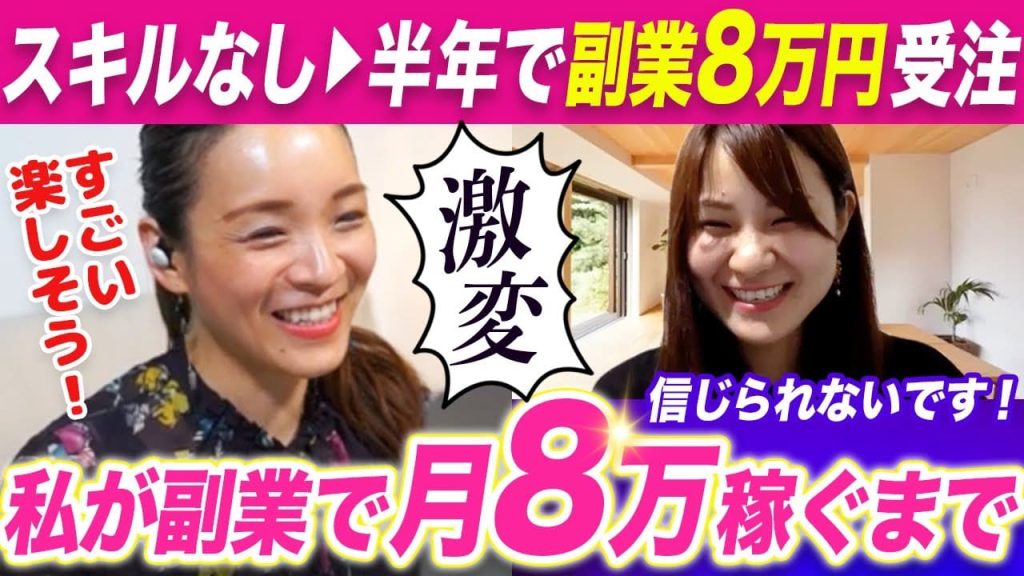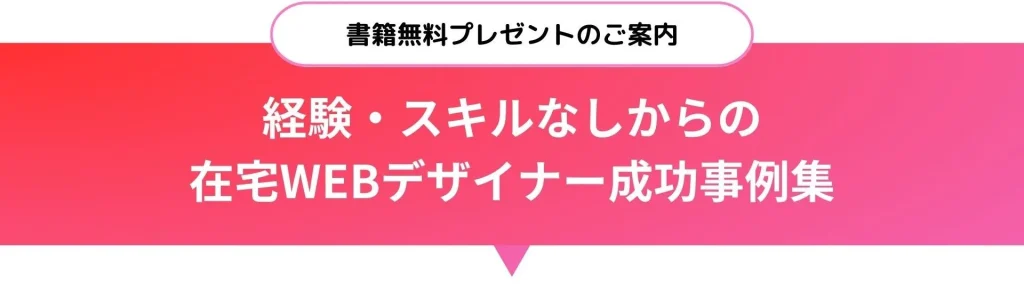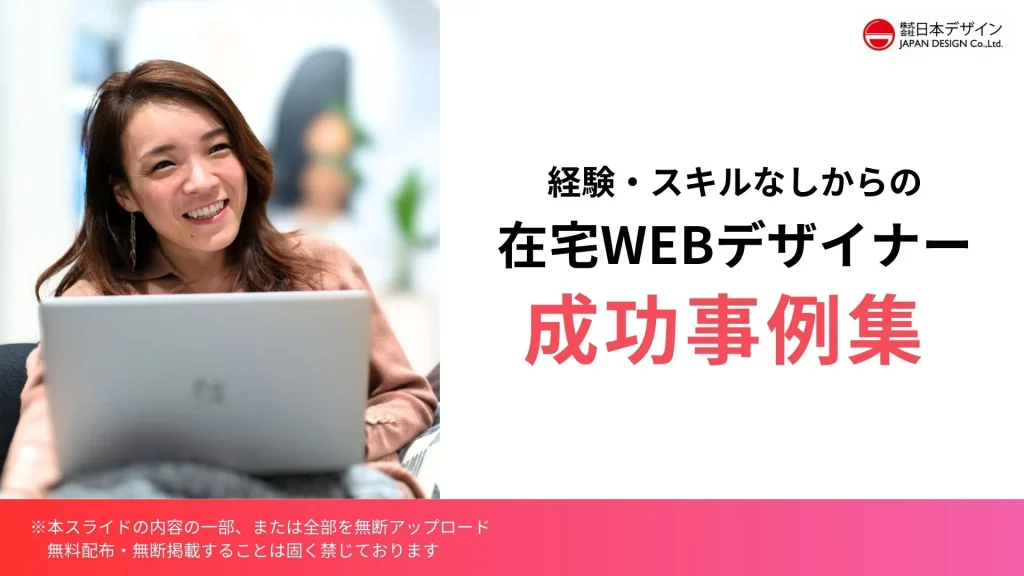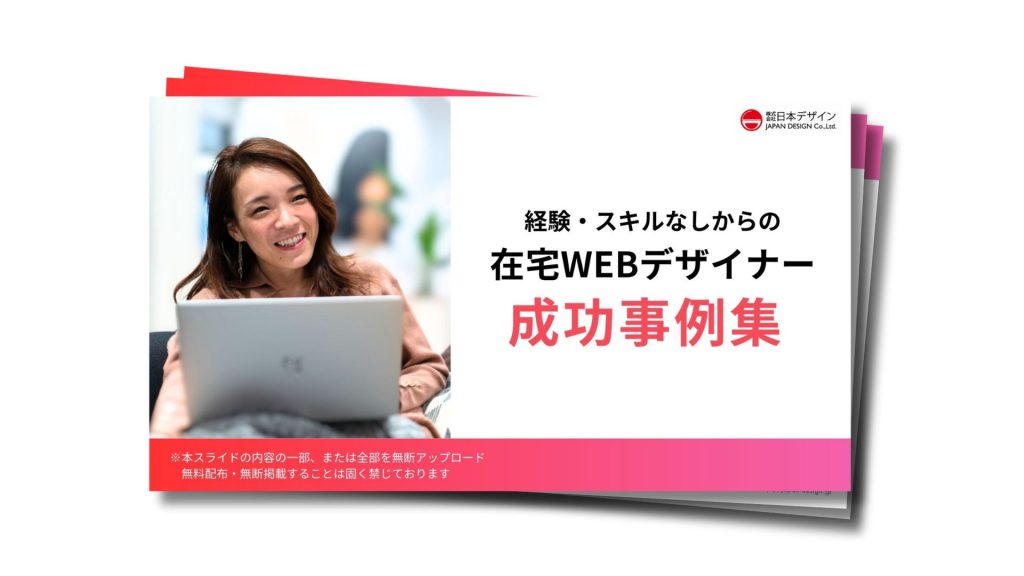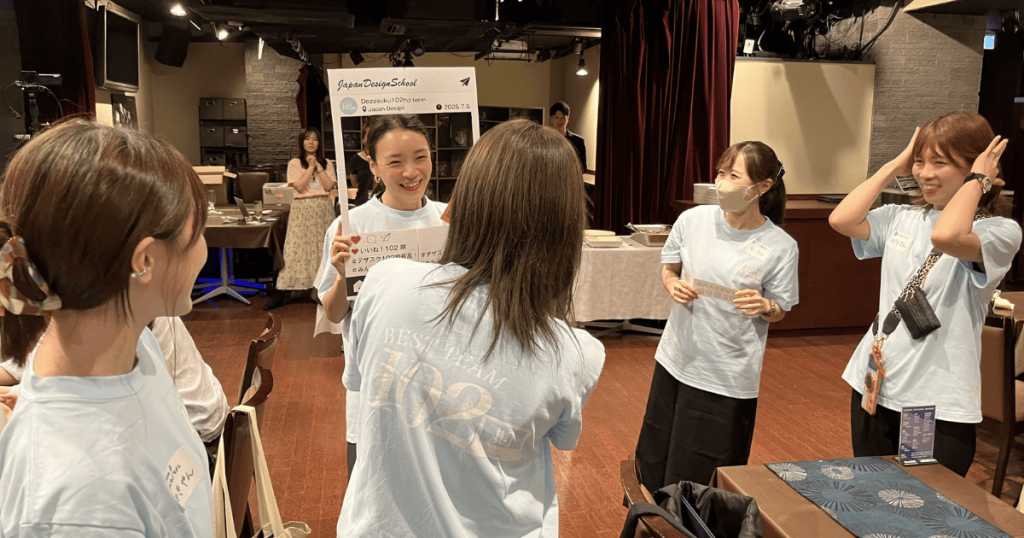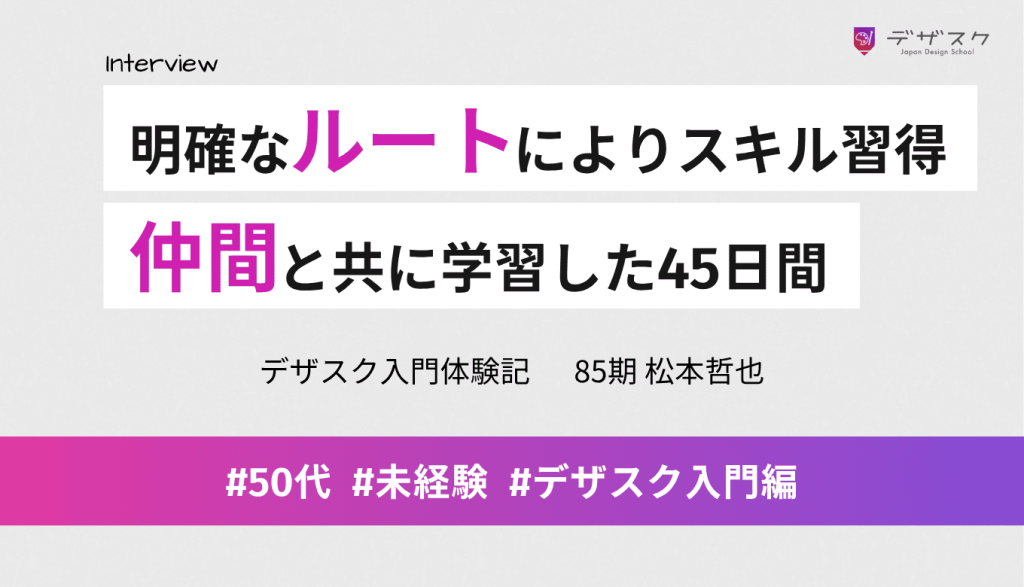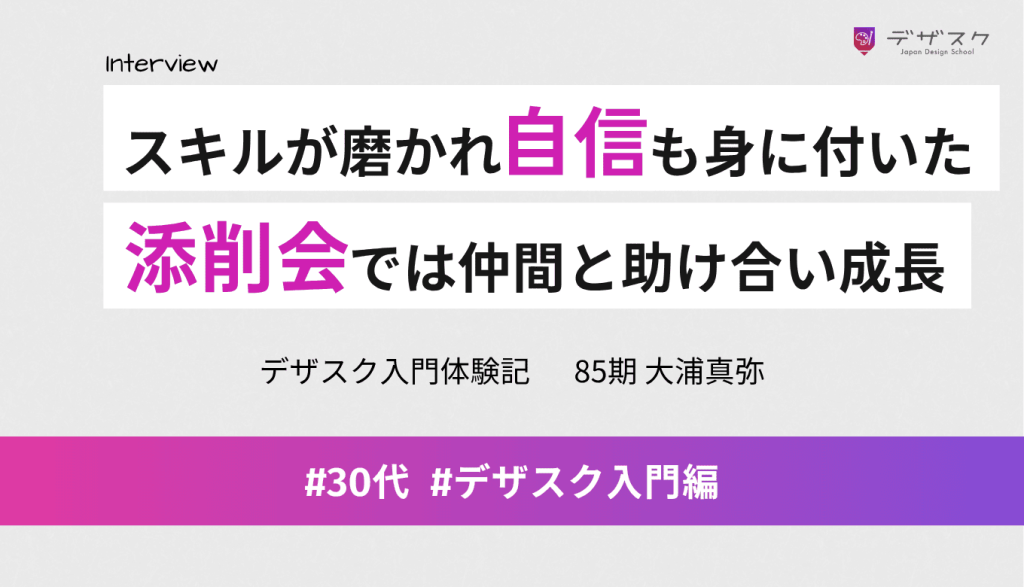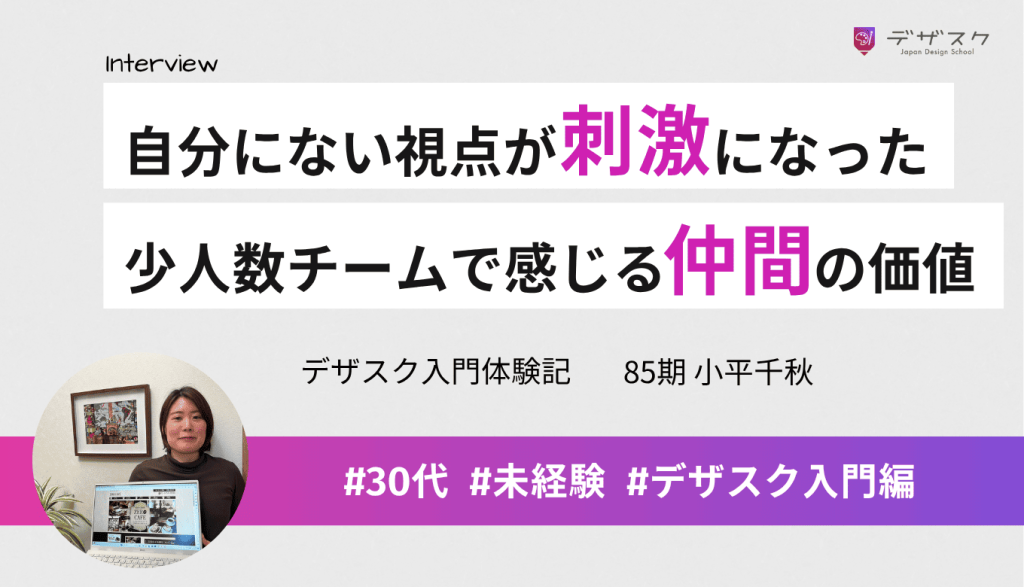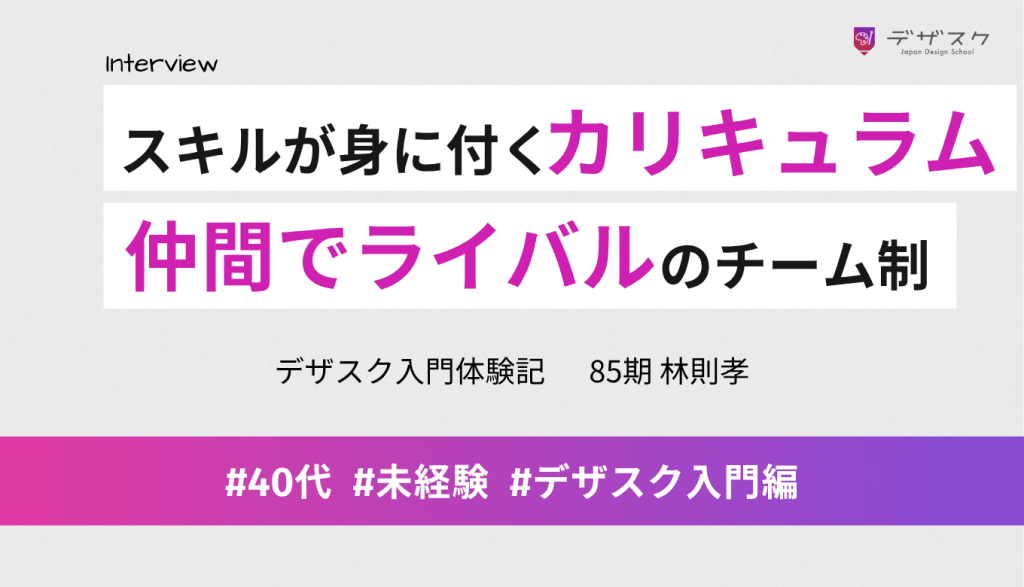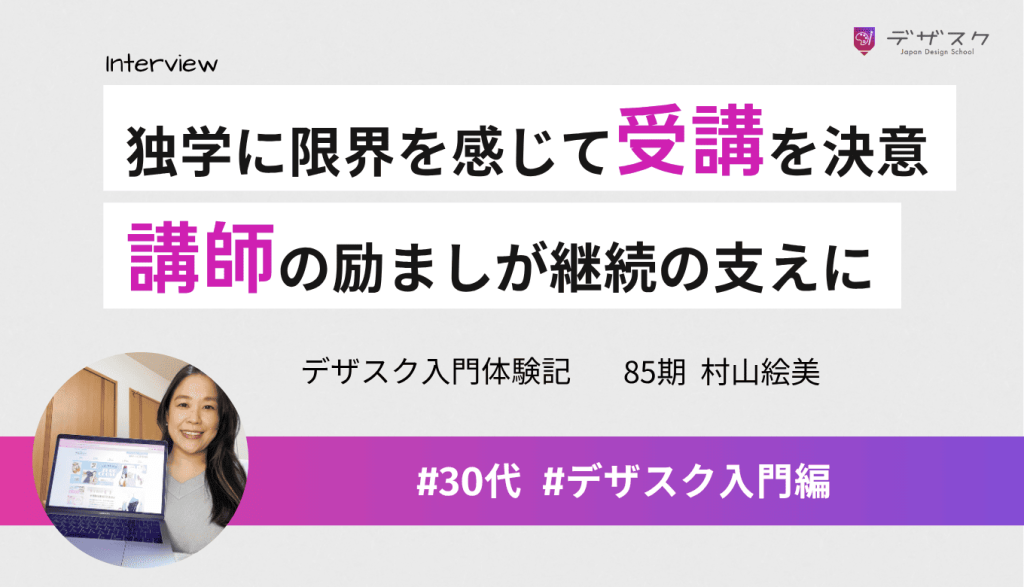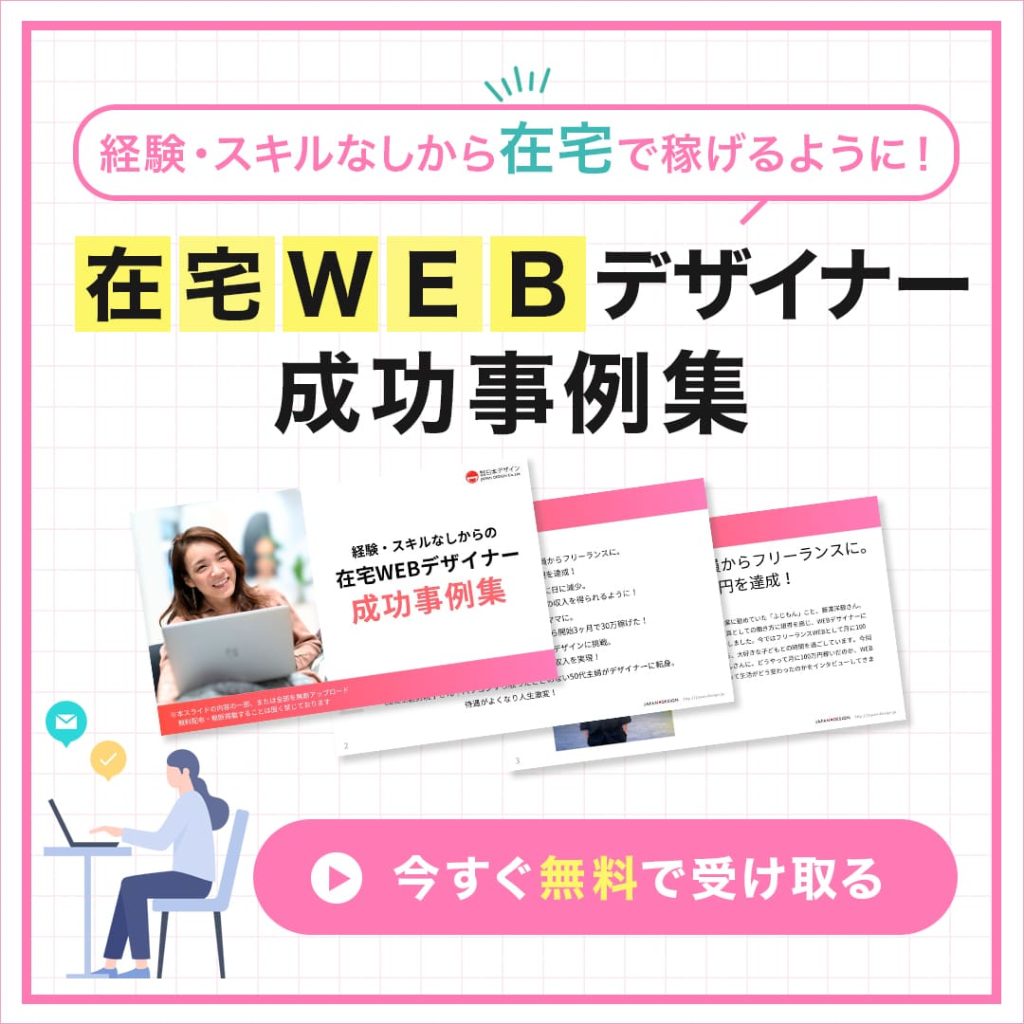「副業してるけど税金対策がわからない…」
「できるなら節税したいけど…」
副業をするときに、税金の話はどうしても気になります。収入を上げるためには、節税することも大切です。脱税にならないように注意したいですよね。
そこで本記事では、副業している人が実践できる節税対策についてお伝えしていきます。
本記事でお伝えする内容は以下の通り。
- 副業ができる5つの節税のやり方
- 脱税にならないための注意点
記事を読んでもらうことで、会社員でも副業で税金対策ができること、脱税にならない正しい節税の方法がわかるはずです。
しっかりとした税金の知識を身につけるためにも、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
【お知らせ】
3,500名以上の人生を変えるキッカケになった「好きなことで生きていく!WEBデザイナーという働き方セミナー」では、
などをお伝えしています。今だけ無料で開催しているので「WEBデザインの学び方がわからない」「WEBデザイン業界について知りたい」という方はぜひご参加ください。
>>詳しくはこちら
副業でもできる5つの税金対策
では、早速、副業でもできる5つの税金対策を解説していきます。
青色申告で特別控除する
まず、紹介する税金対策は「青色申告による特別控除」です。
特別控除は簡単にいうと「課税所得(課税対象となる所得額)から特別にお金を引いて、課税所得を減らしてあげるよ」といった制度。
課税所得が少なくなる分、納めなければいけない税金も少なくなるのです。
そして、この特別控除ができるようになるのが青色申告です。
条件が揃えば最大65万円の特別控除を受けることができます。
控除してもらえる金額は、確定申告するときの形によって変わってきます。
| 控除額 | 条件 |
| 10万円 | 青色申告であること(事業所得であること) |
| 55万円 | ・青色申告であること(事業所得であること) ・複式簿記で青色申告をしていること |
| 65万円 | ・青色申告であること(事業所得であること) ・複式簿記で青色申告をしていること ・e-Taxで青色申告をすること |
大切なのは「複式簿記」と呼ばれる記帳することです。
もう1つの単式簿記より準備が大変ですが、控除額が大きく変わるので、できる限り複式簿記で確定申告をしましょう。
ただし、青色申告をするには条件があります。それは所得が「事業所得」であることです。
2022年10月7日に国税庁から出された「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」で、いくつか例外はあるものの副業でも帳簿をつけていれば「事業所得」と認めてもらえるようになりました。
そのため、副業でも青色申告をしたい人は、自分が例外に当てはまらないかの確認と、帳簿づけをしなければいけません。
青色申告の方法について詳しく解説した記事があるので、実際に青色申告をするときには読んでくださいね。
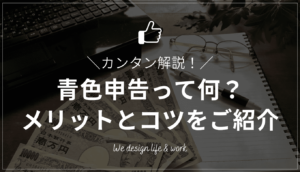
事業で使ったものを経費で計上する
税金対策として、経費を計上して所得額を減らす方法もあります。
経費とは事業で使用したお金のこと。事業活動をするときの支出であり、
- 家賃
- 通信費
- 自家用車
- パソコン/スマホ
- チラシや名刺の印刷料金
- 電気/ガス/水道代、光熱費
- 事業のための勉強用書籍、セミナー代
などのことをいいます。
そもそも、納税額は「(課税所得額ー控除額)×税率」で計算されるのですが、経費があれば所得額を少なくできるので、その分の税額も少なくなります。
ただし、家賃や通信費など、プライベートで使うものは全て経費になるわけではありません。
事業で使っている割合を計算し、その分だけ経費として計上できます。
経費計上の方法について詳しく知りたい方は次の記事を読んでみてくださいね。
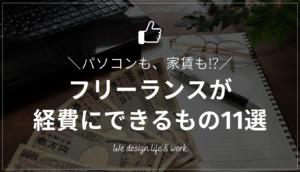
短期前払費用の特例を使う
節税をする方法として「短期前払費用の特例」を使う方法もあります。
なんだか難しそうに聞こえますが、実際にはそんなことはありません。
長期間にわたる支払いを一度にした場合、その経費は支払った年度の経費にしても良いということです。
例えば、2023年6月〜2024年5月までの保険料36万円を2023年5月に一括で支払った場合、本当なら2023年分の経費になるのは6月〜12月分の21万円です。
しかし、短期前払費用の特例を使えば、2023年に支払った36万円分は全て2023年分の経費として計上できるようになるのです。
経費が増えればその分課税所得が減るので、支払うべき税金は少なくなりますね。
ただ、短期前払費用の特例を使うには次のような条件があります。
- お金を支払ってから1年以内に「役務」を受ける
- 実際にお金を支払っている
- 継続的に役務を受ける
- ずっと同じ経理処理をする
短期前払費用の特例はあくまで「役務(無形サービス)」について適用されるものです。
新聞の定期行動、雑誌の定期行動など「資産(有形サービス)」を受ける特例が適応されないので注意しましょう。
また、役務が受けられるのは支払ってから1年以内です。
2023年6月に支払ったものは2024年6月までに終わる必要があります。
少額減価償却資産の特例を使う
少額減価償却資産の特例を使うのも、節税方法の1つです。
簡単にいうと「固定資産を一気に経費にすることができる」という特例ですね。
基本的に、固定資産は減価償却の対象になります。
減価償却…固定資産ごとに決まった耐用年数によって、固定資産の費用を分割して支払っていく方法です。耐用年数が4年、かつ総額20万円のものを買った場合、1年に支払うのは5万円になります。
しかし、特例を使えば固定資産の総額を1年で支払うことが可能になり、1年分の経費が増えるので、支払うべき税金も少なくなるのです。
ただ、この特例を使うには、青色申告をする必要があります。
固定資産の経費を1年でまとめて支払いたい場合は、青色申告をしましょう。
※ちなみにこの特例が認められるのは固定資産の価格が30万円未満の場合のみです。
損益通算をする
日本には副業で赤字が出ると、節税できる仕組みがあります。
それが損益通算です。
損益通算は副業で出た損失を他の所得で埋められるといったもの。
会社員なら副業で出た赤字分を、給与所得で埋めます。
すると、給与所得が少なくなるので、支払うべき税金が少なくなるのです。
しかし、実際に損益通算をするときには、細心の注意を払う必要があります。
むやみな損益通算は脱税になるからです。
世の中にはあえて経費を多くすることで赤字をうみ、わざと損益通算をする人もいます。
そのため、損益通算に対する税務署の目はとても厳しくなっており、少しでも違和感のある損益通算は脱税になる可能性があるのです。
意図せず脱税にならないよう、損益通算をするときには、専門家である税理士に相談しましょう。
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
副業の節税対策で脱税にならないためにすべきこと
副業で節税対策をするときに注意すべきなのが「脱税にならないか」ということです。
税金のルールはかなり複雑で油断をすると、脱税で使ってしまうリスクがあります。
そこで、ここでは脱税をしないためにすべきことをお伝えしていきます。
経費について根拠を持って話せるようにする
脱税を防ぐために、出した経費について明確な根拠をもって説明できるようになりましょう。
脱税が疑われると、税務署の人から
- 何割を経費に回したか
- 割合について何か証拠はあるか
と聞かれることになります。
そのときに曖昧な答えをしたり、証拠が残ってなかったりする場合、脱税になる可能性が高いです。
一方、経費に回した割合について証拠(レシートや領収書)を用いて、論理的に説明できれば、脱税になることはありません。
自分の身を守るために経費を計上するときには必ず正確な割合を出し、その証拠も準備しておきましょう。
税務署が認めなかった過去事例をチェックする
過去の事例をチェックするのも脱税を防ぐには有効です。
先ほどもの損益通算のように節税を試みるときには「これはやってもいいのかな?」と疑問に思う場面が出てきます。
そんなときには、過去の判例を見てみるのがおすすめです。
判例を見れば、どんなものが節税として認められ、どんなものが脱税になるかがわかってきます。
インターネットで「◯◯ 判例」と調べれば、税金関係であった裁判を知ることができますよ。
税理士やビジネス仲間に相談
税理士やビジネス仲間に相談するのも脱税を防ぐには大切です。
税金対策は知っているか知らないかの少しの差で大きく得をしたり、反対に大きく損したりしてしまいます。
とくに副業を始めたてで、税金についてよくわからない方は、自己判断で進めずに困ったらすぐに他の人に相談しましょう。
相談する相手におすすめなのは、税金について正しく理解している弁護士や、副業や個人事業主の経験があるビジネス仲間です。
インターネット上では知れない知識や事例もあるため、実際に知識や経験がある人から直接聞くことも大切にしてみてください。
まとめ
今回は、会社員や副業している人の税金対策について説明してきました。
紹介した税金対策は次の5つです。
- 青色申告で特別控除する
- 事業で使ったものを経費で計上する
- 短期前払費用の特例を使う
- 少額減価償却資産の特例を使う
- 損益通算をする
税金対策は、正しい知識があるかどうかで、結果的に手元に残るお金が大きく変わってきます。
税金対策をするためには、知識を身につけたり、申告書類を書いたりと、多少面倒に思うこともあるかもしれません。やった分だけ自分にとってのメリットが大きいのも事実です。
正しく税金について理解することで、「意図せず脱税になってしまい、結果的に損をしてしまった…」という悲劇も防ぐことができますよ。
きちんと知識を身につけたうえで税金対策をして、自分の自由に使えるお金を増やしていきましょう。