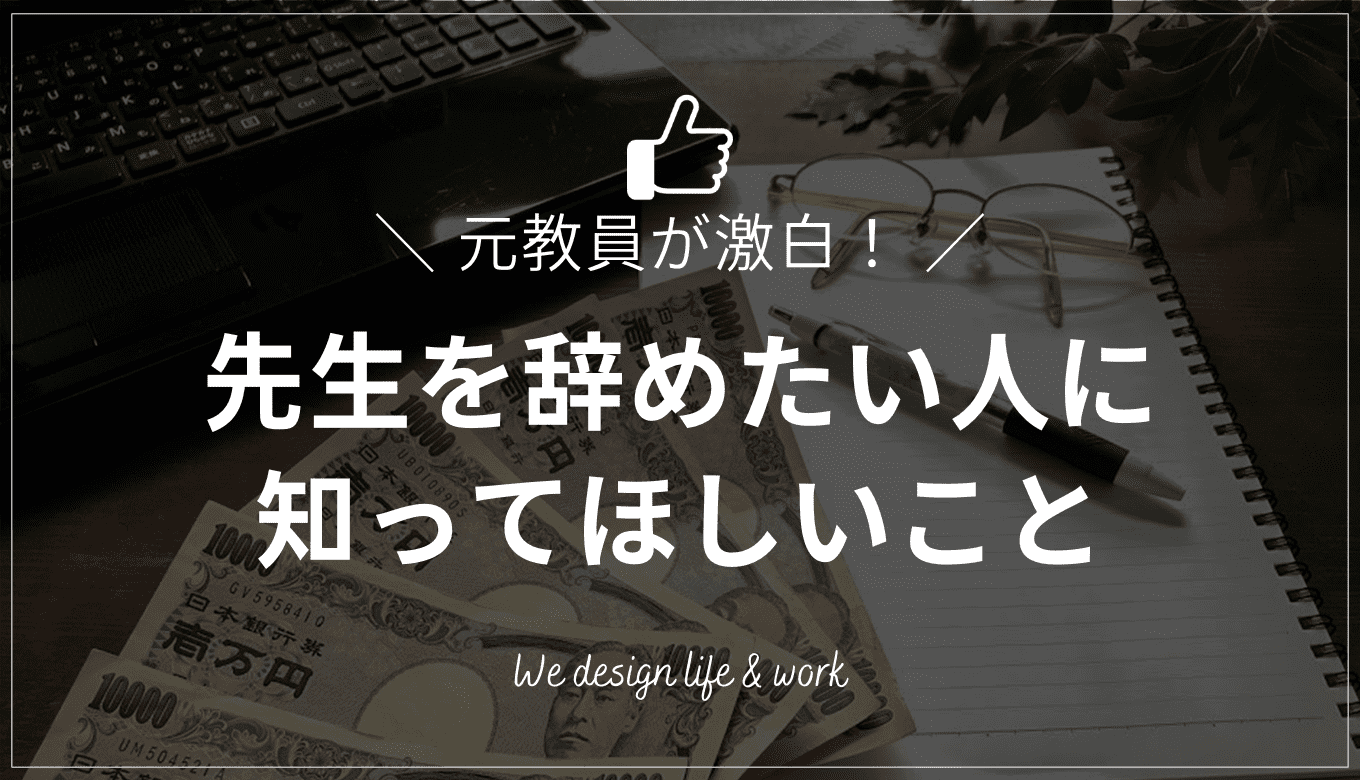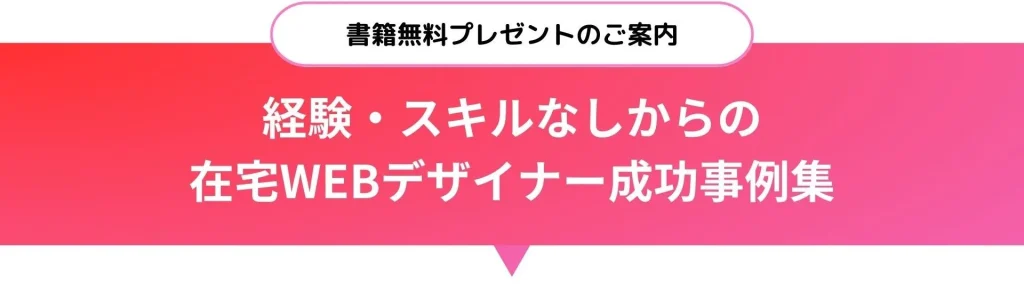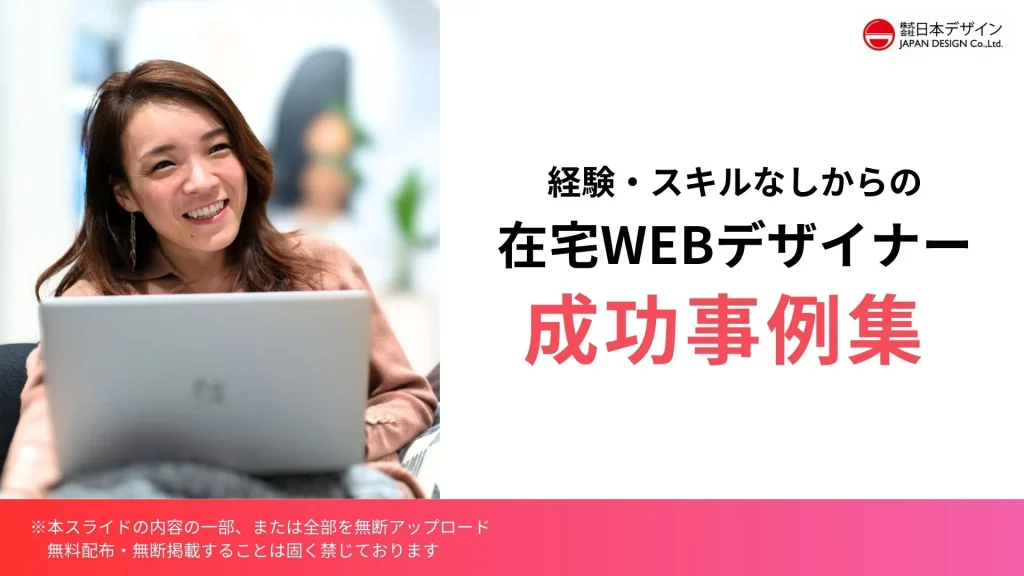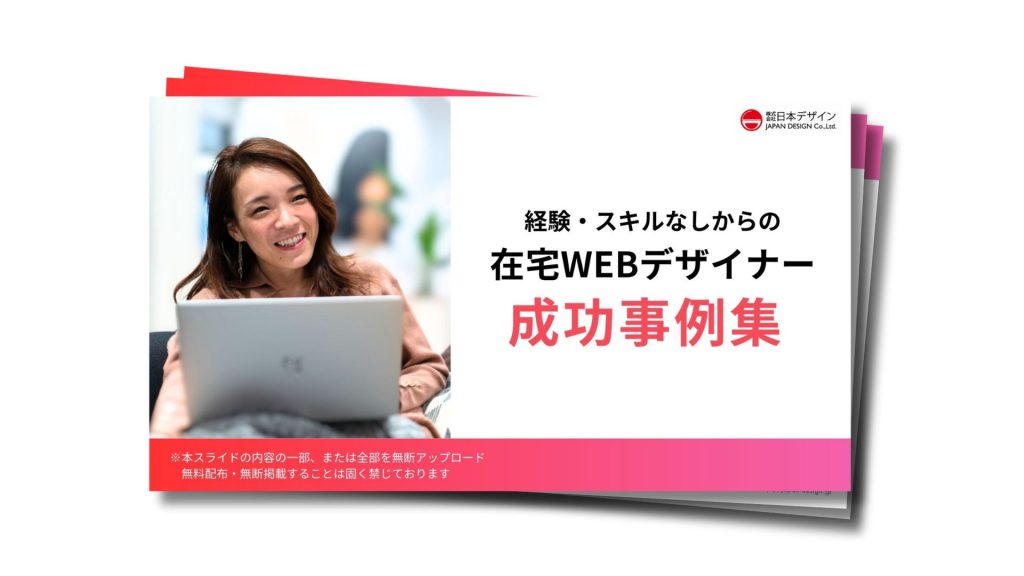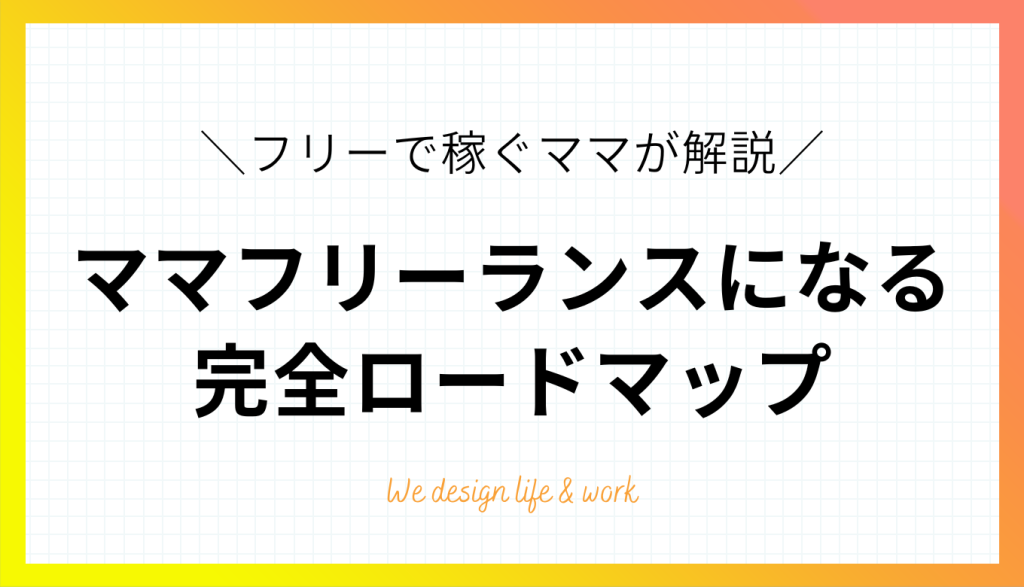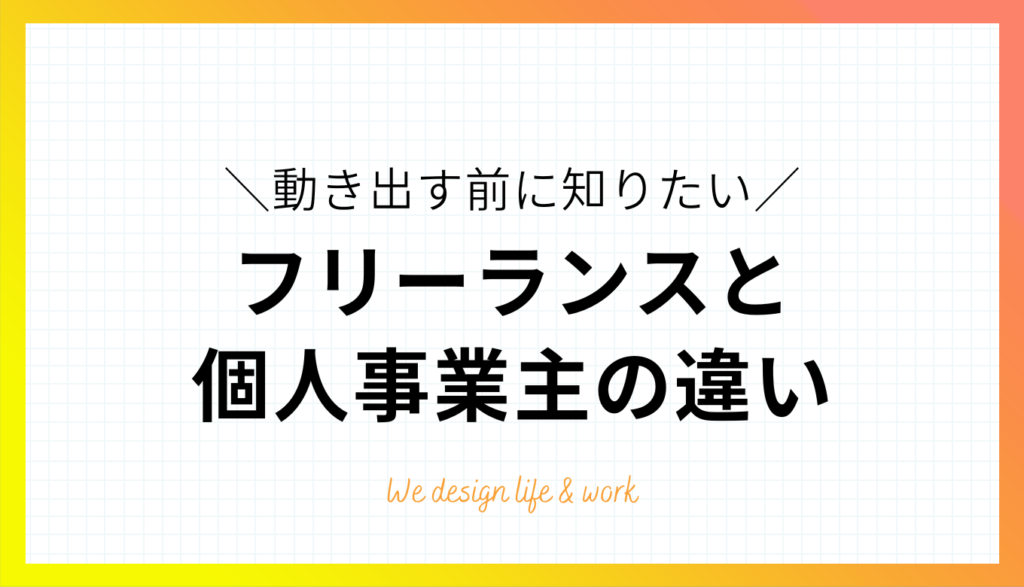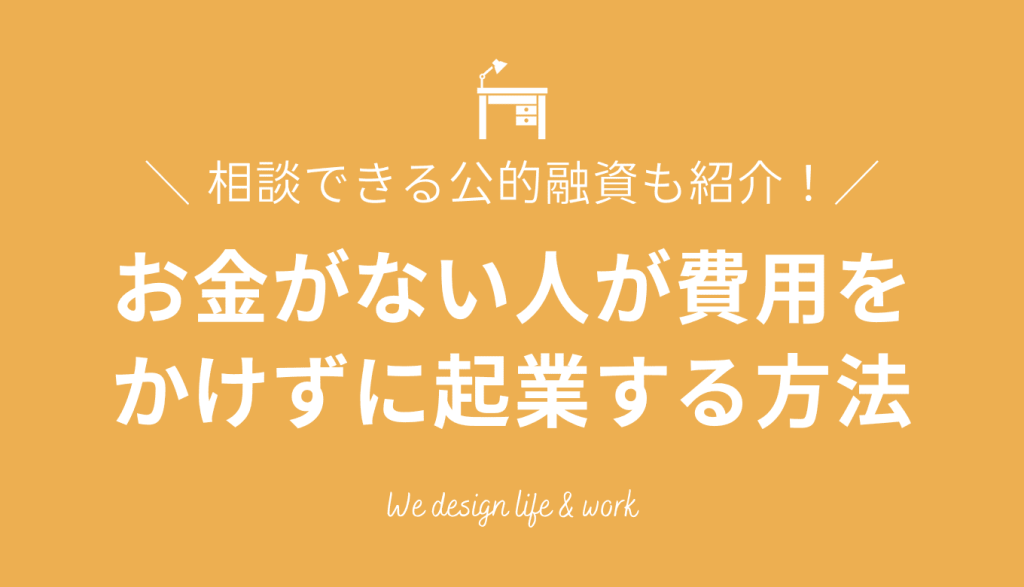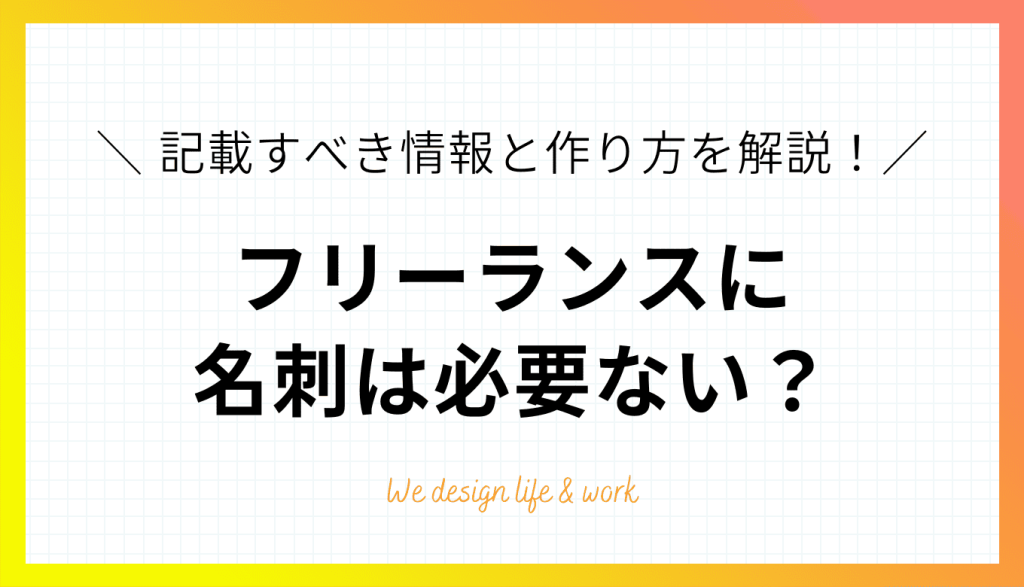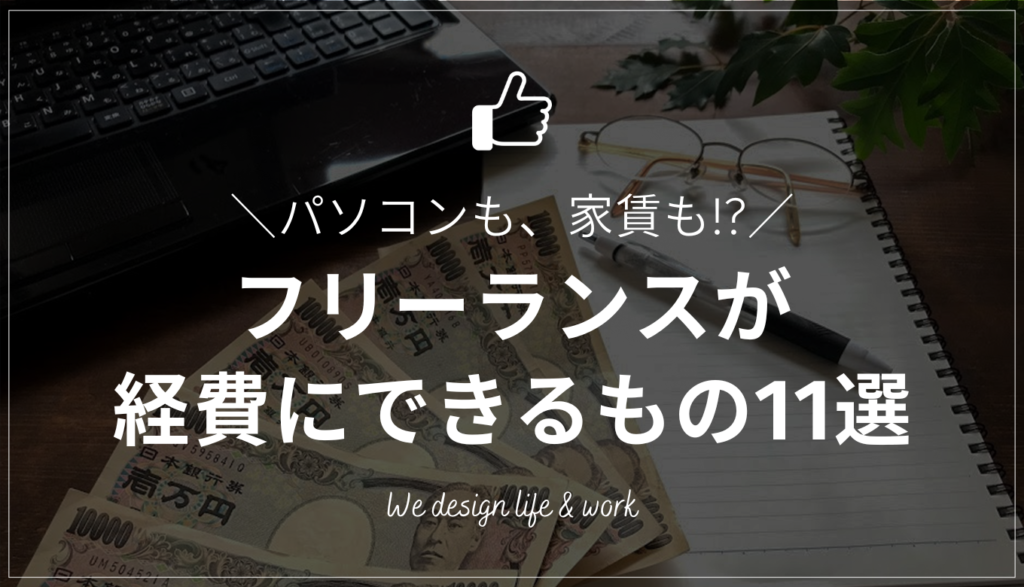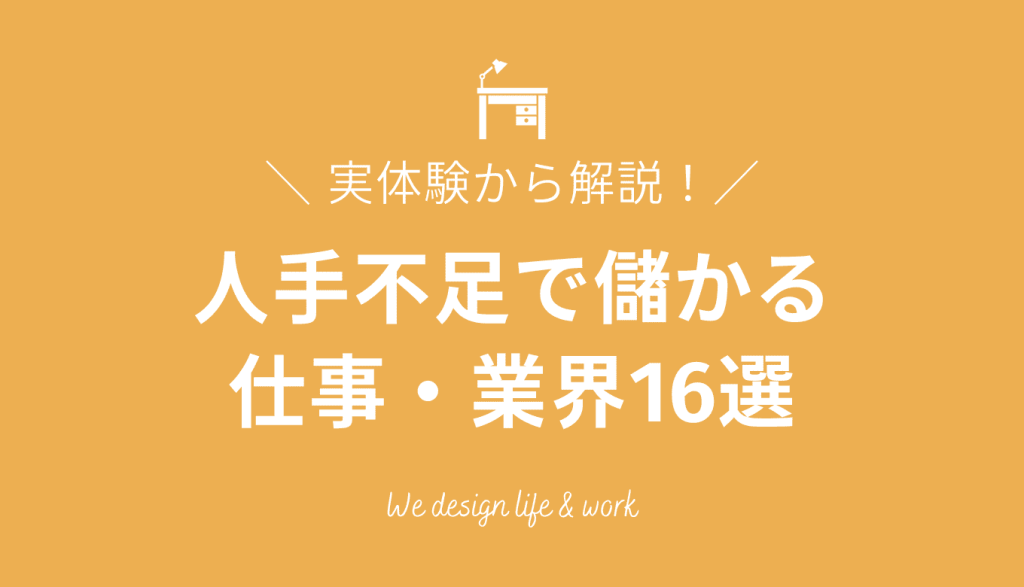「教員を辞めたいんだけど、何をすればいいの?」
「教員を辞めたいんだけど、これって甘え?」
「教員を辞めたいものの、退職後のキャリアをちゃんと構築ができるか不安…」
教員を辞めたい人で、このような悩みや疑問を抱えている人はいませんか?
結論から申し上げると、教員を辞めた方が良い人生を送れる可能性は十分にあります。
筆者である私も、数年前に教員を辞めて現在別の人生を歩んでおり、毎日楽しく過ごせています。
| 筆者の略歴 |
| ・2011-2019年 千葉県内の公立高校で英語の教員として勤務 ・2019-2021年 オーストラリアの大学院に留学 ・2021-2022年 オーストラリア企業にてマーケティングアシスタントとして勤務 ・2022年-現在 日本に帰国し、フリーランスのWEBライターとして活動 |
しかし、辞めたいと考えている全員の先生が「辞める」ことで、ハッピーになれるとは限りません。
ご自身が辞めたいと考える根本理由を特定し、その原因が改善・解消するための方法はないのかしっかりと考えた上で、「辞める」ことを選択肢に入れることが大切です。
この記事では、私の実体験をもとに下記のことについて詳しく解説します。
- 教員を辞めたいと考える人が挙げる主な理由
- 教員を辞める前にできること
- 教員を辞めて実感したメリット・デメリット
- 教員を辞めた方がいい人&辞めないほうがいいひとの特徴
- 教員を退職する流れ
- 教員を辞めた後のキャリアプラン
- 元教員におすすめのお仕事
私自身も実際に辞めているため、この記事では当時の私がこんな情報を知りたかったなと思っていた情報を全て網羅してお伝えします。
読み終わる頃には、教員を辞めた自分を具体的にイメージできるとともに、自分が本当に辞めるべきかどうか適切に判断できるようになるでしょう。
【結論】教員を辞めた方が良い人生を送れる可能性は十分にある

結論から申し上げると、教員を辞めた方が良い人生を送れる可能性は十分にあります。
私自身公立高校の教員を8年間勤めてきて、「公務員」という安定や社会的信用を失うことについて深く悩みました。
しかし、思い切って辞めて今全く異なる人生を歩んでいますが、一度も教員を辞めたことを後悔したことはありません。
むしろ夢だったオーストラリアへの大学院留学を実現でき、現在は自由度の高いフリーランスの仕事ができているため大満足です。
教員を辞めて良いと思えるかどうかは、あなたが何に重きを置いて人生やキャリアを築いていきたいのかによると思います。
「安定した仕事」や「社会的信用が高い立場」に魅力を感じるのであれば教員は良い仕事です。
しかし、「ワークライフバランス」や、「多様な働き方」に重点を置く場合は、教員は決して魅力的な仕事であるとは言えないでしょう。
「教員を辞めたい!」と考えたら、まずはその理由や原因を探り、それが環境や働き方を変えることで改善できないのか考えてみてください。
ちなみに…
総務省が発表した平成26年度の地方公務員教育職退職者に関するデータによると、教員を辞めている人は少なくありません。
一般的な退職にあたる「普通退職」「早期退職募集制度による退職」を選んだ人の合計は全退職者・離職者の27%を占めています。
| 退職・離職理由 | 人数(構成比) |
| 定年退職者 | 22,853名(58.3%) |
| 早期退職募集制度による退職 | 1,958名(5.0%) |
| 勧奨退職 | 5,074名(12.9%) |
| 普通退職 | 8,630名(22.0%) |
| 分限免職 | 7名(0.0%) |
| 懲戒免職 | 141名(0.4%) |
| 失職 | 10名(0.0%) |
| 死亡退職 | 519名(1.3%) |
| 計 | 39,192名 |
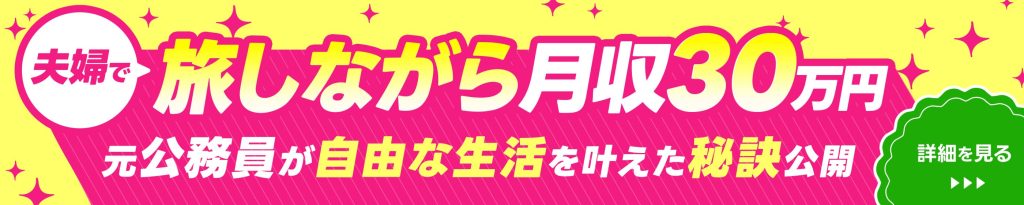
教員を辞めたいと感じたら?まずはその原因や理由を特定しよう!

教員を辞めたいと感じているのであれば、まずはその原因や理由を特定することが大切です。
それは、辞めたい理由や原因によっては解消できる可能性があるからです(詳細は次章参照)。
ここでは、教員が辞めたいと感じる理由としてよく挙げられる要因を下記の3つの観点から詳しく解説します。
- 労働環境についての要因
- 人間関係の要因
- 適性についての要因
それぞれ読みながら、自分が辞めたいと考えている理由として最も当てはまるのはどれか考えるのに参考にしてみてください。
労働環境についての要因
「労働環境」についての要因としてよく上がる理由は、下記の4つです。
- 勤務時間が長いから
- 休暇を取得しづらいから
- 副業が認められていないから
- 自分の努力が給料に反映されないから
ここでは、それぞれの理由について詳しく解説します。
勤務時間が長いから
教員の業務量は年々増加し、ますます勤務時間が長くなっていることから、これがストレスに感じている先生も少なくないでしょう。
- 放課後の会議の頻度が多く、1つひとつの会議時間が長い
- 部活動の指導を行なっている
- 行事が多く、その準備に追われている
- 生徒や保護者の対応を行なっている
- 新たな教科の創設に伴う準備に追われている
- 成績処理に追われている
- 通知表の所見の欄を手書きで書いている
私自身、公立高校の英語の教員を務めていましたが、「情報処理」や「道徳」など自分の専門外の授業などが増えて、どう対応すればいいか途方に暮れていたことを今でも鮮明に覚えています。
また、生徒の進路指導などが理由で在校時間が14時間ほどであったことも一度や二度ではありません。
労働基準法では、労働者は1日8時間、週に40時間ほどの労働をするように定められているにも関わらず、実際に法定労働時間分だけ働いている先生は少ないはずです。
先日、教職調整額が50年ぶりに4%から10%に引き上げになることが話題になりましたが、国のこのような対応から教員の業務量を減らそうという姿勢が見られないことが伺えます。
この制度は「定額働かせ放題」と揶揄されていますが、膨大な業務量とそれに伴う長い勤務時間が解消されるには、まだまだ時間がかかりそうですね。
休暇を取得しづらいから
勤務時間が長いことにあわせて、休暇を取得しづらいのも教員を辞めたい理由としてよく挙げられます。
特に中学校や高校で「部活動」の主顧問を担当されている先生は、部活動の練習や試合などが入ってしまうためなかなか休みを取りづらいですよね。
私自身も、夏休みですらまとまった休みが取りづらくて辛いなと感じたことが何度もあります。
下記の文部科学省のデータを見ると、平均有給休暇取得日数は小学校で11.6日、中学校で8.8日です。(出典:「教員勤務実態調査(平成28年度)の分析結果について」)
年間の有給休暇の日数が20日(繰越の場合は最大40日間)であることを考えると、いずれも取得率は25〜50%程度となっており、有給が取得しやすい環境であるとは言えません。
長い勤務時間に加えて、休暇も取りづらいとなると、仕事で抱えたストレスが解消されづらく心身に支障をきたす恐れがあります。
教員を辞めたいと感じるのも無理はないでしょう。
副業が認められていないから
地方公務員法第38条によって、公務員の副業は認められておりません。
出典:文部科学省「地方公務員法」
私も教員だったときに、よく周囲の友達から「教員の給料って高いからいいよね。」と言われてきましたが、実際はそんなことないですよね。
世間一般の公務員に対する目は厳しく、公務員に対して厳しい政策を打ち出す政治家が支援されてきたことから年々教員の給与は下がり、今では世間の平均ほどの給与になっています。
昔は校長先生になれば年収1,000万円を超えていたようですが、今ではそのようなことはありません。
このような厳しい懐事情、かつインフレが進んでいる現在、副業が認められていないというのはなかなか辛いものがありますよね。
自分の努力が給料に反映されないから
教員の給与は自分がどれほど努力しても給料に反映されず、経験年数が多くなるほど、あるいは主任などの役職などに就くことで給与が上がる仕組みになっています。
私が教員を辞めた理由は数多くありますが、その1つがこれです。
公務員は、一度採用されると余程のことがない限り解雇されることがないため、向上心がなく仕事を頑張ろうとしない教員が少なくありません。
その中でも頑張る教員がいて、仕事をサボる教員のシワ寄せがこのような教員にくるのです。
仕事を頑張っても、給料や賞与に全くプラスにならない、あるいは全く評価されないのは辛いですよね。
私は「一生懸命頑張る教員ほどバカを見る」と感じて、辞めました。
人間関係の要因
次に「人間関係」の要因としてよく挙げられる理由は、下記の3つです。
- 子供達と良い関係を築けないから
- 職場の人間関係にストレスを感じているから
- 保護者からのプレッシャーに耐えられないから
ここでは、それぞれの理由について詳しく解説します。
子供達と良い関係を築けないから
子供達と良い関係を築けないことに悩む教員は多く、決してあなただけではありません。
下記のデータは、都立学校の教員を対象にした教員勤務実態調査における「生徒の悩みや相談に応ずる時間が十分に取れない」という設問に対する教員側の回答結果をまとめたものです。
| 回答項目 | 回答者の割合 |
| とてもそう思う | 37.6% |
| まあそう思う | 47.1% |
出典:東京都教育委員会「都立学校教員実態調査の集計結果について」
これを見ると、84.7%もの教員が業務量の多さや忙しさを理由に、生徒とのコミュニケーションが不足していると回答しています。
生徒と良い関係を築くためには、コミュニケーションを取る時間が必要不可欠です。
しかし、前項でも触れましたが、国は教職調整額を50年ぶりに上げたものの、教員の業務量を減らそうと抜本的な改革をしようとする姿勢が見られません。
つまり、今後も名ばかりの働き方改革を行うだけで業務過多の状態は変わらず、子供達とコミュニケーションを取る時間を確保するのは難しい状況は続くということです。
結果として、子供達と良い関係を築けないことにさらに悩まされ続ける可能性が高いです。
職場の人間関係にストレスを感じているから
教員は「学校」という非常に閉鎖的な環境に身を置いて仕事をすることから、職場の人間関係にストレスを感じやすいです。
私も職員が100人を超える大規模校で勤務していたことがありますが、下記のように「共通項」がある先生としか話をしたことがありません。
- 学年
- 分掌
- 教科
- 部活動
公立の学校であれば「人事異動」という手段に逃げることもできますが、異動地区があるため地区を超えた移動をしない限り、再び苦手な先生と同じ職場になるということは少なくないのが実情です。
実際、「またあの先生と同じ職場だ。嫌だ。」と嘆く先生を数多く見てきました。
職場の人間関係にストレスを感じている教員が、「辞めたい」と感じるのも無理ないですね。
保護者からのプレッシャーに耐えられないから
教員は生徒たちの安全な学校生活、さらにはより良い進路の実現などを担保する必要があることから、ときには保護者から多大なプレッシャーをかけられることがあります。
筆者も進路指導部にいて、ある生徒の有名私大のAO入試対策をサポートしていたことがあるのですが、文化祭の日にその生徒の保護者が進路指導室に来て「先生お願いします。うちの子を志望大学にぜひ受からせてください。」と頭を下げられたことがあります。
教員はやりがいのある仕事ではありますが、逆に言うと保護者や生徒から高い期待を持たれる仕事でプレッシャーを感じることが多い仕事であるとも言えますね。
私は運良く遭遇したことはないのですが、中には「モンスターペアレンツ」と呼ばれる理不尽な要求を教員に押し付ける保護者もいて、その数は増加しているようです。
学校現場における保護者対応の現状に関するアンケート結果
Q. 無理難題要求は増えているか?
| 非常に増えている | 少し増えている | |
| 小学校 | 27% | 62% |
| 中学校 | 26% | 56% |
学力問題に関する全国調査における保護者の利己的な要求の深刻さについての調査結果
| 極めて深刻 | やや深刻 | |
| 小学校 | 25.8% | 52.0% |
| 中学校 | 29.4% | 49.7% |
「教員の仕事に対する意識調査」における「保護者や地域住民への対応が増えたか?」という設問に対する回答結果
| 「とても感じる」+「わりと感じる」の回答者の割合 | |
| 小学校 | 74.9% |
| 中学校 | 70.6% |
※上記の3つのデータの結果は、いずれも齋藤浩氏の論文「親たちはなぜ自制が利かなくなったのか〜学校への利己的言動、増加の背景をさぐる〜」より引用し、筆者が独自に作成
つまり、たとえ異動したとしても、異動先で再び別の保護者からプレッシャーを受ける可能性もあるということです。
辞めたいと感じる教員が少なくないのも、決して不思議ではないでしょう。
適性についての要因
最後に「適性」について要因があるケースですが、主に下記の3つの理由が挙げられます。
- 上手く授業ができないから
- 自分に向いていないと感じたから
- 体力的に厳しいから
ここでは、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
上手く授業ができないから
上手く授業ができないことも、教員を辞めたいと考える理由の1つです。
教員は授業ができてなんぼというところがあるため、授業が上手くできないと「自分には向いていないだろうか」と悩んでしまいますよね。
しかし、必ずしもあなたに問題があるとは限らないため、あまり重く捉えないでください。
たとえば私の場合、同じ教科を教えていても、クラスやタイミングによって「教えやすさ」が異なりました。
普段はリアクションが良くてサクサク進められるクラスであっても、体育のプールの後は気だるい雰囲気が漂っていて、なかなか授業が進まなかったことも一度や二度ではありません。
「うまく授業ができない」のは、経験値や授業の進め方の引き出しの少なさが原因であることも多いです。
すぐに辞めようと考えるのではなく、まずは研修に参加したり他の先生の授業を見学したりするなどして授業力を向上させることを考えてみてください。
自分に向いていないと感じたから
自分は教員に向いていないと感じることもあるでしょう。
実際に私も何度も感じたことがありますし周囲の教員を見ていても感じました。
教員採用倍率は、平成12年をピークに年々減少しています。
出典:文部科学省「令和3年度(令和2年度実施)公立高校教員採用選考試験の実施状況のポイント」
受験者数に対する採用率も高いことから、本来教員には向いていない人でも合格できるようになってきました。
私自身、声が小さくて授業が聞こえないと言われる先生、子供たちと良い関係が築けない先生など教員として明らかに向いていない人の割合が増えたと肌身で感じたということです。
しかし、教員を辞めた立場の私が言うのもなんですが、「自分は教員に向いていないのではないか」と考えるあなたは、教員に向いていないということなどありません。
私の経験ですが、本当に教員に向いていないのは自分を客観視できず、「私は向いていないのだろうか」と考えたこともない人です。
そのため、「自分は合わないのだろうか」とすぐに諦めて辞めてしまうのは非常にもったいないです。
周りの同僚に相談したり、指導力を向上させるために他の教員の授業を見学したりするなどして努力でその自信のなさをカバーしていきましょう。
体力的に厳しいから
歳をとるほど、教員の仕事が辛く体力的に厳しさを感じることもあるでしょう。
私の友人に小学校の教員がいましたが、その友人は「今は若いからいいけど、歳取ってから子供達と休み時間に外で遊ぶのなんて無理。」と言っていました。
私自身も20代の頃は、3ヶ月近くにわたって毎日のように夜の11時まで生徒の進路指導に励んでいた時期がありましたが、それを今またできるかと問われると正直自信がありません。
教員の仕事は、「若さ」でカバーしているところも多々あるため、年をとるほど厳しいと感じる人も多いのは納得できますね。
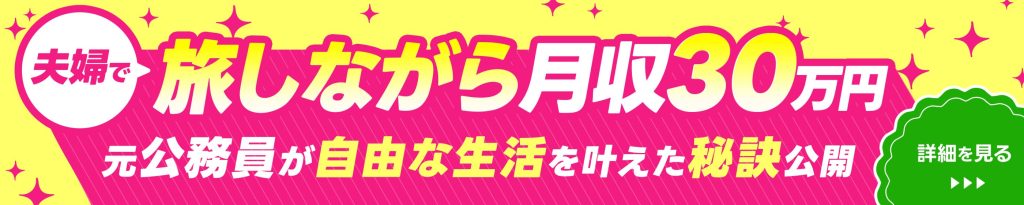
ちょっと待って!教員を辞める前にやってもらいたいこと

教員を辞めたいと悩んでいる方には、まず下記のいずれかの方法でご自身が抱える悩みや問題が解決できないか考えてもらいたいです。
- 辞めたい理由が本当に解決できないか考えてみる
- 異動希望で解決できるか考えてみる
- 周囲の仲の良い教員に相談する
- プライベートで思い切りストレス発散する
- 休暇、場合によっては療養休暇を取得する
前章で紹介した理由によっては、環境や働き方を変えてみることで解決できる可能性もあります。
ここでは、それぞれの方法について詳しく紹介します。
この中の方法で解決しそうな場合は、ぜひ参考にしてみてください。
辞めたい理由が本当に解決できないか考えてみる
辞めたい理由が本当に解決できないか考えてみることで、辞めてから後悔するリスクを軽減できます。
たとえば、特定の同僚・生徒・保護者との人間関係が原因で教員を辞めたいと思っている場合は、人事異動などを希望することで問題が解決されるでしょう。
他にも上手く授業ができないことに悩んでいるのであれば、研究授業を実施して他の先生からアドバイスをもらったり、研修会に参加して新しい知見を得たりすることで悩みが解消される可能性があります。
このような理由から、自分が教員を辞めたいと考えている理由を明確にすることが大切なのです。
問題が解決できないか、よく考えてみてください。
異動希望で解決できるか考えてみる
人事異動で問題が解決できる場合は、ぜひ活用してみましょう。
公立校の教員であれば、同一校で3年間勤務すれば異動希望を出すことができますよね。
もちろん異動希望が必ず通る保証はないのですが、下記のような工夫を凝らすことで異動が実現する可能性が高まります。
- 秋頃に実施される校長面談の際に異動希望とその理由をしっかりと伝える
- 異動希望票をしっかりと記入する
実際に私も校長面談の際に強くアピールしたことで、異動が実現したことがあります。
また、移動希望票についてもどのような学校に異動したいのか可能な限り具体的に記入してください。
「パソコン入力ではなく、手書きで書くことで熱意が伝わり異動しやすくなる」とおっしゃっている先輩教員もいました。
これについての真偽は定かではないですが、いずれにせよ人事異動を熱望していることが周囲に伝わるようにすることが大切です。
周囲の仲の良い教員に相談する
悩みや課題を一人で抱えるのではなく、周囲の仲の良い教員に相談することでストレスが解消されることがあります。
1人で悩んでしまうと、ネガティブな感情がどんどん膨らんで、最終的に自分自身を責めてしまいかねません。
仲のいい教員に相談することで、自分では思いつかなかった解決方法や視点を得られる可能性があります。
また、気持ちがスッキリする効果もあることから、人に話すことはおすすめです。
私自身も20代の頃は特に周囲の同僚に愚痴や悩みを相談して、日々のストレスを解消していました。
教員になるような人は面倒見が良い人が多いです。
きっと、あなたの話を一生懸命聞いてくれるでしょう。
プライベートで思い切りストレス発散する
仕事でストレスを感じている場合、下記のようにプライベートで発散できないか考えてみましょう。
- 美味しいものを食べる
- 旅行に行く
- お風呂にゆっくり浸かる
- 友達と会う
- 趣味に没頭する
- カラオケで大きな声で歌う
- 運動する
私自身の経験では「運動」、特に「ヨガ」がストレス発散に効果的でした。
ヨガは呼吸を大切にするのですが、ヨガを通じて自分の呼吸の浅さを学べました。
深呼吸をすることで深いリラックス効果を得られるため、ストレスが解消されやすくなります。
人それぞれ最適なストレス解消法は異なるでしょう。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、その方法で現在自分が抱えているストレスが発散されないか考えてみてください。
休暇、場合によっては療養休暇を取得する
仕事でのストレスが大きく、下記のような症状が見られた場合は、休暇あるいは療養休暇を取得することがおすすめです。
- 眠れない
- 食欲がない
- 自分が悪いと思い込む
- 何もないのに涙が出てくる
- 頭や肩が痛く、だるい
- 毎日憂鬱で気分が重い
- 何をしていても楽しくない
- 「死にたい」と感じることがある
このようなサインは、うつ病などの精神疾患の初期症状です。
これらの症状を看過してしまうと状況が深刻化してしまい、続けたくても教員の仕事を続けられなくなってしまいます。
教員には90日分の療養休暇があり、校種や勤務先の市町区村によって多少の違いがありますが、「医師からの診断書あるいは領収書」があれば取得することが可能です。
90日を超えると休職になってしまいますが、休職1年目は下記の給与・手当の80%を受給できます。
- 給料
- 扶養手当
- 地域手当
- 住居手当
心身ともに疲れ切っている場合は、辞める前にまずは休暇をとってリフレッシュしてみることがおすすめです。
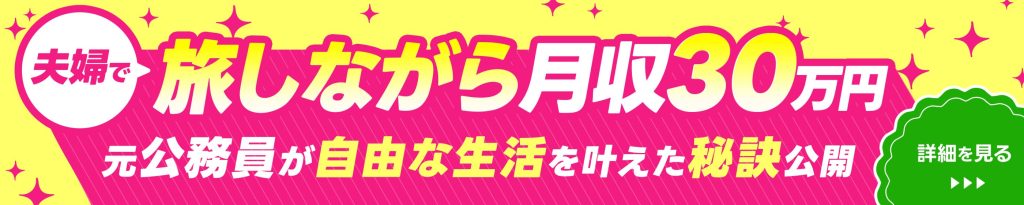
教員を辞めて実感したメリット・デメリット

次に、私自身が感じた教員を辞めたメリットとデメリットについてお話しします。
メリットとデメリットは、それぞれ下記の通りです。
| メリット |
| ・人間関係のストレスから解放される ・時間的にも精神的にもゆとりができる ・プライベートで「生徒の目」を気にしなくて済む ・副業ができて収入アップが狙える ・教員としてのプレシャーから解放される ・快適な環境で仕事ができる |
| デメリット |
| ・社会的な信用を失う ・安定性を失う ・公務員ならではの福利厚生を失う |
ここでは、それぞれのメリットとデメリットついて詳しく説明します。
教員を辞めて実感したメリット6つ
教員を辞めて実感したメリットは、下記の6つです。
- 人間関係のストレスから解放される
- 時間的にも精神的にもゆとりができる
- プライベートで「生徒の目」を気にしなくて済む
- 副業ができて収入アップが狙える
- 教員としてのプレシャーから解放される
- 快適な環境で仕事ができる
ここではそれぞれのメリットについて、実体験を元に解説します。
これを読めば、教員を辞めた後の生活がより具体的にイメージできるようになるでしょう。
人間関係のストレスから解放される
教員を辞めると、人間関係のストレスから解放されてかなり楽に生きることができます。
私自身教員として働いている間、同僚に苦手な人がおり、同じ学年や教科で仕事することになると接点が増えるため非常にストレスを感じていました。
しかし、現在はフリーランスで活動しているため、同僚・上司はおらず人間関係に関するストレスは限りなくゼロに近い状態です。
教員を辞めてから、オーストラリアのさまざまな企業でインターンシップを経験したのですが、気付いたことがあります。
オーストラリア企業Clenergyでのインターンシップ最終日
それは、「どのような仕事をするかも大切ではあるものの、誰と一緒に仕事をするかの方が私にとっては重要で、それがモチベーションの源になる」ということです。
皆さんの中にも、同じような人がいるかもしれません。
同僚や保護者などの人間関係に悩まされており、異動しても状況が大きく変わることがなかったという人は、仕事や職場を変えることで環境や人生そのものを好転させられる可能性があるでしょう。
時間的にも精神的にもゆとりができる
教員を辞めてからは時間的にも精神的にもゆとりができ、のんびりと生活できるようになりました。
下記は、私のとある1日のスケジュールです。
| 時間 | やること |
| 7:30 | 起床 |
| 7:30-9:00 | 朝食・洗顔・着替え・洗濯など |
| 9:00-9:30 | 仕事のメールやメッセージのチェック |
| 9:30-10:00 | オンライン英会話受講 |
| 10:00-12:30 | 記事の執筆 |
| 12:30-13:00 | 昼食 |
| 13:00-14:30 | 記事の執筆 |
| 14:30-15:30 | クライアントとのミーティング |
| 15:30-17:30 | 記事の執筆 |
| 17:30-18:30 | 夕食・出かける準備 |
| 18:30 | 出発 |
| 19:00-20:30 | ジムにて運動 |
| 20:30-21:00 | 帰宅 |
| 21:30-22:00 | 入浴 |
| 22:00-24:00 | 自由時間 |
| 24:00 | 就寝 |
| 時間 | やること |
| 7:30 | 起床 |
| 7:30-9:00 | 朝食・洗顔・着替え・洗濯など |
| 9:00-9:30 | 仕事のメールやメッセージのチェック |
| 9:30-10:00 | オンライン英会話受講 |
| 10:00-12:30 | 記事の執筆 |
| 12:30-13:00 | 昼食 |
| 13:00-14:30 | 記事の執筆 |
| 14:30-15:30 | クライアントとのミーティング |
| 15:30-17:30 | 記事の執筆 |
| 17:30-18:30 | 夕食・出かける準備 |
| 18:30 | 出発 |
| 19:00-20:30 | ジムにて運動 |
| 20:30-21:00 | 帰宅 |
| 21:30-22:00 | 入浴 |
| 22:00-24:00 | 自由時間 |
| 24:00 | 就寝 |
英会話やジムなど、自分がやりたいこととも両立することができています。
教員のときには、ヨガやジムに行きたくて用意していても突発的に生徒がトラブルを起こしたり、会議が延びたりして自分のやりたいことができず、結果的にストレスの発散をすることが難しかったです。
しかし、今では「あれもやらなくちゃ。これもやらなくちゃ。」という焦燥感から解放され、心が安定した生活を送れています。
プライベートで「生徒の目」を気にしなくて済む
教員を辞めると、「生徒の目」を気にせず生活できるため非常に楽です。
初任の頃に、ある生徒が男性教員と女の人が一緒に歩いていたところを写真に撮ってTwitterに投稿したため、厳しく叱り投稿をその場で消させたことがあります。
この経験がきっかけで、教員はいつどこで誰に見られているか分からないということに気付かされました。
特に何か悪いことをしているわけではないのですが、休みの日や夜に学校周辺を歩いているとソワソワした気持ちになったことは何度もあります。
しかし、教員を辞めてからはこのような「パパラッチ」にいつも監視されているような感覚から完全に解放されたため、のびのびと生活することができています。
副業ができて収入アップが狙える
教員を辞めると、副業をして収入アップが狙える可能性があります。
令和2年に実施された厚生労働省の調査によると、副業をしている人の割合は回答者全体の9.7%に及び、そのうちの90%近くが毎月5万円以上の副業収入を得ているそうです。
出典:厚生労働省「副業・兼業に係る実態把握の内容等について」
毎月70万円を超える収入を得ている人が10.3%もいることから、副業で教員時代の収入を大きく上回る可能性があるでしょう。
全ての民間企業で、副業や兼業が認められているわけではありません。勤務先で副業が禁止されていないかよく確認してください。 また副業をする際には、下記の点にも注意しましょう。
- 確定申告を必ず行う
- 住民税の支払額が増える可能性があることを忘れないようにする
教員としてのプレッシャーから解放される
教員を辞めたら、教員としてのプレッシャーから解放されて楽に生きやすくなります。
前章でもお話ししましたが、教員は生徒や保護者からの期待が大きく、時には過度な要求やプレッシャーを受けることもあるでしょう。
そのためか、私自身いつも「教員とはこうあるべき」という考えに取り憑かれていたところがありました。
しかし、教員を辞めてから母や元同僚から「憑き物が取れたみたいにスッキリしたね。重責から解放されたのが分かる。顔つきも変わった。」言われました。
私自身としても、現在は教員としてのプレッシャーから解放されてかなり楽に生きていると実感しています。
快適な環境で仕事ができる
教員を辞めると、快適な環境で仕事ができるようになるでしょう。
公立高校の教員になって驚いたことはたくさんありますが、その中でも衝撃的だったことは「自由に冷房を使えるわけではない」ということです。
教室に冷房がつけられている学校の数は下記のように増加していますが、私が働いていた学校のほとんどは職員室にはつけられていませんでした。
出典:文部科学省 報道発表「公立学校施設の空調(冷房)設備の設置状況についてお知らせします」
あまりに暑すぎて、パソコンが熱暴走を起こし仕事にならないこともあったほどです。
冷房をつけて仕事をしようとすると、先輩の先生から「冷房にかかる電気代は保護者が出しているんだよ。それは電気泥棒だよ。」と言われ、何とも言えない気持ちになったことを今でも鮮明に覚えています。
現在これほど劣悪な労働環境は、少なくとも私が経験した限りではありません。
教員を辞めると、今よりも快適な環境で仕事ができる可能性が高いです。
教員を辞めて実感したデメリット3つ
つづいて、教員を辞めて実感した下記の3つのデメリットについてもお話しします。
- 社会的信用を失う
- 安定性を失う
- 公務員ならではの福利厚生を失う
これらのデメリットについて事前に理解しておくことで、いざ教員を辞めたときに「知らなかった」「こんなはずではなかった」と後悔するリスクを軽減することにつながるでしょう。
ぜひメリットだけでなく、デメリットについても知っておいてください。
社会的信用を失う
教員を辞めることで社会的な信用が失われて、生活に支障をきたす可能性があるので注意が必要です。
私自身は今のところ経験したことがないのですが、教員を早期退職した元同僚が辞めてからローンが通りづらくなったとぼやいていたことがあります。
安定した収入が約束されている公務員は社会的な信用が高く、下記のような場面で審査が通りやすいです。
- マイホームの購入
- カードローンの契約
- クレジットカードの契約
- 賃貸契約
もし教員を辞めるのであれば、これらの契約や手続きを先に行ってから辞めることをおすすめします。
安定性を失う
教員を辞めてしまうと、その強みである「安定性」を失うことにつながるため注意が必要です。
犯罪や交通事故などを引き起こしたり、自分から退職を申し出たりすることがない限り、教員は解雇されることがありません。
常に給与が支給され、退職金も約束されています。
私は教員を辞めると考えたときに、この「公務員ならではの安定性」を捨てることが最も悩んだポイントです。
しかし、「このまま教員続けていたら、英語コースの担任持って、進路部長やらされて、そのうち管理職になるんだろうな」と将来の自分がなんとなくイメージできており、そのような人生を退屈であると考えたことが退職する決め手となりました。
現在は、明日の自分もどうなるか分からない状況ではありますが、毎日ワクワクしながら楽しく仕事に取り組んでいます。
教員を辞めたいと考えているものの、この「安定性」を捨てる勇気が持てないという人は少なくないでしょう。
ぜひよく考えてから行動に移してください。
公務員ならではの福利厚生を失う
教員を辞めると、下記のように「公務員ならではの」福利厚生を失ってしまいます。
- 退職金制度
- 年2回(およそ4.4ヶ月分)の賞与の支給
- 夏季休暇などの長期休暇の取得
- 交通費の全額支給
- 賃貸の家賃補助
- 公立学校共済組合への加入
- 最大3年間取得できる育休
全ての民間企業で、これらの福利厚生が完備されているわけではありません。
特に退職金制度については、民間企業で義務化されておらずもらえない可能性もあります。
このような事実を知らずに教員を辞めて他の仕事に転職してしまうと、生活レベルが下がったりワークライフバランスが取れなくなってしまったりして、QOL(生活の質)が下がってしまい後悔する恐れがあるでしょう。
今はこれらの福利厚生を当たり前のように享受していても、失ってから初めてその大切さに気づくことはよくあることです。
現在私はフリーランスとして活動しているため、自由に働ける分休暇や退職金はありません。
老後に備えて倹約しながら生活するように心がけています。
これらの福利厚生に対するありがたみも考慮に入れながら、辞めるべきかじっくり考えることが大切です。
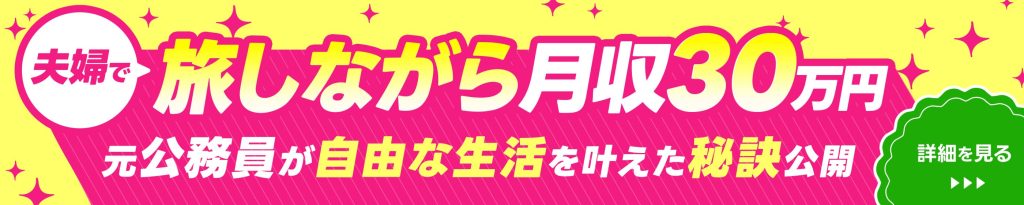
教員を辞めた方がいい人・続けた方がいい人の特徴

ここまで教員を辞めるメリットとデメリットについて、私の実体験をもとに説明してきましたが、まだ教員を辞めるべきか判断できない人も少なくないでしょう。
「公務員」という社会的な立場や安定性、そして大学や大学院での教職課程や教員採用試験など努力をして勝ち取ったポジションを簡単に諦められないのは当然のことです。
ここでは、教員を辞めた方がいい人の特徴、そして続けた方がいい人の特徴について紹介します。
ご自身は辞めるべきか判断する際に、ぜひ参考にしてください。
辞めた方がいい人の特徴
教員を辞めた方が良い人の特徴は、下記の通りです。
- 教員を辞めたい理由が明確で、解決する手段や方法がない人
- ワークライフバランスを重視している人
- 生徒や保護者、同僚とのコミュニケーションが辛いと感じている人
- 心身ともに体調がすぐれない人
- 責任感が強すぎる人
- 20〜30代前半で、第二新卒あるいは中途採用で転職活動しやすい年齢の人
うつ病などの精神疾患に罹っても、誰も責任を取ってくれません。
あなたを守るのは、あなた自身しかいないのです。
教員を辞めたいと考える原因を解決する術がない場合、あるいは不眠が続く、やる気が出ないなど心身に影響が出てきた場合は、一刻も早く教員を辞めて新たなキャリアを築いた方が良いでしょう。
続けた方がいい人の特徴
下記のような特徴を持つ人は、教員を辞めると後悔する可能性があることから仕事を続けることをおすすめします。
- 教員を辞めた自分を想像すると、ネガティブなイメージしか湧いてこない人
- 幼い頃から教員になることに夢を抱いていた人
- 「公務員」という立場に大きな魅力を感じている人
- 老後のお金が心配な人
- 仕事に「安定性」を求める人
このような特徴がある人は、人事異動の活用や仕事の効率化を目指した工夫などを通じて、現在抱えている課題やストレスを解決できないかよく考えてみましょう。
教員を退職する流れ

つづいて、教員を退職する流れを3ステップで紹介します。
下記の手順で教員を退職してください。
- STEP1: なるべく早めに管理職に退職の意思を伝える
- STEP2: 後任に引き継ぎを行う
- STEP3: 学校の備品や資料などを返却する
ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説します。
これらのステップを踏まえて退職準備を進めることで、周囲に迷惑をかけることなくスムーズに退職できるでしょう。
ぜひ参考にしてください。
STEP1: なるべく早めに管理職に退職の意思を伝える
私の場合、教頭先生、校長先生の順で退職の意思を伝えました。
退職の意思を伝えるタイミングですが、注意が必要です。
私は留学先の大学院の入学が決定してから、つまり9月頃に意思を伝えたのですが、校長先生に「遅い」と叱られました。
教員採用試験の関係で、退職者分の人員を確保する必要があることから遅くても7月までに伝えてもらいたかったそうです。
退職する3ヶ月前に意思を伝えることが一般的ですが、公立校の教員は事情が異なるようなので注意しましょう。
なるべく早めに管理職に伝えてください。
STEP2: 後任に引き継ぎを行う
次に、下記の後任に引き継ぎを行います。
- 学級担任
- 分掌
- 教科担当
- 部活動
- 係・委員会
管理職に退職の意思を伝えたときに言われたことなのですが、人事に関することなので内示が出るまでは周囲の同僚には退職することを言わないでください。
つまり、後任への引き継ぎは3月に入ってから行うことになります。
後任の先生が困らないように、引き継ぎは丁寧かつ念入りに行いましょう。
口頭で伝えるだけでなく、「書面」に残しておくことがおすすめです。
書面に形にしておくことで、退職後に学校から電話がかかってきたり呼び出されたりするリスクを軽減できます。
また、年度末ではなく年度途中で退職する場合は、下記のことも後任者にしっかりと伝えましょう。
- 各クラスの授業の進み具合
- 試験範囲
- 定期試験やテストまでの残り授業時間
- 年度内の行事
- 各クラスの概況や生徒情報
STEP3: 学校の備品や資料などを返却する
無事に引き継ぎが終わったら荷物の整理を始め、パソコンや指導マニュアルなど学校の備品は全て返却することを忘れないようにしてください。
生徒の成績などの個人情報、あるいは新年度のクラス情報などの機密情報などは、管理職や先輩教員に確認して適切に処分することが必要です。
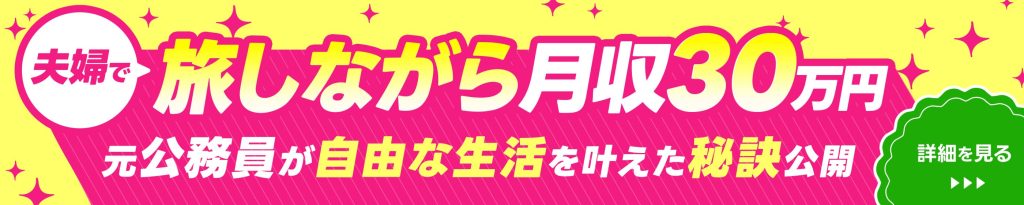
教員を辞めた後どうする?4つのキャリアプラン

教員を辞めたいものの、その後のキャリアが心配でなかなか行動に移せないという人も多いでしょう。
教員を辞めた方におすすめのキャリアプランは下記の4つです。
- 同業種に転職する
- 異業種に転職する
- 独立・開業する
- 留学やスクールでスキルアップする
ここではそれぞれのキャリアプランについて詳しく解説します。
これを読めば、教員退職後のキャリアプランをより具体的にイメージできるようになるでしょう。
同業種に転職する
現在の職場環境や人間関係が原因で教員を辞めたいものの、「教えること」が好きである場合は同じ教育業界に転職することがおすすめです。
他の業種への転職と比較すると、教員時代に身につけた経験やスキルがそのまま活かせて即戦力になることからスムーズに転職活動を進められる可能性が高いでしょう。
就労環境が変われば、楽しく仕事ができる可能性があります。
異業種に転職する
下記のような「未経験者採用」に積極的な業界であれば、異業種に転職することも決して夢ではありません。
- 建築業
- 運送業
- 介護業界
- IT業界
- 美容業界
- サービス業界
- 観光業界
これらの業界は「人手不足」に悩んでいることから、「未経験者」であっても積極的に採用する傾向があります。
独立・開業する
組織に対してしがらみや不自由さを感じていたり、自分でやりたいことが明確であったりする場合は、独立や起業も視野に入れても良いでしょう。
しかし、下記のデータからも分かるようにフリーランスや個人事業主として働き続けることは決して容易ではありません。
出典:中小企業白書「平成28年度中小企業の動向」
日本は諸外国と比較すると起業後の企業生存率は高いですが、開業年数を減るにつれて廃業率も高まっていき、10年間生存できる個人事業主はわずか10%程度であるとも言われています。
教員は、常に安定した給与と賞与が保証されているとともに、民間企業のように営利目的の仕事ではないため「儲け」を考えながら仕事をしたことがない人が大半です。
そのような環境で仕事をしていた教員が独立・開業することは並大抵ではないことを念頭に入れておいた方が良いでしょう。
留学やスクールでスキルアップする
もし経済的な余裕がある場合、あるいはやりたいことが明確でそれを実現するために新たな知識やスキルを身につける必要がある場合は、留学やスクールを通じてスキルアップを図るのもおすすめです。
留学先のMonash大学
私自身もオーストラリアの大学院に留学し、その後現地企業でマーケティングアシスタントとして1年勤務し、その経験を活かして現在フリーランスのSEOライターとして活動しています。
スクールや留学は、時間とお金がかかってしまう点がデメリットですが、スキルが身に付くため即戦力として採用してもらえる可能性が高くなります。
また、私自身留学には大枚をはたきましたが、人脈の構築やオーストラリアでしかできない経験など、お金には代え難い貴重なものを得ることができたため大満足です。
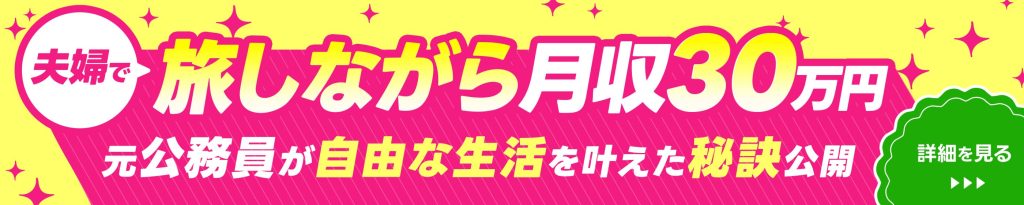
教員を辞めたい人におすすめの仕事

教員を辞めたいものの、「どんな仕事に再就職ができるの?」と不安に感じる人も多いでしょう。
私も、昔はそうでした。
教員を辞めたい人におすすめの仕事は、下記のとおりです。
- 学習塾講師
- 教材の編集
- 営業職
- 事務職
- IT系の制作職
ここでは、それぞれの仕事について詳しく紹介します。
離職・退職後にどのような仕事をしたいか考える際に、役立ててください。
学習塾講師|教えることを続けたい人におすすめ
教員を辞めた理由が就労環境や人間関係で、「教えること」そのものが好きな人には「学習塾講師」の仕事をおすすめします。
学習塾講師は成績アップ、あるいは志望校合格を目指した子どもたちの学習指導をする仕事です。
私自身も経験がありますが、教員と比較すると「結果」や「数字」が求められる仕事であるためシビアな世界です。
しかし、自分の努力が数字としてはっきりと表れ、給与にも反映されるためやりがいを感じることができるでしょう。
- 教えるのが好きな人
- 苦手分野を努力して克服した経験がある人
- 面倒見が良く、人と接するのが好きな人子どもと関わるのが好きな人
- 人前で話すことが得意な人
- 学習意欲が高い子の指導をしたい人
教材の編集|教科の専門知識を活かしたい人におすすめ
教科の専門知識を活かしたい人には、教材の編集に関わる仕事がおすすめです。
「教材」と一口に言っても、下記のように多岐にわたります。
- 教科書
- 問題集
- ドリル
- デジタル教材
- 音声アプリ
教育現場で身につけた知識や経験は、現場で求められている教材や、学習指導要領に沿った教材を制作するのに大いに役立つはずです。
- 粘り強く物事に取り組める人
- リサーチが好きな人
- 正確な作業が得意な人
- 自分の仕事を形にしたい人
営業職|成果を出した分給与を得たい人におすすめ
成果を出した分の給与を得たい人におすすめなのが、「営業職」です。
これまでさまざまなタイプの生徒や保護者を見てきた教員は「人を見る目」があります。
また、難しいことをわかりやすく説明することに長けているため、プレゼンテーションも得意な人が多いでしょう。
このような観察力やコミュニケーション能力は営業職に不可欠なスキルであることから、元教員の方は営業職に向いています。
また、営業職は努力した分成果が報酬として得られるため、モチベーションが維持しやすくなる点も特徴です。
- 記憶力が優れている人
- 相手の立場になって物事を考えられる人
- フレンドリーで話しかけやすい人
- 傾聴力に長けている人
- 問題解決能力がある人
事務職|デスクワークが合っている人におすすめ
デスクワークが得意な人は、事務職とくに学校事務員に転職するのも良いでしょう。
学校事務員の主な仕事は、下記の通りです。
- 経理事務
- 施設管理
- 授業の運営サポート
- 来校者の窓口対応
- 電話・メールの対応
- 教員の事務管理や給与計算
学校の事務員は、一般的な事務作業に加えて生徒や保護者への対応が必要になることから、教員で培った生徒・保護者対応の経験やスキルが活かせます。
私は教員時代に学年会計をやっており、会計業務を事務の先生に教えていただきながら業務を行っていましたが、下記のようなMicrosoftOfficeが使いこなせると仕事がしやすくなるでしょう。
- Access
- Excel
- Word
また、公立校の教員と同様に学校事務員も地方公務員であることから、試験に合格することが必要です。
- 人と関わるのが好きな人
- 教育のサポートに興味がある人
- 計画的に物事を進められる人
- 業務を円滑に進めるためのコミュニケーション能力が高い人
- 事務手続きを正確にこなせる人
- 仕事に「安定性」を求める人
IT系の制作職|将来性や自由度を重視したい人におすすめ
将来性や自由度を重視したい人には、WEBデザイナーやWEBライターのようなIT系の制作職がおすすめです。
経済産業省によると、2030年にはIT人材がおよそ60万人不足すると考えられています。
常に人材不足で喘ぐ業界であることから、比較的未経験者でも参入しやすい業界です。(出典:経済産業省 商務情報制作局「参考資料(IT人材育成の状況等について)」)
また、IT業界については市場規模もIoTやAI市場を中心に年々拡大することが予想されることから、将来性についても心配ないでしょう。(出典:経済産業省 商務情報制作局「参考資料(IT人材育成の状況等について)」)
筆者も現在はフリーランスのWEBライターとして2年ほど活動しておりますが、少しずつ仕事量が増え、文字単価も上昇しています。
今では少ない労働時間であるにも関わらず、教員時代と同じくらいの年収にまで達しています。
- 知識欲や学習意欲が高い人
- 論理的に物事を考えるのが好きな人
- 柔軟な考え方ができる人
- 自主的に行動できる人
- コミュニケーション能力が高い人
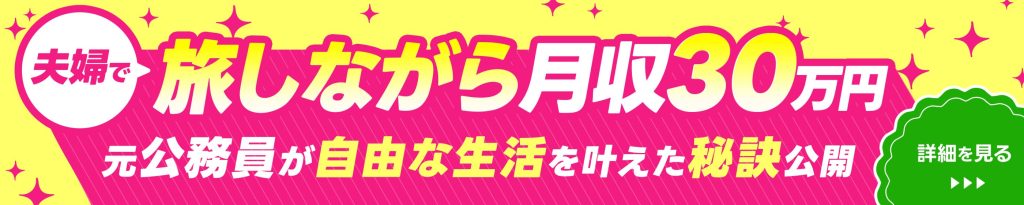
教員を辞めたいと悩む人からよくある質問

最後に、教員を辞めたいと悩む人からよくある質問とその回答をご紹介します。
教員を辞める前にしておくべきことは何ですか?
私自身が考える教員を辞める前にしておくべきことは、下記の通りです。
- お金を貯めておく
- ビジネススキルやマナーを勉強しておく
退職後すぐに新しい仕事が見つかればいいですが、必ずしもそうであるとは限りません。
そのような場合に備えて、およそ半年分の生活防衛資金があると良いでしょう。
お金があると精神的に余裕ができます。
そして、「教員を辞めなければよかった」と後悔するリスクを軽減することにもつながるのです。
また、学校は閉鎖的な空間であるため、外部の人とやり取りする機会が非常に少ないのが特徴ですが、民間企業の場合は異なります。
Eメールの書き方や名刺の受け渡しの仕方など、基本的なビジネススキルやマナーを勉強しておくことで転職後に恥ずかしい思いをするリスクを軽減できるでしょう。
年度途中に退職できますか?
年度途中に退職することはできます。
教員が退職できる時期について、厳密なルールはありません。
しかし、年度内で退職する場合は後任の先生を見つける手間がかかること、場合によっては見つからず他の職員に負担を与えてしまう可能性があります。
私の知り合いも年度途中に産休に入ったのですが、後任がなかなか見つからず結局他の教員が交代で彼女のクラスの授業を行なったそうです。
このような事態を防ぐためにも、可能であれば年度末に退職することをおすすめします。
円満退職を実現しやすくなるでしょう。
社会保険の手続きはどうなりますか?
退職日から14日以内に、各市町区村の窓口に足を運び社会保険から新たな健康保険に加入してください。
なお、国民健康保険へ切り替える際には「資格喪失証明書」が必要です。
これは学校(事務室)に申告すれば作成してもらえる書類であるため、退職前に作成の依頼をしておきましょう。
退職金はもらえますか?
はい、退職金はもらえます。
私は8年間教員を勤めていましたが、およそ100万円の退職金をもらえました。
勤続年数が長くなるほど、受給額も増えます。
手続きについてですが、基本的には学校側の指示に従って書類手続きを行うだけです。
転職活動はいつから始めるべきですか?
転職活動については、教員を辞めることを決断したらなるべく早めにスタートさせることがおすすめです。
厚生労働省が発表した「直前の勤め先を離職してから現在の勤め先に就職するまでの期間」に関する調査結果によると、大多数の離職者が2ヶ月以内に新しい職に就いています。
| 転職活動にかかる期間 | 割合 |
| 1ヶ月未満 | 29.3% |
| 離職期間なし | 24.8% |
| 1ヶ月以上2ヶ月未満 | 12.5% |
| 10ヶ月以上 | 7.7% |
離職期間が長くなるほど新しい職に就きづらくなるとともに、経済的な不安も大きくなるでしょう。
離職後にすぐに新しい仕事が始められるように、なるべく早めに転職活動をスタートさせてください。
転職活動に不安を感じる方は、エージェントを活用するなどプロの手を借りて転職活動を進めることをおすすめします。
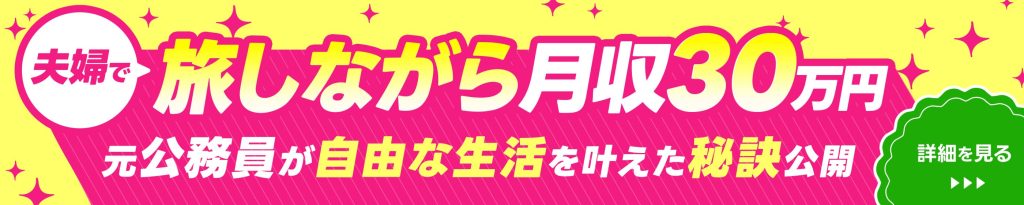
まとめ:教員を辞めたい人はよく考えて後悔のない選択を!
この記事では、下記のことについて筆者の体験を元に説明しました。
- 教員を辞めたいと考える人が挙げる主な理由教員を辞める前にできること
- 教員を辞めて実感したメリット・デメリット
- 教員を辞めた方がいい人&辞めないほうがいいひとの特徴
- 教員を退職する流れ教員を辞めた後のキャリアプラン
- 元教員におすすめのお仕事
筆者も辞める前は、「公務員」という安定性や社会的信用を失うことに大きな不安を抱え、なかなか辞めることの決心がつきませんでした。
しかし、今では全く異なる人生を歩んでおり、辞めてから5年間1度も後悔したことはありません。
私はたまたま運が良かったところがありますが、中には退職後に「辞めなければ良かった」と後悔する人もいるでしょう。
辞めた後に後悔することがないように、なぜ教員を辞めたいのか根本原因を徹底追求し、その原因を改善あるいは解消するための術がないかどうかを真剣に考えてみてください。
解決方法がないときに初めて「辞める」ことを選択肢に入れることで、辞めた後に後悔するリスクを軽減できるでしょう。
ぜひよく考えて後悔のない選択をしてくださいね!