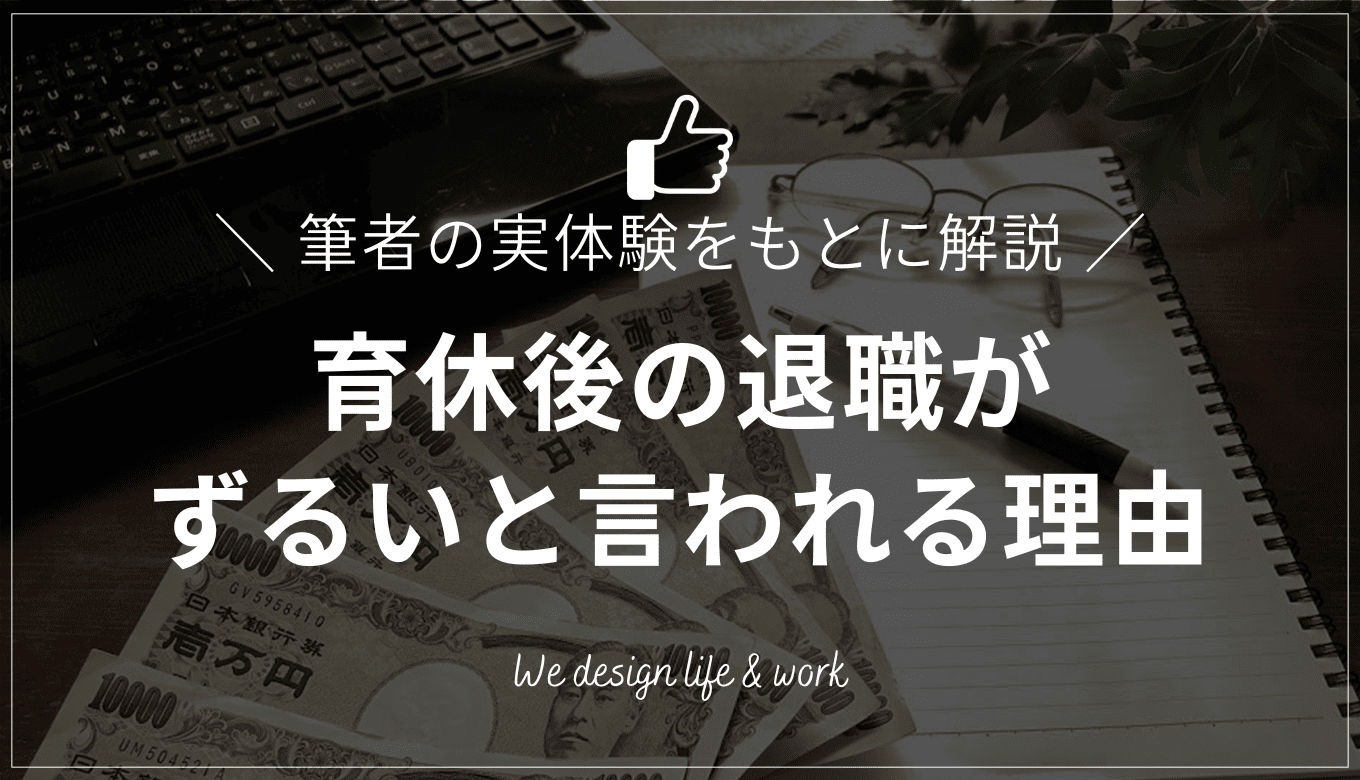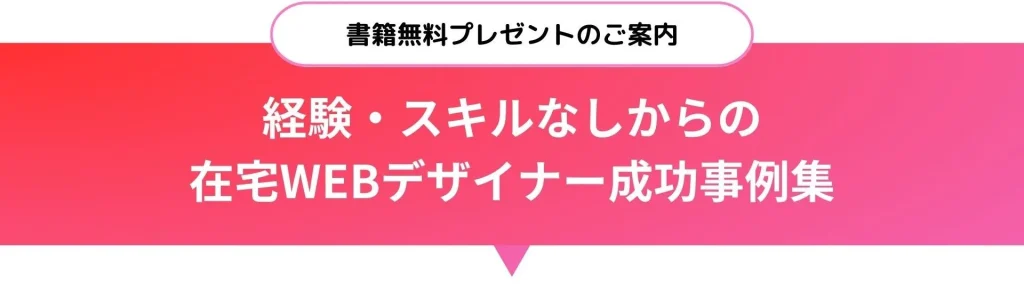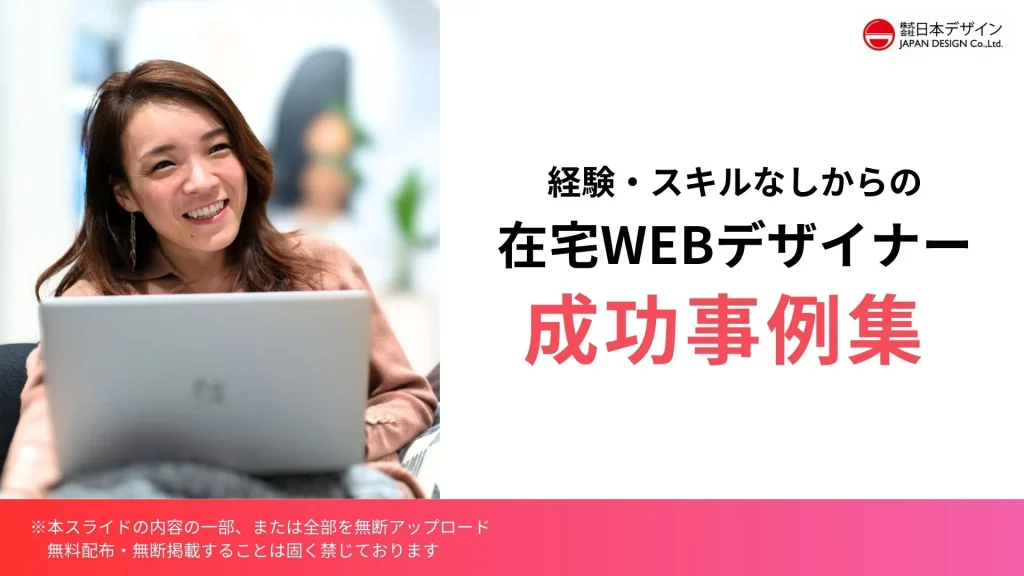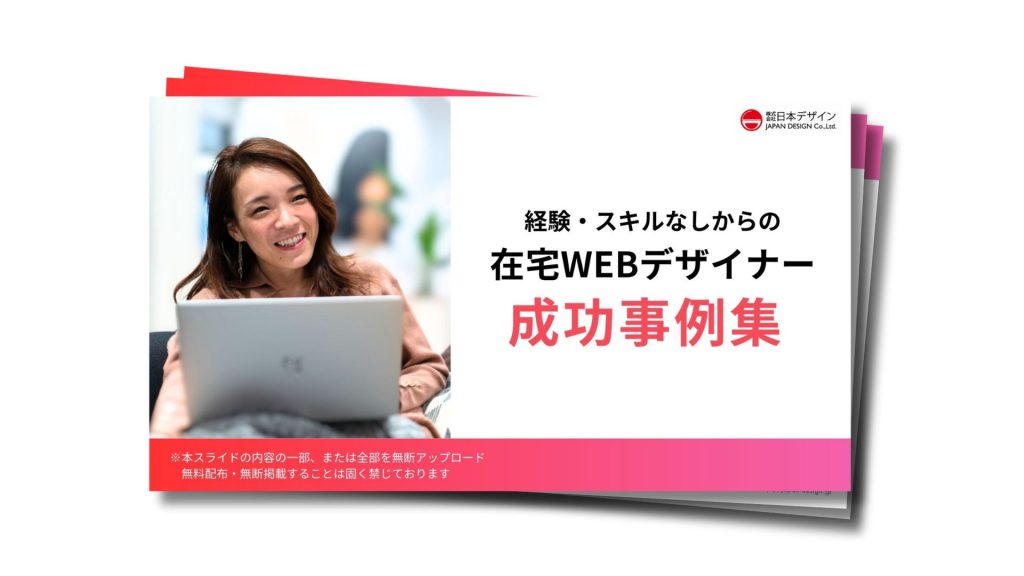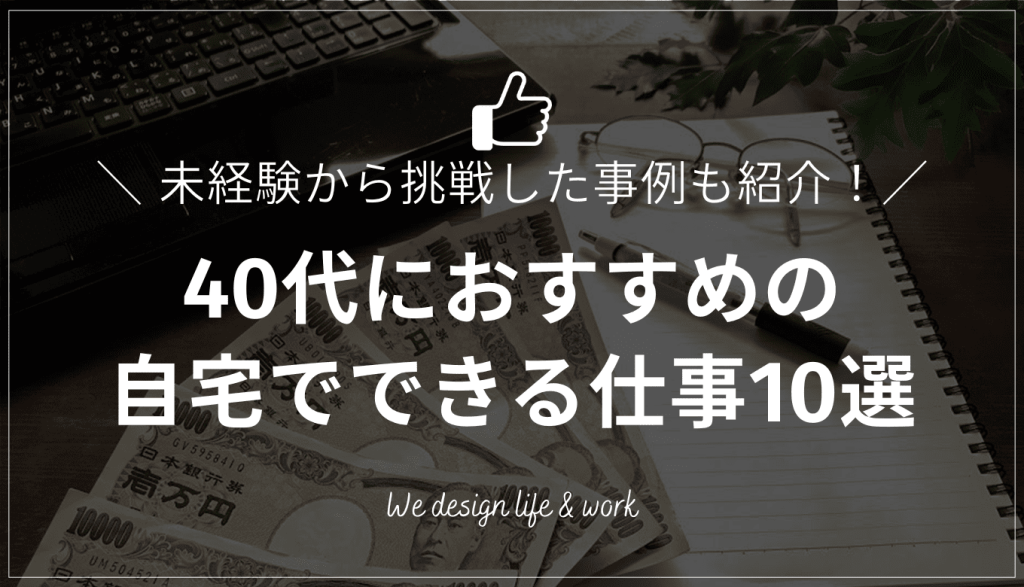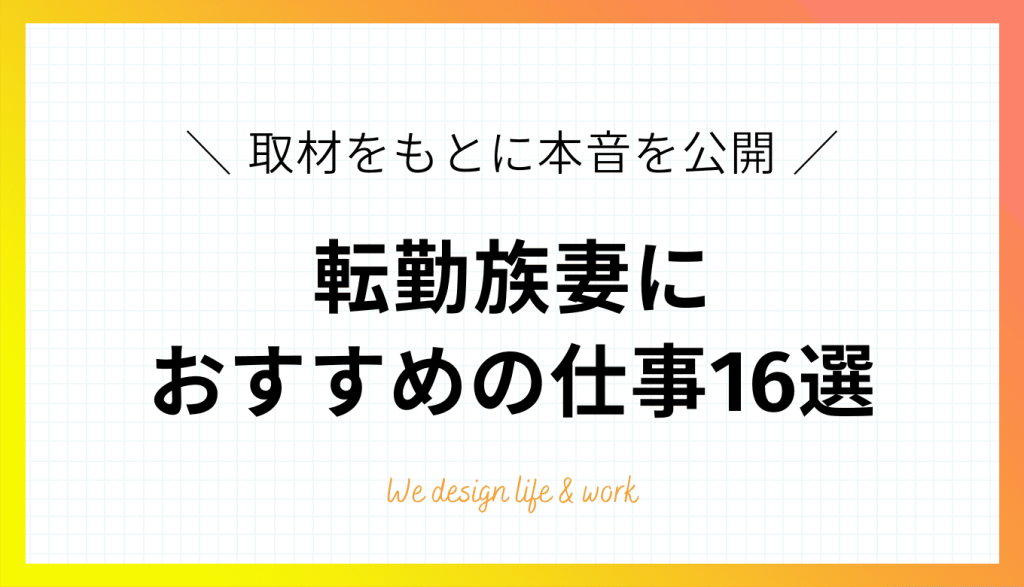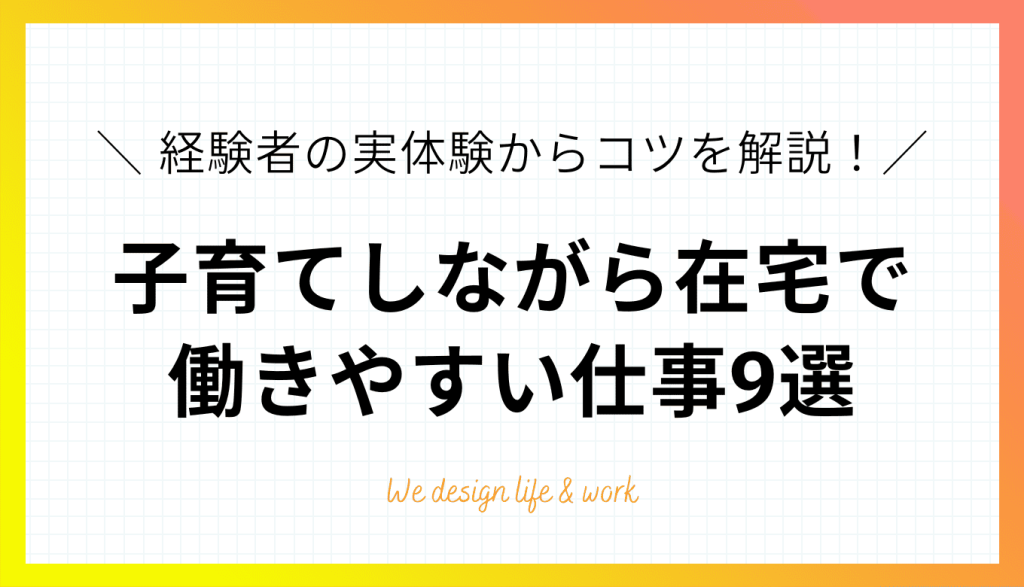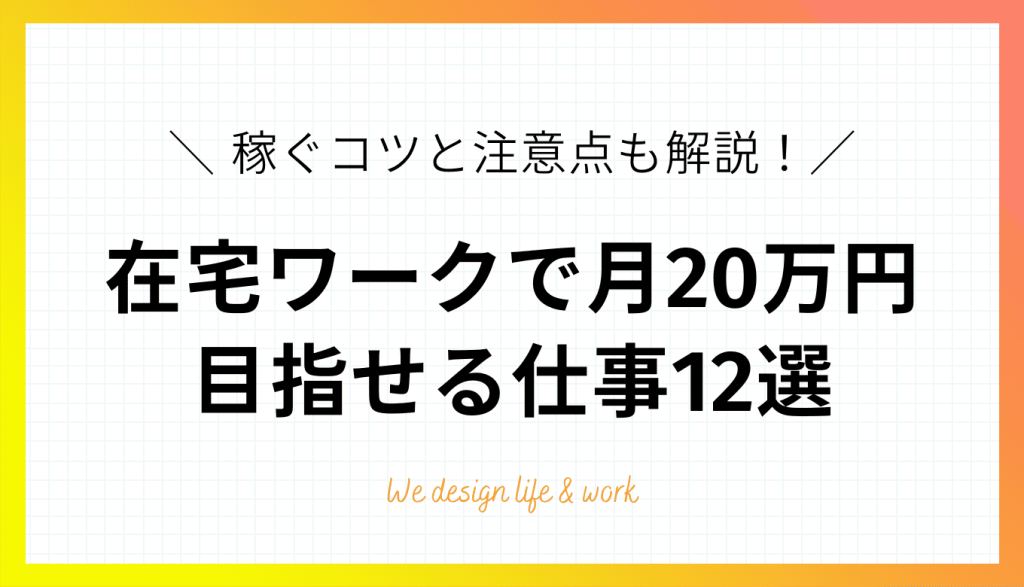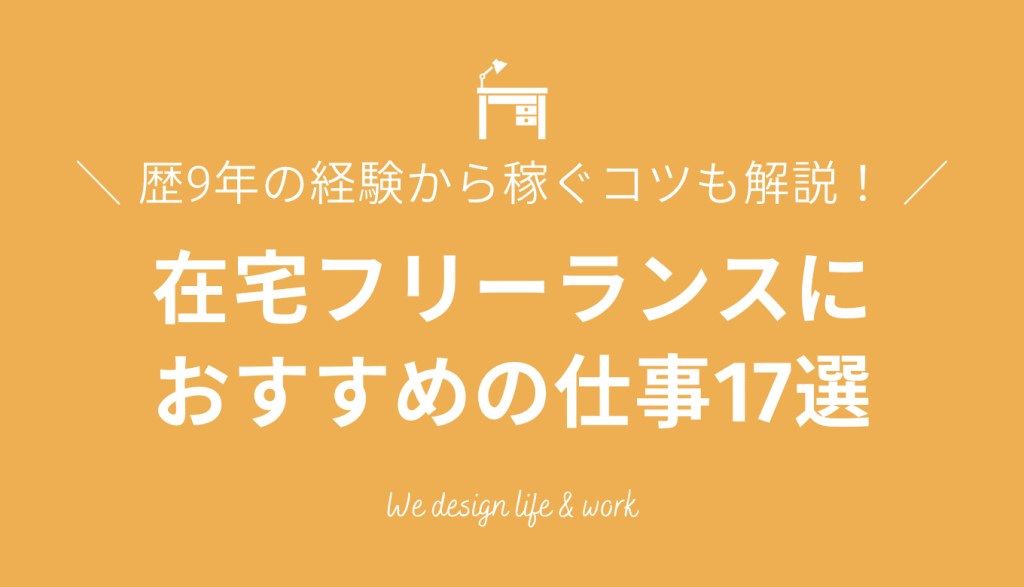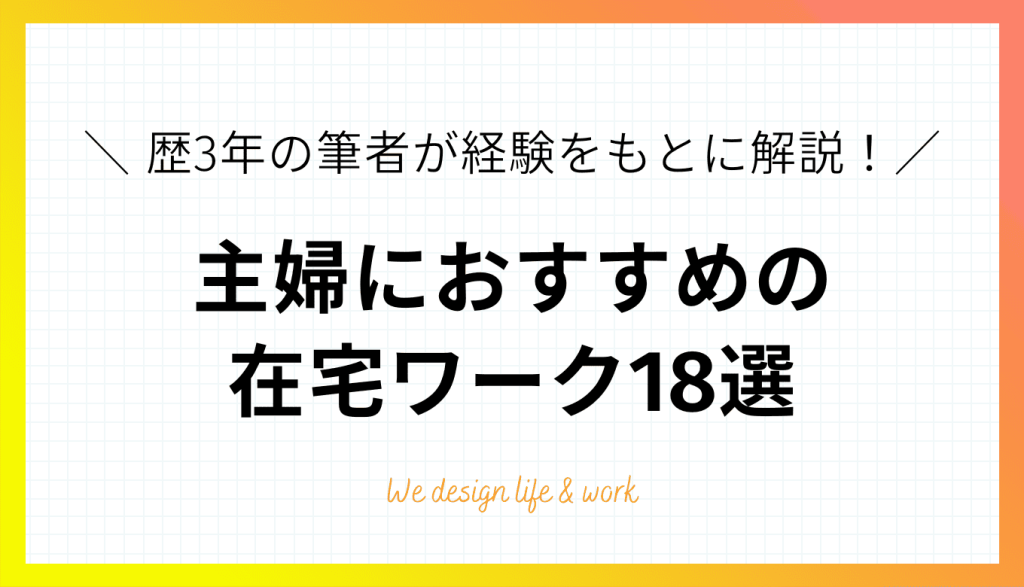「仕事と子育ての両立は大変そう」
「子育てに専念したい」
子育てと仕事の両立に自信がなくなる人や、子どもに向き合いたい気持ちが強くなり、育休後すぐの退職を考える人は多いでしょう。
しかし、育休後すぐに退職してずるいと思われないかを懸念し、行動できない気持ちもわかります。そこで、本記事では、育休後の退職がずるいと思われる理由を深掘りし、円満に退社する伝え方や手順などを紹介します。
私自身、子育てに向き合いたい気持ちと社会復帰したい思いで葛藤し、復帰後1年で退職しました。また、育休後すぐに退職した同僚も何人かおり、当時の評判も振り返りながら以下の内容を解説していきます。
- 育休後の退職は法的には問題ないが注意が必要
- 育休後の退職はずるいと思われる3つの原因
- 育休後に退職したいと考えてしまう理由3選
- 育休後に退職する3つのデメリット
- 育休後に退職してずるいと思われない伝え方のコツ3選
- 育休後に退職する場合の具体的な5つの手順
- 育休後の退職で注意すべきこと
本記事を参考に、育休後の退職に後めたさを感じる人や、本当に退職するべきか迷いがある人は、いちど立ち止まって考えてみてください。
育休後の退職は法的には問題ないが注意が必要

育休後すぐの退職や復帰せずそのまま退職する場合、法的にはなにも問題ありません。
下記の厚生労働省が発表しているデータのとおり、育休後に退職する人は一定数います。
<育児休業終了後退職者割合>
| 女性 | 男性 | |
| 2018年 | 10.5% | 5.0% |
| 2021年 | 6.9% | 2.5% |
| 2023年 | 6.8% | 2.7% |
| 女性 | 男性 | |
| 2018年 | 10.5% | 5.0% |
| 2021年 | 6.9% | 2.5% |
| 2023年 | 6.8% | 2.7% |
参照:厚生労働省|令和5年度雇用均等基本調査
また、育休終了と同時に退職すれば、育児休業給付金は満額受け取れます。
ただし、勢いで退職してしまうと後悔する可能性が高いです。
子育てに専念するために退職した場合でも、実際に子どもと一対一の生活が続けば社会復帰したくなるかもしれません。
本記事で解説する、育休後の退職のデメリットや注意点を参考に、すぐに退職しても問題がないかよく考えてみましょう。
育休後の退職はずるいと思われる3つの原因

育休後の退職がずるいと思われる3つの原因を解説します。
- 育休取得は復職が前提で認められるから
- 人員配置や業務配分のしわ寄せが残るから
- 新規採用や人材育成などの負担が発生するから
自分が育休後に退職した場合、ずるいと思われる原因のどれに当てはまるか考えてみましょう。
原因1:育休取得は復職が前提で認められるから
育休後の退職がずるいと思われてしまう理由は、育休の取得が復職を前提として認められているからです。
育休は育児と仕事を両立したい人を支えるものですが、復帰する意思がないまま制度を使ったと受け取られると、周囲から反感をかう可能性があります。
復帰を前提にした人員配置や、業務をカバーして育休に協力していた職場にとって、突然の退職は裏切られたと思われても仕方がありません。
最初から復帰するつもりがないのに、育児休業給付金目当てで育休をとったと、制度を悪用したと受け取られてしまうこともあります。
実際に私が働いていた会社で、育休終了と同時に退職した人がいましたが、育児休業給付金だけもらって退職してずるいと思われていたようです。
原因2:人員配置や業務配分のしわ寄せが残るから
育休後に退職すると人員配置や業務配分のしわ寄せが残り、ずるいと思われることがあります。
- 一時的にカバーした業務の負担が減らない
- 業務の引き継ぎが不十分でクレームにつながった
- 新たな人員の確保が間に合わない
育休のため一時的に仕事を引き継いだ同僚は、復職した人がふたたび担当すると期待しています。
また、以前働いていた職場のルールでは、育休に入っている社員はひとりとカウントされてしまうため、求人を出すことや別の部署から人を確保するのはできない決まりになっていました。
復帰を前提に人員配置を考慮していた会社は、新たな人員確保を早急にしなくてはなりません。
復帰を期待して人員配置や業務配分を考えていた会社や同僚へ、仕事量の負担が増えずるいと思われることがあります。
原因3:新規採用や人材育成などの負担が発生するから
育休後の退職がずるいと思われる理由は、新規採用や人材育成などの負担が発生するからです。
復帰を前提に体制を整えていたにも関わらず退職となると、会社は新しい人材の確保と育成に時間も費用もかけなければなりません。
- 求人掲載や紹介料などの採用費用
- 新人研修や教育のための時間
- 業務習得までの生産性の低下
- ほかの従業員の負担増加による時間外労働
- ほかの従業員から不満が出たことによる士気の低下
ブランクはあっても業務に慣れている育休中の人が復帰するよりも、新しく人を採用してひとり立ちさせるほうが、時間と費用的な負担は大きいです。
また、実際に人材を育成する現場では残業につながり、チーム全体の士気が下がってしまいます。
現場での労力的な負担や、企業側のコストが増えるため、育休後の退職がずるいと思われがちなのです。
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
育休後に退職したいと考えてしまう理由3選

育休後に退職したいと考えてしまう以下3つの理由を深掘りします。
- 仕事と子育ての両立が思ったより大変だった
- 職場や同僚からの理解が得られず居心地が悪い
- 子育てに専念したい気持ちが強くなった
仕事より子育てやプライベートを充実させたい場合や、職場の環境次第で退職したいと考えることがあります。
自分が育休後に退職したいと感じた理由と照らしあわせながら考えてみましょう。
理由1:仕事と子育て・家事の両立が思ったより大変だった
育休後に退職したいと考えてしまう理由は、仕事と子育ての両立が思ったより大変だったことが考えられます。
- 保育園の送り迎え
- 子どもの急な発熱対応
- 朝の準備が間に合わない
- 家事の時間が減り部屋が散らかる
- 睡眠時間の確保が困難
実際に私も育休から復帰後、保育園の送り迎えをしながら通勤していましたが、時間に余裕がない毎日にストレスを感じていました。
また、保育園に入園した直後から1年間は風邪をもらいやすく、急なお迎え要請は日常茶飯事です。
仕事を休まなくてはならない日が続けば、業務がたまり仕事への影響も増えます。
家事をゆっくりできる時間もなくなるため部屋が散らかりがちで、外食と食費が増えたことも大変でした。
理由2:職場や同僚からの理解が得られず居心地が悪い
職場や同僚からの理解が得られず居心地が悪い場合、育休後に退職したいと考えてしまう可能性が高いです。
育児との両立に対する配慮がなく、周囲の視線や言葉にストレスを感じる場合があります。
- 時短勤務への嫌味を言われる
- 急な休みや早退を白い目でみられる
- 子育て支援制度が整っていない
- 協力を求めるのが気まずい空気がある
- 職場に育児中の人が少なく相談できない
- 復帰後の仕事量が極端に少ない
- 復帰前と同じ仕事量で帰れない
育休明けは生活のリズムも変化し、心身ともに負担を感じやすい時期です。
実際に私も育休明けは、保育園の送り迎えを加えた通勤スケジュールに慣れるのが体力的にも大変でした。
そんな状況の中、復帰後の職場に居場所がないと感じてしまうと、退職を考えるのは自然なことです。
理由3:子育てに専念したい気持ちが強くなった
子育てに専念したい気持ちが強くなり、育休後に退職を考えることがあります。
子どもの成長に向き合う日々のなかで、そばで見守りたいと思いが深まりますよね。
実際に私も、発達の変化が早い乳幼児期の成長を、ひとつひとつ見逃したくないと感じていました。
保育園に預けることへの迷いや、仕事との両立による負担感から、仕事よりも家庭を優先したいと考える人も多いでしょう。
子どもと過ごす時間を優先したいと感じたとき、退職が現実的な選択肢に見えがちです。
前の職場でも、子育てに専念したいと復帰後に退職する人も多々いました。
育休後に退職する3つのデメリット

育休後に退職するデメリットを3つ紹介します。
- キャリアにブランクが生まれる
- 経済的に不安定になる可能性がある
- 職場の人間関係が悪化する可能性がある
会社から離れ、子育てに専念できる環境が整う反面、デメリットがあることも忘れてはなりません。
育休後に退職して後悔がないように、デメリットを理解し自分の状況を考慮しながら判断しましょう。
デメリット1:キャリアにブランクが生まれる
育休後に退職するデメリットは、キャリアにブランクが生まれることです。
一定の期間中に仕事から離れると、再就職しようとした際に不利になる場合があります。
応募先の企業から、以下のような不安をもたれるからです。
- 即戦力で活躍できるか
- 仕事の感覚が鈍っていないか
- 働く意欲があるか
- 最新の業務知識があるか
- すぐに辞めてしまわないか
- 職場の雰囲気に適応できるか
また、就業条件が限られる場合や、希望する職種に就きにくくなることもあります。
業界の変化が早い職種では、知識やスキルのアップデートが遅れやすくなるのも現実です。
育児に専念する選択は尊重されるべきものですが、今後のキャリアを見すえたうえで慎重に判断しましょう。
将来の選択肢を広げるためにも、キャリアの継続を立ち止まって考えるのが大切です。
デメリット2:経済的に不安定になる可能性がある
育休後に退職すると、経済的に不安定になる可能性がある点がデメリットです。
毎月の収入がなくなると、家計への影響は避けられません。
特に住宅ローンや教育費など、大きな固定出費がある家庭では、生活にゆとりがなくなる場合もあります。
育休中は給付金があるため収入が完全に途絶えるわけではありませんが、退職後はなくなります。
配偶者の収入だけで生活を支えるには、事前の資金計画が必要です。
また、子育てには想定外の支出も多く、急な出費に対応できないことも考えられます。
今後子どもの人数が増える可能性があるなら、教育費はさらに増えます。
今後の生活を安定させるためにも、退職を決める前に家計やライフプランを見直し、将来の収支をシミュレーションし長期的な視点で判断しましょう。
デメリット3:職場の人間関係が悪化する可能性がある
育休後に退職する場合のデメリットは、職場の人間関係が悪化する可能性がある点です。
復職を期待されていた人が辞めた場合、同僚や上司に不信感を与え、実務上での負担を増やしてしまうことがあります。
育休中は、周囲が業務を引き継いで対応する場面が多く、復帰を前提に準備をしていた会社や同僚にとって急な退職は想定外です。
感謝の気持ちや退職理由の説明に誠実さが欠けていると、関係がぎくしゃくするきっかけになります。
退職後も同じ業界で働きたいと考えている場合、人間関係の悪化はハードルになることもあります。
円満な退職を目指すためにも、誠意ある説明と感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
育休後に退職してずるいと思われない伝え方のコツ3選

育休後に退職してずるいと思われない伝え方には、3つのコツがあります。
- 前向きな退職理由を伝える
- 上司、職場全体の順番に伝える
- 同僚や上司に感謝の気持ちを伝える
実際に育休後の退職を考えているなら、職場への伝え方には要注意です。
ずるいと思われて職場との関係が悪化しないように工夫しましょう。
コツ1:前向きな退職理由を伝える
育休後に退職してもずるいと思われない伝え方のコツは、前向きな退職理由を伝えることです。
退職は大きな決断ですが、周囲に誠実な印象を残すためには、納得感のある説明が欠かせません。
退職の理由が明確で前向きであれば、職場の人も応援しやすいからです。
個人的な事情や感情だけではなく、将来を見すえた意思を示しましょう。
- 子育てに専念したい
- 家庭と両立しやすい働き方を目指したい
- やりたいことに挑戦したい
- 自分の強みを活かせる環境を探したい
- キャリアの幅を広げたい
- 資格の取得に専念したい
退職後になにをしたいか、どう成長したいかなど、前向きな意思が伝わる言い方にするのが大切です。
円満な関係を築いたまま次のステップへ進みましょう。
コツ2:上司、職場全体の順番に伝える
退職の意思は、上司、職場全体の順に伝えるのがずるいと思われないコツです。
上司への報告や相談が後回しになると、信頼を損ねるおそれがあります。
職場の人間関係を円満に保つためにも、伝える順番は意識すべきポイントです。
例えば先に同僚へ話してしまい本人以外の口から上司の耳に入ると、自分が後回しにされたと受け取られ心象が悪くなります。
退職の決断は大切な選択ですが、周囲の配慮を欠かさない姿勢は円満な退職につながります。
- まず直属の上司に相談する
- 今後の動き方や報告の仕方の指示を仰ぐ
- 職場全体には上司の了承を得てから共有する
丁寧な順番で伝えることで、周囲からずるいと思われにくいです。
コツ3:同僚や上司に感謝の気持ちを伝える
育休後に退職してずるいと思われないために、同僚や上司に感謝の気持ちを伝えましょう。
退職が周囲に負担をかけることもあるため、誠意をもって感謝の気持ちを伝える姿勢が信頼の獲得につながります。
感謝の気持ちが伝われば、退職後も良好な関係を保ちやすいです。
特に、育休中にサポートを受けた相手には、心を込めた言葉があると印象が変わります。
- 育休中の業務引き継ぎへの感謝
- 退職に理解ある対応への感謝
- 在籍中の経験に対する感謝
- 励ましや声かけへの感謝
- 職場環境への感謝
感謝の気持ちを丁寧に伝え、円満な退職をめざしましょう。
育休後に退職する場合の具体的な5つの手順

育休後に退職する場合の具体的な5つの手順に沿って解説します。
- 直属の上司に早めに相談する
- 退職届の準備をする
- 漏れなく引継ぎをする
- 退職の挨拶をする
- 社会保険や失業保険の手続きをする
紹介するスムーズな手順に沿って進め、円満に退職する準備を整えましょう。
手順1:直属の上司に早めに相談する
育休後に退職する場合、まず直属の上司に早めに相談しましょう。
退職の意思を職場に伝える場面では、順番とタイミングが重要です。
上司への相談が遅れると、職場内の調整や引き継ぎの準備に影響が出ます。
できるだけ早い段階で上司に気持ちを伝え、今後の対応を丁寧に話し合うべきです。
相談する際には、理由を明確に伝えると同時に、これまでの感謝を伝える姿勢が大切です。
誠意をもって退職の意思を示すことで、円満な退職につながります。
育休後に退職を申し出るのは、気まずさや不安を感じるかもしれませんが、まずは直属の上司に早めに伝えましょう。
手順2:退職届の準備をする
退職の意思を伝えた後は、書類を提出して正式な手続きを進める必要があります。
退職届は感情的な理由ではなく、職務に対する感謝や今後の意思を丁寧に書くことが望ましいです。
記入にあたっては、企業ごとのルールやフォーマットがあれば従ってください。
特に育休明けの退職は周囲への影響も大きいため、礼儀正しく、誠意ある表現を意識することが大切です。
提出するタイミングは、引き継ぎや後任の選定などを考慮し、余裕をもっておこなうよう心がけましょう。
退職届の準備は形式的に済ませるのではなく、丁寧な姿勢を見せることが円満な退職につながります。
手順3:漏れなく引継ぎをする
担当していた業務を漏れなく引き継ぎし、育休後の退職をスムーズに進めましょう。
引き継ぎが不十分だと、業務に支障が出て職場に迷惑をかけてしまいます。
業務の内容や手順、担当者しかわからない細かなポイントまで、できるだけ明確に伝えることが重要です。
業務ごとにドキュメントにまとめておくと、引き継ぎされた人が確認しやすくなります。
また、引き継ぐ相手に直接説明すると認識のずれが減ります。
- 業務をリストアップする
- 業務目的を明確化する
- 業務内容を手順に分解する
- ドキュメントにまとめる
- 関係各所の連絡先をまとめる
- 対応履歴をまとめる
- やり取り履歴をまとめる
- 問い合わせ対応のルールまとめる
担当業務を漏れなく引き継ぐことで、退職後に会社の人が困らないような体制をつくり、職場に対する誠意を示しましょう。
手順4:退職の挨拶をする
引き継ぎが済んだら、関係各所に退職の挨拶をしましょう。
社内だけでなく社外の人にも挨拶を丁寧にすると、真摯な印象が残ります。
特に育休明けは、復帰を前提に調整している職場が多いため、丁寧な言葉で感謝の気持ちを伝えるのが大切です。
直接、挨拶する機会がない場合は、メールや手紙を活用しましょう。
内容は短くても問題ありませんが、感謝の気持ちや引き継ぎ先などを丁寧に伝えると好印象です。
お世話になった人に対して感謝を言葉にすることで、人間関係を円満に保てます。
円滑な退職のためにも、退職の挨拶は丁寧におこないましょう。
手順5:社会保険や失業保険の手続きをする
育休後の退職で最後にやるのは、社会保険や失業保険など必要な手続きです。
生活の安定や医療費の負担を軽減するため、退職後に必要な手続きを確実に進める必要があります。
退職後に必要な手続きの例は以下のとおりです。
- 健康保険の任意継続または国民保険への切り替え
- 年金の種別変更手続き
- 失業保険の受給申請
- 雇用保険被保険者証の確認
- 児童手当などの変更届
会社を退職すると、これまで勤務先が対応していた保険や年金の扱いが変わります。
手続きをしないまま放置すると保障を受けられない場合があるため、早めに行動しましょう。
手続きを円滑に進めるためにも、あらかじめ必要書類や期限をリストアップしておくと効率よく進められます。
育休後の退職で注意すべきこと

育休後の退職では3つのことに注意しましょう。
- 就業規則を確認する
- 退職後のキャリアプランを考える
- 保育園を退園する必要がある
退職は人生の大きなターニングポイントになります。
退職後の生き方を考え、必要な手続きを忘れずにおこなうなど慎重に進めるべきです。
記事の内容を参考に、今後自分がどのように動くべきかイメージしてください。
注意点1:就業規則を確認する
育休後に退職する際に注意すべきことは、就業規則の内容を事前に確認することです。
就業規則の内容で確認すべきことは以下のとおりです。
- 退職の申し出期限
- 退職届の提出期限
- 退職届フォーマットの有無
- 退職金の有無
例えば、退職届の提出期限が1か月前までと明記されている場合、その期限を過ぎるとトラブルに発展する場合があります。
また、育休中の退職に特別なルールを設けている場合もあります。
スムーズな退職のために、会社の規則には従うことが必要です。
トラブルを避けるためにも、まずは就業規則を確認し、不明点は早めに人事担当者に相談しましょう。
注意点2:退職後のキャリアプランを考える
退職後のキャリアプランを考えておくと、育休後に退職しても安心です。
方向性を定めないまま退職すると、後悔する場合や判断ミスをするおそれがあります。
退職を検討する段階で、自分がどのような働き方を目指すかを明確にしておくことが重要です。
- 子育てと両立しやすい職種
- 自分の得意や経験が活用できること
- キャリア再構築のタイミング
- 子どもの年齢ごとの最適な働き方
- 学び直しの必要性
- 収入の見込みと安定性
- やりがいを感じる業務内容
キャリアプランニングでは、タイミングに応じて優先する軸を決めましょう。
子どもが幼いうちはパートタイムや派遣社員など、時間に融通がきくほうが働きやすい場合があります。
子どもが成長してから仕事に打ち込むことも選択肢のひとつです。
注意点3:保育園を退園する必要がある
育休後に退職する場合、保育園を退園する必要があります。
保育園に通うには、保護者の就労が条件になっている場合が多いからです。
収入が途切れるだけでなく、子どもの預け先がなくなるのは大きな負担になります。
ただし、子どもが4歳になる年には幼稚園に通わせる選択肢もあります。
近年では、預かり保育や給食を提供する園も増えてきているため、働くママも無理なく通える環境が整いつつあります。
実際に私の子どもも、退職と同時に保育園を退園しましたが、幼稚園に通える年齢だったため転園し在宅ワークに切り替えました。
子どもが年中(5〜6歳)になる頃には、仕事をはじめるママも徐々に増え、預かり保育を利用する園児も多数いました。
退職後の生活と子育てを両立させるには、保育環境を整える準備を進めておきましょう。
保育園と幼稚園の違いを理解したうえで、自身のライフスタイルにあったベストな選択をしてください。
まとめ

育休後の退職はずるいと思われることもありますが、法律的な問題はありません。
働く人の気持ちやライフスタイルの変化にあわせて退職を選ぶのは当たり前です。
ただし、退職の伝え方や手順をミスしてしまうと以下のようなデメリットにつながります。
- キャリアにブランクが生まれる
- 経済的に不安定になる可能性がある
- 職場の人間関係が悪化する可能性がある
育休後に退職してずるいと思われないように、誠実に丁寧な対応をするのが重要です。
また、就業規則を事前に確認し、退職後のキャリアプランを考えておきましょう。
育休後に退職したからといって、人生が終わりではありません。
自分の正直な気持ちに向き合い、将来を見越した最適な選択をしてください。