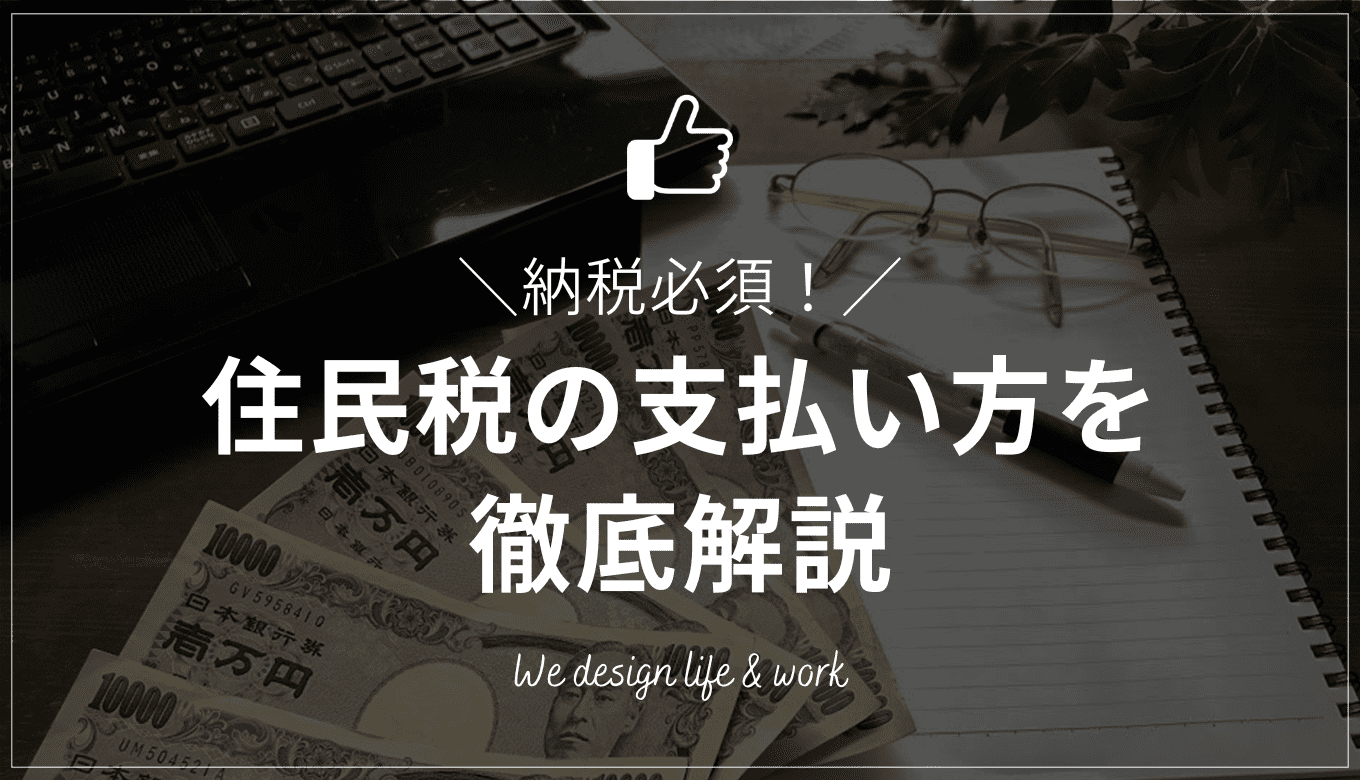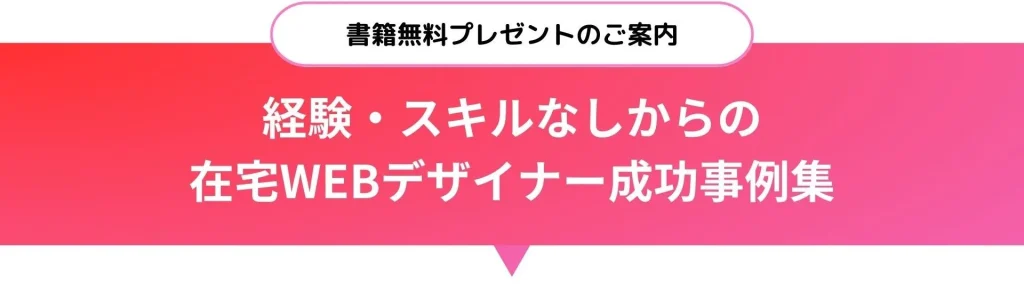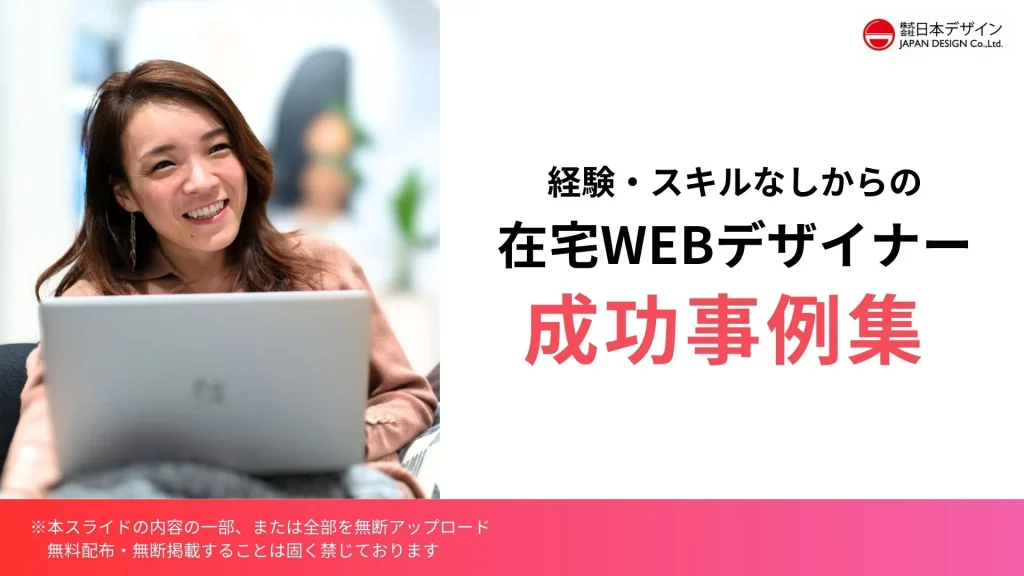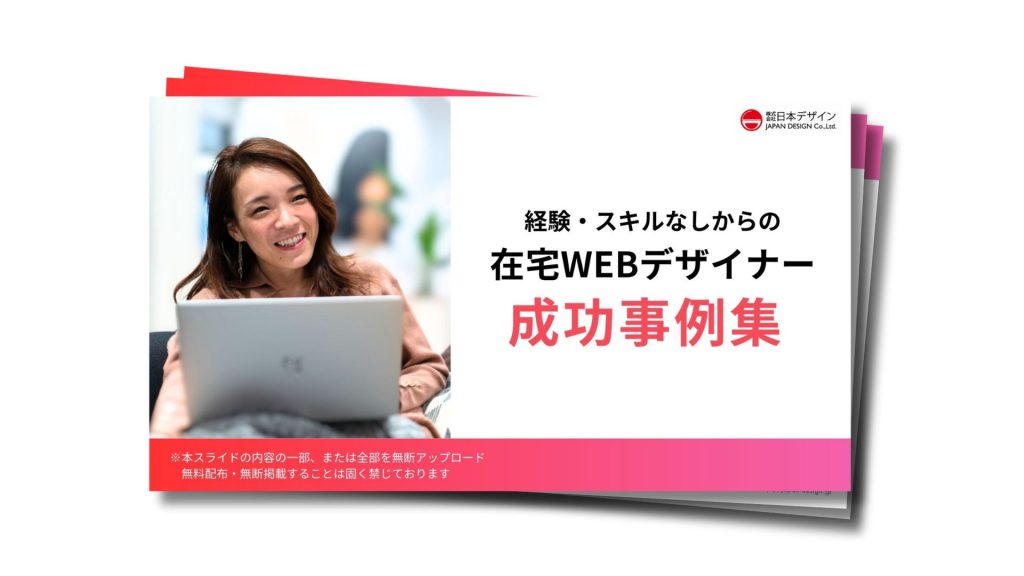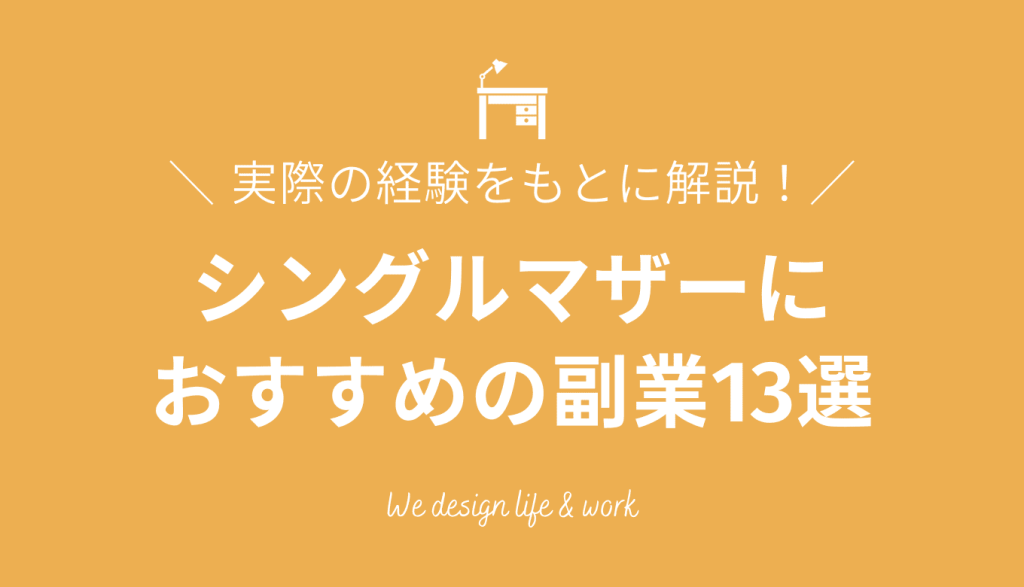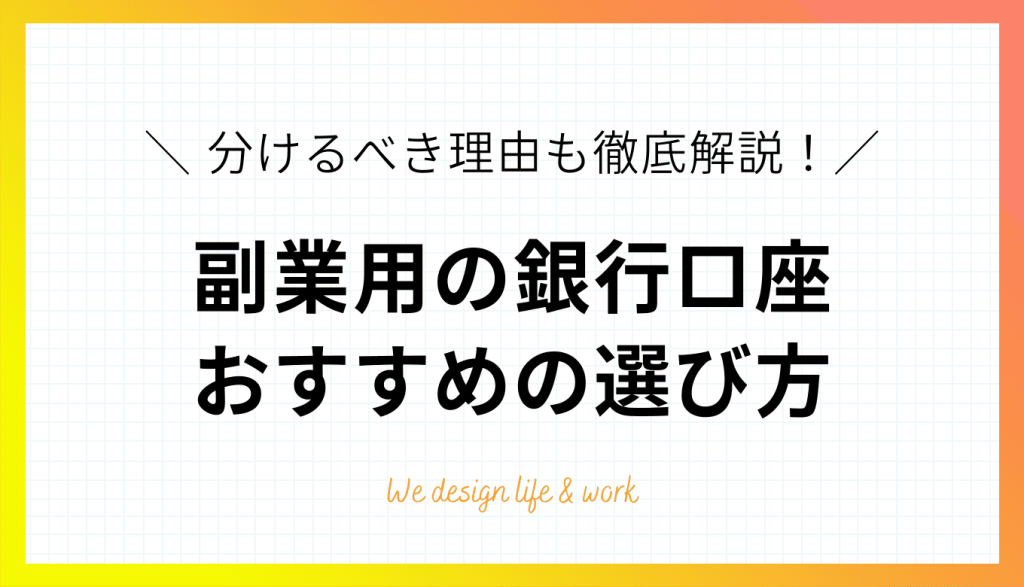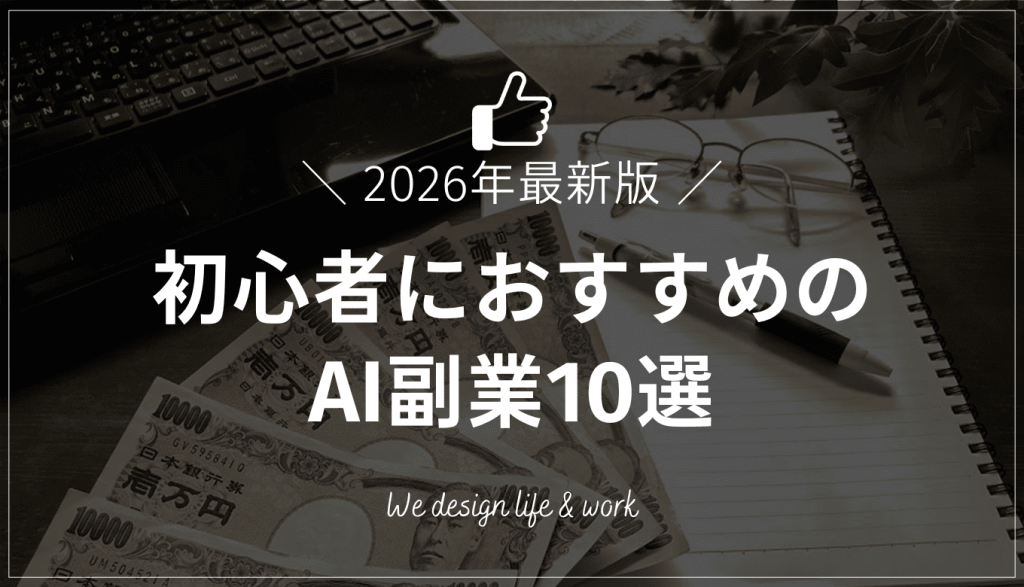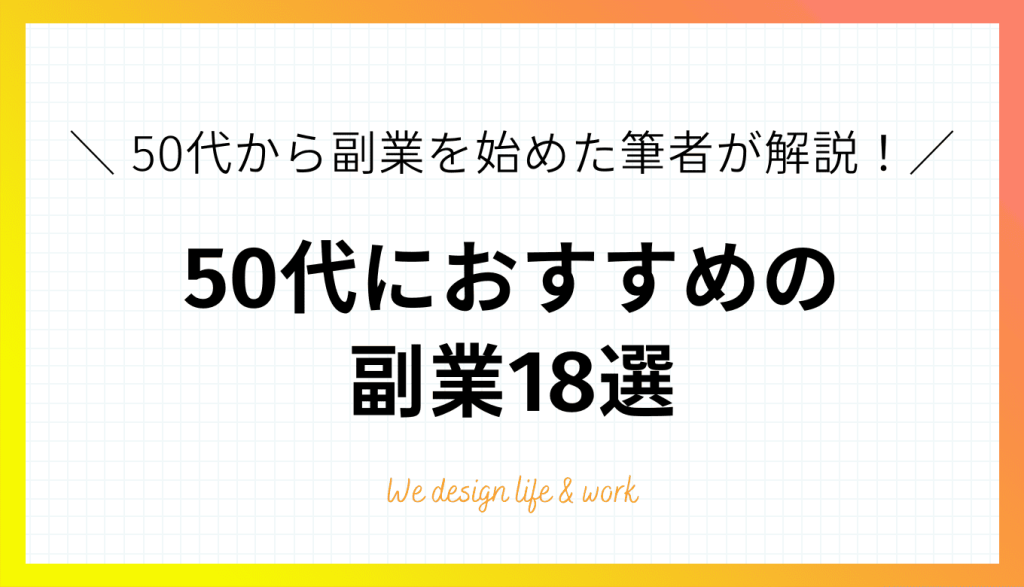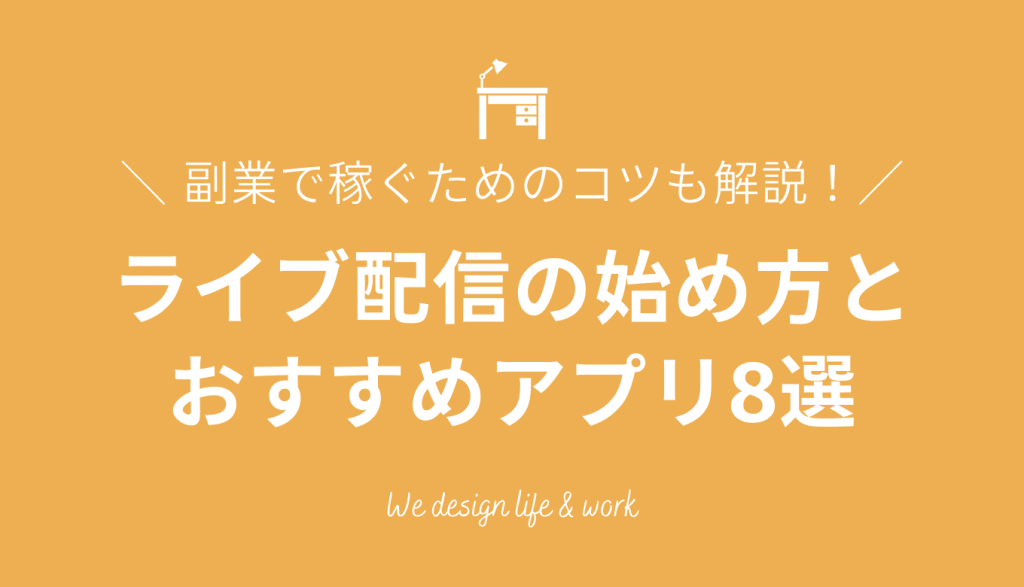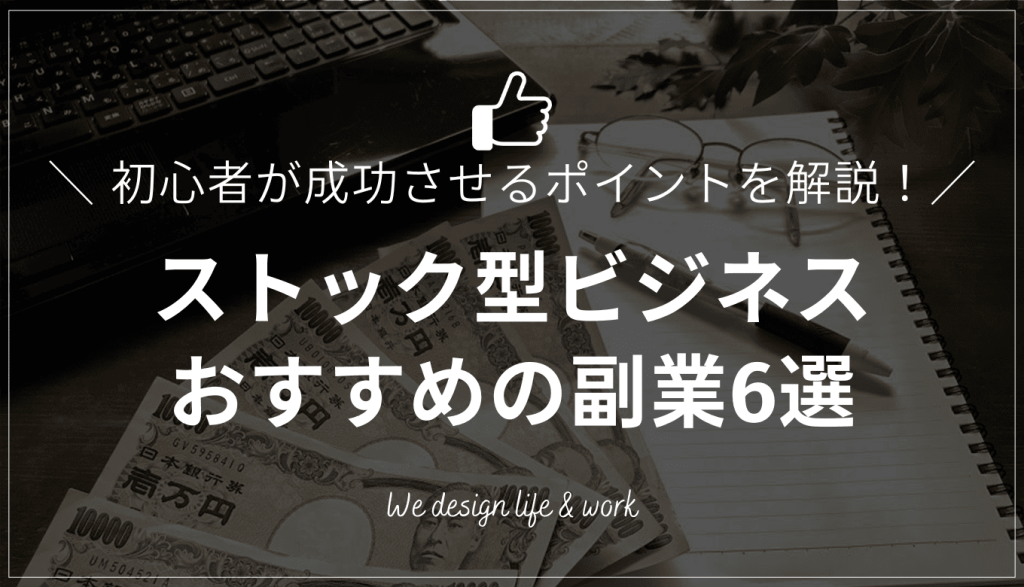副業を始めると、税金についてこれまで以上に気を遣わなければいけません。とはいっても、住民税、確定申告、年末調整などいろいろとあって、何をやる必要があるのか迷ってしまいますよね。
税金を正しく納められていないと、延滞税を払う必要ができてしまい結果的に損をしてしまうこともあります。せっかく副業で稼いだお金を、無駄にしてしまうほど悲しいことはありませんよね。
そのため、今回は副業の納税で気をつけるべき住民税について解説しました。
- 副業したら住民税は払わなくちゃいけないの?
- 住民税の種類がよくわからない…
- 住民税の払い方について知りたい
などの疑問や悩みを持っている方に、ぜひ読んでいただきたいです。正しく納税して、安心して副業に取り組んでいけるようにしましょう!
副業での住民税は必ずかかる
副業による収入が低ければ住民税がかからないということはありません。「20万円を超えなければ大丈夫」といった話を聞いたことがある方もいるかと思います。
しかし、それは所得税の話であって住民税には当てはまらないです。
副業による収入が20万円以下の人は、所得税を払わずに済み、確定申告の必要がありません。住民税は所得税の取り扱いとは別になっているので、副業分の収入が20万円以下でもすべての人が支払う必要があります。
住民税の計算式は、以下の通りです。
住民税=課税所得×10%+均等割+調整控除額
均等割とは、定められた額を一律に課税するもので、その金額は自治体によって異なります。市区町村民税は3500円から4400円、都道府県民税は1500円から2500円までです。
式を見てわかるように、所得が大きくなればなるほど住民税の支払い額は大きくなります。
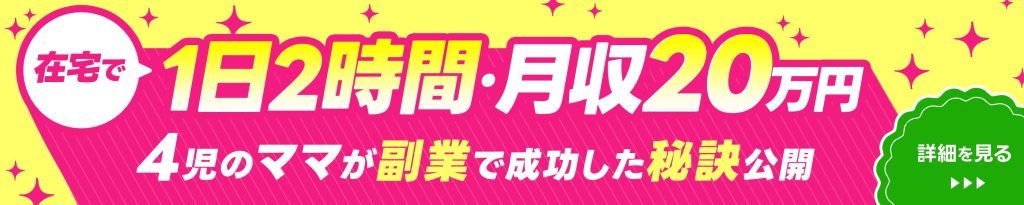
副業で支払う住民税のパターン
住民税には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。それぞれ支払い方が違うため、1つずつ説明していきますね。
特別徴収
特別徴収は、給与所得者が徴収の対象となる住民税です。給与所得者とは、会社員やアルバイトなどで勤務先から給料や賞与をもらう人のこと。
こちらは、6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収されます。毎月の給料から天引きされているので、給与所得者が自ら直接納税手続きをする必要はありません。
そのため、会社に勤めるなどで給与を所得している人は、意識せずとも毎月住民税を納められています。
普通徴収
普通徴収とは、区市町村から送付される納付通知書で住民税を自ら直接納める方法です。こちらは6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納税します。
会社員は基本的に特別徴収で納税しているため、普通徴収で直接住民税を支払った経験がある方は少ないでしょう。
フリーランスの方や自営業者の方が納税する際の方法が、普通徴収になります。
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
住民税を特別徴収で支払うと副業がバレる
会社員が副業をしている場合、住民税の支払い方法によっては勤務先に副業がバレる可能性があります。
通常、会社員の住民税は「特別徴収」として給与から天引きされます。しかし、副業で得た収入にも住民税が発生するため、副業分の住民税が給与に上乗せされると、会社の経理担当者が「住民税額が不自然に高い」と気づくことがあるのです。
副業を会社に知られたくない場合は、住民税の支払い方法を「普通徴収」に変更するのが有効です。「普通徴収」を選択すると、副業分の住民税は自分で納付するため、会社には影響しません。
※ただし、会社に副業がバレる要因は住民税だけではありませんし、倫理的な問題や懲戒免職等のリスクがあるため、会社に内緒で副業をすることは推奨しておりません。
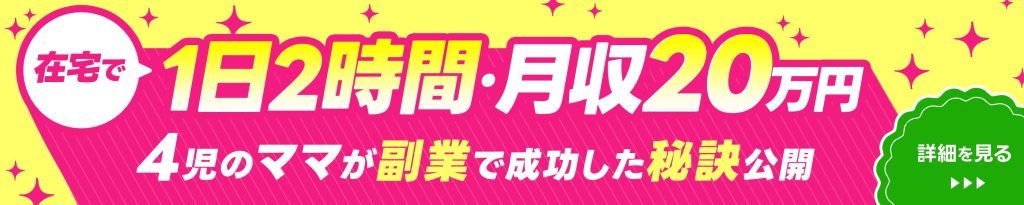
副業による住民税の支払い方
自分の所得の種類がわかったら、いよいよ住民税の支払い方について説明していきます。
副業のなかでも、所得の種類が給与所得のみの場合は、住民税が給与から天引きされる特別徴収に分類されるため、自ら支払い手続きをする必要がありません。
注意したいのが、普通徴収に当てはまる事業所得や雑所得などについてです。
給与所得のように会社が天引きしてくれるわけではないので、自ら支払い手続きをする必要があります。
普通徴収の支払い方法は、確定申告をしているかどうかによって変わるので、注意してください。
確定申告をしている場合
副業所得が20万円を超えている場合は、税務署へ確定申告をする必要があります。確定申告を行うのは、例年2月16日から3月15日頃までの期間です。
- 前年の所得の確定申告を行う
- 住民税に関する欄を記入した確定申告書を提出する
- 個人宛に納税通知書と納付書を送付する
- 一括か4期分割のどちらかで住民税を納付する
確定申告をしていない場合
副業所得が20万円を下回る場合は、税務署への確定申告は必要ありません。しかし、住民税の納付は必須になるため、市役所など自治体へ直接申告することが必要です。
その際、自治体から直接送付される納税通知書(納付書)で納税します。住民税の年税額が記載されている納税通知書は、通常5月下旬から6月中旬に送られてくるものです。
納期は年4回となっており、東京都の納期は6月末日、8月末日、10月末日、1月末日です。地方自治体によって異なる場合もあるので、書面の記載事項を確認しておきましょう。
納税通知書が送られてくる封筒には、納付書が同封されています。支払いは、納付書の裏面に書いてある取扱金融機関やコンビニエンスストアでおこないましょう。
最近では、口座振替やクレジットカード払いに対応している自治体も増えています。クレジットカードを使うとネットで支払いができたり、ポイントが貯まったりするというメリットもあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。
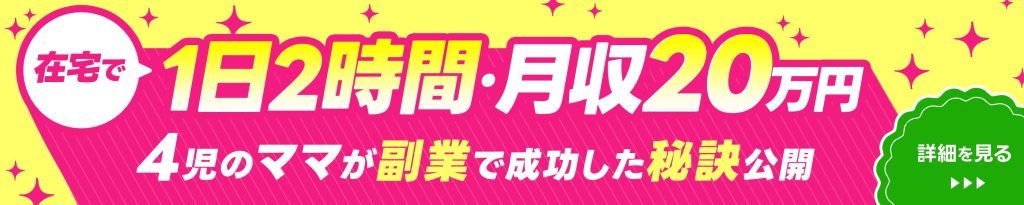
住民税を支払う際の注意点
住民税の支払い方はわかりましたか?
最後に、住民税の支払いにおける注意ポイントをお伝えします。
いざ住民税の支払いをする前に、確認してください!
申告・支払い期限を把握して守る
注意点1つ目は、申告・支払い期限を把握してきちんと納期に間に合わせることです。住民税の支払い期限は確定申告と同様3/15になります。
気づいたら締め切りを過ぎていた……ということが起こると、罰則として延滞税を支払わなくてはなりません。
支払いの遅延日時が長いほど延滞税の金額も高くなってしまいます。せっかく副業で稼いだお金を必要以上に失わないように、きちんと期日を確認して早めに納税するようにしましょう。
転職・退職時の支払いに気をつける
2つ目に、転職・退職した際の支払いにも注意が必要です。退職した場、会社員が退職した後は、天引きできなくなった分を自分で納付しなければなりません。
住民税の計算は、前年の所得から算出されます。
退職後に収入がなくなった場合でも、前年度に収入があれば関係なしに納めなければならないんです。退職した後も気を抜かず、住民税の支払いの準備をしておきましょう。
クレジットカード支払いだと領収証が発行できない
3つ目の注意点は、クレジットカード支払いだと領収書が発行されないということです。金融機関やコンビニではハンコを押した領収書がもらえますが、カード払いでは領収書がもらえません。
証明が必要な場合は、市町村役場に納税証明書を請求しなくてはならないので手間になってしまいます。
また、クレジットカードではシステム手数料がかかってしまうというデメリットも。支払いにおける手間やかかるお金の違いを踏まえたうえで、自分にあった支払い方法を選んでいきましょう。
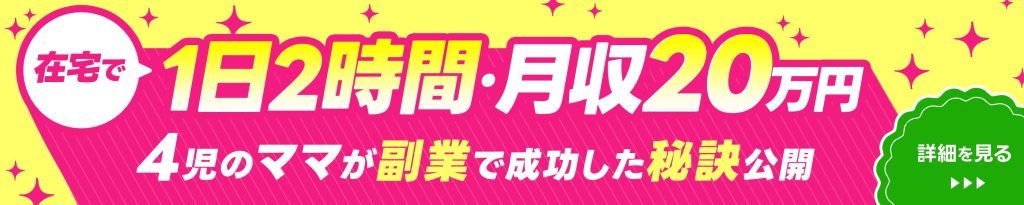
まとめ
副業における住民税の支払い方は理解いただけましたか?
一件、複雑で難しいと感じる方もいるかもしれません。
そんなときは、1つずつ項目を確認して整理してみてください。
チェックポイント
- 副業分の所得はどの種類に分類されるか
- 特別徴収と普通徴収のどちらか
- 収入ー経費=所得はいくらになるか
- 確定申告する必要があるか
上記が確認できれば、自分がどの支払い方をすればよいのかが明確になるはずです。
この記事のポイントをまとめると、
- 副業をしたら必ず住民税を支払う必要がある
- 給与所得以外の場合、自分で直接納税をしなくてはならない
- 副業所得が20万円を超えたら確定申告
- 確定申告をしない場合は、直接自治体に申告する
副業をすると、本業だけのときと比べてやることや考えることが増え、慣れないうちは大変なことも多いでしょう。
一見、納税は面倒くさいと思うこともあるかもしれませんが、正しく納税することが、結果的に副業での収入を守る道になります。
早めに準備や確認をおこない、思い切り副業の業務を頑張ってくださいね。
あなたが自分らしく働けるように応援しています。