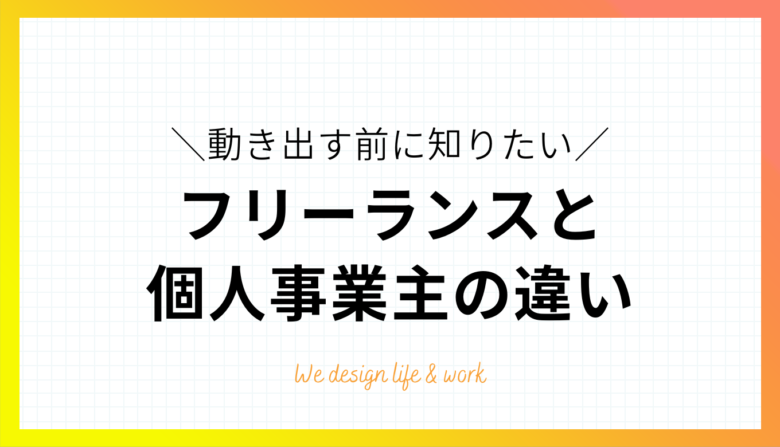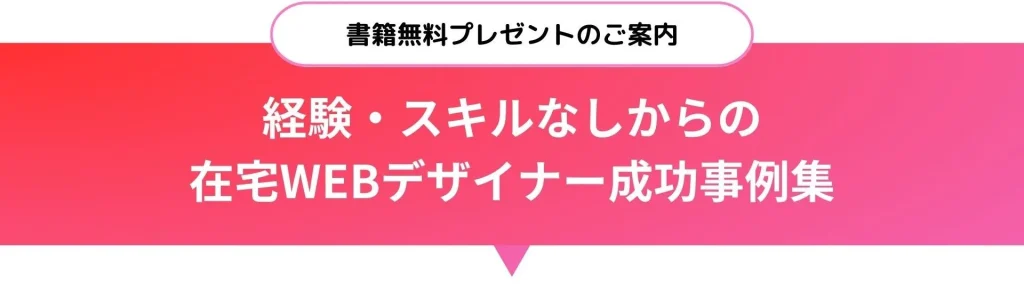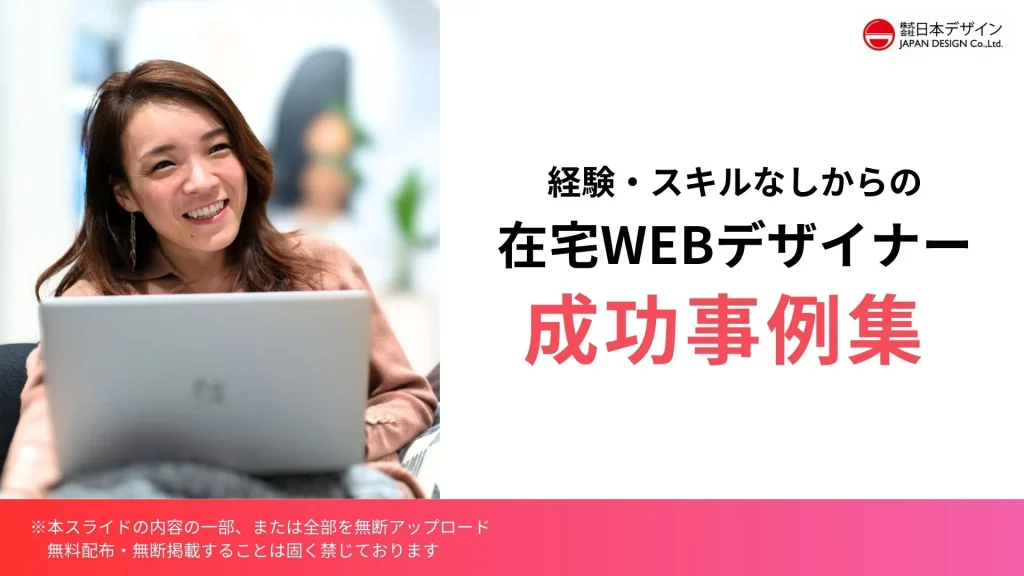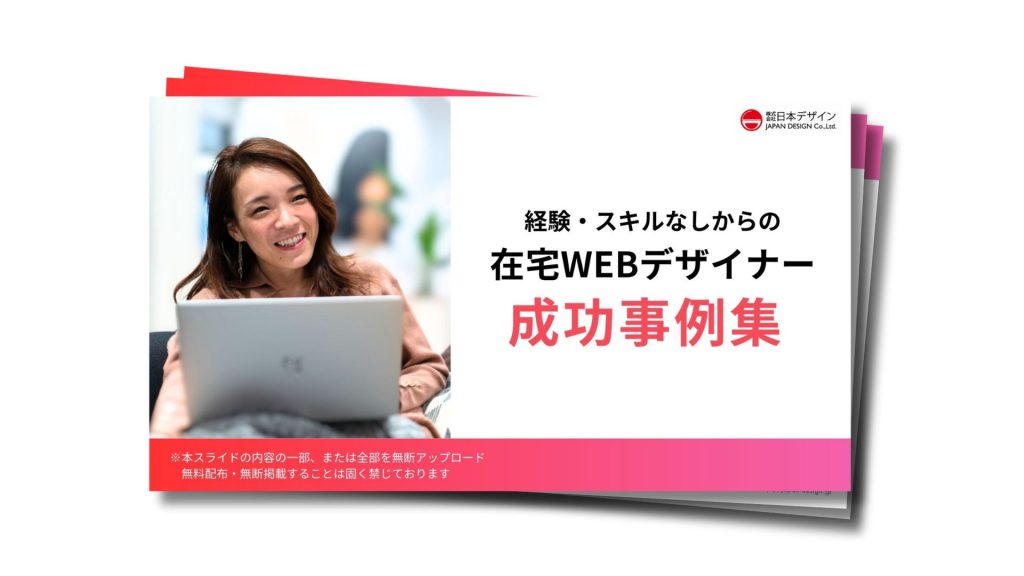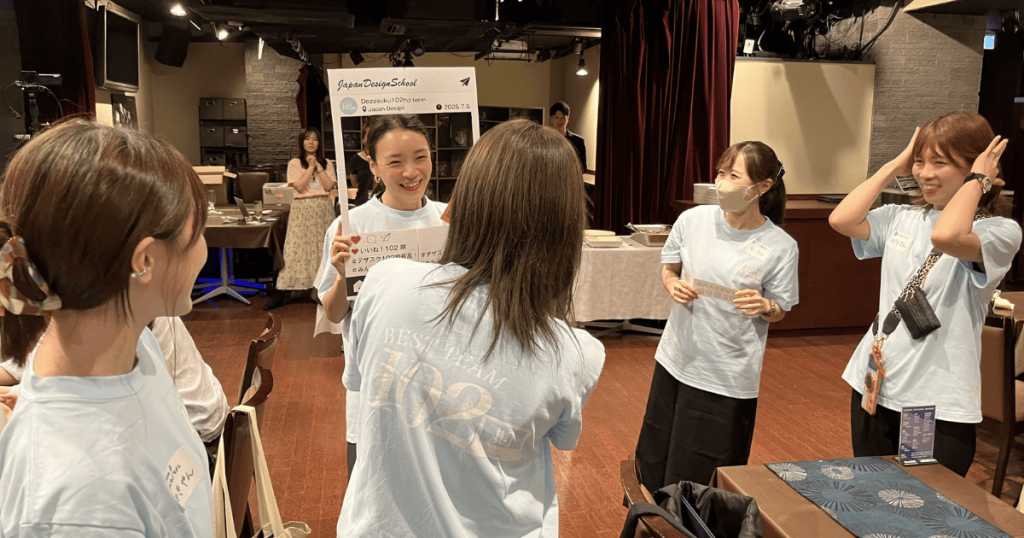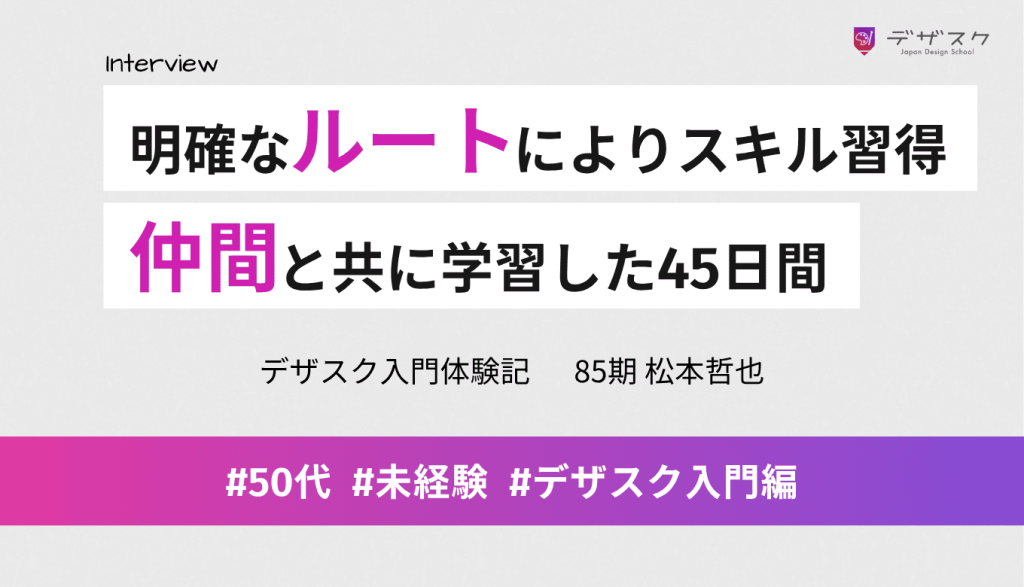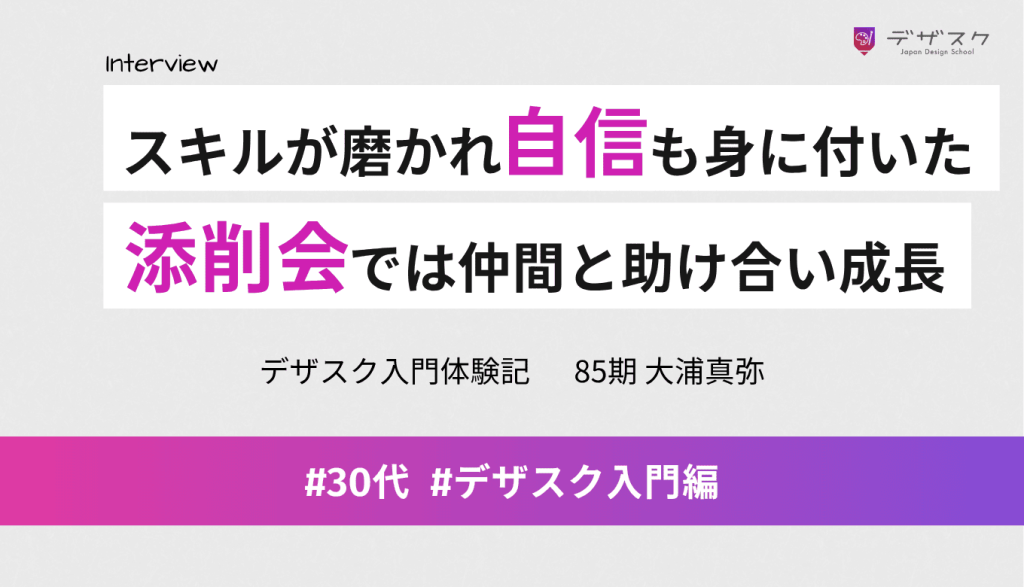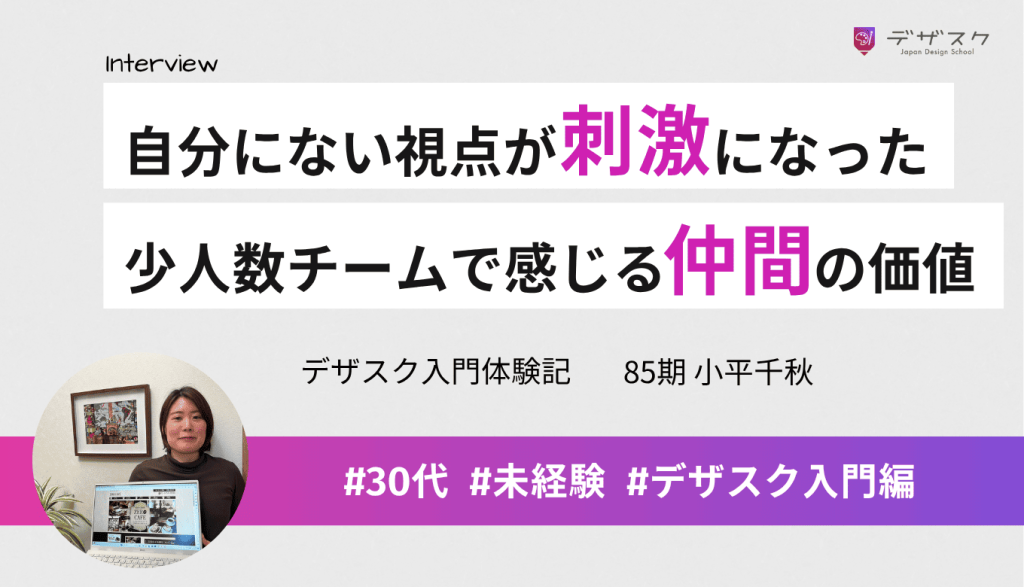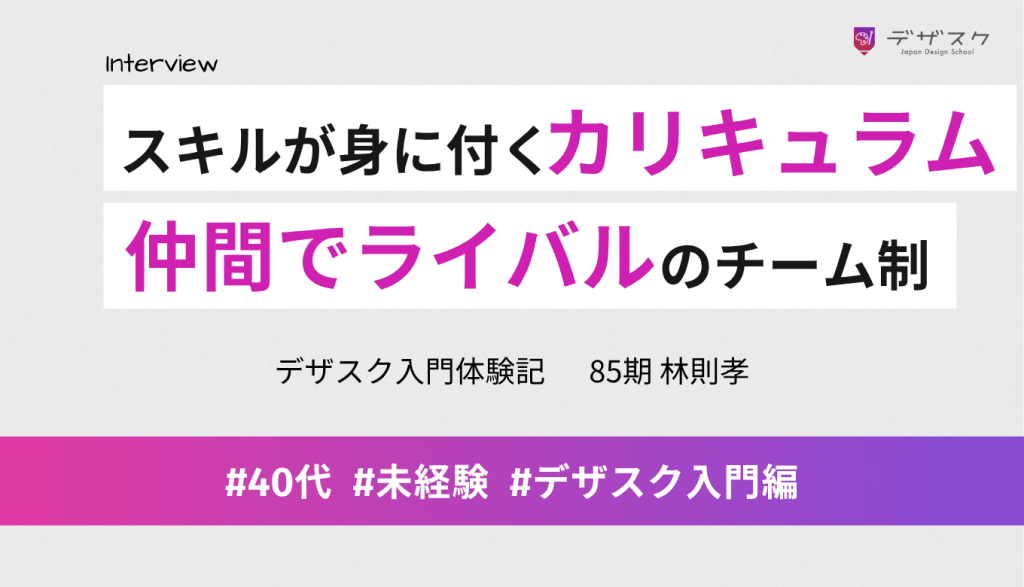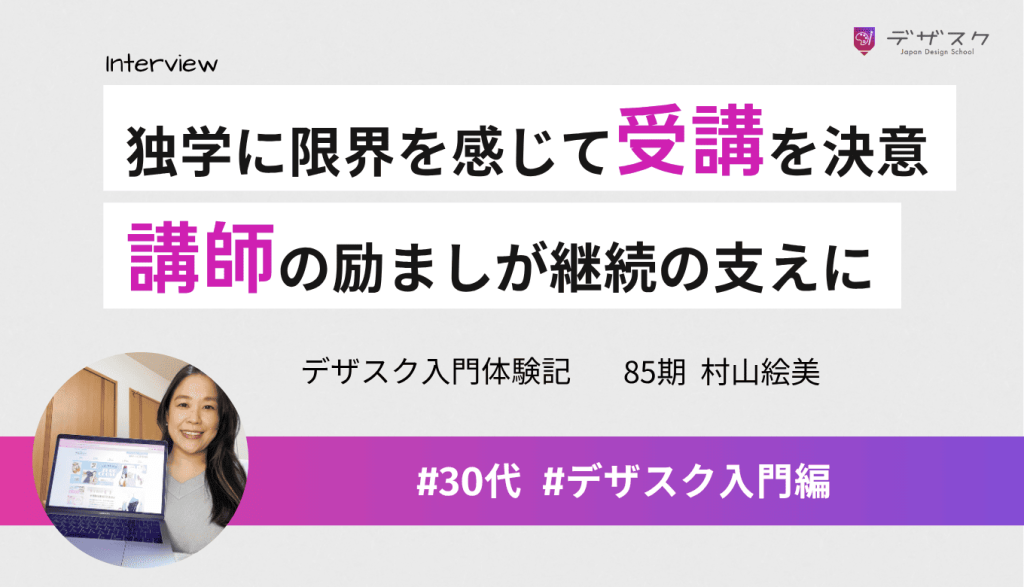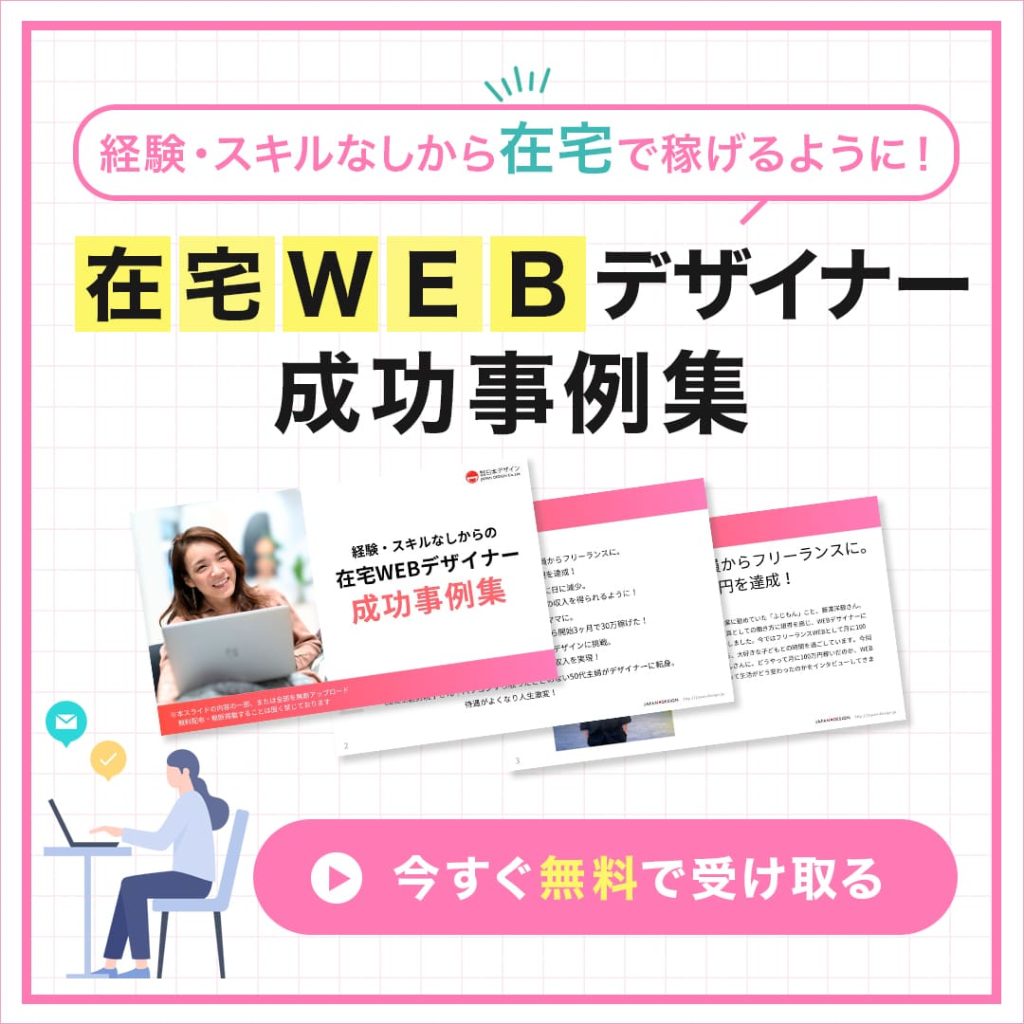「フリーランス」と「個人事業主」はどちらも会社に属さず働くイメージがありますが、「2つの働き方って実際に何が違うの?」と感じている方もいるのではないでしょうか。
特に、これから独立を考えている方にとっては、税金や手続きなど、具体的な違いが気になるところですよね。
子育てと両立しながら在宅WEBライターとして働く私も、まさに同じ疑問を持っていました。
私の場合、WEBライターとして働き始めた当初はフリーランスという形で活動していましたが、報酬が増え始めた段階で開業届を提出し、個人事業主となりました。
その経験を踏まえて、本記事では「フリーランス」と「個人事業主」の違いをわかりやすく解説するとともに、どちらで働く方が節税や手続き面で有利なのかを実体験を交えながらお伝えしたいと思います。
また、本記事では以下のような内容もご紹介していきます。
- フリーランスが個人事業主として開業する方法
- 開業届を提出する「メリット」と「デメリット」を体験談から解説
- 覚えておきたい4種類の税金
- 活用できる4種類の補助金や助成金
- 検討したい3種類の年金対策
「フリーランスと個人事業主、どちらで働くのが自分にとってベストなのか知りたい」「税金や社会保険についての不安を解消したい」という方は、ぜひ最後までお読みください。
【お知らせ】
3,500名以上の人生を変えるキッカケになった「好きなことで生きていく!WEBデザイナーという働き方セミナー」では、
などをお伝えしています。今だけ無料で開催しているので「WEBデザインの学び方がわからない」「WEBデザイン業界について知りたい」という方はぜひご参加ください。
>>詳しくはこちら
フリーランスと個人事業主の違いとは?

これから独立して働こうと考えている方は、「フリーランス」と「個人事業主」、どちらの働き方を選ぶべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
「フリーランス」と「個人事業主」は混同されることが多い言葉ですが、実際は法律的な定義や扱いに違いがあります。
ここでは、それぞれの特徴や違いについてわかりやすく解説していきます。
大きな違いは法律上の定義か否か
「フリーランス」と「個人事業主」はそもそもジャンルの違う言葉です。
フリーランスは「特定の企業に属さずに、個人で仕事を受注する」といった働き方を指す一方で、個人事業主は「開業届を出し、個人で事業を営む人」を指す税法上の定義を指す言葉です。
つまり、フリーランスとして働いている人でも、税務署に開業届を提出することで個人事業主になることができます。
ここで、フリーランスと個人事業主それぞれの特徴を整理しておきましょう。
| フリーランス | 個人事業主 | |
| 必要な手続き | なし | 開業届を税務署に提出 |
| 納める税金 | ・所得税 ・住民税 | ・所得税 ・住民税 ・個人事業税 |
フリーランスは働き方を指す言葉で、個人事業主はその働き方に法的な位置づけが加わったものと考えると、イメージしやすいと思います。
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人は、どちらも事業を行う形態ですが、法的な位置づけや税金、責任範囲などに違いがあります。
それぞれの特徴を、表で確認してみましょう。
| 個人事業主 | 法人 | |
| 法的な位置づけ | 税法上の定義 | 法律上の組織 |
| 事業形態 | 個人事業主 | ・株式会社 ・合同会社など |
| 設立手続き | 税務署への開業届の提出 (無料) | 法務局での設立登記 (登録免許税15万円~、設立費用がかかる) |
| 税金の仕組み | 累進課税 (所得が多いほど税率が高くなる) | 税率は一定だが赤字でも税金 (均等割)が発生する |
| 責任範囲 | 事業主本人が無限責任を負う | 会社の資本金の範囲内で有限責任 |
| 社会的信用 | 法人に比べて低い傾向あり | 法人であること自体が信用力の証明となる場合が多い |
| 利益分配 | 所得はすべて事業主のものとして扱われる | 経費や役員報酬を計上後の利益を株主に分配 |
| 節税の可能性 | 一部の経費を計上可能 | 節税方法が多岐にわたる (経費計上、役員報酬設定、退職金制度など) |
こうして見比べてみると、「手続きが煩雑な法人化にメリットはあるの?」と疑問に思う方もいることでしょう。ここで、年間収入500万円、経費100万円で事業を行った場合、個人事業主と法人での税負担を比較してみます。
| 個人事業主 | 法人 | |
| 収入 | 500万円 | 500万円 |
| 経費 | 100万円 | 100万円 |
| 課税所得 | 400万円(500万円-100万円) | 400万円(500万円-100万円) |
| 税率 | 約20%(超過累進課税) | 約15%(法人税) |
| 所得税額 | 80万円 | 60万円 |
| 手取り収入 | 収入500万円-経費100万円-所得税80万円=320万円 | 収入500万円-経費100万円-所得税60万円=340万円 |
個人事業主は、超過累進税の影響で、所得が高くなると税率が上がるため税負担が重くなります。
一方で法人は、一定の税率で計算されるため、所得が多い場合には法人の方が税負担が軽くなる傾向があります。
このように、個人事業主と法人にはそれぞれメリットとデメリットがあり、事業規模や将来の計画に応じて選択するのが重要なのです。まずは個人事業主から始めて、収入が安定した段階で法人化を検討するケースが一般的です。
フリーランス・個人事業主と混同されやすい働き方

フリーランスや個人事業主という働き方が注目される一方で、「自営業」「業務委託」「ノマドワーカー」といった似たような働き方も多く、具体的な違いがわかりづらいと感じる方も多いのではないでしょうか。
これらの働き方は、それぞれ似た点もありますが、法律上の定義や仕事の進め方には違いがあります。
ここでは、フリーランスや個人事業主と混同されやすい働き方について、それぞれの特徴と違いをわかりやすく整理していきたいと思います。
①自営業
自営業は、一般的に「自分で事業を営むこと」を指します。個人でお店を経営したり、職人として独立するなど、その形態は多岐にわたります。
自営業者の中には、個人事業主として税務署に開業届を提出している人もいれば、法人を設立し、従業員を雇っている人も含まれます。そのため、「個人事業主=自営業」ではありません。
たとえば、カフェを経営するオーナーは自営業ですが、法人を設立していれば個人事業主ではありません。一方で、法人化していないカフェオーナーは個人事業主に該当します。
このように、自営業は働き方というより、事業形態全般を示す概念として使われるのが特徴です。つまり、個人事業主も自営業の一種と考えることができます。
②業務委託
業務委託は、働き方ではなく、業務を外部に依頼するための契約形態を指します。フリーランスや個人事業主は、この業務委託契約を結ぶことが一般的ですが、雇用形態そのものとは異なります。
業務委託契約には大きく分けて3つの種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 契約形態 | 内容 | 具体例 |
| 請負契約 | 成果物の納品に対して報酬が支払われる契約 | ・記事執筆 ・デザイン制作 ・システム開発 ・建設工事など |
| 委任契約 | 法律行為を伴う業務に対する契約 | ・弁護士 ・税理士 ・司法書士など |
| 準委任契約 | 法律行為を伴わない業務に対する契約 | ・コンサルティング業務 ・医師の診察など |
フリーランスや個人事業主は業務委託契約の中で仕事を受注することが多いですが、業務委託そのものは契約方法であり、フリーランスや個人事業主とは概念が異なると覚えておきましょう。
たとえば、会社員であっても副業として業務委託契約を結ぶケースがあります。
③ノマドワーカー
ノマド(nomad)とは元々「遊牧民」を意味する英語で、現代では「自由な働き方」を象徴する言葉として使われています。
この働き方の特徴は、カフェやコワーキングスペース、自宅など、場所にとらわれず仕事をする点にあります。ノマドワーカーはフリーランスのイメージが強いですが、会社員でもリモートワークを活用して働く場合、ノマドワーカーと呼ばれることがあります。
重要なのは、「ノマドワーカー」という言葉が雇用形態を指しているわけではないことです。
フリーランスや個人事業主であっても、オフィスに通っている場合はノマドワーカーとは言えません。一方、会社に属していても、場所を問わず働ける環境であればノマドワーカーとして認識されます。
フリーランスが個人事業主として開業するための3ステップ

開業届の手続きはとってもカンタン!
個人事業主に切り替えようか検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね。
Step1.開業届の書類を入手する
まずは、開業届の書類を入手しましょう。
開業届は最寄りの税務署で受け取ることもできますし、国税庁のホームページからダウンロードしてもよいです。
Step2.必要事項を入力し、必要な書類を準備する
開業日、屋号、マイナンバー、事業内容などに必要事項を入力して作成しましょう。
個人事業主に切り替えるには開業届の他に、例えば顔写真付きのマイナンバーカードが必要になります。
あるいは顔写真入りの本人確認書類と、個人番号の通知書でも大丈夫です。
その他に必要なものは、提出する方法によって異なるのでこのあと説明しますね。
Step3.開業届を提出する
開業届を提出するには、次の3つの方法があります。
- 税務署の窓口に持参
- 郵送
- インターネット(e-Tax)
1つずつ説明していきます。
税務署の窓口に持参
税務署の窓口に直接持って行く方法です。
窓口に持参すれば、記入漏れなどがあってもその場で直せますし、わからないことがあったらすぐに相談することもできます。
「これで合っているかわからない…」と不安を抱えている方は、直接税務署に持参するのをおすすめします。
ただ、税務署の開庁時間は平日の8時30分から17時までとなっているので、平日忙しい場合は難しいかもしれません。
開業届を提出するときには、基本的に次の3つが必要です。
- 開業届・印鑑
- 個人番号がわかるもの
- 本人確認書類
郵送
税務署宛に郵送する方法です。
郵送を利用すれば、わざわざ税務署まで行かずに済みます。
郵便で送る以外に、税務署の時間外収受箱に自分で投函する方法もあります。
手間がかからないので忙しい方におすすめですが、ミスがあればやり直しになってしまうことがあります。
書類漏れや書き間違いがないかよく確認してから送りましょう。
郵送するものは次のとおりです。
- 開業届(個人事業の開業・廃業届出書)
- 開業届の控え
- 返信用封筒・返信用切手
- 個人番号がわかるもの
- 本人確認書類
- 青色申告承認申請書
開業届を郵送する際には、本人確認書類の写しなど個人情報が記載されている重要なものも同封します。
そのため、郵便物が間違いなく税務署に届いたかどうかも確認できた方が確実ですので、簡易書留・レターパックなど追跡可能な方法で送りましょう。
開業届を郵送する宛先は、自分が納税している税務署です。
個人事業主の場合、納税地は原則自宅の住所地になります。
税務署の住所は、国税庁のホームページで調べられます。
インターネット(e-Tax)
国税庁のオンラインサービスであるe-Taxにより、インターネットで税務署に申請する方法です。
e-Taxを利用すれば、家にいながらでも開業届を出すことができます。
ただ、事前準備が少し面倒というデメリットがあります。
e-Taxで開業届を提出する場合、パソコンとインターネット環境、ICカードリーダライタ、マイナンバーカードが必要です。
さらに、次のような事前準備をしなければなりません。
利用者識別番号の取得
e-Taxを利用するためには、利用者識別番号と呼ばれる16桁のID番号を取得する必要があります。e-Taxのホームページから開始届出書を作成・送信すれば、利用者識別番号を取得できます。
電子証明書の取得
インターネットを通じて申請をする場合、送信時に本人であることを証明しなければなりません。このために用いられるものが電子証明書です。電子証明書は電子的に本人であることを証明するもので、印鑑証明書と同じ意味のもの。電子証明書はマイナンバーカードに格納されているので、通常はマイナンバーカードを使います。
e-Taxソフトのインストール
e-Taxで開業届を提出するためには、e-Taxソフトが必要になります。e-Taxのホームページの「各ソフト・コーナー」からe-Taxソフトをダウンロードし、インストールします。e-Taxソフトを立ち上げ、申請・申告等一覧の中から、「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択し、必要事項を入力します。
入力が完了したら、ICカードリーダライタをパソコンに接続してマイナンバーカードをセットし、電子署名を付与して送信します。
青色申告をする場合には、同様に「所得税の青色申告承認申請書」も入力・送信してください。これで開業届の提出が完了です。
補足:会社員を辞めて個人事業主になる場合は健康保険と年金の手続きが必要
会社員を辞めて個人事業主になる場合は、「社会保険」を「国民健康保険」に、「厚生年金」を「国民年金」に変更する手続きが必要になります。
放置すると無保険状態になったり、将来の年金額が減少する可能性があるため、速やかに対応しましょう。
必要な手続きについて表にまとめましたので、参考にしてみてください。
| 【1】社会保険→国民健康保険への変更手続き |
| 会社員時代の健康保険は退職とともに失効するため、市区町村の役所で国民健康保険に加入する必要があります。保険料は前年の所得に基づき計算され、収入が増えると負担も増加します。 ただし、退職後の健康保険を一定期間継続できる「任意継続被保険者制度」を選ぶことも可能です。この制度では、退職前と同じ保険を最長2年間利用できます。 ▶参考資料:日本年金機構|国民健康保険等へ切り替えるときの手続き |
| 【2】厚生年金→国民年金への変更手続き |
| 最寄りの年金事務所で、国民年金への加入手続きを行います。国民年金保険料は、誰でも一律月額16,980円(2024年12月現在)です。 ただし、所得が低い場合は保険料の減免や猶予制度を申請できます。また、将来的な年金額を確保したい場合は、付加保険料(月額400円)を上乗せして支払うことも検討しましょう。 ▶参考資料:日本年金機構|国民年金保険料 |
| 手続きのタイミング |
| 健康保険や年金の切り替えは、退職後14日以内に行う必要があります。 期限を過ぎるとペナルティやリスクが生じる可能性があるため、なるべく早めに手続きを進めましょう。 |
| 注意点 |
| ①健康保険料や国民年金保険料は、会社員時代に会社が負担していた部分も全額自己負担となります。そのため、独立前に月々の支出額をシミュレーションしておくことが重要です。 ②配偶者や子供がいる場合は、扶養に関する手続きも必要になります。 |
手続きの内容は、住んでいる地域や個人の状況によって異なるため、必ず事前に市区町村役場や年金事務所に問い合わせて、詳しい情報を確認するようにしましょう。
筆者が感じたフリーランスが個人事業主として開業する3つのメリット

現在は在宅WEBライターとして活動している私ですが、フリーランスとして働く中で、「開業届」を提出して個人事業主になることで得られるメリットは大きいと感じました。
私自身、開業届を出すまでは気づかなかった利点がいくつもあり、収入や仕事の安定性に良い影響を与えています。
ここからは、実際にフリーランスから個人事業主として開業した経験のある私が、メリットだと感じた4つのポイントをお伝えしていきたいと思います。
メリット1:誰でも無料かつ簡単に開業できる
個人事業主としての開業は、非常に簡単です。
開業届は税務署に無料で提出でき、特別な資格や条件は必要ありません。私は、フリーランスとして活動する中で、徐々に仕事が増え始めたタイミングで開業届を提出しました。
税務署のホームページから開業届をダウンロードし、基本的な個人情報と事業の概要を記載して、先述したステップの通りに税務署へ提出するだけです。
特に厳しい審査などもなく、窓口とe-taxで提出した場合はその場ですぐに受理されます。郵送の場合のみ、受理されるまでに1週間程度かかるようです。
提出後はすぐに個人事業主として活動を始められるため、スタートのハードルが低い点も、初心者にとっては助かりました。
個人事業主への開業には初期費用がかからないため、私のように収入が少ないフリーランスでも気軽に手続きできます。
メリット2:経費を計上できる
経費を計上できるようになるのは、個人事業主として開業届を提出する大きなメリットのひとつです。
経費が認められることで税負担が軽減されるため、特に収入が増えてきたタイミングでは、開業届を出すメリットが大きくなります。
たとえば、Aさんがフリーランスとして、年間収入300万円で仕事をしているとします。経費として、以下のような支出をしている場合を考えてみましょう。
- インターネット代:月額7,000円
- オンラインツール代:月額1万円
- オンラインサロン会費:月額1万円
- 書籍代:年間5万円
| フリーランス(開業届未提出) | 個人事業主(開業届提出済) | |
| 年間収入 | 300万円 | 300万円 |
| 経費 | 0円(認められない) | 37万4,000円 (2万7,000円×12ヶ月+5万円) |
| 所得 | 300万円 | 262万6,000円 |
| 所得税(概算) | 20万2,500円/年 (300万円×税率10%-控除額9万7,500円) | 16万5,100円/年 (262万6,000円×税率10%-控除額9万7,500円) |
※所得税はあくまでも概算であり、厚生労働省の公式ホームページ「所得税の税率」を参考に算出しました。
フリーランスとして働いていても、開業届を提出していない場合、税務上は「雑所得」として扱われます。この場合、仕事に使ったインターネット料金や勉強用の書籍代などの経費が認められず、報酬全額が所得と見なされてしまいます。
つまりAさんの場合、所得税だけを見ても、開業届を提出することで約3万7,400円の節税になるということです。さらに、所得が少なくなると、所得税や住民税が軽減されるだけでなく、国民健康保険料の負担も減る可能性があります。
開業届を出すのは簡単な手続きですが、その後の節税効果は大きなものになります。
私自身も、収入が安定してきたタイミングで開業届を提出し、経費精算や節税のメリットを実感しました。フリーランスの働き方が長期化しそうな場合は、早めに開業届を提出することをおすすめします。
メリット3:節税効果が大きい「青色申告」を選択できる
開業届を提出し、青色申告を選択することで、さらに大きな節税効果を得られます。
青色申告では、最大65万円の控除が受けられるほか、赤字が発生した場合に翌年以降に繰り越すことも可能です。私も初年度は収入が少なく、経費が多かったため、この制度の恩恵を受けられました。
青色申告のためには、会計ソフトを利用して帳簿を作成する必要がありますが、私は簡単なクラウド会計ソフトを使い、1日数分の作業で済ませています。
このように、少しの手間で大きな節税効果が得られる青色申告は、仕事の波があるフリーランスにとっては非常に助かる制度です。
青色申告による優遇を受ける際には、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出しましょう。
青色申告については、以下の記事でも詳しく解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてくださいね。
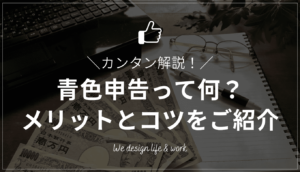
メリット4:社会的信用を得られやすい
個人事業主になると、仕事における信頼性が向上するだけでなく、事業管理や資金面でのメリットも得られます。
開業届を提出すると「屋号」を持てるため、請求書や名刺に記載することで、よりプロフェッショナルな印象を与えることができます。私のような在宅ワーカーでも、こうした小さな工夫で仕事の幅を広げられるのは嬉しいポイントです。
さらに、事業専用(屋号名義)の銀行口座を開設することで、プライベートの資金と事業資金を明確に分けられるようになり、お金の流れが把握しやすくなります。
加えて、補助金や助成金、さらには融資を受ける際にも「個人事業主」としての立場が社会的信用を高めてくれます。
プライベートと事業を明確に分け、資金管理や信頼性の向上を図れるのは、個人事業主として活動する大きなメリットです。
筆者が苦労した個人事業主として開業する3つのデメリット

個人事業主として開業することには多くのメリットがありますが、その一方でいくつかのデメリットも存在します。
ここからは、私が実際に経験した苦労をもとに、個人事業主が特に注意すべき3つのデメリットを紹介します。
これから開業を考えている方は、こうした点もしっかりと理解し、対策を練ることが大切です。
デメリット1:自分で確定申告をしなければならない
私が個人事業主をしていて感じた大きなデメリットは、確定申告などの手続きを自分自身で行わなければならないことです。
確定申告とは、1年間の所得を計算し、国に納めるべき税金を申告する手続きです。会社員であれば会社が代わりに手続きをしてくれますが、フリーランスや個人事業主は自分で行う必要があります。
この手続きを大きな負担に感じる個人事業主も多いことでしょう。
私も、開業した当初は所得の計算がとても複雑に思えて、「どこまでが経費として認められるか」を調べることに時間がかかりました。
例えば、光熱費の事業分割合やパソコンの減価償却費用など、細かい部分で迷うことが多く、税制に関する知識が足りなかったと痛感しています。
確定申告は大変ですが、きちんと管理していけば納税額を減らすための節税対策になるため、個人事業主として活動を続けるのであれば必ず覚えておきたい部分です。
確定申告の具体的な方法については、以下の記事からご確認いただけます。
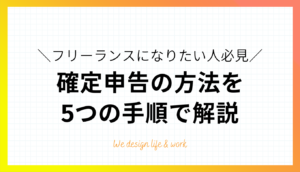
デメリット2:個人事業主税の支払い義務が生まれる可能性がある
個人事業主として開業すると、所得に応じて「個人事業税」の支払い義務が生じる可能性があります。
これは、フリーランスとして働いているだけでは発生しない税金のため、開業を検討する上で知っておくべき重要なポイントです。
個人事業税は、都道府県が課税する地方税です。すべての事業に課税されるわけではなく、地方税法で定められた法定業種(詳しくは後述します)に該当する場合にのみ、課税対象となります。
個人事業税の計算方法は、以下の通りです。
| (事業所得-事業主控除290万円)×税率=個人事業税※事業所得とは(収入-必要経費) |
税率は業種によって異なりますが、一般的には3%~5%です。たとえば、所得が500万円で税率が5%の業種の場合は、以下のように計算します。
| (500万円-290万円)×5%=10万5,000円 |
つまりこの場合、10万5,000円の個人事業税を納めることになります。特に、開業した当初や収入が290万円を超えたばかりの頃は、この個人事業税を予期せぬ負担に感じることもあるでしょう。
そのため、個人事業主として開業をする前に、業種ごとの税率や対象条件を確認し、計画的に所得を管理することが重要なのです。
デメリット3:扶養から外れる可能性がある
所得が一定額(主に年間130万円)を超えると、配偶者の扶養から外れるという点には注意が必要です。
この場合、個人事業主になること自体が直接の原因ではなく、開業せずにフリーランスとして働いていたとしても、所得が扶養の基準を超えれば扶養から外れることになります。
扶養から外れると、収入に応じて「所得税」「住民税」「国民健康保険料」「国民年金保険料」などを支払うことになります。これらの支払いが重なることで、働き損になる可能性もあるため、収入調整には常に気をつけなければなりません。
しかし、フリーランスや個人事業主でも配偶者の扶養範囲内で働けるケースがあります。
| 配偶者の扶養に入れるケース |
| 年間収入が130万円未満(月額108,333円以下)の場合は、配偶者の扶養に入ることができ、健康保険料や年金が免除されます。 ただし、加入条件は配偶者の所属する健康保険組合によって異なるため、注意が必要です。 |
| 扶養の加入条件の具体例|4パターン |
| ①経費を差し引いた後の所得が130万円以下であれば扶養が認められるケース ②会社に定められた経費のみ計上ができ、それを引いた後の所得が130万円以下であれば扶養が認められるケース ③総収入(経費計上前)が130万円を超えると扶養から外れなければならないケース ④そもそも個人事業主として開業届を出した段階で、扶養から外れなければならないケース どの規定が適応されるのかを、配偶者の勤務先に確認しておくことが大切です。 |
また、会社によっては、開業届を出したこと自体が扶養条件に影響を及ぼすケースもあります。たとえば、以下のような条件が付いているケースです。
- 所得に関わらず、開業届を出した時点で扶養から外れる
- 雇用されていないと扶養に入ることができない
このような条件が付きで扶養が認められている会社もあるため、開業届を出す前に配偶者の会社に確認することが大切です。
私自身、子供の行事や家庭の事情を考慮して働き方を調整しているため、いまも収入が130万円以下に収まるように工夫していますが、いずれは扶養から外れることも視野に入れています。
私のように家庭の事情で働き方に制限がある場合は、働き方や収入の計算方法が特に難しい点となります。
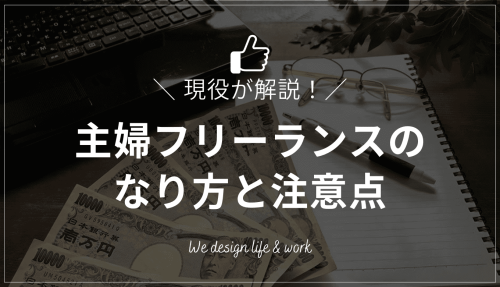
個人事業主が納める必要のある税金4種類
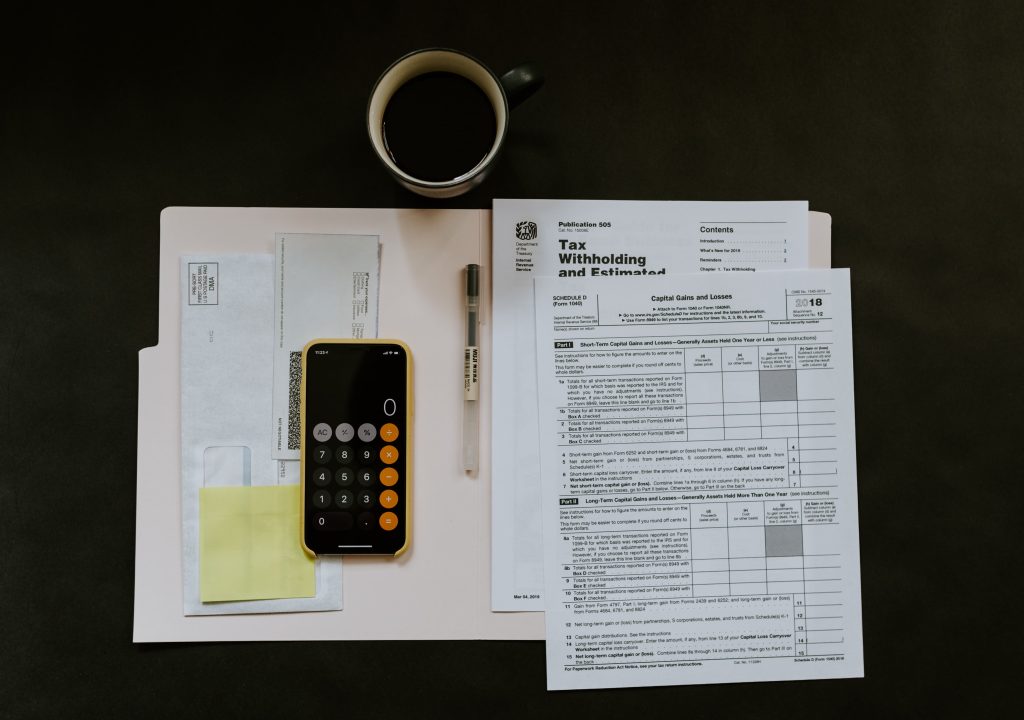
社会人には、収入に応じた税金を正しく支払う義務があります。
フリーランスや個人事業主は、会社員とは異なり、自分自身で確定申告をして税金を納める必要があるため、税金の知識は欠かせません。
フリーランスや個人事業主が納める必要のある主要な税金は、以下の4種類です。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
ここからは、これらの税金について、わかりやすく解説していきます。
税金のことをよく分からずに放置してしまうと、後で多額の税金を請求されたり、ペナルティを課される可能性もあるため、個人事業主になるならしっかり覚えておきましょう。
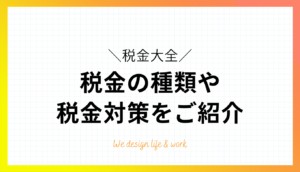
所得税
所得税とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課せられる国税です。つまり、稼いだお金から必要経費を差し引いた「儲け」に対してかかる税金のことを指します。
所得税の計算は少し複雑で、所得金額に応じて税率が上がる「超過累進課税」方式が採用されています。
累進課税の詳細な税率は、こちらの表でご確認ください。
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円~194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
(参考資料:国税庁|所得税の税率)
具体的な例を挙げると、年間の売上が500万円で、必要経費が200万円だった場合、所得は300万円になります。この300万円に対して所得税が課税されるわけです。
ただし、「所得控除」という制度があり、例えば配偶者控除や扶養控除、基礎控除などを活用することで、課税対象となる所得金額を減らすこともできます。
所得税の考え方
| 概要 |
| ・1年間の所得(儲け)に対して課せられる国税 ・税率は超過累進課税方式 ・所得控除を利用すれば、課税対象となる所得を減らせる |
| 計算方法 |
| (所得金額-所得控除)×税率(超過累進課税方式) |
| 課税対象 |
| 1月1日~12月31日までの所得 |
| 納税先 |
| 国 |
| 納税方法 |
| 確定申告(通常2月16日〜3月15日) |
| 納付時期 |
| 確定申告期間内 ※場合によっては予定納税(前年の所得に応じてあらかじめ一部を納付) |
住民税
住民税は、都道府県と市区町村に納める地方税です。
前年の所得に基づいて計算され、翌年に納付することになります。つまり、2024年の所得に対する住民税は、2025年に納付することになります。
住民税は以下の2つの要素で構成され、これらの合計を地方税として支払います。
- 所得割: 所得金額に応じて課税(所得に応じて税率変動)
- 均等割: 所得に関わらず一定金額を課税
例として、2024年度の東京都の住民税を見てみましょう。
| 所得割:都民税4%+区市町村民税6%=合計10%均等割:都民税1,000円+区市町村民税3,000円=合計4,000円 |
(参考資料:東京都|個人住民税)
住民税は、確定申告をしていれば、後日市区町村から納付書が送られてきます。
なお、住民税は自治体によって税率や金額が異なるため、お住まいの自治体の情報を確認してくださいね。
地方税の考え方
| 概要 |
| ・都道府県と市区町村に納める地方税 ・所得割と均等割がある ・前年の所得に基づき計算され、翌年に納付 |
| 計算方法 |
| ・所得割:所得金額×税率 ・均等割:自治体ごとに定められた一定額 |
| 課税対象 |
| 前年の所得 |
| 納税先 |
| 都道府県/市区町村 |
| 納税方法 |
| ・自治体から送付される納付書 ・口座振替 ・クレジットカード納付 ・スマートフォン決済アプリ ・金融機関等のペイジー対応のATM ・eLTAX(地方税ポータルシステム)など |
| 納付時期 |
| ・原則として6月、8月、10月、1月の年4回払い(自治体によって異なる場合あり) ・一括納付も可能 |
個人事業税
個人事業税は、特定の事業を営む個人に課される地方税です。
すべての事業者に課税されるわけではなく、法律で定められた業種(法定業種)に該当する場合にのみ課税されます。
2024年12月現在、課税対象となる事業は100業種ほどあり、個人事業税の税率はその業種によっても異なります。
課税対象となる業種
| 第1種事業(税率5%) |
| ・物品販売業 ・運送取扱業 ・料理店業 ・遊覧所業 ・保険業 ・船舶ていけい場業 ・飲食店業 ・商品取引業 ・金銭貸付業 ・倉庫業 ・周旋業 ・不動産売買業 ・物品貸付業 ・駐車場業 ・代理業 ・広告業 ・不動産貸付業 ・請負業 ・仲立業 ・興信所業 ・製造業 ・印刷業 ・問屋業 ・案内業 ・電気供給業 ・出版業 ・両替業 ・冠婚葬祭業 ・土石採取業 ・写真業 ・公衆浴場業(むし風呂等) ・電気通信事業 ・席貸業 ・演劇興行業 ・運送業 ・旅館業 ・遊技場業 |
| 第2種事業(税率4%) |
| ・畜産業 ・水産業 ・製造業 |
| 第3種事業(税率5%) |
| ・医業 ・公証人業 ・設計監督者業 ・公衆浴場業(銭湯) ・歯科医業 ・弁理士業 ・不動産鑑定業 ・歯科衛生士業 ・薬剤師業 ・税理士業 ・デザイン業 ・歯科技工士業 ・獣医業 ・公認会計士業 ・諸芸師匠業 ・測量士業 ・弁護士業 ・計理士業 ・理容業 ・土地家屋調査士業 ・司法書士業 ・社会保険労務士業 ・美容業 ・海事代理士業 ・行政書士業 ・コンサルタント業 ・クリーニング業 ・印刷製版業 |
| 第3種事業(税率3%) |
| ・あんま・マッサージまたは指圧 ・はり・きゅう ・柔道整復 ・その他の医業に類する事業 ・装蹄師業 |
(参考資料:東京都|個人事業税)
個人事業税は、年間の所得が290万円を超えた場合に課税されます。確定申告をしていれば、後日都道府県から納付書が送られてきます。
個人事業税の考え方
| 概要 |
| ・法定業種に該当する個人事業主に課される地方税 ・所得が290万円を超えた場合に課税 ・税率は業種によって異なる(3〜5%) |
| 計算方法 |
| (事業所得-各種控除)×業種ごとの税率(3%~5%) |
| 課税対象 |
| 一定の事業所得(法定業種に該当し、所得が290万円を超えた場合) |
| 納税先 |
| 都道府県 |
| 納税方法 |
| ・都道府県から送付される納付書 ・口座振替 ・クレジットカード納付 ・スマートフォン決済アプリ ・金融機関等のペイジー対応のATMなど |
| 納付時期 |
| 原則として8月と11月の年2回払い |
消費税
消費税は、商品やサービスの消費に対して課される国税で、消費者が負担し、事業者が納税する仕組みです。消費税の申告と納税は、確定申告とは別に行う必要があります。
フリーランスや個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。消費税の計算は、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引く「仕入税額控除」という方法で行います。
ここで重要なのが、2023年10月1日から導入された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」です。
インボイス制度のポイント
| 適格請求書(インボイス)とは |
| 従来の請求書に加えて、登録番号、適用税率、消費税額などの記載が追加された「適格請求書(インボイス)」という請求書を使って消費税の仕入税額控除を行う制度。 |
| 年収1,000万円以下のフリーランスや個人事業主への影響 |
| ・課税事業者: 原則、インボイスがないと仕入税額控除が受けられない。免税事業者からの仕入れは控除対象外となる(ただし、経過措置あり) ・免税事業者: インボイス発行ができないため、課税事業者との取引で不利になる可能性がある |
インボイス制度の導入により、所得に関わらず課税事業者になる(適格請求書発行事業者の登録を受ける)ことを検討する必要が出てきました。
特に、課税事業者と取引のある免税事業者は、今後の事業戦略を検討する必要があるでしょう。
消費税の考え方
| 概要 |
| ・商品やサービスの消費に対して課される国税 ・前々年の課税売上高が1,000万円を超えると納税義務が発生 ・インボイス発行事業者の登録を受けている場合は、1,000万円以下でも納税義務が発生 |
| 計算方法 |
| 売上にかかる消費税-仕入にかかる消費税(仕入税額控除) |
| 課税対象 |
| 商品やサービスの売上 |
| 納税先 |
| 国 |
| 納税方法 |
| 消費税の申告書を提出して納税 |
| 納付時期 |
| ・課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内 ・場合によっては中間申告が必要となる場合がある(前年の消費税額が48万円超の場合など) |
個人事業主が受けられる補助金・助成金

最後に、個人事業主が受けられる補助金・助成金を紹介します。
個人事業主はいかに資金を調達するのかが、事業を継続するためのカギになります。
個人事業主になろうと考えている方は、次のような補助金や助成金も検討してみるとよいでしょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、日本商工会議所や全国商工会連合会の支援を受けながら経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓に励むときに費用の3分の2まで(最大50万円)補助してもらえる制度のことです。
個人事業主を含む事業者が順調に販路を拡大しながら事業を維持・拡大するのを支援しています。
例年2月末に応募要項が発表され、募集期間はその年の政府予算の状況によって違いますが公募開始からおよそ2〜3ヵ月程度です。
詳しくは、日本商工会議所のホームページをチェックしてみてください。
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
革新的なものづくりやサービスにチャレンジする中小企業の研究開発や、人材育成などを支援する補助金です。
ほぼ毎年、募集期間内に中小企業庁が公募をおこなっています。
詳しい公募の期間や認定される事業については、中小企業庁の「経営サポート『ものづくり(サービス含む)中小企業支援』」のページをチェックしてみてください。
自治体による補助金
市町村の自治体が地域活性化などを目的に、ホームページ作成、展示会出展などの経費を補助する補助金などがあります。
例えば次のような補助金があります。
東京都・創業助成事業
東京都中小企業振興公社が一定の要件を満たす都内での創業予定者、または創業5年未満の中小事業者に対して、創業初期に必要な経費の一部を給付しています。
東京都・ホームページ作成支援
豊島区では、企業のPRや販路拡大を目的としたホームページ・ECサイトを、新規で作成する区内中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。
大阪府・大阪起業家グローイングアップ事業
大阪府でおこなわれるビジネスプランコンテストで受賞した有望な起業家に補助金を給付するもので、優勝者には補助金100万円、準優勝2名以内に50万円を支給しています。
各自治体によって応募要項や応募期間などが違いますので、自分の事業所所在地の自治体へ問い合わせてみるとよいでしょう。
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、「新型コロナウィルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
- 新型コロナウィルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1ヵ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
フリーランスや個人事業主が覚えておきたい年金対策

フリーランスや個人事業主は、厚生年金に加入している会社員とは異なり、国民年金のみに加入している状態です。
将来の年金受給額が会社員に比べて少なくなる可能性があるため、老後資金について準備しておく必要があります。
ここからは、フリーランスや個人事業主でも活用できる3つの年金対策について、わかりやすく解説していきます。
- 国民年金基金
- 小規模企業共済
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
これらの制度をうまく活用することで、将来の年金受給額を増やしたり、節税効果が得られるため、しっかり覚えておきましょう。
国民年金基金
国民年金基金は、国民年金に上乗せして加入できる公的な年金制度です。国民年金だけでは将来の年金受給額が不安という方にとって、上乗せの年金として活用できます。
国民年金基金の大きな特徴は、掛金が全額所得控除(所得税や住民税を計算する際に、所得から一定の金額を差し引くことができる制度)の対象となることです。掛金が全額控除されるため、節税効果が期待できます。
基本的には、月額で積み立てていく形で年金を増やすことが可能です。
国民年金基金の特徴
| メリット |
| 将来の年金額が増える 65歳以降、一生涯受け取れる 掛け金が全額所得控除対象となり、節税になる 掛け金は一定のため、月々の負担を調整しやすい 万一のとき、家族に一時金が支給される |
| デメリット |
| 一度加入すると、途中でやめられない(解約返戻金もない) インフレヘッジ(物価高騰によって日本円の価値が下落した際に受ける影響)ができない |
| おすすめの人 |
| 将来の年金受給額を増やしたい人 節税したい人 |
| 参考リンク |
| 全国国民年金基金の公式ホームページ 日本年金機構の公式ホームページ |
小規模企業共済
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための退職金制度です。毎月積み立てた掛金は、廃業時や退職時に共済金として受け取ることができます。
最大の特徴は、「掛金を拠出する時」と「受け取る時」の両方で税制優遇を受けられるという点です。
掛金は月額1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に選択できます。事業の状況に合わせて掛金を変更することも可能です。
小規模企業共済の特徴
| メリット |
| 退職金や事業終了時に備えることができる 掛け金が全額所得控除対象となり、節税になる 解約時は、納付月数に応じて掛金の最大120%が受け取れる 受け取り方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選択できる 一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が適用される |
| デメリット |
| 加入期間20年未満で解約すると、元本割れになる 共済金の受け取り時に所得税が課税される 掛金は必要経費として計上できない 掛金を途中で減額すると、元本割れのリスクがある |
| おすすめの人 |
| 将来の退職金準備をしたい人 節税したい人 所得が高い個人事業主、フリーランス、中小規模企業の経営者や役員 |
| 参考リンク |
| 独立行政法人 中小企業基盤整備機構の公式ホームページ 中小企業庁の公式ホームページ |
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、運用方法を選んで将来の年金として受け取る制度です。iDeCoは現在、つみたてNISAと並んで会社員の間でも利用者が増えています。
大きな特徴は、掛金・運用益・給付を受け取る際それぞれで税制優遇を受けられることです。また、運用方法を自分で選べるため、リスクをコントロールしながら積み立てていける点も大きな魅力と言えます。
以前は自営業者などが主な対象でしたが、2017年以降対象者が拡大され、多くの人が加入できるようになりました。しかし、誰でも加入できるわけではなく、いくつかの条件があります。
大きく分けると、以下の通りです。
| 被保険者種別 | 対象者 | 対象外 |
| 国民年金の第1号被保険者 | ・20歳以上60歳未満の自営業者とその家族 ・フリーランス ・学生 | ・農業者年金に加入している人 ・全額免除 ・半額免除等を受けていない人 (障害基礎年金受給者は受給可能) |
| 国民年金の第2号被保険者 | ・ 65歳未満の会社員 ・ 65歳未満の公務員 | ・企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入していて、iDeCoの掛金額+企業型DCの事業主掛金額=月額5.5万円を超える人 ※一部企業型DCの規約でiDeCoへの加入が制限されている場合がある |
| 国民年金の第3号被保険者 | ・第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(専業主婦など) | |
| 国民年金の任意加入被保険者 | 以下のいずれかの条件で、国民年金に任意で加入した人 ①60歳以上65歳未満の人 ②20歳以上65歳未満の海外居住者の人 ③国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない人 | ・65歳以上の人 ・国民年金保険料を納付していない人 ・国民年金保険料の免除 ・納付の猶予を受けている人 |
このように、iDeCoは多くの方が利用できる制度となっていますが、細かい条件もあるため、自分が加入対象であるかどうかをしっかり確認することが大切です。
詳しくは、iDeCoの公式サイトや金融機関の窓口などで確認することをおすすめします。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の特徴
| メリット |
| 掛け金が全額所得控除対象となり、節税になる 運用益(運用中に増えた利益)に税金がかからない 一度にまとめて受け取る場合は「退職所得控除」、分割で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用される 月5,000円から1,000円単位で設定可能 低コストで運用できるものが多い |
| デメリット |
| 60歳までは引き出すことができない 運用成績によっては元本割れのリスクもある 加入時と運用時に手数料がかかる |
| おすすめの人 |
| 個人事業主やフリーランス、小規模事業主 自分で運用しながら将来の年金準備をしたい人 税制優遇を最大限に活用したい人 公的年金や退職金の受取額が少ない人 退職金制度がない会社員 |
| 参考リンク |
| iDeCoの公式ホームページ 厚生労働省の公式ホームページ |
フリーランスや個人事業主の年金について詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。
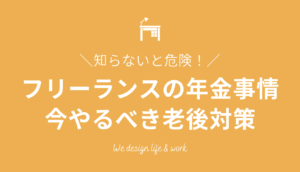
まとめ

本記事では、フリーランスと個人事業主の違いについて、私の実体験を交えながら詳しく解説してきました。
「フリーランス」は特定の企業に雇用されずに仕事をする働き方を指し、「個人事業主」は税務署に開業届を提出して事業を営む個人を指します。つまり、フリーランスとして働いている人が開業届を提出すれば、その人は個人事業主にも該当します。
その違いを理解することで、自分にとって最適な働き方や、適切な節税対策が見えてくるはずです。
改めて、この記事でお伝えした重要なポイントをまとめてみました。
- 開業届を出すかどうかは、個々の状況によって判断する必要がある
- 開業届の提出は節税や社会的信用の向上につながる
- 個人事業主になると確定申告が必要になる
- フリーランスで働く方も、将来的に個人事業主として開業する選択肢を視野に入れることができる
私がWEBライターとして独立してからの道のりを振り返ると、フリーランスとして活動していた時期も、個人事業主として活動している現在も、それぞれにメリットとデメリットがありました。
特に、個人事業主として開業してからは、経費計上による節税効果を実感することができ、事業を継続していく上で大きな支えとなっています。
どちらの働き方が良いということは一概には言えません。大切なのは、それぞれの特徴を理解し、自身の状況や目的に合った働き方を選ぶことです。
この記事を通して、これから独立を考えている方、フリーランスとして活動している方にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。もし、将来的に事業を拡大し、法人化を検討することになったとしても、個人事業主としての経験が必ず役に立つでしょう。