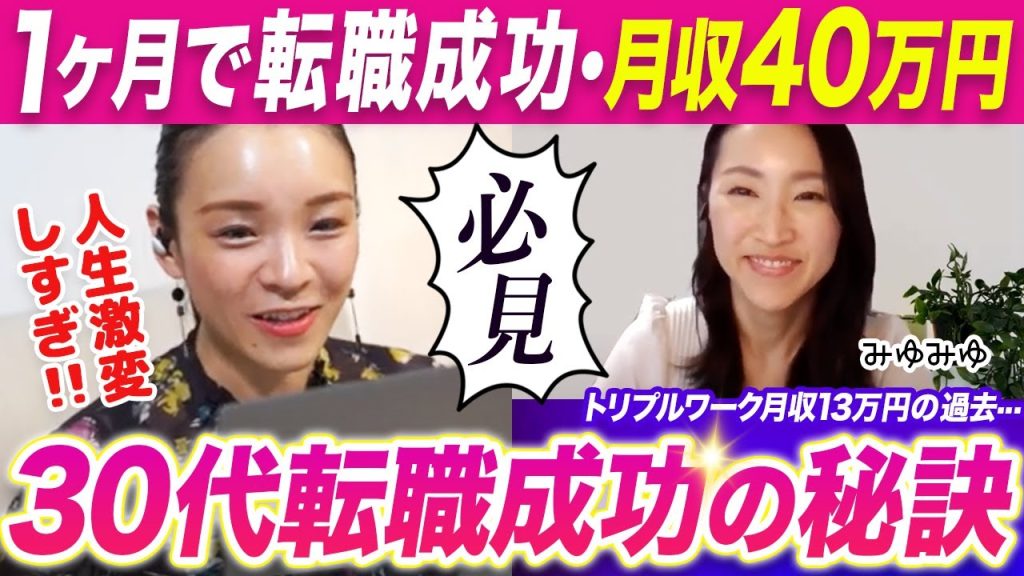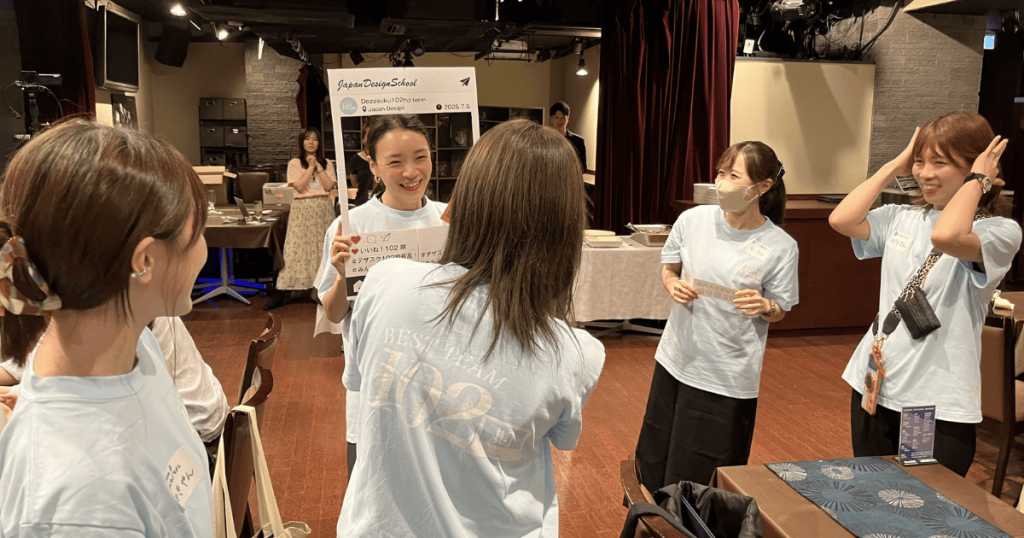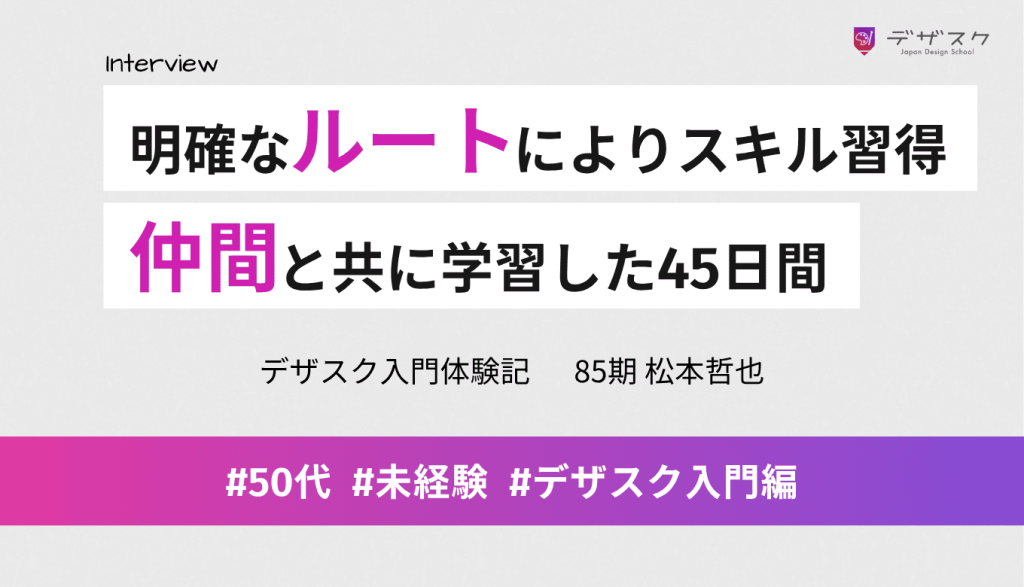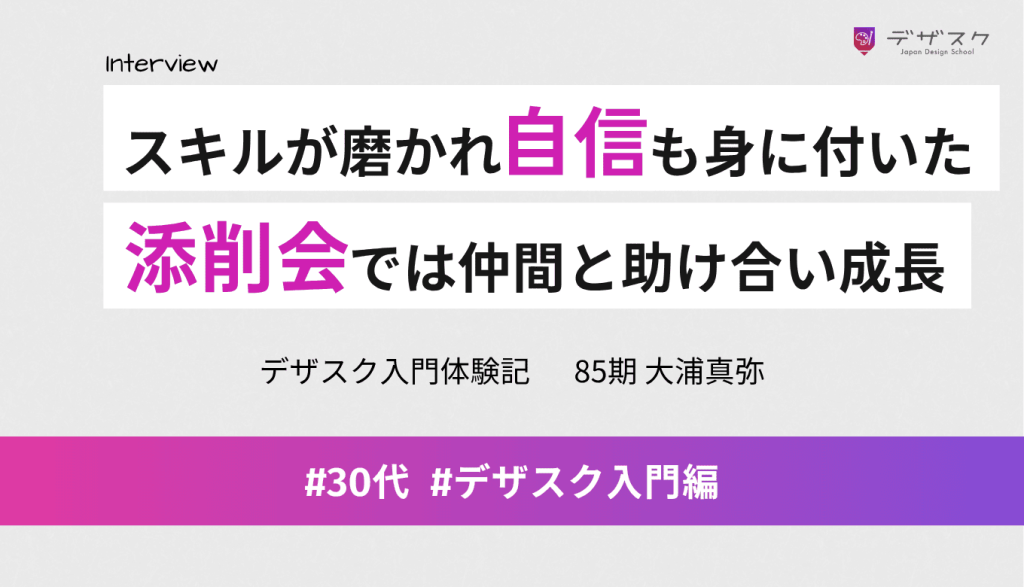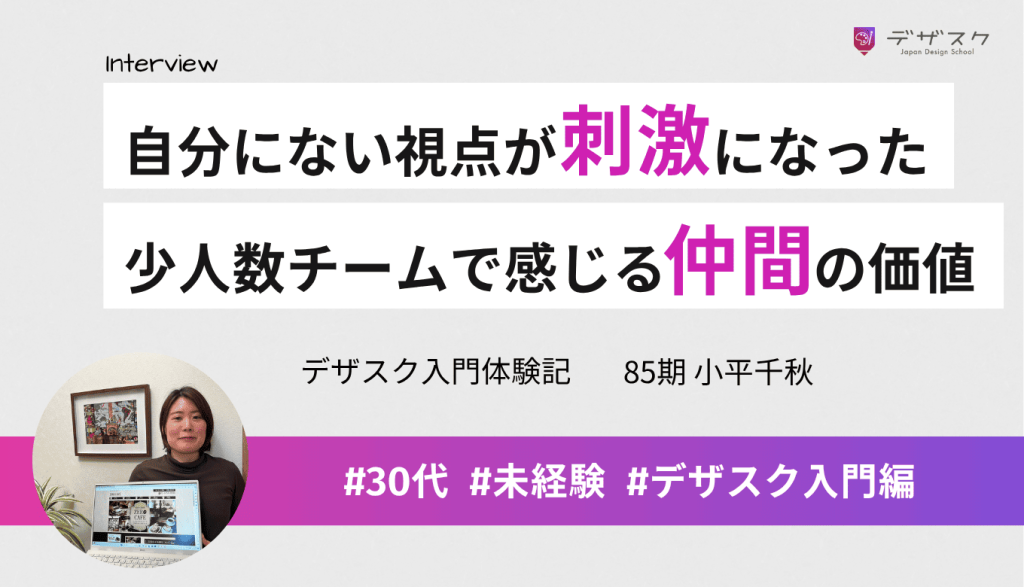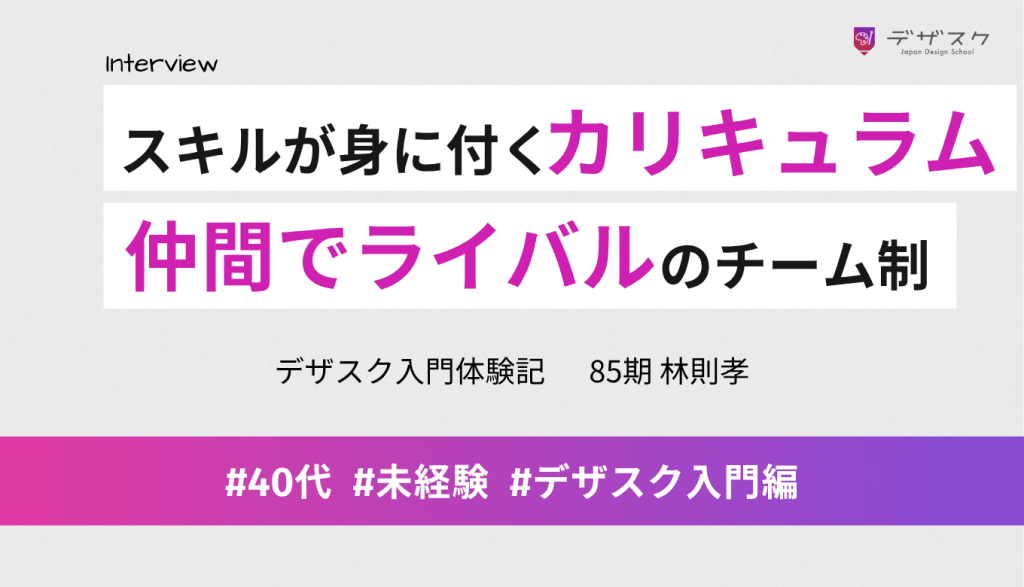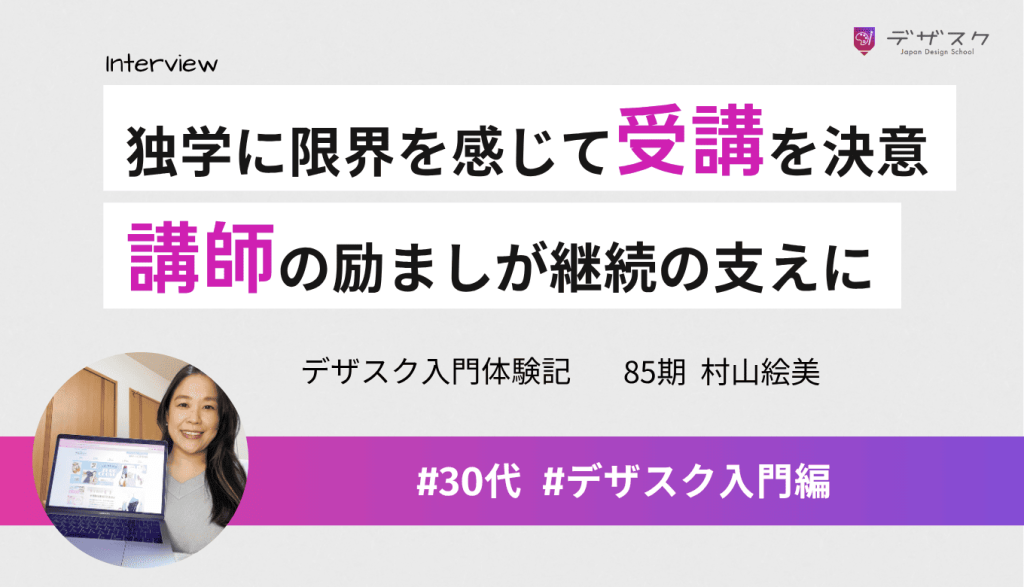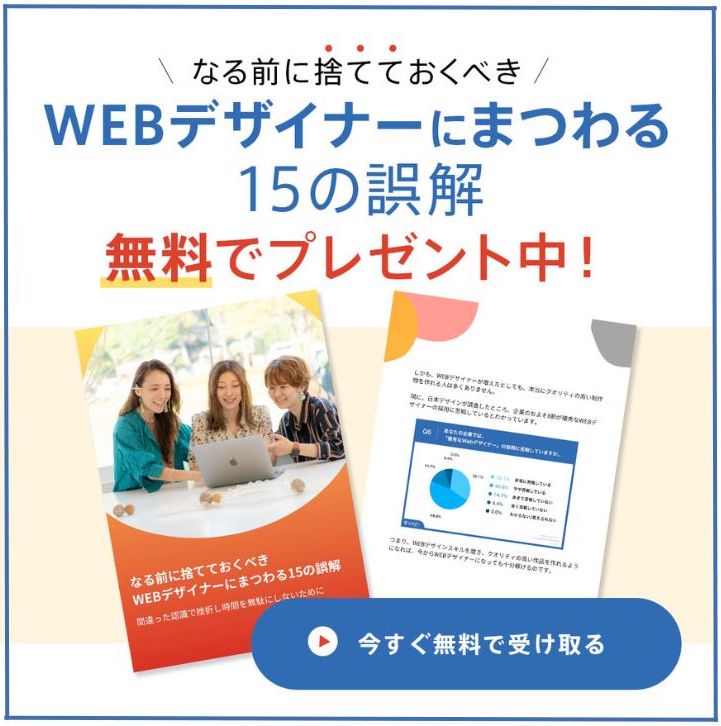デザインというと、つい写真やイラストなどのグラフィックに目が行きがちですが、情報を伝える上で欠かせないのは、文字ですよね。
文字は単に情報伝達の道具であるだけでなく、古くからそのときどきの時代や場面の雰囲気に合わせて、一定の法則で装飾されて使われてきました。
たとえば、太く真っ直ぐな文字は力強く、大胆、男性的なイメージ。
細くて曲線的なフォルムの文字は、優しく洗練された、女性的なイメージ、というように。
このようなイメージや雰囲気、ニュアンスを伝える文字のかたちを「書体」と呼びます。
そして、同じ書体で統一性を持ってデザインされた、アルファベットなどの文字のグループを「フォント」と呼んでいます。
つまり、日本語の場合はひらがな、カタカナ、漢字が全てそろった書体グループがフォントになりますね。
デザインにおいては、違う種類のフォントを組み合わせることで、見る人の目を引いたり、情報を整理する効果が期待できます。
でも、やみくもに違うフォントを使えばいいというわけではありません。
全体としてのバランスが取れていないと、読みづらかったり、情報が頭に入らなかったり、最悪の場合は見向きもされないことだってあるのです。
この記事では、デザイナーとして知っておきたいフォントの特徴、素敵に見える組み合わせ、センスの良い配置、印刷時に気をつけたいこと、などが身につくおすすめの本を紹介します。
【お知らせ】
3,500名以上の人生を変えるキッカケになった「好きなことで生きていく!WEBデザイナーという働き方セミナー」では、
などをお伝えしています。今だけ無料で開催しているので「WEBデザインの学び方がわからない」「WEBデザイン業界について知りたい」という方はぜひご参加ください。
>>詳しくはこちら
自分にあったフォントの本を見つける方法
おすすめのフォント本を紹介する前に、まずは自分に合ったフォント本の選び方を紹介していきます。
<フォント本の選び方>
- ノウハウ重視か見本重視か確認してから買う
- 和文と欧文どちらについての本か確認してから買う
良いフォント本を手に入れたとしても、自分が求めている内容でなければ上手く活用することはできません。
そのため、フォント本を選ぶときは口コミでおすすめかどうかはもちろん、自分に合ったものを選ぶことが大切なのです。
上記にあげた選び方について詳しく解説していくので、フォント本選びを失敗したくないという人はチェックしてくださいね。
ノウハウ重視か見本重視か確認してから買う
フォント本を選ぶときは、ノウハウを知りたいのか、フォントのデザイン見本として活用できる本が欲しいのか、目的をハッキリさせることが大切です。
フォント本は、
- フォントの活用方法や歴史、プロの考察などノウハウが凝縮されているもの
- 沢山のフォントが掲載されている見本帳のようなもの
と、大きく2パターンに分けることができます。
ノウハウ本はどのようにフォントを選べばいいのかやプロの考察も載っており、知識として沢山の情報を取り入れることができる本です。
一方沢山のフォントが掲載されている見本帳のようなフォント本は、フォント選びに迷ったときに辞書のような活用方法もできますし、パラパラと眺めているだけでも刺激になる本。
どちらも手元に置いておいて損はない本ですが、知識が欲しいのに見本しか載っていない、逆に見本になるものが欲しいのにノウハウしか載っていない本を買ってしまうと、自分の目的とはそれてしまいますよね。
フォント本選びに失敗しないためにも、
- 知識が欲しいのか?
- 手元においておける見本が欲しいのか?
自分がどちらのノウハウ本が欲しいのかハッキリさせてから購入してください。
和文と欧文どちらについての本か確認してから買う
フォント本を選ぶときは、和文フォントと欧文フォント、どちらについての本が欲しいのかも明確にしておきましょう。
<和文フォントと欧文フォント>
| 概要 | |
| 和文フォント | 漢字・かな・英数字・記号等で構成される |
| 欧文フォント | 英数字・記号等で構成される |
簡単にまとめると、日本語用フォントが「和文フォント」、英数字要が「欧文フォント」ということです。
和文フォントでも英数字は入力することはできますが、余白やベースの考え方が違うので欧文フォントとは違った仕上がりになります。
和文フォントと欧文フォントは基本的な構成が違うので、日本語を表すためのフォント本が欲しいのか、英数字をメインに取り扱ったフォント本が欲しいのかで何を選ぶべきかも変わってくるのです。
フォントを学べるおすすめ本一覧
| 題名 | 価格 | おすすめの人 | 本のタイプ |
| ほんとにフォント | 1,980円 | 初心者 | 見本帳タイプ |
| 実例付きフォント字典 | 4,290円 | 初心者 | 見本帳タイプ |
| 文字のきほん | 1,520円 | 初心者 | ノウハウ本タイプ |
| 『愛のあるユニークで豊かな書体。』 フォントかるたのフォント読本 | 1,980円 | 初心者 | ノウハウ本タイプ |
| 続・和文フリーフォント集 | 2,310円 | 初心者 | 見本帳タイプ |
| 平野甲賀100作 | 1,650円 | 初心者 | 見本帳タイプ |
| もじ鉄 書体で読み解く日本全国全鉄道の駅名標 | 1,870円 | 初心者 | ノウハウ本タイプ |
| 絶対フォント感を身につける | 1,980円 | 中級者 | ノウハウ本タイプ |
| タイポグラフィの基本ルール | 1,960円 | 中級者 | ノウハウ本タイプ |
| 文字のデザイン・書体のフシギ | 1,572円 | 中級者 | ノウハウ本タイプ |
| 時代をひらく書体をつくる | 2,970円 | 上級者 | ノウハウ本タイプ |
| 明朝体活字 その起源と形成 | 4,620円 | 上級者 | ノウハウ本タイプ |
| 市川崑のタイポグラフィ | 2,750円 | 上級者 | ノウハウ本タイプ |
| 作字百景 ニュー日本もじデザイン | 3,080円 | 上級者 | 見本帳タイプ |
※価格は全て2023.11現在のAmazonを参考
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
和文フォントのおすすめ本14冊
まずは、和文フォントについて詳しく執筆されている本が欲しい人におすすめの14冊をご紹介します。
それぞれ、本のタイプや特徴など詳しく解説していくので是非参考にしてくださいね。
ほんとにフォント
| 金額 | 1,980円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・圧倒的人気を誇るフォント本 ・NG例とOK例が分かりやすい |
今、フォント関連の本のなかで最も多くの支持を集めている人気の本です。
ポスター、チラシ、DM、本の表紙、メニュー、データ資料、など、第一印象が決め手の媒体を例に、コンセプトに合ったフォントが説明されています。
NG例とOK例の対比が具体的でわかりやすく、手元に置いておきたい一冊です。
また、違うフォントの組み合わせパターンのデザイン紹介もあり、フォントの使い方で印象がずいぶん変わるのを実感できるでしょう。
(※Amazonサイトに飛びます)
実例付きフォント字典
| 金額 | 4,290円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・膨大な量のフォントを一覧できる ・国内26社のフォントを比較できる |
2500種類近い和文書体を一覧できる、圧巻の見本帳です。
「デザイナー必携」の呼び声も高い、入門者のみならず上級者にも好評の一冊。
人気の179書体については、ポスターやパッケージ、本の装丁など、実例も紹介されているので、デザインの参考になるでしょう。
また、モリサワをはじめ、国内26社のフォントを見比べることができるので、各社のフォントサブスクサービスを比較検討するのにも役立ちます。
(※Amazonサイトに飛びます)
文字のきほん
| 金額 | 1,520円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・ページ数が少ないので本が苦手な人でも読みやすい ・フォントや文字に関する基礎知識を網羅している |
A5判の総ページ144ページという薄さながら、文字に関する知識をぎゅっと詰め込んだ一冊です。
「書体とは?フォントとは?」という説明から始まって、和文書体と欧文書体の特徴、文字の歴史、媒体別のフォント使用例、主なフォントメーカーと代表的なフォントの紹介、フォントの作り方、選び方、入手方法など、入門者が知りたい情報が詰まっています。
豊富な図解や写真説明によって、内容も整理されており、手っ取り早く、フォントについて学べるでしょう。
(※Amazonサイトに飛びます)
『愛のあるユニークで豊かな書体。』 フォントかるたのフォント読本
| 金額 | 1,980円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本 |
| おすすめポイント | ・ネガティブな面も正直につづられている ・歴史や用途までまとめて学ぶことができる |
「愛のあるユニークで豊かな書体。」は、フォントかるた制作チームによるフォント解説本です。
「このフォントは評判が良くない」などネガティブな面も赤裸々につづられています。
全89種類のフォントの歴史や用途、実例まで詳しく紹介されており読み応えのある一冊です。
(※Amazonサイトに飛びます)
続・和文フリーフォント集
| 金額 | 2,310円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・個性的なフォントを80種収録されている ・楽しく読み進められるフォント愛がつまった内容 |
フォントグラフィック・大谷秀映さんによる日本語フリーフォントが80種類収録されている本書。
前作である「和文フリーフォント集」とは全て違うフォントが収録されているので、両方合わせて購入すればフォント見本帳として幅広く活躍します。
個性的で見ているだけでも楽しい誌面に加え、大谷秀映さんのフォントに対する想いや考えも載っていて隅々まで読みたくなる一冊です。
(※Amazonサイトに飛びます)
平野甲賀100作
| 金額 | 1,650円(※現在Amazonでは電子書籍のみ) |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・平野甲賀さんの作品が100例掲載されている ・本の中にある作品はオンラインで購入可能 |
独特なデザインで数十年にわたり出版業界を牽引してきたグラフィックデザイナー・装丁家の平野甲賀さんの作品が豊富にまとめられた本書。
本に出てくる作品は、販売サイトに移動しそのまま購入できるようになっています。
フォントの見本帳が欲しい人はもちろん、平野甲賀さんファンの方にもおすすめの一冊です。
(※Amazonサイトに飛びます)
もじ鉄 書体で読み解く日本全国全鉄道の駅名標
| 金額 | 1,870円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・身近な「鉄道」に関するフォントが豊富 ・見本帳としてはもちろん旅のお供としても楽しい一冊 |
鉄道の中でも看板などに採用されている文字が好きな人を、「もじ鉄」と呼びます。
もじ鉄視点から鉄道で採用されている文字やフォントについて詳しく掲載されており、フォントについて学ぶためだけではなく、旅行や出勤・通学も楽しくなるでしょう。
身近な存在である鉄道からフォントを知ることができるので、初心者にもおすすめの一冊です。
(※Amazonサイトに飛びます)
絶対フォント感を身につける
| 金額 | 1,980円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン中級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・例をもとに分かりやすく解説されている ・身近なフォントがとりあげられていて親近感がある |
本書は、2015年にデザイン誌MdNが取り上げた、特集3回分に加筆したムック本です。
聞こえた音を本能的に正確な音階で聞き取ることのできる「絶対音感」になぞらえて、フォントの特徴を把握し、デザインに合ったフォントを的確に見分けられる感覚「絶対フォント感」を養うためのノウハウが詰まった一冊です。
もちろん、これを読んだからといってすぐに、絶対フォント感が身につくわけではありませんが、フォントの特徴や系譜などを学ぶことによって、使用するフォントを決める時の判断基準に深みが出ることは間違いなしです。
(※Amazonサイトに飛びます)
タイポグラフィの基本ルール
| 金額 | 1,960円(※Amazonでは現在電子書籍のみ販売) |
| おすすめの人 | フォントデザイン中級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・一冊手元に置いておきたいフォントの教科書的存在 ・正しい知識と技を知ることができる |
ひとことで言えば、ザ・教科書。
手元に置いて、いつでも見返したい一冊です。
第一線の書体デザイナー/グラフィックデザイナーが、文字を美しく見せる技を、豊富な実例や詳しい説明と共に披露しています。
正統派の技を、正しい背景知識とともに本書で学べば、文字のデザインにもぐっと自信が付くでしょう。
(※Amazonサイトに飛びます)
文字のデザイン・書体のフシギ
| 金額 | 1,572円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン中級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・特別講義の内容を誰でも読むことができる ・あらゆる視点からフォントについて学ぶことができる |
「文字のデザイン・書体のフシギ」は、神戸芸術工科大学ビジュアルデザイン学科にて行われた、祖父江慎氏・藤田重信氏・加島卓氏・鈴木広光氏による特別講義を収録した本です。
一人一人視点が違うので、あらゆる角度からフォントについての知識を深めることができます。
(※Amazonサイトに飛びます)
時代をひらく書体をつくる
| 金額 | 2,970円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン上級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・橋本和夫氏の実体験を通した歴史を知ることができる ・活字・写植・デジタルのデザインの流れがわかる |
金属活字、写植、デジタルフォントの文字印刷の変遷の中で、書体デザイン・制作・監修をされてきた橋本和夫氏へのインタビューをまとめた本です。
橋本氏の実体験を通してフォントの歴史を知ることで、これまで紹介してきた本とは違う側面から、フォントを身近に感じることができるでしょう。
温故知新、あなたの中の何かが変わった、そんな手応えも感じるかもしれません。
(※Amazonサイトに飛びます)
明朝体活字 その起源と形成
| 金額 | 4,620円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン上級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・プロ目線のマニアックな知識が満載 ・フォントの歴史を深く学ぶことができる |
この本を読んだ後はきっと、「マニアックだなあ」と、ニヤニヤしてしまう人もいるかもしれませんね。
佐藤タイポグラフィ研究所で書体設計者として実績を積まれた小宮山博史氏が、国内外の膨大な資料を集めて、明朝体活字の歴史をルーツからまとめ上げた渾身の一冊です。
ここまで明朝体にのめり込む小宮山氏のこだわりに触れることで、あなた自身も、お気に入りのフォントに対して、マニアックなこだわりを持ちたくなるかもしれません。
(※Amazonサイトに飛びます)
市川崑のタイポグラフィ
| 金額 | 2,750円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン上級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・馴染みある作品たちもでてくるのでマニアックな話を楽しく聞くことができる ・知識としてはもちろん、一冊の本として面白く読み進められる |
市川崑監督による犬神家の一族のテロップ表現といえば、L字型極太明朝体が私たちの記憶に鮮明に残っています。
L字型極太明朝体は、その後の映像表現に関するテロップに大きな影響を与えているのです。
私たちの記憶に残るだけでなく、テロップ表現において大きな爪跡を残したL字型極太明朝体について映画評論・デザイン評論の二つの視点から分析されている本書。
かなりマニアックな内容になりますが、読み物としても面白い一冊です。
(※Amazonサイトに飛びます)
作字百景 ニュー日本もじデザイン
| 金額 | 3,080円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン上級者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・文字をまるでアートのように表現している ・デザイナーごとの表現を感じることができる |
作字百景 ニュー日本もじデザインは、デザイナー40組によって約800点の作例が掲載されている本です。
デザイナーごとに違う自由な表現は、まるでアートのよう。
見本帳として役に立つことはもちろん、パラパラと見ているだけでも刺激になる本です。
(※Amazonサイトに飛びます)
欧文フォントのおすすめ本8冊
和文フォントの次は、欧文フォントのおすすめ本を8冊ご紹介します。
フォントのふしぎ ブランドのロゴはなぜ高そうに見えるのか?
| 金額 | 3,150円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・誰もが知る有名ブランドロゴがメインなので読み進めやすい ・考察が面白く読み物としても魅力的 |
欧文フォントの専門家である小林章さんが撮影した写真とコラムで、欧文フォントの秘密をテーマに書かれた本書。
誰もが知る有名ブランドのロゴはなぜ高級感があるのか、という疑問に対しての小林さんの考察がとても面白く、フォント本としてはもちろん一冊の読み物としてもおすすめです。
(※Amazonサイトに飛びます)
欧文書体―その背景と使い方
| 金額 | 2,750円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・欧文フォント初心者でも分かりやすい ・実用性が高く長く役に立つ |
先述した「フォントのふしぎ ブランドのロゴはなぜ高そうに見えるのか?」同様、小林章さんによって「現場で活躍するプロのデザイナーのお役に立つこと」を念頭に書かれた「欧文書体―その背景と使い方」。
欧文フォントの成り立ちや使い方などが分かりやすく解説されており書体の選定にも役に立ちます。
実用性も高いので、初心者の人は手元に置いておいて損はないでしょう。
(※Amazonサイトに飛びます)
となりのヘルベチカ マンガでわかる欧文フォントの世界
| 金額 | 1,760円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・漫画形式で読みやすい ・楽しみながらフォントの理解を深めることができる |
「となりのヘルベチカ マンガでわかる欧文フォントの世界」は、4コマ漫画やイラスト多めのコラムなので本が苦手という人にもおすすめできる一冊です。
漫画形式ではあるものの、欧文フォントの成り立ちや特徴だけでなく、マメ知識までしっかり学ぶことができます。
(※Amazonサイトに飛びます)
欧文書体 2 定番書体と演出法
| 金額 | 2,750円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン中級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・前作よりより深く、実践的な部分を学ぶことができる ・写真と共に分かりやすく解説されている |
「欧文書体―その背景と使い方」では触れていない、一歩深い部分まで欧文フォントについて解説されている「欧文書体 2 定番書体と演出法」。
- どう使ったら効果的なのかを考えてるかい分ける
- 書体デザイナーの意図を読み取る
この2つをテーマに執筆されています。
小林さんが実際に欧米各地で撮影した写真と共に分かりやすく解説してくれているので、前作より難しいのではと思う人も一度手に取ってみてください。
(※Amazonサイトに飛びます)
英文サインのデザイン 利用者に伝わりやすい英文表示とは?
| 金額 | 2,420円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン中級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・日本人では気が付きにくいポイントを解説してくれている ・デザインと分かりやすさを両立できる具体的提案がある |
翻訳家と欧文書体デザイナーによって英文サインを解説している本書。
デザインが良いだけでなく、私たち日本人に分かりやすいような英文サインを作るためにはどうしたらいいのか、分かりやすく解説してくれています。
日本人の感覚では気付きにくいこともあるので、英字サインや欧文フォントに苦戦している人は是非手に取ってほしい一冊です。
(※Amazonサイトに飛びます)
1ページずつ学ぶ文字レイアウトの法則
| 金額 | 2,420円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン中級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・欧文フォントの間違いを選らせるような知識が満載 ・小型本なので読みやすい |
本書が取り上げているのは欧文の文字レイアウトのみですが、プロなら知っておきたい知識の詰まった、こだわりの一冊です。
これを読めば、欧文フォントを使うときのデザインも、グッと引き締まりそうです。
文字組の常識や、オーファンやウィドーなどのタブーなど、四六判208ページの小型本ながら、専門知識が網羅されています。
素人デザイナーさんが知らずにやってしまいがちな、プロのデザイナーから見たら「変」な間違いを避けたい方には、まずおすすめです。
(※Amazonサイトに飛びます)
アイデア No.392 2021年 1月号
| 金額 | 2,348円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン中級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・世界各国の書体デザイナーから知識を吸収することができる ・外国で使われているフォントを沢山見ることができる |
「アイデア No.392 2021年 1月号」は、世界各地の書体デザイナー10組により、各国の書体デザイン使用状況や普及率について掲載されている本です。
各国で使われているフォントデザイン例も豊富なので、普段あまり目にしないフォントに刺激をもらえます。
(※Amazonサイトに飛びます)
ブランディングのためのカスタムフォントとタイポグラフィ
| 金額 | 5,489円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン上級者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・まるでアート本のようなフォントデザインが豊富に掲載 ・見ているだけで刺激をもらえる内容 |
これはもう、アート本です。
ブランドが独自にデザインしたカスタムフォントや、それを使ってポスターやプロダクトに展開したタイポグラフィの実例が紹介されています。
いずれも「かっこいい!」とため息の出るような、ぶっ飛んだデザインばかり。
手がけたデザイナーの生の言葉で、メイキングストーリーが綴られています。
フォントのお勉強は一休みして、本書のページをめくって、インスパイアされてください。
(※Amazonサイトに飛びます)
和文フォントも欧文フォントも学べるおすすめ本7冊
続いては、和文フォントも欧文フォントもどちらも参考になる内容が盛りだくさんのおすすめ本を7冊ご紹介します。
それぞれどんな本なのか、詳しく解説していきます。
マネするだけでセンスのいいフォント
| 金額 | 1,980円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・ベストセラーシリーズ ・参考になるおしゃれフォントが豊富 |
ベストセラー「3色だけでセンスのいい色」シリーズの第二弾です。
キャッチコピー、説明、テイストの3種類のフォントを組み合わせることで生まれる、オシャレ可愛い作品例が、そのままデザインの参考として使えます。
ぱらぱらとページをめくって、フォントの組み合わせの妙と、気分を上げてくれるデザインを楽しむのもまた良し。
(※Amazonサイトに飛びます)
レタースペーシング タイポグラフィにおける文字調整の考え方
| 金額 | 2,420円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・文字間調整について徹底的に解説されている ・和文・欧文・和欧混植全ての文字間調整について学べる |
字詰め、カーニングなどの文字間調整、それはデザイナーにとって、永遠の課題ではないでしょうか。
本書は、文字間調整に焦点をしぼり、デザイナーならではの感覚的なアプローチと、論理的な解説を組み合わせて、まじめにこだわった本となっています。
和文、欧文、和欧混植のそれぞれの場合について学ぶことができ、「何となく」の字詰めから一歩抜け出す助けとなるでしょう。
各項目はすべて見開き完結なので、どのページからでも読み進められ、読み物としても最適です。
(※Amazonサイトに飛びます)
新装復刻版 現代図案文字大集成
| 金額 | 1,650円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・文庫本サイズで読みやすい ・豊富な作品例が見本帳としても最適 |
「新装復刻版 現代図案文字大集成」は、グラフィックデザイナー・辻克己氏編著によって昭和9年に発刊された「現代図案文字大集成」のニューバージョンです。
どこか懐かしさを感じるフォントデザインから、新しさを感じるものまで沢山の作品例が掲載されています。
文庫本サイズの本なので、読みやすく持ち運びにも便利です。
(※Amazonサイトに飛びます)
数字で伝える広告デザイン
| 金額 | 4,290円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン中級者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・数字フォントについて徹底解説されている ・作品例が多く見ているだけで刺激になる |
広告においては、日付や価格など数字で表される情報は重要ですね。
いかに正確に、印象深く、これらの情報を見る人の頭に焼き付けるか、デザイナーは細心の注意を払って、綿密にデザインを作り上げます。
たかが数字と侮ることなかれ。
簡潔性、美術姓、意外性、遊び心…、あの手この手で練り上げられた広告デザインの作品例を見れば、あなたの引き出しもぐんと広がることでしょう。
(※Amazonサイトに飛びます)
あるあるタイポ
| 金額 | 4,290円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン中級者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・作品例には解説やアドバイスがついている ・遊び心満載で見ているだけで刺激を得られる |
前述の2冊と違い、遊び心の詰まったタイポグラフィの見本帳。
章のタイトルからして、「線で見せるタイポ」「グッと読ませるタイポ」「太字でだいぶインパクト」など、思わず興味をそそられる、イメージ先行の構成になっています。
文字でこんなに自由に遊べるんだ!と視界が開ける爽快感を味わってください。
デザイン例には、ポイント解説やアドバイスが付いています。
さらに、デザインのバリエーション展開も披露されていて、あなたの好奇心をこれでもかと言わんばかりに刺激してくる本です。
(※Amazonサイトに飛びます)
オンスクリーン タイポグラフィ 事例と論説から考えるウェブの文字表現
| 金額 | 3,300円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン上級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・オンスクリーンの文字表現について詳しく学ぶことができる ・紙媒体と画面上の違いについて知ることができる |
「オンスクリーン タイポグラフィ 事例と論説から考えるウェブの文字表現」は、パソコンやスマートフォンなど画面上にあるタイポグラフィに関しての論説と事例がまとめられた本です。
パソコンやスマートフォンが身近な存在になりすぎて当たり前のように感じていましたが、媒体が変わるのであればフォントも変えていかなければいけないというのは当然のことですよね。
見落としがちな大切なことに気付かせてくれる、そして学びを与えてくれる一冊です。
(※Amazonサイトに飛びます)
フォントの話をしよう
| 金額 | 2,420円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン上級者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・プロの思考を知ることができる ・フォントメーカー側のインタビューもある |
「フォントの話をしよう」は、タイポグラフィのインタビュー集です。
プロが実際に手掛けたデザインについて、なぜそれを選んだのか、どう改良していったのかなど詳しく知ることができます。
マニアックな内容もありますが、考え方の引き出しを増やし、これからの活動の幅を広げるのに役に立つ一冊です。
(※Amazonサイトに飛びます)
フォントだけでなくデザインセンスがアップするおすすめ本2冊
最後は、フォントだけでなくデザインセンスがアップするおすすめ本を2冊ご紹介します。
フォントに関する本ではありませんが、フォント含むデザインについて学べる内容になっている本です。
デザインに携わる人であれば、読んでおいて損はありませんよ。
見るだけでデザインセンスが身につく本
| 金額 | 1,980円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | 見本帳タイプ |
| おすすめポイント | ・デザインセンスが見るだけでアップする ・初心者にも分かりやすく解説されている |
この本はフォントに特化しているわけではありませんが、デザイン超初心者向けに、見るだけでデザインセンスが身についちゃうくらいわかりやすく解説されています。
フォントと合わせて色の組み合わせやレイアウトについても学びたい方におすすめの一冊。
デザインを勉強するなら、手元に持っておいて損はないですよ!
(※Amazonサイトに飛びます)
素人ですが、デザインしてみました
| 金額 | 1,540円 |
| おすすめの人 | フォントデザイン初心者 |
| 本のタイプ | ノウハウ本タイプ |
| おすすめポイント | ・イラストが多いので読みやすい・初心者が知りたいテクニックが豊富 |
タイトル通り、デザイン初心者向けの本です。
フォントに特化した内容ではありませんが、可愛いイラストのストーリー仕立てのマンガから、気軽にプロのデザイナーのノウハウを学べます。
フォントに関する部分では、フォントのイメージやサイズ、文字詰め、装飾など、ちょっとの工夫で見やすくセンス良くできるポイントを紹介。
「何となく」から卒業して、デザインを使う場面やコンセプトなど、デザインの背景情報をふまえて「何をどう伝えたらいいか」を考えるクセをつける一歩を後押ししてくれます。
(※Amazonサイトに飛びます)
まとめ
今回は、フォント本の選び方と、おすすめフォント本を30冊ご紹介しました。
フォントは、選ぶものによってデザインの雰囲気も大きく変わるだけでなく、歴史や使い方など本当に奥が深いものです。
- デザインに携わる人であれば読んでおいて損はない本
- フォントの教科書的な本
- 見るだけでフォントの参考になる本
様々なジャンルの本を紹介しましたが、30冊全てを読破するのは難しいと思います。
- 和文・欧文フォントどちらについての本が欲しいのか
- ノウハウ本と見本帳タイプどちらが欲しいのか
欲しい本の種類を明確にしてから、今回の記事を参考に自分に合ったフォント本を見つけてくださいね。