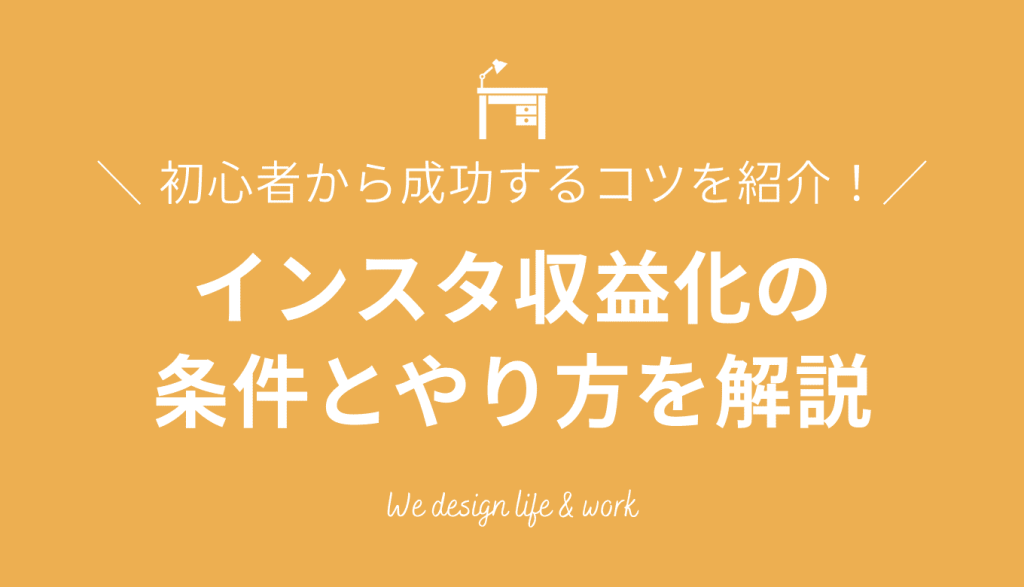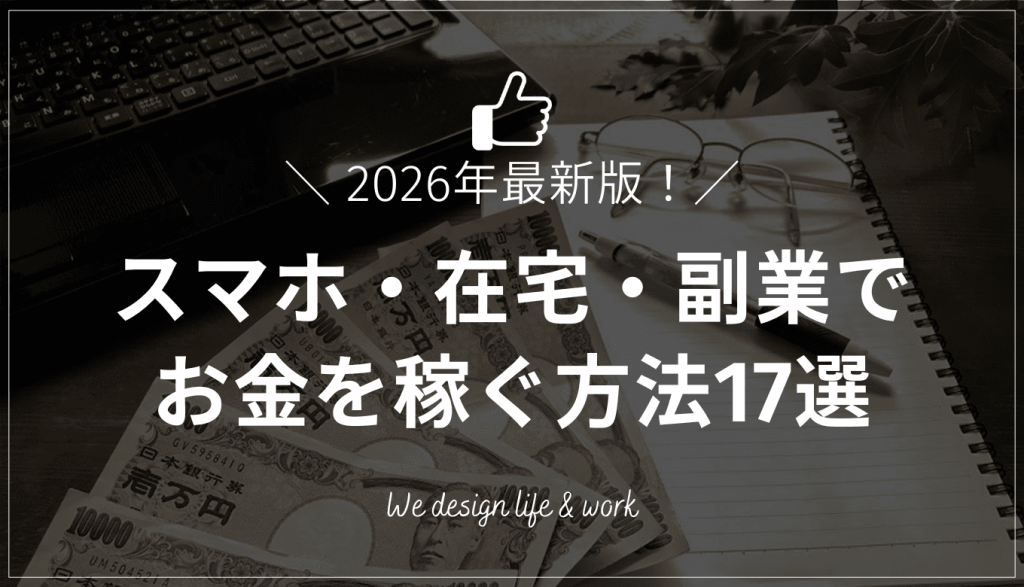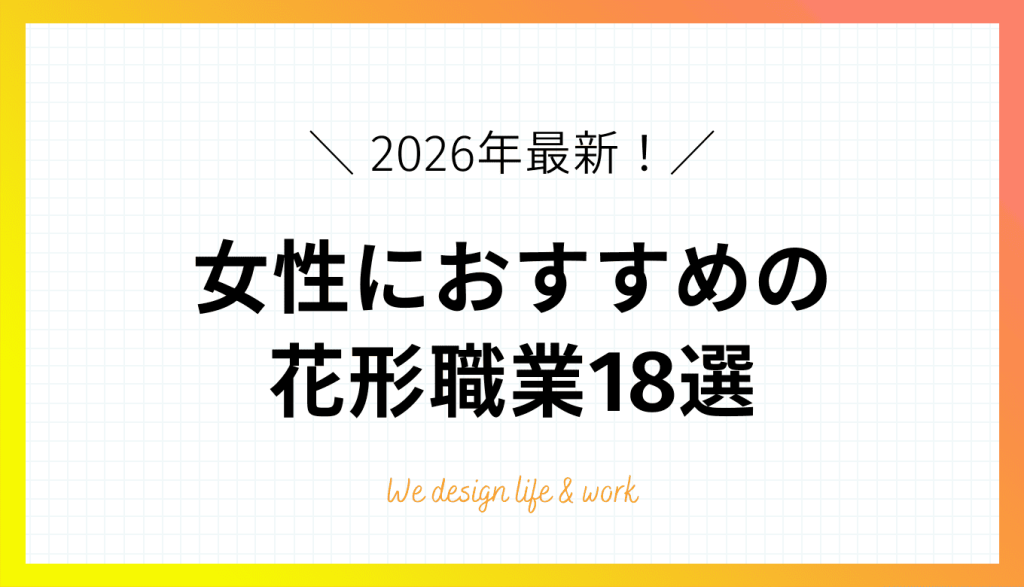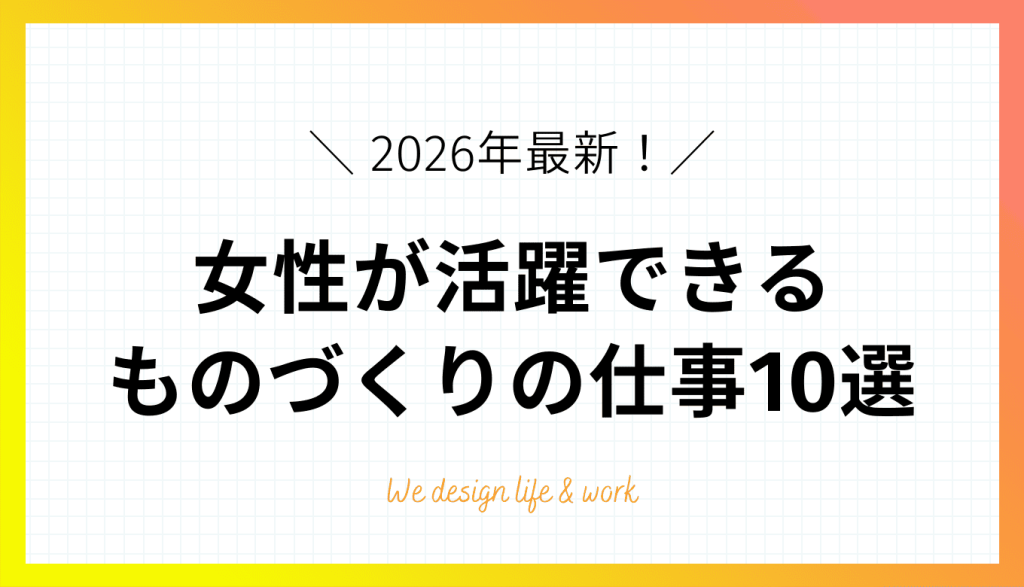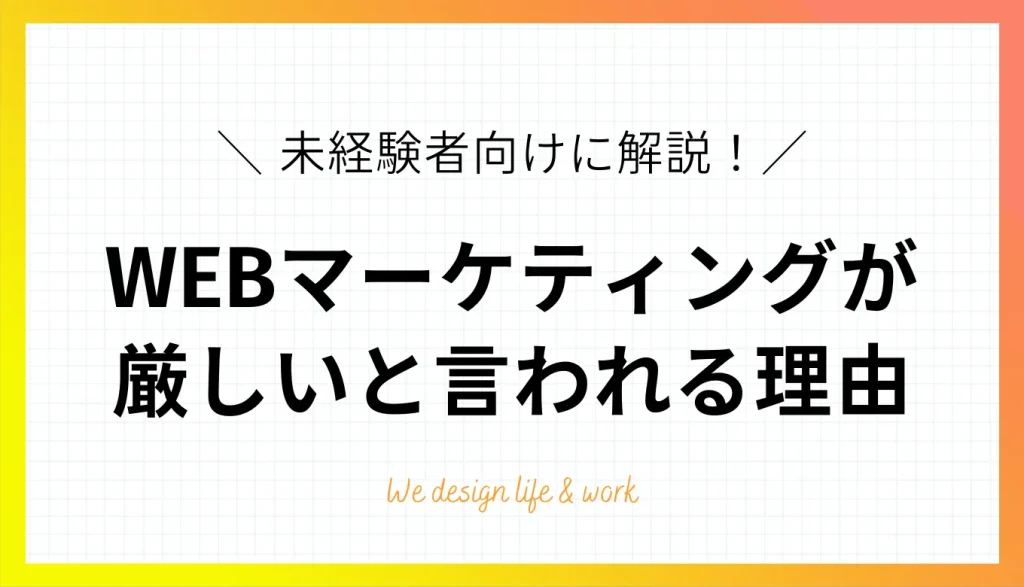AI技術の進化によって、働き方や求められるスキルは急速に変化しています。
自動化の波が広がる一方で、人間だからこそ発揮できる力が求められる職業も少なくありません。
この記事では、AIに奪われにくく、将来も安定して働ける15の仕事をご紹介します。
長期的なキャリア形成を考えるうえで、これからの時代に必要とされる職業選びの参考にしてみてください。
AI導入の現状と働き方の変化
効率化だけでなく、働く目的や価値観そのものが見直される時代になりました。
人とテクノロジーがともに成長する社会では、柔軟な発想と主体的な姿勢が求められます。
ここでは、以下の2つについて詳しく解説していきます。
- 生成AI活用に積極的な日本企業は49.7%
- 日本企業のAI導入は発展途上!今後さらなる拡大へ
日本の現在のAI普及率と、世界と比較した際の結果を詳しくみていきましょう。
生成AI活用に積極的な日本企業は49.7%
総務省の調査によると、日本企業のうち「積極的に活用している」または「一部の業務に限定して利用している」企業の割合は49.7%に達しました。
前年の42.7%から着実に増えており、生成AIへの関心の高まりが数字にも表れています。
ただし、米国(84.8%)、ドイツ(76.4%)、中国(92.8%)と比べると、まだ導入が進んでいるとは言い切れません。
| 国名 | 積極的に活用 | 限定的に利用 | 合計(活用方針あり) | 方針未定 | 禁止・不明 |
| 日本 | 23.7% | 26.0% | 49.7% | 31.8% | 18.5% |
| 米国 | 39.2% | 45.6% | 84.8% | 9.1% | 6.1% |
| ドイツ | 39.2% | 37.2% | 76.4% | 12.9% | 10.7% |
| 中国 | 48.5% | 44.3% | 92.8% | 4.2% | 2.9% |
総務省|企業におけるAI利用の現状を参考に作成
この結果から、日本企業の多くがAI導入に慎重な姿勢を保っていることがわかります。背景には、活用方法がまだ明確でないことや、情報漏えいへの不安、導入や運用にかかるコストなどが挙げられます。
特に中小企業では、AIに詳しい人材が不足していることも大きな課題です。
とはいえ、この慎重さは単なる「遅れ」ではありません。新しい技術を取り入れる際に、リスクを最小限に抑え、品質や安全性を重視するのは日本企業らしい特徴といえます。
日本企業のAI導入は発展途上!今後さらなる拡大へ
AI導入の流れは日本でも確実に広がっていますが、全体としてはまだ発展途上の段階にあります。
総務省の調査によると、企業規模によって導入の進み具合には明確な差があり、大企業では26.1%が「積極的に活用中」、中小企業では17.5%にとどまっています。
特に中小企業では、「方針を定めていない」と回答した割合が約半数に達しており、導入の準備が整っていない実態が浮かび上がっているでしょう。
| 規模 | 積極的に活用 | 限定的に利用 | 方針未定 | 禁止 | わからない |
| 大企業 | 26.1% | 29.6% | 25.8% | 5.4% | 13.2% |
| 中小企業 | 17.5% | 18.6% | 47.6% | 1.4% | 16.8% |
総務省|企業におけるAI利用の現状を参考に作成
一方で、AIの導入によって得られる効果は明確になりつつあります。先行して取り組む企業では、業務時間の削減や人手不足の解消、社内ナレッジの共有効率化など、具体的な成果が報告されています。
AI導入を「単なる自動化」ではなく、「人の力を補う仕組み」としてとらえる動きが広がれば、導入のハードルは大きく下がるでしょう。
AI導入はまだ途中段階ですが、その流れは確実に前進しています。
今後、実践的な知見が蓄積されていけば、AIが「一部の企業のツール」から「社会全体の基盤」へと進化していくでしょう。
AIの力を活かしながら、人にしかできない価値を生み出す働き方が、日本でも当たり前の時代になっていくはずです。
AIに奪われる仕事の特徴
AIが得意とする分野が広がるなかで、人の手を介さなくても成り立つ仕事が増えつつあります。
働き方の見直しが求められる今、どのような職種が影響を受けやすいのかを理解することが重要です。
ここでは、AIに代替されやすい仕事の特徴を3つご紹介します。
- 手順定が固され、繰り返し処理が中心の仕事
- 人との関わりや感情対応が少ない仕事
- AI化が進みやすいデスクワーク中心の仕事
今後のキャリアを考えるうえで、少し意識しておきたいポイントです。
特徴①:手順定が固され、繰り返し処理が中心の仕事
AIに代わりやすい仕事の代表例が、決まった手順を何度も繰り返すルーティン作業です。
判断よりも正確さやスピードが重視されるため、AIが得意とする分野といえます。
近年では、オフィスだけでなく、工場や物流、店舗など現場レベルでもAIの導入が進んでいますよ。
| 業務の種類 | 主な内容 |
| 製造・組立 | ラインでの検品・仕分け・組み立て作業など |
| 物流・倉庫管理 | 商品の仕分け、在庫スキャン、配送ルート管理など |
| 小売・接客 | セルフレジ、在庫補充、価格チェックなど |
| 交通・監視 | 駐車場の入出庫管理、信号制御、監視カメラ映像の分析など |
上記の仕事は、ルールが明確で手順が固定されているため、AIやロボットによる自動化が進みやすい領域です。
実際、物流センターではAIが倉庫内を自動走行して商品を仕分けし、工場ではAIカメラが品質検査をおこなうなど、人の手が担っていた作業が徐々に置き換えられています。
とはいえ、完全にAI任せにはできません。
突発的な機械の異常判断、現場の安全確認といった部分には、まだ人の判断が欠かせません。
今後は、AIが繰り返し作業を担い、人は状況判断や改善に関わる「考える仕事」へと役割が変わっていく流れがさらに強まっていくでしょう。
特徴②:人との関わりや感情対応が少ない仕事
マニュアル通りに進められる仕事や、相手の感情を読み取る必要がない仕事ほど、自動化の対象になりやすくなっています。
近年では、接客業やサービス業でもAI化が進み、人の関与が最小限で成り立つ仕組みが広がっていますよ。
| 業務の種類 | 主な内容 |
| 受付・案内 | チャットボットやAI案内端末による対応、受付予約管理など |
| 販売・サービス | 無人レジ、オンライン注文システム、配達ルート最適化など |
| 警備・点検 | 監視カメラのAI分析、施設巡回ロボットの導入など |
| 交通・運転 | 自動運転バス、配送ドローン、無人搬送車(AGV)など |
上記の業務では、利用者の質問や要望に対してAIが即座に応答できるようになっており、スピードと効率の面で人を上回るケースも増えています。
特に定型的な対応や、感情のやり取りを必要としないやりとりはAIが得意とする領域です。
ただし、トラブル対応やクレーム処理など、相手の感情を理解して行動するような場面では、人の存在が欠かせません。
AIが担うのはあくまで「効率化できる部分」であり、人にしかできない心の通ったやり取りこそ、今後より価値のあるスキルとして求められていくでしょう。
特徴③:AI化が進みやすいデスクワーク中心の仕事
書類作成やデータ入力、数値の計算など、決まったルールに沿っておこなう作業もAIが最も得意とする分野です。
正確さが求められる業務ほど、人の手よりもAIのほうが効率的に処理できるようになっています。
| 業務の種類 | 主な内容 |
| 一般事務 | データ入力、書類作成、スケジュール管理など |
| 経理・会計 | 伝票処理、請求書作成、売上管理など |
| 営業サポート | 顧客情報の登録、メール送信、契約書の作成補助など |
| 人事・総務 | 勤怠集計、採用データ管理、社員情報の更新など |
こうした仕事は、ルールが明確で作業の流れが一定のため、AIやRPA(業務自動化ツール)に置き換えやすい特徴があります。
すでに多くの企業で、単純な入力作業や帳票管理の自動化が進んでおり、人の手を介さずに処理できる体制が整いつつあるでしょう。
AIは人為的なミスを防ぎ、コスト削減にもつながるため、今後さらに導入が進むと考えられます。
ただし、すべてのデスクワークがAIに置き換わるわけではありません。
クライアントとのやり取りや、判断力・提案力が求められる業務は引き続き人の役割が欠かせません。
今後は、AIが単純作業を担い、人はより企画的・創造的な業務に集中する流れが加速していくでしょう。
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
AIに奪われない仕事の特徴
AIの進化によって多くの仕事が変化する一方で、人にしかできない役割も確実に存在しています。
テクノロジーが進歩しても、人の感性や判断が求められる分野はなくなりません。
求められるのは、機械には再現できない「人間らしさ」をどう活かすかです。
ここでは、AI時代にも価値を発揮し続ける仕事の特徴を3つご紹介します。
- 専門知識と人間的対応を組み合わせる仕事
- 状況に応じた判断や調整が求められる仕事
- 発想力や表現を通じて新しい価値を生み出す仕事
変化の波が大きい今だからこそ、長く活躍できる仕事の特徴を知っておきましょう。
特徴①:専門知識と人間的対応を組み合わせる仕事
情報を分析して最適解を出すことはAIが得意ですが、「相手の立場を理解し、安心できる言葉を選ぶ」といった対応は人にしかできません。
例えば、医師やカウンセラーのように、専門知識に基づきながらも、相手の感情をくみ取って対応する仕事は、今後も高い需要が続くでしょう。
こうした仕事に共通するのは、「知識だけで完結しない」という点です。
どのようなに正しい情報でも、相手が受け入れやすい形で伝えることができなければ、意味を持ちません。
- 相手の表情や言葉から感情を読み取る必要がある
- 同じ状況でも人によって対応を変える柔軟さが求められる
- 信頼関係を築く過程が成果につながる
そして、専門知識を人のために活かすためには、次のようなスキルが欠かせません。
| 項目 | 内容 |
| 専門性 | 理論に基づいて説明できる力 |
| 伝達力 | わかりやすく伝える力 |
| 共感力 | 相手の気持ちをくみ取る姿勢 |
AIが論理的に導く「正解」だけでは、心に響くコミュニケーションは生まれません。専門性と人間らしさをかけ合わせることこそ、これからの時代に価値を発揮する働き方といえます。
特徴②:状況に応じた判断や調整が求められる仕事
AIが苦手とするのは、変化する環境に合わせて行動を切り替える力です。
現場では、予期しない出来事が起こることも多く、マニュアル通りに進まない場面が少なくありません。
AIは過去のデータに基づいて最適解を導きますが、「今この状況でどう動くか」を決める力は人にしかありません。
例えば、教師は授業中の生徒の反応を見て進行を変え、経営コンサルタントは企業の変化に合わせて戦略を調整します。
常に周囲の状況を観察し、最適な判断を積み重ねる仕事は、AIでは代替できません。
- 環境の変化を前提に、臨機応変に行動する必要がある
- 計画外の事態でも、冷静に全体の流れを立て直す力が求められる
- 関係者の立場を踏まえ、現場をスムーズにまとめる役割を担う
| 観点 | 求められる力 |
| 状況把握力 | 問題の要因や背景を的確に見抜く力 |
| 判断力 | 短時間で複数の選択肢から最善を選ぶ力 |
| 調整力 | 人・時間・情報を整理し、流れを整える力 |
AIが示すのは理論的な最適解ですが、実際の現場では常に想定外が起こります。
変化を読み取りながら最善の手を打てる人こそ、これからの社会で欠かせない存在です。
特徴③:発想力や表現を通じて新しい価値を生み出す仕事
AIが得意なのは、過去のデータをもとに最も効率的な答えを導くことです。
一方で、人には前例のないところから新しい発想を生み出し、誰かの心を動かす表現を形にする力があります。
こうした創造的な仕事は、AIが踏み込めない分野になるでしょう。
例えば、WEBデザイナーはクライアントの世界観や目的を読み取り、色や構成、動きを通してメッセージを届けます。
また、研究者は既存の理論を超えて新しい発見を目指し、社会にまだない価値を生み出します。
どちらも、過去の答えではなく「これからの可能性」を描く仕事です。
- 作品や研究に、個人の世界観や解釈が強く反映される
- 「正解」が存在せず、答えを自らつくり出す過程が重視される
- 感情や美意識など、数値で表せない感覚が成果を左右する
| 観点 | 求められる力 |
| 創造力 | 既存の枠を超えて新しいアイデアを形にする力 |
| 表現力 | 思いや意図をデザインや言葉で伝える力 |
| 洞察力 | 社会や人の変化を読み取り、次の方向性を示す力 |
AIは「過去の答え」を導くことはできても、「未来の価値」を描くことはできません。
発想と表現を通じて新しいものを生み出す仕事は、これからの社会でも人が中心であり続けます。
AIに奪われない仕事ランキング15選
AIの登場で、仕事の「得意・不得意」は機械と人とでわかれ始めています。
効率やスピードを競う時代から、発想や共感といった“人ならではの強み”が評価される時代へ。
これからの社会で長く活躍できる人は、どのような仕事を選ぶのでしょうか。
ここでは、AIに奪われない仕事をランキング形式で15選ご紹介します。
| 順位 | 職業 | 専門+人間対応 | 判断・調整力 | 創造性 |
| 1位 | 教師・保育士 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2位 | 経営コンサルタント | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3位 | 営業職 | ◎ | ◎ | ◯ |
| 4位 | 弁護士 | ◎ | ◎ | ◯ |
| 5位 | 研究者・科学者 | ◯ | ◎ | ◎ |
| 6位 | カウンセラー・心理士 | ◎ | ◎ | △ |
| 7位 | 医師 | ◎ | ◎ | △ |
| 8位 | 看護師 | ◎ | ◎ | △ |
| 9位 | クリエイター(デザイン・映像・ライティングなど) | ◯ | ◯ | ◎ |
| 10位 | AIエンジニア・データサイエンティスト | ◎ | ◯ | ◯ |
| 11位 | 美容師・メイクアップアーティスト | ◯ | ◯ | ◎ |
| 12位 | プロスポーツ選手・指導者 | ◯ | ◎ | ◯ |
| 13位 | 作業療法士・理学療法士 | ◎ | ◯ | △ |
| 14位 | 介護福祉士 | ◎ | ◯ | △ |
| 15位 | 整体師 | ◎ | ◯ | △ |
| 順位 | 職業 | 専門+人間対応 | 判断・調整力 | 創造性 |
| 1位 | 教師・保育士 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2位 | 経営コンサルタント | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3位 | 営業職 | ◎ | ◎ | ◯ |
| 4位 | 弁護士 | ◎ | ◎ | ◯ |
| 5位 | 研究者・科学者 | ◯ | ◎ | ◎ |
| 6位 | カウンセラー・心理士 | ◎ | ◎ | △ |
| 7位 | 医師 | ◎ | ◎ | △ |
| 8位 | 看護師 | ◎ | ◎ | △ |
| 9位 | クリエイター(デザイン・映像・ライティングなど) | ◯ | ◯ | ◎ |
| 10位 | AIエンジニア・データサイエンティスト | ◎ | ◯ | ◯ |
| 11位 | 美容師・メイクアップアーティスト | ◯ | ◯ | ◎ |
| 12位 | プロスポーツ選手・指導者 | ◯ | ◎ | ◯ |
| 13位 | 作業療法士・理学療法士 | ◎ | ◯ | △ |
| 14位 | 介護福祉士 | ◎ | ◯ | △ |
| 15位 | 整体師 | ◎ | ◯ | △ |
第1位:教師・保育士
子どもと日々向き合い、成長を支える仕事です。
知識を教えるだけでなく、心に寄り添い、社会のなかで生きる力を育てていきます。
AIが進んでも、人のぬくもりや信頼関係に基づく教育は、決して置き換えられません。
- 子どもの個性や発達に合わせて関わり方を変える
- 感情の動きを感じ取り、安心できる環境をつくる
- 家庭や地域とつながりながら成長を見守る
- 教育や保育の現場は社会に欠かせないため需要が安定
- 子どもの成長を間近で感じられることが大きなやりがい
- 感謝の言葉や笑顔が、仕事の励みになる
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| 教材・学習支援 | AIによる教材作成や学習進捗の記録が一部導入 | 個別学習支援ツールとして活用範囲が拡大中 |
| 事務処理・管理 | 書類作成やデータ整理の自動化が進行中 | 業務効率化による負担軽減が期待される |
AIはあくまで業務を支える補助的存在にとどまり、子どもの気持ちを受け止め、成長を支える役割は人の手に委ねられています。
第2位:経営コンサルタント
企業や組織の課題を見つけ、改善へ導く仕事です。
数字やデータだけに頼らず、現場の空気や人の心理を読み取りながら戦略を立てていく力が求められます。
AIが分析を支援するようになっても、「人の感情を動かし、組織を動かす力」は人にしかありません。
- 顧客ごとに異なる課題を見極め、最適な解決策を提案する
- 経営者や現場と対話を重ねながら、実行まで伴走する
- 状況の変化に合わせて方針を柔軟に調整する
- 経営課題は常に発生するため、景気に左右されにくい
- 経営層と深く関わり、成果をともに喜べる達成感がある
- 経験を積むほど専門性が高まり、キャリアの幅が広がる
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| データ分析 | 市場や財務情報の分析をAIが支援 | 判断材料の精度向上とスピード化が進む |
| 業務効率化 | 調査・資料作成などの定型業務を自動化 | コンサルタントが戦略立案や交渉に集中できる環境へ |
| 意思決定支援 | シミュレーションや予測分析の導入が拡大 | 経営判断の補助ツールとして定着見込み |
経営の舵取りを支えるコンサルタントは、これからも必要とされ続ける職業です。
第3位:営業職
営業職は、人との関係を築きながら、商品やサービスを届けていく仕事です。
単にモノを売るだけでなく、相手の気持ちを理解し、信頼を積み重ねていくことが何より大切になります。
AIがどれだけ発達しても、「人の心を動かす力」は人間にしか備わっていません。
特に、顧客の課題を引き出しながら提案をおこなう営業職は、今後も必要とされ続ける分野です。
- 顧客の話を丁寧に聞き取り、最適な提案につなげる
- 相手の表情や声のトーンから感情を読み取り、柔軟に対応する
- 契約後も関係を育て、長く信頼される存在を目指す
- 売上を支える役割として、どの企業にも欠かせない仕事
- 「あなたに任せたい」と言われる瞬間に大きなやりがいを感じる
- 成果が数字に表れるため、努力が報われやすい環境でもある
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| 顧客管理 | CRMツールやAI分析で顧客データを可視化 | 顧客理解の精度が上がり、提案がより的確に |
| 商談準備 | AIが過去データをもとに提案資料を作成 | 営業担当者は対話や信頼構築に集中しやすくなる |
| 需要予測 | AIによる購買データ分析が普及 | 市場の動きを先取りした提案が可能に |
AIは営業活動を支える“頼れるパートナー”になりつつあります。
しかし、どんなに便利になっても、相手の表情を見て空気を読む力や、信頼を築く姿勢は人にしかできません。
営業職は、AI時代にこそ「人間らしさ」が光る仕事です。
第4位:弁護士
弁護士は法律の知識をもとに、人や企業のトラブルを解決へ導く仕事です。
離婚や相続、労働問題、企業法務など、扱う分野は幅広く、単に法を適用するだけではなく、依頼者の気持ちや背景を理解したうえで最善の解決策を探ります。
AIが法令や判例を整理できるようになっても、「どう伝えるか」「どう折り合いをつけるか」といった人の感情を扱う部分は人間にしか担えません。
- 依頼者の立場や思いをくみ取り、最適な形で問題を整理する
- 交渉力と倫理的な判断力が成果を左右する
- 法の知識に加え、人の感情に寄り添う姿勢が欠かせない
- 専門職としての社会的信用が高く、長期的に活躍しやすい
- クライアントの人生や事業を支える責任の大きさがやりがいにつながる
- 解決に導いたときの「ありがとう」という言葉が最も報われる瞬間
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| 契約書作成・判例検索 | 自動生成ツールや検索AIの導入が進行 | 業務効率化が進み、判断や交渉に時間を使えるように |
| 法務支援サービス | 企業法務を中心にリーガルテックが普及 | 弁護士のサポートツールとして定着見込み |
AIは文書作成や情報整理を助ける存在になりましたが、依頼者の本音を引き出し、正義と感情の間で最善の答えを導くのは人間の仕事です。
弁護士は、AI時代にも「人の心を守る職業」として揺るがない立場にあります。
第5位:研究者・科学者
研究者・科学者は新しい知識や技術を生み出す、知的探求の最前線に立つ仕事です。
データを分析するだけでなく、「なぜそうなるのか」を考え、仮説を立て、検証を重ねながら真理を追究していきます。
AIが計算や解析を担えるようになっても、研究の出発点となる発想や着眼点は人の思考から生まれるものです。
- 自ら課題を設定し、仮説を立てて検証をおこなう
- 予想外の結果から新しい視点を見いだす柔軟な思考が必要
- 長期間にわたって粘り強く成果を積み重ねる根気が求められる
- 専門分野における知見や技術の蓄積が、そのまま価値になる職業
- 発見や成果が社会の発展に直結するため、知的満足度が高い
- 一人で黙々と考える時間が多く、探究心の強い人に向いている
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| データ解析 | 膨大なデータ処理をAIが補助 | 実験効率が向上し、分析精度も高まる |
| シミュレーション | AIが仮説の検証を自動化 | 研究者は発想や理論構築に集中できる環境へ |
| 文献検索 | 研究論文の自動要約・整理が進行中 | 情報収集のスピード化で研究開発が加速 |
AIは分析や整理を担う有力なパートナーとなりつつありますが、「問いを立てる力」や「常識を疑う視点」は人間だけが持つ知的能力です。
第6位:カウンセラー・心理士
カウンセラーや心理士は、心の悩みや不安に寄り添い、安心を取り戻す手助けをする仕事です。
相手の表情や声のトーン、沈黙の間にある感情まで感じ取りながら、丁寧に言葉を交わしていきます。
AIがどれだけ進化しても、人の心を理解し、思いに寄り添うことは人間にしかできません。
- 言葉やしぐさ、雰囲気から相手の感情を読み取る
- 話を聴きながら気持ちを整理し、回復へのきっかけをつくる
- 状況や性格に合わせ、支援の方法を柔軟に変える
- 医療・教育・福祉など幅広い分野で需要があり、安定した働き方ができる
- 相談者が少しずつ前向きになる過程を見守れる
- 感謝の言葉を直接受け取れることが大きなやりがいになる
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| アセスメント(心理検査)の補助 | テスト結果やアンケートの自動集計・傾向分析が進む | 心理士がAIの数値を参考にし、臨床判断や面談の質を高める動きが拡大 |
| 記録管理の効率化 | 面談記録や経過メモをAIが整理 | 多職種連携やケース共有の補助ツールとして活用が進む |
AIは「心を理解する存在」ではなく、心理士の判断を支えるツールとして今後使われていくでしょう。
データ処理をAIに任せることで、専門家はより深く人と向き合う時間を確保できます。
第7位:医師
医師の仕事は、AI時代でも人間にしかできない判断と対応が求められる職業です。
患者の訴えを聞き取り、表情や声の変化を読み取りながら、病気の背景や生活習慣まで考慮して診断をおこないます。
AIが得意なのはデータ解析ですが、人の命を預かる現場では、経験と倫理観に基づく柔軟な判断が欠かせません。
- 症状や検査結果を総合して診断・治療方針を決定する
- 患者の不安を受け止め、信頼を築くコミュニケーションを重視する
- 緊急時に冷静かつ迅速な対応が求められる
- 医療の需要は今後も続き、AIの導入後も高い専門性が評価される
- 患者の回復を支えることで、人の役に立つ実感を得られる
- 経験を積むほど専門性が深まり、キャリアの安定性も高い
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| 画像診断支援 | レントゲンやCT画像の解析でAIが補助 | 医師の診断をサポートし、見落とし防止に活用 |
| 手術支援ロボット | 外科手術の一部で実用化 | 医師の操作を補助し、安全性や精度を高める方向へ |
| 電子カルテ分析 | データ整理や病状予測に活用 | 診療内容の効率化や予防医療の精度向上に貢献 |
AIは医師の仕事を奪うのではなく、医療の質を高めるためのパートナーとして進化しています。
最終的な判断や患者との信頼関係の構築は、これからも人間にしかできない重要な役割です。
第8位:看護師
看護師は、患者の体調だけでなく、表情や声の調子など、わずかな変化から異変を察知する仕事です。
医師の指示を待つだけではなく、現場で自ら判断し、必要に応じて行動する瞬間も多くあります。
AIがデータを処理することはできても、人の感情を感じ取り、寄り添うことはできません。
- 状況を的確に判断し、患者の命や安心を守る現場対応力が必要
- 医師や家族、介護職など多職種との連携が欠かせない
- 身体だけでなく、心のケアを含めたトータルサポートをおこなう
- 医療・福祉分野全体で人材不足が続いており、今後も高い需要が見込まれる
- 患者からの「ありがとう」を直接受け取れる仕事で、達成感が大きい
- 病院、訪問看護、介護施設など働く場所の選択肢が多く、ライフスタイルに合わせやすい
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| バイタルデータ管理 | 自動測定機器や記録アプリが導入済み | 異常値を自動で通知し、早期対応をサポート |
| 記録・申し送り | 音声入力や電子カルテ連携が進行中 | 看護師がケアに専念できる環境が整いつつある |
| 見守りシステム | 転倒検知や夜間見守りにAI活用 | 高齢者施設などで導入拡大中 |
AIは看護師の仕事を効率化する存在ですが、患者の不安を受け止める温かさや信頼関係は人間にしか築けません。
人に寄り添う力が求められる限り、看護師の役割がなくなることはないでしょう。
第9位:クリエイター(デザイン・映像・ライティングなど)
クリエイターは、情報を「作品」という形にして人の心に届ける仕事です。
デザインや映像、文章などの分野では、社会の空気感や人の感情を読み取り、それを表現に変える力が欠かせません。
AIは効率的にデータを整理し、参考となる案を生み出すことはできますが、「どのような想いを伝えたいか」「どうすれば共感を得られるか」といった部分は人にしか描けません。
- 人の感情や体験をもとに、共感を呼ぶ作品をつくる
- 流行や文化の変化をとらえ、表現へ落とし込む柔軟さが必要
- 技術よりも、発想や構成力、表現の方向性を決める力が重視される
- SNSや動画サービスの普及により、個人の発信やクリエイティブ需要が拡大
- 自分の考えや世界観が形になる仕事で、成果が目に見えやすい
- 働く場所や形を選びやすく、スキル次第で長く活躍できる
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| 制作サポート | 構図・タイトル案などの下書きにAIを活用 | 作業の効率化ツールとして定着見込み |
| 効果分析 | 広告やSNS投稿の反応分析で活用が進む | 表現の方向性を検討する材料として活用 |
| 自動生成 | テンプレート的な画像・文章の生成が普及 | 一方で、感性を活かす創作は人が中心のまま |
AIは制作を支える存在にはなっても、「心を動かす表現」を作り出すことはできません。
人の感情をくみ取り、物語を形にする力こそ、これからの時代に求められるクリエイターの価値です。
第10位:AIエンジニア・データサイエンティスト
AIエンジニアやデータサイエンティストは、AIそのものを設計・開発・運用する立場にあり、AI時代の中核を担う仕事です。
AIをどう活かすかを考える側であるため、AIに取って代わられるどころか、発展を支える重要な存在といえます。
AIの仕組みを理解したうえで、社会や企業の課題を解決するアルゴリズムを設計するには、専門知識だけでなく柔軟な発想も求められます。
特に、倫理面の配慮や利用ガイドラインの設計、ユーザーの使いやすさを意識したUI/UXの調整などは、人の判断が欠かせません。
- AIや機械学習モデルの設計・運用を通して社会課題を解決する
- 技術だけでなく、データの読み取りやビジネス理解も必要
- 新しい技術やトレンドを常に学び続ける姿勢が求められる
- DX(デジタル変革)の進展により、企業・行政ともに需要が急増
- 自分が開発したシステムが業務効率化や社会貢献に直結する
- スキルの更新が必要だが、専門性を高めるほど安定性が増す
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| 機械学習モデル開発 | 企業内外でデータ解析の需要が拡大 | 自動化が進んでも設計・検証工程は人が主導 |
| 倫理・ガイドライン策定 | 個人情報・偏見リスク対策が課題 | AIの安全活用を支える専門人材の重要性が上昇 |
| UI/UX設計 | AIツールの操作性改善に人の感性が不可欠 | 利用者視点の設計力が評価される時代に |
AIはツールとして進化を続けていますが、それを動かすのは人の判断と創造力です。
技術の使い方を設計し、社会にどう活かすかを考えるAIエンジニア・データサイエンティストの役割は、今後さらに重要になっていくでしょう。
第11位:美容師・メイクアップアーティスト
美容師やメイクアップアーティストは、人の魅力を引き出すために感性と技術を使う仕事です。
AIやロボットが発展しても、髪の質感・肌の色・表情・雰囲気など、目の前の人に合わせて提案や調整をおこなう感覚的な作業は機械には再現できません。
施術を通して信頼関係を築き、「自分に似合う」をともに見つけていく過程こそが、この職業の本質です。
- 髪や肌の状態を見極め、その人に合うスタイルを提案する
- 会話や雰囲気づくりを通じて顧客の気持ちに寄り添う
- 手技と感性を組み合わせ、仕上がりを微調整する柔軟さが求められる
- 「誰から受けるか」が重視されるため、人にしかできない接客価値が続く
- 技術を磨くほどリピーターが増え、独立や開業にもつながる
- 美容室やサロン、ブライダル、撮影現場など活躍の場が幅広い
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| カウンセリング支援 | AIが髪質や肌色を解析し、スタイルを提案 | あくまで参考情報であり、最終判断は美容師がおこなう |
| 予約・顧客管理 | AIがスケジュール調整や履歴分析をサポート | 顧客データを活かした提案の質向上が期待される |
| 教育・技術習得 | AI教材や3Dシミュレーションで練習可能 | 若手美容師のスキル育成を補助する仕組みとして発展中 |
AIは技術を補うツールにはなっても、人の心をつかむ「接客」や「提案の瞬間」は代わりになりません。
感性・共感・関係性が価値を生むこの仕事は、AI時代でも人の手で輝き続ける分野です。
第12位:プロスポーツ選手・指導者
AIがスポーツの世界に導入され、データ分析やトレーニング管理は年々進化しています。
それでも、試合の流れを読み取り、瞬時に判断して行動する力は人間にしかありません。
風の向き、観客の熱気、相手選手のわずかな動き、こうした状況を感じ取ってプレーを変化させるのは、経験と感覚の積み重ねによるものです。
指導者もまた、AIでは代替できない存在です。
選手の性格やその日のコンディションを見極め、励ますのか、あえて厳しく指導するのかを瞬時に判断します。
数字だけでは測れない人間的なつながりが、チームの力を引き出す鍵になります。
- 状況に応じて瞬時に判断し、最善の行動を取る柔軟さが必要
- 選手や仲間との信頼関係を築くコミュニケーション力が重要
- 経験と感覚をもとにしたメンタルサポートや戦術判断が求められる
- スポーツは教育・健康・エンタメの要素を持ち、需要が途切れにくい
- 努力や成長が結果として見えるため、達成感を得やすい
- 指導者や解説者など、選手引退後も活躍の場が広がりやすい
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| データ分析 | 試合データや選手の動きをAIが解析 | 戦術や練習メニューの精度向上に活用される |
| コンディション管理 | ウェアラブル端末で心拍数や疲労を計測 | ケガの予防やパフォーマンス維持に貢献 |
| 映像解析 | AIが試合映像を分解・比較して改善点を提示 | 指導の効率化と育成サポートに役立つ |
AIは練習や分析を支える便利なツールですが、プレーの瞬間に判断し、心を動かす力は人にしかありません。
スポーツの本質である「感情と熱意」は、これからも人間が生み出すものです。
第13位:作業療法士・理学療法士
AI技術が進んでも、患者一人ひとりの体調・性格・生活環境に合わせて方法を考えるこの仕事は、人にしかできません。
作業療法士は、食事や着替え、家事など日常生活の動作を取り戻すための訓練をおこないます。
理学療法士は、歩く・立ち上がるといった基本的な身体の動きを回復させるサポートを担当。
どちらの職種も、患者の気持ちをくみ取りながら、わずかな体の変化を見逃さずに支える力が求められます。
- 体の状態だけでなく、生活の背景や目標に合わせてリハビリを設計
- 表情や動きの変化を感じ取り、訓練を柔軟に調整する
- 信頼関係を築きながら、患者の意欲を引き出すサポートをおこなう
- 高齢化が進むなかで、医療・介護の現場で需要が高い
- 回復の過程を間近で見守れるため、やりがいを感じやすい
- 経験を積むことで、専門性を活かした独立や教育職への道も開ける
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| 動作解析 | センサーで歩行や姿勢を計測し、AIが分析 | データの客観評価が可能になるが、調整は人が担う |
| リハビリ支援機器 | ロボットやAI機器が一部導入 | 訓練の効率化には役立つが、判断や声かけは人の役割 |
| 経過管理 | AIが記録を整理し、回復データを可視化 | 治療計画や最終判断はセラピストが主導 |
AIはリハビリを支えるツールにはなっても、「どのような生活を取り戻したいか」を理解する力は持っていません。
人の想いに寄り添いながら回復を支える作業療法士・理学療法士は、今後も欠かせない存在です。
第14位:介護福祉士
介護福祉士は、高齢者や障がいのある人の生活を支え、心身の両面から安心できる日常を整える専門職です。
AIが得意とするのは記録や情報整理といった定型業務ですが、利用者の表情や声のトーンから体調や気分を感じ取り、対応を変える力は人にしかありません。
小さな変化に気付き、温かい言葉をかけることで安心を与えられるのが介護福祉士の強みです。
- 利用者の心身の状態に合わせて柔軟に支援内容を調整する
- 身体介助だけでなく、精神的なケアや寄り添いも重視する
- 家族や医療スタッフと連携し、チームで支える
- 高齢化が進む日本で、今後も需要が高い
- 感謝の言葉を直接もらえる機会が多く、やりがいを実感しやすい
- 経験を積むことで、ケアマネジャーや施設責任者などへのキャリアアップも可能
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| 介助ロボット | 移乗や歩行補助の機器が一部導入 | 体の負担を減らすサポートツールとして活用が進む |
| 記録システム | AIが介護記録を整理・分析 | ケア内容の共有や業務効率化に役立つ |
AIは介護現場の負担を減らす道具として発展していますが、人の心を支える存在にはなれません。
介護福祉士は、技術よりも「思いやり」と「寄り添う力」で人の人生を支える、これからも欠かせない仕事です。
第15位:整体師
整体師は、体の歪みや筋肉の緊張を整え、痛みや不調を改善へ導く手技の専門家です。
患者の姿勢や生活習慣を見極めながら、手の感覚で微細な変化を読み取って施術をおこないます。
AIによる姿勢分析やデータ診断の技術は進化していますが、実際の触診や圧の強弱の調整、筋肉の硬さを指先で感じ取る感覚は人にしかできません。
また、施術中の会話や空気感を通して、心身の緊張を和らげるのも整体師ならではの役割です。
- 一人ひとりの体の状態を観察し、手技を変える柔軟な対応が求められる
- 姿勢・生活習慣・メンタルなど、全体のバランスを見ながら調整する
- 手の感覚や経験に基づく施術が中心で、AIでは再現できない分野
- 慢性的な肩こりや腰痛などの悩みが増えており、需要は安定している
- 「体が楽になった」「よく眠れるようになった」と直接感謝される機会が多い
- 独立開業や出張サービスなど、働き方の自由度が高い
AI導入の流れ
| 項目 | 現状 | 今後の見通し |
| 姿勢解析・データ測定 | AIが姿勢や筋肉のバランスを数値化 | 施術前後の効果測定や記録補助として導入が進む |
| 予約・顧客管理 | 顧客データをAIが自動整理 | リピーター対応やカルテ管理の効率化に役立つ |
AIは分析や事務管理の領域でサポートしますが、「手の感覚」「人との信頼」「空間の安心感」は人にしか生み出せません。
整体師は、データではとらえきれない“人の感覚”を扱う仕事として、これからも求められ続けるでしょう。
AIの進化で生まれた新しい仕事
AIの進化は、人の仕事を奪うだけでなく、新しい働き方や職業を生み出しています。
テクノロジーの発展にともない、従来になかった分野が次々と登場し、専門知識や創造力を活かせる場が広がりました。
ここでは、AI時代に生まれた新しい仕事の一部をご紹介します。
- AIを安全に運用するリスク管理・倫理の専門職
- AIを広め、人のスキル成長を支える教育職
- AIと協働して成果を生み出す実践的な職種
AIを活用することで、人とテクノロジーが協働する新しい働き方が広がっています。
AIを安全に運用するリスク管理・倫理の専門職
AIを安全に活用するための専門職として注目されているのが、AIガバナンス担当者です。
生成AIの普及により、業務効率の向上や新しい価値創出が進む一方で、誤情報の拡散や著作権侵害、データ漏洩といったリスクも増えています。
この職種は、AIを企業のなかで「安全に」「倫理的に」使うためのルールづくりや運用体制の整備を担う役割です。
AIガバナンスは単なる法令遵守ではなく、企業の信頼を守りながらAIの価値を最大限に活かすための経営課題ともいえます。
- データ漏洩や誤情報などのリスクを予測・防止する力
- 公平性や透明性を保ち、社会的信頼を守る倫理的判断力
- 国内外の法規制を理解し、適切に対応する知識
- 技術と経営の両面からAIの活用方針を設計する戦略的思考
海外ではAI規制の整備が進み、日本でもガイドラインの策定が進行中です。
こうした動きに対応できる人材の需要は今後さらに高まるでしょう。
AIを広め、人のスキル成長を支える教育職
AIを活用する力を社会に広め、人のスキル成長を支える専門職として注目されているのが、AIリテラシー講師や企業内研修トレーナーです。
生成AIの普及によって、業務効率の向上や新たな発想の創出が進む一方、AIを正しく理解し、目的に応じて活用できる人材の育成が重要になっています。
AIリテラシー講師は、企業や教育機関でAIの基礎や活用法を教える教育者です。
ChatGPTなどを題材に、日常業務への活かし方や発想力を高める使い方を伝え、AIを安心して活用できる社会づくりを支えます。
企業内研修トレーナーは、社員向けにAI導入研修をおこない、実務に直結するスキル習得を支援します。業務効率化やDX推進を現場から支える中心的な存在です。
- 生成AIの仕組みや活用法をわかりやすく伝える指導力
- 職種や課題に合わせてAIツールを使い分ける応用力
- 受講者の理解度を見極め、成長をあと押しするコミュニケーション力
- AIを組織に定着させる教育設計力
AIを扱う力が成果に直結する今、人と技術をつなぐ教育職の重要性は、今後さらに高まっていくでしょう。
AIと協働して成果を生み出す実践的な職種
AIと人の強みを組み合わせ、成果を最大化する専門職として注目されているのが、プロンプトエンジニアとマーケティングアナリストです。
生成AIの発展により、文章作成・分析・企画立案などの業務でAIをパートナーとして使いこなす人材の価値が高まっています。
プロンプトエンジニアは、AIに与える指示文(プロンプト)を設計し、求める結果を精度高く引き出す専門職です。
AIの特性を理解し、最小限の入力で最大の成果を導くスキルが求められます。
マーケティングアナリストは、AIで収集・分析した膨大なデータをもとに、消費者行動の傾向を読み解き、戦略を立案する職業です。
AIによる分析結果を人の洞察とかけ合わせ、実践的なマーケティング施策を生み出します。
- AIの出力を的確に制御し、目的に合った成果を導く設計力
- データや生成結果を判断し、人の視点で価値を見極める分析力
- AIを業務の一部ではなく、ともに成果を生み出す「協働相手」として活かす発想力
AIと人が互いの得意分野を補い合う時代に、こうした職種は今後さらに重要な役割を担っていくでしょう。
AI時代に選ばれる人になるために磨きたい3つのスキル
AIの進化が加速するなかで、求められる人材の姿も変わりつつあります。
これからの時代に必要なのは、AIに置き換えられない発想力や判断力を育て、テクノロジーと協働できる人です。
AIを恐れるのではなく、使いこなして成果を高める力が問われています。
ここでは、AI時代に選ばれる人になるために磨いておきたい3つのスキルをご紹介します。
- 相手の本音をくみ取る“対話力”
- 新しい知識を吸収し続ける“学習力”
- 状況を読み取り最適解を導く“判断力”
変化の速い時代を生き抜くために、今こそ意識して身につけたい力です。
スキル①:相手の本音をくみ取る“対話力”
相手の本音をくみ取る“対話力”は、AI時代にこそ求められる人間的なスキルです。
どれほどAIが進化しても、感情や空気を読み取り、心を通わせながら信頼関係を築けるのは人だけです。
相手の言葉を正確に理解するには、話の内容だけでなく、その背景にある気持ちや状況を感じ取る姿勢が欠かせません。
まず意識したいのは、心理的安全性の高い関係づくりです。
安心して話せる環境が整っていれば、相手は本音を話しやすくなります。
否定せずに受け止める、意見の違いを尊重する、評価制度や会話の場を見直すなど、小さな積み重ねが信頼を育てます。
また、傾聴と共感の姿勢も重要です。相手の目を見てうなずく、穏やかに表情を変えるなど、態度で関心を示すことが大切です。
言葉以上に伝わる反応が、相手の安心感を生み、素直な意見を引き出せるでしょう。
スキル②:新しい知識を吸収し続ける“学習力”
技術が急速に進化する今、数年前の常識がすぐに古くなることも珍しくありません。
AIを効果的に使いこなすためには、変化を恐れず、常に新しい知識を取り入れる姿勢が欠かせません。
学習力を高めるには、まず自分の課題を明確にすることが大切です。
目的を持って学ぶことで、膨大な情報の中から必要な知識を選び取れるようになります。
さらに、AIやオンライン講座を活用すれば、時間や場所にとらわれず、効率的に学びを深められますよ。
学んだ内容は、実践を通して身につけてこそ価値を持ちます。
得た知識を試し、失敗から学ぶ姿勢が、次の成長を生み出します。
絶えず変化するAI時代において、学び続ける人こそが新しいチャンスをつかむ存在です。
スキル③:状況を読み取り最適解を導く“判断力”
AIを使う場面が増えても、最終的な判断を下すのは人間です。
AIは情報を整理し、選択肢を提示してくれますが、その中から何を選び、どう行動につなげるかは人の判断にかかっています。
だからこそ、状況を正しく読み取り、最適な答えを導く“判断力”が欠かせません。
判断力を高めるには、まず情報を見極める力が必要です。
AIが出した答えをそのまま信じるのではなく、根拠や背景を確かめ、自分の目的に照らして考える習慣を持ちましょう。
さらに、多角的に考える姿勢も大切です。
ひとつの意見に偏らず、さまざまな視点からリスクと可能性を見極めることで、より正確な判断ができます。
AIを頼りにしつつも、最終的な決断を人が下せるかどうかが、AI時代に選ばれる人の条件です。
これからの時代に“選ばれる人”になるための3つの考え方
これからの時代に選ばれるのは、知識やスキルだけでなく、自ら考え、変化に前向きに向き合える人です。
AIをはじめとする新しい環境のなかで、自分らしく価値を発揮するためには、意識すべき考え方があります。
ここでは、これからの時代を生き抜くために大切な3つの考え方をご紹介します。
- 自分の得意分野をAIとかけ合わせて活かす
- 人にしかできない「信頼を築く力」を磨く
- 変化を前向きにとらえ、自分の軸を育てる
どのような環境でもチャンスをつかむために意識したい考え方です。
考え方①:自分の得意分野をAIとかけ合わせて活かす
AI時代において、自分の得意分野を活かすだけではなく、それをAIとかけ合わせることが重要です。
自分のスキルとAIを組み合わせることで、より高い価値を生み出すことができるでしょう。
- 作業の自動化
- AIを使用して定型的な作業を自動化し、その分の時間をクリエイティブな業務や価値創造に充てることができます。反復作業をAIに任せることで、より戦略的な仕事に集中できます。
- パーソナライズされたサービス提供
- AIを活用して、個々のニーズに合わせたサービスやアドバイスを提供できます。データ分析に基づく最適な提案をおこない、よりパーソナライズされた対応を実現します。
AIと得意分野をかけ合わせることで、効率化と創造性を両立させ、他の人にはできない価値を生み出すことができますよ。
考え方②:人にしかできない「信頼を築く力」を磨く
信頼関係とは、お互いに信じて頼れる関係のこと。
仕事において信頼があると、最小限のやり取りでスムーズに進められ、チーム全体の生産性も高まります。
逆に、信頼を失うと小さな確認や修正が増え、時間も労力もかかってしまいます。
信頼は一日で築けるものではなく、日々の積み重ねが大切です。
次の5つの行動を意識してみましょう。
- 小さな約束を守る:時間を守る、頼まれたことを確実にこなすなど、基本を徹底することが信頼の土台になります。
- 言動を一致させる:いったことを責任を持って実行する人は、「誠実な人」として評価されます。
- できないことは正直に伝える:無理をして約束を破るより、素直に伝える方が信頼を保てます。
- 間違いは素直に認める:失敗を隠さず謝れる姿勢が、誠実さを印象づけます。
- 感謝を言葉にする:助けてもらったときに「ありがとう」を伝えることで、関係がより強くなります。
信頼は人と人をつなぐ最も強い絆です。誠実な行動を積み重ねて、AI時代でも選ばれる人になりましょう!
考え方③:変化を前向きにとらえ、自分の軸を育てる
AI時代は変化のスピードが速く、今のやり方がすぐに古くなることもあります。
多くの人は「変えたいけど、失敗したら怖い」と感じがちですが、変化を恐れず動ける人こそこれからの時代に求められます。
大切なのは、「変えてみてもいい」という空気をつくることです。
挑戦した人を否定せず、失敗も評価の一部として受け止めることで、前向きな行動が生まれます。
さらに、自分の軸を持つことも必要です。
何を大切にしたいのかを明確にすれば、変化のなかでも迷わず行動できます。
変化に前向きな姿勢は、天性ではなく積み重ねで育つ力です。
試し、考え、また挑戦する。その繰り返しが、自分の軸を強くしていくでしょう。
まとめ|AIとともに働く時代を、自分の力で切り開こう!
AIが当たり前に使われる今、求められているのは「AIに負けない人」ではなく、「AIとともに成長できる人」です。
変化を恐れず、学び続け、自分の強みを活かす姿勢こそが、これからのキャリアを支える力になります。
環境や技術が変わっても、自分の価値を高めるのは自分自身です。
AIの発展により、働き方の選択肢も大きく広がりました。
自宅でスキルを磨きながら自由に働く人も増え、WEBデザインのようなクリエイティブ職はその代表例です。
WEBデザイナーは、パソコン1つあれば、時間や場所を問わずに働ける仕事です。
就職だけでなく、フリーランスや副業として活動する方も多くいます。
「興味はあるけれど、どうしたらいいかわからない」
そんな方は、WEBデザイナーの働き方オンラインセミナーにぜひ参加してみてください。
業界のリアルな現状や、未経験からデザイナーになるための近道をわかりやすくご紹介します。
参加は無料です。
AI時代をどう生きるかを自ら選び、自分の力で未来を切り開いていきましょう。